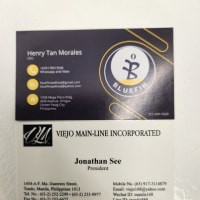平成29年5月17日(水)
我が家にも、亡き祖父が丹精込めて農業をやっていた頃の農地がわずかですが残っています。畑は茶畑と野菜やみかんを、水田では稲をそれぞれ少しずつ作っていました。父が早く亡くなったために、祖父が亡くなる平成10年頃までは100歳近くになった祖父を家族が支えながら、何とか維持できていたのですが、亡くなった後は母が自宅近くにある小さな畑で自家用の野菜を作り、そのほかは、専業農家の方々や親戚の農家などに委託して耕作していただくことなどで、貸付地として何とか農地を維持してきました。
農地は一度荒廃させると元に戻すことは大変で、しかも、雑草が生えると隣接地の農地にまでその種が飛び、そちらでも雑草が生えやすくなるという大変な迷惑をかけてしまいます。
最近は、私と同じような立場の方も増えて、荒廃農地化が進んでいます。周辺農地への影響などは先に触れたとおりですが、その農地を有効活用することで、地域農業の活性化につなげることができます。
現在の農業は、生産効率を高め生産コストを抑制するために、機械化が進められています。機械化が進んでも、農地が小さかったり分散しているとその効果が発揮しにくくなります。ましてや、荒廃農地がそれを拒んでいるようでは、周辺の農業が停滞してしまうことすらあります。
作れなくなった農地を、隣接する農家に一体の農地の一部として使っていただければ、効率は一気に上昇します。しかし、かつて農地を貸すことで様々な権利関係の問題が生じてきました。戦前に貸していた農地は、戦争直後の「農地解放令」により、小作人から地主に戻さなくてもいい仕組みが導入され、その後も、そのイメージが残っているせいか、「土地を貸しても戻らない」という思い込みもあって、また、農業をやらなくても農地の所有者というだけで農地が持つ特別な権利が得られることで、それを維持するためにあたかも農業をやっているような地主も多くいました。
しかし、高齢化と担い手不足により耕作ができる農家が減っています。その結果、耕作放棄地は増えていくことになりました。
農業の衰退は、国の衰退につながります。食料戦略が描けない国は滅びてしまいます。私は、世界で一番安心して、安全な食料を提供できるのが日本の農業だと思っています。その思いは、私が県議会議員としての政策課題の中では、重要な位置を占めています。
国も県も農業振興に力を入れ、農業の担い手対策や、効率化された農業、生産、加工、販売などを手がける6次産業化を進めています。これらの人材育成や機材購入、生産技術の研究、農地整備のための土地改良などには、多額の税金が投入され、その本気度を感じざるを得ません。
しかし、農地所有は個人の権利の場合がほとんどで、「大地の恵み」といいますが、その大地が確保できてこそ安定的な農業が可能となります。つまり、個人の権利である農地をどう活用できるかで、所有権を確保しながら貸し付けていくことが重要となりました。その実現のために、土地の権利を保証し農家の耕作の権利も保証する仕組みが、公が関与する「農地中間管理機構」です。今、この機構の活用が注目されています。
さて、私事に戻りますが、耕作を委託していた農家や親戚がここ数年の間に高齢化や死去に伴い、農地を返してきました。農業の経験のない私は、祖父が元気な頃は手伝いをしていたものの、農業生産技能は全く習得していません。農業は、生半可のことではできませんが、その知識はゼロです。
県議になって7年目を迎え、当初から農業施策に関心があったことで、多くの農家と接してきました。そのうちに、自分でもできることをやってみようと思い、昨年からみかんの苗木を植え、農家やJA関係者のアドバイスを受けてトライしています。施肥や予防散布、除草、剪定など2年目を迎え苦労しながら始めました。根気のいる仕事ですが、日々の農作物の成長を大変楽しく眺めています。

(昨年植えたみかんも、今年は倍くらいの大きさに生長した)

(10本植えたみかんの苗木の内、今年は8割にみかんの花が咲いた)
しかし、私が所有する全ての農地の内、私自身ができることはごくわずかです。私がもう少し挑戦できる余地を残して、中間管理機構にお願いし農地の活用を進めながら、祖父が残した大切な農地を何とか維持しています。