『日本の戦後補償問題』、1996年執筆
今日、第二次大戦後のアジアにおける国際軍事裁判である極東国際軍事裁判(以下、東京裁判とよぶ)が、日本の戦争に対する罪をいったいどれだけ追及したのかを疑問視する議論が数多くなされている。それと同時に、日本に東京裁判で裁かれたような罪がほんとうに存在したのか、裁かれるべきでない行為が罪として裁かれなかったか、裁判そのものが公正さを欠いていなかったかといった東京裁判の問題点を指摘する主張も少なくない。そうした東京裁判をめぐる議論を一望することは、日本の戦争責任に対する認識を考えるうえで、何らかの手がかりになるだろうと思われる。
そこでまず、東京裁判をめぐる議論として、東京裁判そのものを問題視する後者の議論からみてみよう。後者の議論としては、たとえば「勝者の裁き」としての東京裁判の問題点を指摘する主張がある。
大沼保昭氏は、東京裁判は「欧州枢軸国の主要戦争犯罪人の裁判及び処罰を目的とする協定により設立され」、「欧州枢軸国の利益のために(中略)犯罪を犯したものを裁判し、かつ処罰する権限を有する」ものであり、そうである以上、戦勝国による敗戦国に対する一方的な裁きに終始したことについては、裁判所自身の責任によるものではないと指摘する(28)。米国による原爆投下や、ソ連の日ソ中立条約破棄についての訴訟は、関連性なしとして斥けられる運命にあったが、極東国際軍事裁判所条例第12条の「いかなる種類たるとを問わず起訴事実に関連なき争点及び陳述を排除する」によれば、訴訟法的に問題ないことであった。しかし一方で、法が法であるための基本的要件はその普遍的適用性にあるはずであり、それを著しく欠いているものは法としてとうてい認め難い(29)。すなわち東京裁判の評価としては、東京裁判を裁判たらしめた極東国際軍事裁判所条例を含めて、その裁判総体の普遍性を問題とすべきであるという(30)。
東京裁判で「平和に対する罪」をとりあげることの合法性と、それが指導者の刑事責任に結びつくことについての違法性にもいくつかの疑問が投げかけられている。
たとえばドイツのクヌート・イプセン氏は、1983年5月28日に東京で開催されたシンポジウムにおいて、国際軍事裁判所の法的管轄権を問題とし、「平和に対する罪」に関する国際軍事裁判所の管轄権は、当時有効な国際法に基づくものではなかったことを指摘した。さらに1928年の不戦条約に従えば、戦争に訴えることは違法行為であったが、それを個人の刑事責任として処断する国際刑法はなかったことにも言及している(31)。この点については、戦争違法観と指導者責任観の結合という論理構造を持つ「平和に対する罪」の問題点を指摘するものもある。つまりこの両者の結合は第二次大戦末期になされたものであり、「平和に対する罪」は当時の既存の国際法を判断基準とする限りにおいては、国際法上の犯罪としては認められなかったという主張である(32)。
これに対し前者の議論は、東京裁判が日本の戦争責任を十分に追及できなかったという問題点を指摘するものである。
そのひとつが天皇不起訴である。戦後、天皇の戦争責任は大きな政治問題となった。東京裁判において、天皇を被告人として訴追するのが法的にたとえ困難であったとしても、最低限天皇を証人として喚問することは可能であった。それどころか、日本の戦争遂行過程を明らかにするうえで、それは不可欠だったはずである。それにもかかわらず天皇訴追がなされなかったのは、占領政策を円滑かつ効果的に進めるため、天皇の存在がきわめて有用であるというアメリカの判断があり、そこに東京裁判が政治主義的、便宜主義的に進行したという問題点が指摘されなければならない(33)。
荒井信一氏は、第二次大戦後の軍事裁判であきらかにされるべき問題は、戦争について天皇が実質的に果たした役割がいったい何であったかにあったという。ゆえに東京裁判が、天皇を被告として裁かなかったことで、天皇の実質的な役割が、起訴に値しない程度のものであることが示されたとする。その後、天皇の戦争責任問題があらためて噴出してくるようになったが、それは東京裁判をはじめアジアの各地で連合国によって行われた戦争犯罪法廷による戦後処理が不徹底であり、この問題の決着を避けたためであった。すなわち東京裁判に働いたアメリカの政治的配慮が、天皇の戦争責任を今日にまで持ち越させたというのである(34)。
東京裁判が、日本の行為の直接の被害者であるアジアを軽視したまま進行し、結局、戦争における日本の加害者としての立場を明確にしないままに終わってしまったという点もひとつの大きな論点となっている。中国は東京裁判に判事を送り出しており、形式的には日本の戦争責任を追及できる立場にあった。しかし実際には、中国が東京裁判に対してもつ影響力は限られていた(35)。戦前もしくは戦時中の日本の好意により多くの犠牲者をだした挑戦、東南アジアには、日本の戦争責任を追及する機会すら与えられていなかったのである。
この問題について荒井氏は、戦後イギリスがシンガポールでおこなったインド国民軍裁判と後沢裁判を例に挙げ、戦犯裁判が植民地支配者の公正さを示すショウウインドウの役割を果たしたり、植民地支配に対する独立運動への懲罰であったことを指摘している。そのうえで、東京裁判が植民地支配者の側からおこなわれたBC級裁判の限界と、現地民衆の受けた戦争被害や犯罪行為、その責任の追及などが事実上きわめて限定された結果ゆえに、アジアの不在が問題視されるようになったという。東京裁判の限界が、アジアにおける日本の戦争責任の問題があらためて問われる歴史的理由となったとする主張である(36)。
しかしなによりも指摘されなければならないのは、東京裁判と日本国民との関係である。
東京裁判は、日本の戦争指導者の一部を一般国民から切り離して処罰することで日本の戦争責任を裁いた。そのため、日本国民の戦争責任とは一体何であるのかは、あきらかにされなかった。むしろ日本国民の大部分は、東京裁判を、日本の一部指導者の戦争の罪を問う、自分たちとは無縁の出来事として受け止めた(37)。そして東京裁判で起訴された罪については、すでに処罰が済んでおり、解決されたものであるとの認識をもつようになったのである。
大沼氏は、日本の戦争責任論の展開の中で、「誰が」「誰に対して」「いかなる根拠から」「いかなる程度の」責任を負い、「いかなる方法で」責任をとるべきかという厳密な論理操作がおこなわれなかったことを問題として指摘する(38)。戦争責任と国民との関係が検証されなかった東京裁判は、日本国民の免責意識を生むひとつの大きな原因となって作用したのである。
| 2.1 敗戦責任論、被害者意識 << | >> 2.3 日本の政治家による「妄言」 |
















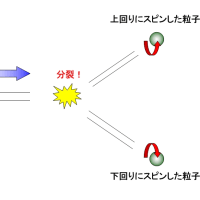
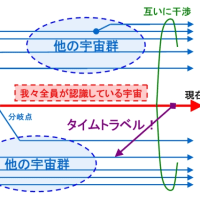
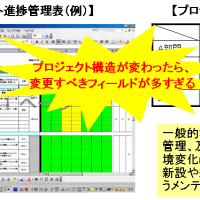
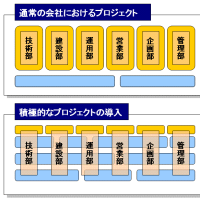





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます