クラークの次は、同じくSF三巨匠の一人ハインライン。
‘12ローカス社ベスト 21位、’06SFマガジン長編ベストでも41位と日米で評価が高い(であろう)作品です。
1959年発刊、1960年のヒューゴー賞作品。
ハインライン、超有名作の「夏への扉」(少なくとも日本では)は昔から大好きで何回読んだかわからないほどですが、それ以外はどうもマッチョでアメリカンな印象で苦手意識があり殆ど読んでいませんでした。(短編集「時の門」を読んだくらい)
「異星の客」や「月は無慈悲な夜の帝王」などが有名どころなんでしょうが、分厚いしなんだかとっつきにくい...。
「夏への扉」はハインラインの中では異例の軟派作品なんでしょうねぇ。
9年くらい前にこの本の訳者でもある矢野徹氏著(一部共著)の「連邦宇宙軍シリーズ」にはまり、この作品の中で「宇宙の戦士」が頻繁に取り上げられていたため気になって本書を新品を購入しました。(奥付2004年6月)

余談ですがこの「連邦宇宙軍シリーズ」雑なところはありますがかなり面白いです。
私の中で日本SFベストを上げればこれはベスト10には入ります。
「名作」というよりひたすら「面白い」作品ですが...。
で、買ったのですがぱらっと読むとなんだかマッチョなお話そうで、それなりの厚みの本なので読みだす気がなかなか起きず9年間が過ぎてしまいまいした。
その間「ガンダム」の元ネタだということや、「エンダーのゲーム」との関連性などいろいろ耳年増的に知識を入れていて「読みたい」気分が高まり読み始めました。
内容(裏表紙記載)
単身戦車部隊を撃破する破壊力を秘め、敵惑星の心臓部を急襲する恐るべき宇宙の戦士、軌道歩兵。少年ジョニーが配属されたのはこの宇宙最強の兵科であった。かれの前には一人前の戦士となるための地獄の訓練が待ち受けている・・・・・・いつしかジョニーは、異星人のまっただ中へ殴り込み降下をかける鋼鉄の男に成長していた! 未来の苛烈な宇宙戦を迫真の筆致であますところなく描き出し、ヒューゴー賞に輝いた巨匠の問題長編!
読んでみてまず思ったことは、「あぁ「夏への扉」と同じ作者だ」ということ。
主人公の独白や楽天的かつ前向きかつちょっと情けないところなどがそっくりでした。
他の長編を読んでいないので???ですがハインラインの主人公はみんなこんな感じなんでしょうか?
次に思ったことは、男性ホルモンたっぷりでアメリカンな作品であること。
いろいろ議論を呼んだようですが、思いっきり暴力肯定小説です。
作中語られる言葉「暴力は、歴史上、ほかの何にもまして、より多くの事件を解決している。その反対意見は希望的観測に過ぎぬ。この事実を忘れた種族は、その人命と自由という高価な代償を払わされてきた」思いっきりストレート、ど真ん中な主張。
発表時期がベトナム戦争時期だったようですからまぁ議論になるでしょうねぇ。
ただ21世紀になっても紛争があると米軍が乗り込んでいくという構図は変わらずで、それに代わる真に有効な解決手段がないというのも現実であったりはします。
ただ訳者の矢野徹氏の「だが、下士官兵にあって戦争を知った人間ほど、心から戦争を嫌い、ファシズムを嫌っているものはほかにはいないと思うのだが・・・・・・。」という気持ちもわかる気もします。
ブッシュJr政権でも実戦経験のあるパウエル国務長官が一番の穏健派だったりしましたからねぇ。
東日本大震災の時にも本当に活躍したのは自衛隊だという話もあるようです。
(この辺偉そうに書いていますが所詮一般サラリーマンの社会認識なので浅いのは自分でも承知はしているつもりです。)
軍隊という組織をどうとらえるか??深く考えると「う~ん」となってしまう小説です。
ただ深く考えなければ、きわめて単純に楽しめる青年の成長小説となっています。
最初の方でも書きましたが、主人公が絶妙。
キャラ的には主人公は「のらくろ」か夏目漱石の「坊ちゃん」のように感じました。
なんだかとぼけているんですが真面目で楽観的で、まぁ頭は悪くないんだろうなぁという感じ。(そんなにかしこくもないのがまたいい)
物語中で兵隊としての教育を通してどんどん成長していくわけですが、成長した「自分」を実感しないでとまどいながら事をなしていきます。
この辺、自分のことを考えても実感があります、気持ちは大学生くらいのままなんですが社会的には40代オヤジでえらそうなことをいっている。
皆さんもそんな思いありませんか?
そういう意味では「超人」が主人公の「エンダーのゲーム」などより身近に感じられます。
なおエンダーのゲームとは敵が昆虫型宇宙人ということでは設定似ていますが他はかなり色合いの違う作品です。
(SFは過去の名作の設定援用しているんだろうなと改めて感じました、古典読まないとなぁ)
一方で「二等兵物語に宇宙服を着せただけ」という批判もあるようで、それもまぁそうだなぁというくらいストレートな作品です、なにせ私も思い出したのが「のらくろ」と「坊ちゃん」ですから....。
400頁超の本ですが4時間くらいで読み終わりましたしねぇ。
(あとまったく個人的なおもしろさなのですが主人公が赴いた惑星の一つが亜酸化窒素リッチな大気なのがツボにはまりました...仕事上。)
でもまぁとにかく素直に面白いですし、あけすけに語られた「軍隊」「暴力」礼賛についていろいろ考えることも多い名作かと思います。
ハインラインの他の長編も読みたくなりました。
↓よろしければクリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
‘12ローカス社ベスト 21位、’06SFマガジン長編ベストでも41位と日米で評価が高い(であろう)作品です。
1959年発刊、1960年のヒューゴー賞作品。
ハインライン、超有名作の「夏への扉」(少なくとも日本では)は昔から大好きで何回読んだかわからないほどですが、それ以外はどうもマッチョでアメリカンな印象で苦手意識があり殆ど読んでいませんでした。(短編集「時の門」を読んだくらい)
「異星の客」や「月は無慈悲な夜の帝王」などが有名どころなんでしょうが、分厚いしなんだかとっつきにくい...。
「夏への扉」はハインラインの中では異例の軟派作品なんでしょうねぇ。
9年くらい前にこの本の訳者でもある矢野徹氏著(一部共著)の「連邦宇宙軍シリーズ」にはまり、この作品の中で「宇宙の戦士」が頻繁に取り上げられていたため気になって本書を新品を購入しました。(奥付2004年6月)

余談ですがこの「連邦宇宙軍シリーズ」雑なところはありますがかなり面白いです。
私の中で日本SFベストを上げればこれはベスト10には入ります。
「名作」というよりひたすら「面白い」作品ですが...。
で、買ったのですがぱらっと読むとなんだかマッチョなお話そうで、それなりの厚みの本なので読みだす気がなかなか起きず9年間が過ぎてしまいまいした。
その間「ガンダム」の元ネタだということや、「エンダーのゲーム」との関連性などいろいろ耳年増的に知識を入れていて「読みたい」気分が高まり読み始めました。
内容(裏表紙記載)
単身戦車部隊を撃破する破壊力を秘め、敵惑星の心臓部を急襲する恐るべき宇宙の戦士、軌道歩兵。少年ジョニーが配属されたのはこの宇宙最強の兵科であった。かれの前には一人前の戦士となるための地獄の訓練が待ち受けている・・・・・・いつしかジョニーは、異星人のまっただ中へ殴り込み降下をかける鋼鉄の男に成長していた! 未来の苛烈な宇宙戦を迫真の筆致であますところなく描き出し、ヒューゴー賞に輝いた巨匠の問題長編!
読んでみてまず思ったことは、「あぁ「夏への扉」と同じ作者だ」ということ。
主人公の独白や楽天的かつ前向きかつちょっと情けないところなどがそっくりでした。
他の長編を読んでいないので???ですがハインラインの主人公はみんなこんな感じなんでしょうか?
次に思ったことは、男性ホルモンたっぷりでアメリカンな作品であること。
いろいろ議論を呼んだようですが、思いっきり暴力肯定小説です。
作中語られる言葉「暴力は、歴史上、ほかの何にもまして、より多くの事件を解決している。その反対意見は希望的観測に過ぎぬ。この事実を忘れた種族は、その人命と自由という高価な代償を払わされてきた」思いっきりストレート、ど真ん中な主張。
発表時期がベトナム戦争時期だったようですからまぁ議論になるでしょうねぇ。
ただ21世紀になっても紛争があると米軍が乗り込んでいくという構図は変わらずで、それに代わる真に有効な解決手段がないというのも現実であったりはします。
ただ訳者の矢野徹氏の「だが、下士官兵にあって戦争を知った人間ほど、心から戦争を嫌い、ファシズムを嫌っているものはほかにはいないと思うのだが・・・・・・。」という気持ちもわかる気もします。
ブッシュJr政権でも実戦経験のあるパウエル国務長官が一番の穏健派だったりしましたからねぇ。
東日本大震災の時にも本当に活躍したのは自衛隊だという話もあるようです。
(この辺偉そうに書いていますが所詮一般サラリーマンの社会認識なので浅いのは自分でも承知はしているつもりです。)
軍隊という組織をどうとらえるか??深く考えると「う~ん」となってしまう小説です。
ただ深く考えなければ、きわめて単純に楽しめる青年の成長小説となっています。
最初の方でも書きましたが、主人公が絶妙。
キャラ的には主人公は「のらくろ」か夏目漱石の「坊ちゃん」のように感じました。
なんだかとぼけているんですが真面目で楽観的で、まぁ頭は悪くないんだろうなぁという感じ。(そんなにかしこくもないのがまたいい)
物語中で兵隊としての教育を通してどんどん成長していくわけですが、成長した「自分」を実感しないでとまどいながら事をなしていきます。
この辺、自分のことを考えても実感があります、気持ちは大学生くらいのままなんですが社会的には40代オヤジでえらそうなことをいっている。
皆さんもそんな思いありませんか?
そういう意味では「超人」が主人公の「エンダーのゲーム」などより身近に感じられます。
なおエンダーのゲームとは敵が昆虫型宇宙人ということでは設定似ていますが他はかなり色合いの違う作品です。
(SFは過去の名作の設定援用しているんだろうなと改めて感じました、古典読まないとなぁ)
一方で「二等兵物語に宇宙服を着せただけ」という批判もあるようで、それもまぁそうだなぁというくらいストレートな作品です、なにせ私も思い出したのが「のらくろ」と「坊ちゃん」ですから....。
400頁超の本ですが4時間くらいで読み終わりましたしねぇ。
(あとまったく個人的なおもしろさなのですが主人公が赴いた惑星の一つが亜酸化窒素リッチな大気なのがツボにはまりました...仕事上。)
でもまぁとにかく素直に面白いですし、あけすけに語られた「軍隊」「暴力」礼賛についていろいろ考えることも多い名作かと思います。
ハインラインの他の長編も読みたくなりました。
↓よろしければクリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










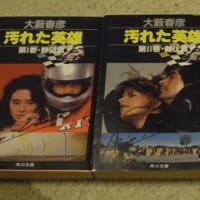
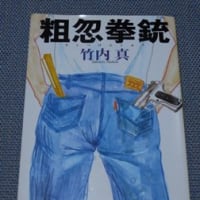
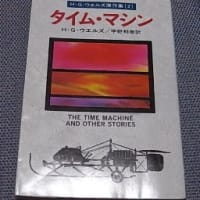
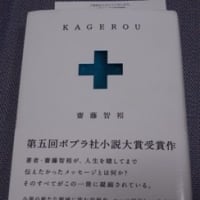
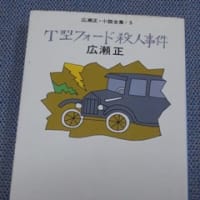
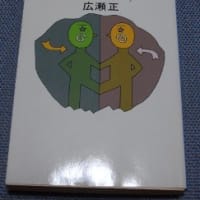


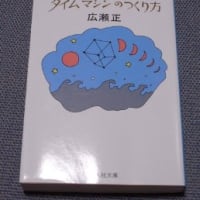
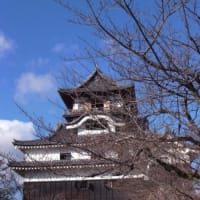
SFファンではありませんが、十代にかなりな影響を受けまして、読み返そうとする時に、貴兄のブログに当たりました。参考にさせて頂いております。
因みに私は60年代半ばの産まれで50代前半。
職業は鍼灸マッサージ師。開業と雇われを半ばする立場です。
職歴は数多あるのですが、最初の仕事が自衛官でして。その為に本作から投稿をさせて頂きます。
訓練所のエピソードで、除隊を悩むジョニーが、長距離行軍中に軍楽隊と並走して、自分が下り坂を降りている…乗り越えたのだと気がつくシーンがありました。
あれはリアルな感じがいたしました。似た経験が有りましたから。
私は機動歩兵ならぬ機械化歩兵でした。具体的にはヘリに搭乗する歩兵です。空挺のような特科ではなく普通科。映画の「地獄の黙示録」診ていなやつです。いきなり下ろされるので、健脚であるのが大事でして、主役の気持ちが理解できる気がしたです。
ハインラインの描く軍人民主主義には?が在りましたが。
60年代に「三矢研究」で、クーデター研究と騒がれた事件があります。これで自衛官は、政治的研究を忌避するようになりました。
北部方面は冷戦期には最大兵力の場でしたし、
最も武装独立の可能性が高い地域と見られてましたから、
シビリアンコントロールのしばりと言うか、
隊員の政治的活動参加や、サークル活動は煩かったのですね上が。
そのせいか、兵役経験者だけが参政権を持つ社会というのは想像もつかなかったです。
ハインラインは現代というよりも、文官と武官の区別が少なくて、庶民の100人隊長が政治的権利を持っていた共和制ローマをモデルにしたのでは?かように考えています。
もう一つ初読(20歳で訓練中の事故で入院していた時)から20年してから再読して気がついたのですが、主役のジョニーは「白人」ではありませんね?
ハインラインもはっきりと書いてはいないのですが、ワスプの名前ではない。制度化した人によると、フィリピン系ではなかろうかと?
私もヒスパニックを再読で疑いました。
堂々と非白人のヒーローを正面に出し難い時代たったのでしょうが、一種の反骨を感じます。
羽翼の巨頭と言われる彼ですが、
「異星の人」の作家だけあるなと思います。
では、また。
はじめましてです。またコメントありがとうございます。
私は70年生まれですので雨亭さんは年上ですね。
今時のSFも読みたいのですが定番抑えてからと思うとなかなかたどり着きません・・・。
何はともあれよろしくお願いいたします。
雨亭さんは自衛隊にいらっしゃったんですね。
そんな方がリアリティを感じられるということであれば本作の軍隊の描写は確かなものなんでしょう。
「軍」経験はないですが、25年間社会人生活を送っているなかで「プロフェッショナル」になるためには若いうち(若くなくてもかもしれませんが)に多少は無理が必要な気はしますし、よく人を見て厳しく接してくれる鬼軍曹的な人もいてもいい気はします。
ただ今時少し間違えるとブラックということになりますし、難しいですね。
本作では軍政民主主義も含めてハインラインかなり楽天的に書いてます・・・。
政体などというものは雨亭さんも書いているローマ時代やら古代ギリシャででもなければ「これが正しい」といいきれるものはないでしょうね。
(結局それも短期間かつ局地的なもにだったわけですし)
ハインラインの作品は「正義」をある意味単純化して書いているところがあり、本人がどこまで信じているのかは「?」ですが、そこまで単純化して書かれると「本当にそうかー?」と疑問を感じて考え出してしまうところがありそこが長所なのかもしれません。(^^;)
(狙っているかは???)
また雨亭さんも書かれているとおり主人公は有色人種であることが最後に明かされています。
(矢野徹訳版では解説に書いてあったと思います。)
ハインライン、ある意味偏った強烈な信念を持った人ですが「公平でありたい」という意味では古きよきアメリカ人の典型ではあったんでしょうね。
生前不遇だったディックを経済的に援助していたりしたみたいですし。
晩年の作品は内容紹介見ただけでもかなり強烈な偏りがありそうで引いているのですが・・・。
ミスター・アメリカンSF作家ですね。