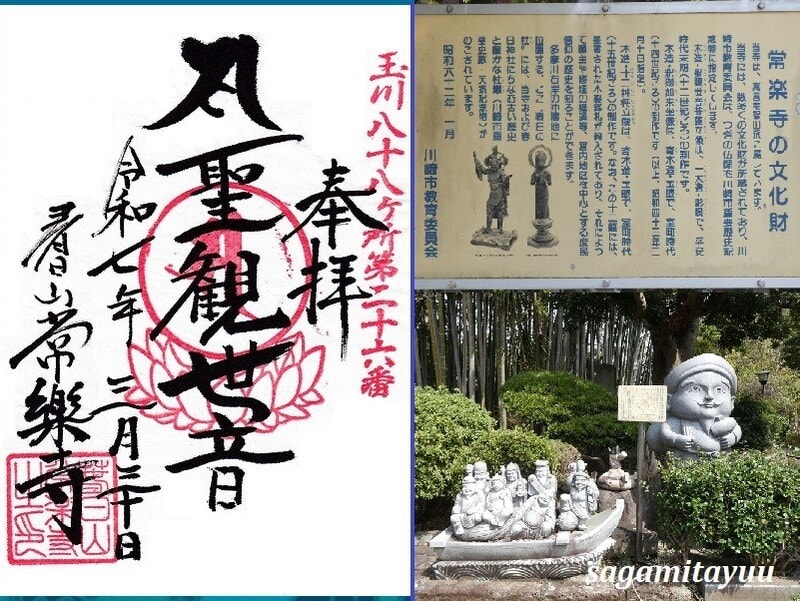川崎市中原区上小田中に浄土宗寺院「宝林山泉澤寺」は鎮座している。創建は延徳3年(1491)、開山は好善、開基は吉良頼高氏の菩提寺である。本尊は阿弥陀如来。当寺の前にはかつての中原街道の「県道45号線」が通っている。「中原街道」は東海道の脇街道で交通の要所であり、大正時代までは「門前市」が立ったほどである。当寺は元々(1491年=延徳3)は武蔵国多摩郡烏山村(世田谷区烏山)にあったが、天文19年(1550)に領主の吉良頼康によって現在地に移転した。江戸時代には上田元俊を初代とする旗本上田家の菩提寺となった。移転時に頼康は上丸子山王社に釈迦如来像を奉納し、武運長久を祈ったという。現在「釈迦如来像」は上丸子山王社の旧別当寺だった「大楽院」に移されている。「寺号標」(山門)より入山すると正面に入母屋造・銅板瓦棒葺の「本堂」(安永7年再興)、左に有形文化財で格式の高い袴腰付の形式の「鐘楼」がある。屋根は切妻造、瓦葺で建立年代は18世紀後期頃とされる。当寺は準西国稲毛三十三所観音霊場17番札所である。(2503)