
いわき市生涯学習プラザに飾られていました生け花。

季節を感じさせます。

以下、森先生のレジメ6枚。
「寛文十年(1671年)から延享二年(1745年)までの
年貢諸役(籾・大豆・金)の変遷」が
わかる史料です。






いろいろ変遷があり
今日の史料のもとになりました膨大な「内藤家文書」は現在
明治大学が所有しています。
その関係もあり
森先生のお話になったと思われます。

そのいくつかの現物を
パワーポイントで見せていただきました。

貴重な史料が
いわきから離れたことは残念だが。
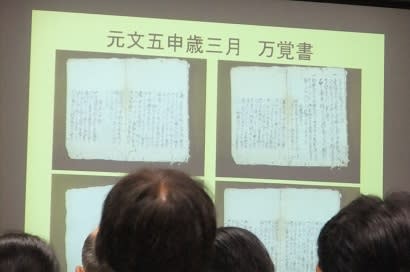
こうして散逸しないで
明治大学に所蔵されてよかった。
困難な藩財政状況に役人達は如何に立ち向かったのか
~元文一揆前後の内藤磐城平藩の財政状況と本〆役の役割~
講師は
森 朋久先生(明治大学博物館 研究調査員)
1)元文三年一機前後の財政状況
①寛文十年(1671年)から延享二年(1745年)までの
年貢諸役(籾・大豆・金)の変遷
② 一揆直前の年貢諸役の変遷
③ 町方・郷役金仕法と一揆
→内藤家文書の一部(享保十五年「御用勘定よりご勘定ニ付万覚書」より)
2)元文五年財政改革→一揆後の版財政立て直し
①一揆の代償と役人の不正・・・農民に譲歩→財政がさらに悪化。
→「正徳元卯七月 諸品覚書」より
② 倹約令の発令
③ 人的な組織の確立
④ 磐城役所での改革
⑤ 江戸役所での改革
⑥ 改革の成果(グラフ参照)
一揆の影響のために財政赤字を領内に転嫁できなかったので、
各役所諸向の倹約と各役所下級役人や
諸手当削減、諸役所における勘定事務の厳密化により
元文以降の財政赤字を目指した。
→元文五年以降収入は安定的に
・・・・改革は役立ったと!!
3)本〆役の新設
①一揆直後の人事刷新
②本〆役の職務
③元文五年改革での本〆役の役割
4)本〆役の系譜 本〆役設置以前の財政運営者
①藩財政前期の版財政運営
②本〆就任者・・・1、松賀正元
③本〆就任者・・・2、松賀伊織
④本〆就任者・・・3、島田理助
5)最後に
磐城から延岡へ転封まで
目立ったことはなく
天文五年以降は
それなりの成功を収めたと考えられると。
ですから
転封は幕府領との関係ではないのかと森先生は結論されました。
森先生
丁寧なレジメによる
貴重なお話ありがとうございました。
ファイナンス研究会
ITサポーターいわき
と今日は大忙し。
いわきは現在
大雨になりました。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます