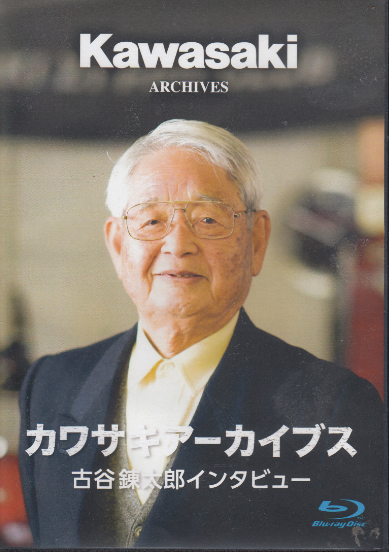2月11日、建国記念日である。
私たちが小学校の頃は『紀元節』であった。
『節』がどんな意味か解らなかったが、『節』のついた日は休みであった。
「天長節」4月29日や「明治節」11月3日があって、今もなお祭日としては残っている。
戦時中で、教育勅語も紀元節の歌詞も難しくて解らなかったが、小学生でも兎に角暗記して、覚えていた。
紀元節と言えば、
このような小学唱歌があって歌ったものである。
紀元節
作詞 高崎正風
作曲 伊沢修二
『小学唱歌 第一巻』明治25年(1892年)3月14日
一、
雲にそびゆるちほのねおろしに艸も木も
なびきふしけん大御世を仰ぐけふこそ楽しけれ
二、
うなばらなせるはにやすの池のおもよりなほひろき
めぐみのなみにあみし世を仰ぐけふこそたのしけれ
三、
天つひつぎのみくら千代よろづに動きなき
もとゐ定めしそのかみを仰ぐ今日こそたのしけれ
四、
空にかがやく日の本の萬の國にたぐひなき
國のみはしらたてし世を仰ぐけふこそ楽しけれ
間違いなく、小学唱歌なのに歌詞はこんなに難しいのである。
流石に2番からは覚えていないが、一番は今でも良く覚えている。
この感想が後ろに幾つかついていて、こんな意見である。
この楽曲に関する解説を投稿してください。
2008/02/11(月) 12:11 竹之上
紀元節を朗々と歌うと爽やかで気持ちが良い。
建国記念日など全然馴染めない。
2008/02/11(月) 13:17 kokko
今、歌っても格調の高い詩・メロディはいいですね。往時が懐かしいです。
2008/02/11(月) 15:06 春風
万葉の匂いが感じられ日本人のアイデンティティが高まる
格調のある詩文であります。
戦後生まれですが 日本人があまりにも歴史を忘れかけている嘆かわしい現状であります。
これは、昨年の紀元節の日のコメントだが、私もこの人たちに近い感想である。
何も戦前の体制などがいいということではなくて、
同じ日を、呼び名を変えるだけで、残すのなら、それも同じような意味合いで残すのなら、わざわざ変える意味もないように思う。
どこまでどのように遡ればいいのか解らぬが、
私の子供の頃は、昭和15年が紀元2600年であった。
紀元の年数で4で割れたら「うるう年」、昭和は1を足して4で割れたら「うるう年」とこどもの頃、習っていた。
私の年代は、日本史を習わなかった年代だと思う。
終戦が昭和20年、中学1年生であった。
中学、高校の頃までは、日本の歴史をどう教えるのか、先生のほうも解らなかったのでは、なかろうか?
歴史をちゃんと、習った覚えがない。
いまだに、『2600年もあったのに、何故700年も短くなって1950年か』と単純にそう思ったりしている。
最近では、やっと西暦にも慣れたのだが。
ただ、単純に
『雲にそびゆる高千穂の~』と言う歌詞も、その旋律も、懐かしいのである。