私は、いまさらマルクスなんか読んでも未来は何も見えないと考えている。このブログでもたびたびマルクスを批判してきた。それゆえ「資本論」がタイトルに入る本など、敬遠してほとんど読んでいなかった。しかしこの本に関しては、内容はほとんど環境問題についてということなので、読んでみた。
本の内容を簡潔に述べれば、晩年のマルクスは、『資本論』までに自ら構築した理論の誤りに気づき、成長神話を捨て、エコロジーの原則に立脚して、循環型で自然と調和していた資本主義以前の農村共同体を評価し、それを発展させる形での「脱成長コミュニズム」という境地に達していたということ。そして、その晩年のマルクスのビジョンを活かして未来社会を構想しようということである。
マルクスのビジョンは革命の前に地球を滅ぼす
『資本論』までのマルクスは、明らかに生産力至上主義者であり、成長賛美論者である。またマルクスは、プロレタリア革命を起こすために、農村共同体を解体して民衆のプロレタリア化を押し進めるという「資本の本源的蓄積過程」は徹底的に推し進められるべきとし、それが歴史の必然であると考えていた。
地球上すべての地域の、自然と共生したライフスタイルを持っていた農村人口が、生産手段の全てを失い、寄る辺のないプロレタリアートの大群になって析出されるのが歴史法則だというのだから、はっきり言ってマルクスの考えは、新自由主義者のそれと同じである。すべての労働者が正社員ですらない派遣社員になるのが理想郷と考える新自由主義者とマルクスの、いったい何が違うのかといえば、その後に革命が起こって別のユートピアが出現するのか否かというだけである。
そのような「資本の本源的蓄積過程」なるものを進めれば、プロレタリア革命など起こる前に、地球そのものが、人類が生存不可能な状態にされ、人類は滅び去るだろう。それゆえ、斎藤氏は従来の「マルクス主義」と呼ばれているものを乗り越えねばならないと考える。それはよい。
晩年のマルクスと農村共同体
晩年のマルクスは生産力至上主義的な考えを捨てていた。著者が力説する通り、それは事実であろう。資本主義以前の農村共同体を解体するのではなく、むしろそれを維持し、発展させる形で、共産主義社会に至ることが可能だと考えるようになっていた。
これはロシアのナロードニキの女性革命家のヴェーラ・ザスーリチに宛てた手紙の中でなどで論じているビジョンである。本書も、この手紙やマルクスのノートなどを手掛かりに晩年のマルクスの思想的大転回を明らかにしようとしている。
私は農学部出身であり、東南アジアの熱帯林地域で農村共同体やコモンズの研究もしていたから、いまから25年も前の大学院生時代にマルクスのザスーリッチへの手紙などは読んでいた。それを読んで「晩年のマルクスはずいぶんまともなになっていたのだな」とは思った。しかし、「だから何なの?」という感じであった。
亡くなる直前の老人が、過去の自らの誤りを認めて改心したところで、その晩年の思想については何も著作を残していない。体系だって何も論じていないのだ。そんなものを掘り下げようとしたところで、未来を展望する力にはならない。それに「マルクス主義」と呼ばれる彼の思想は、『資本論』までの著作によって知られ、認識されている。晩年のそれではない。
それにマルクスは文献の中だけで、共同体の研究を行っているので、共同体に対する理解に誤りが多いのだ。それゆえアジアの農山村で、現実に存在する「共同体」の機能を実証的に研究した方がはるかに有益だと、大学院時代の私は思った。だから文献に拘泥せずに野外へ出て研究を行った。
だいたいマルクスが、ロシアのナロードニキとの論争を経てそのような境地に達成したのなら、当のナロードニキの再評価でもした方がよいのではないか。ナロードニキの思想家のピョードル・クロポトキンも、晩年のマルクスが到達したという「脱成長コミュニズム」と親和的な思想を述べている。日本だったら、エコロジーに基づく共同体主義の思想家として安藤昌益でも再評価すべきだろう。
晩年のマルクスが断片的に述べた思想については、自然生態系を無視して議論を進めてきた経済学者にありがちな成長神話を捨て、「エコロジズム」に至った一事例として取り上げればよい。「これこそマルクス主義だ」などと大げさに言ってはいけない。実際、それほどの価値ある思想とは思えない。
自由放任主義でマルクスとは対極的と見なされるジョン・スチュアート・ミルも、後年に成長神話を批判するようになり、経済成長しない「定常状態」を理想と考えるようになっていた。ミルのそれも、晩年のマルクスが至った境地とそれほど遠くない。つまりマルクスもミルも、自然生態系との共生のために成長神話を捨てるに至った経済学者の一人程度に位置づければよい。
晩年のマルクスも、せいぜい「エコロジズム」の先駆者の一人程度に等身大の評価をし、過大評価せず、これからの世代が発展させていくべきヒントを与えてくれた程度に位置付ければよいのだ。というのも「マルクス主義」の名を冠しただけで、運動に分断と対立を生むことになる。それこそ資本主義の延命を利する利敵行為になりかねないからだ。
著者の「コモン」理解は観念論
マルクス本人は文献の中だけで「共同体」の研究をしているので、人びとの生活の場である現実の「コモン」に対する理解が浅い。その理解の浅さというか観念性を、著者の斎藤氏も踏襲している。たとえば「本源的蓄積が始まる前には、土地や水といったコモンズは潤沢であった。・・・共同体の構成員であれば、誰でも無償で必要に応じて利用できるものであった」などと述べている(242頁)。これは現実を知らないことからくる、観念的ユートピアの表明でしかない。
著者は、資本主義以前は連綿として、「潤沢なコモン」が続いていて、コモンズの解体の中で資源の希少性が高まったかのように述べているが、明白な間違いである。資本主義以前であっても、資源は希少化していた。資本主義以前も、それぞれの時代によって、コモンはあったりなかったり、そのルールも強まったり弱まったりしていたのだ。
「コモン」は、資源の希少化にともなって生成される。たとえば日本の農山村共同体の入会林の管理慣行なども、江戸時代の中期以降に発達したのだ。薪炭材や刈敷などが潤沢に得られた中世には、入会林など存在しない。江戸時代初期に人口密度が高まり、列島の中での自給圏内での成長が限界に達し、資源が希少化し、村落間で、さらに村落内で資源利用をめぐる紛争が頻発化したからこそ、厳密な境界やルールを持つコモンズとしての入会林が生成されていったのだ。
灌漑用水だって潤沢になど得られなかったからこそ、コモンとして管理された。それはたえず紛争を生み出す緊張関係を伴うものだった。川の上流と下流で、命がけの灌漑用水の奪いあいがあった。資源が希少だからこそ「コモン」が発生したのであって、潤沢だから発生したのではない。
的外れなグリーン・ニューディール批判
本書はSDGs批判とグリーン・ニューディール批判から始まる。冒頭いきなり「SDGsは大衆のアヘンである」から始まるのである。私は「マルクス主義こそ大衆のアヘンである」と言い返したい。
本来は味方につけるべきものを罵倒して敵に回してしまうのが、マルクス本人の独善性であり、性癖であった。著者は、従来の「マルクス主義」と呼ばれていたものを乗り越えたいようなのだが、味方にすべきものまで敵に回すような物言いをするところは、「マルクス主義」そのものであるといえる。
グリーン・ニューディール批判にしても、批判対象がトーマス・フリードマンなのだから的外れこの上ない。トーマス・フリードマンは、新自由主義の旗手として活躍してきたのであって、グリーン・ニューディールの旗手でも何でもない。フリードマンは、新自由主義が旗色悪くなってきたので、グリーン・ニューディールに迎合的なことを言い出しているだけの単なる変節漢でしかない。
まともなグリーン・ニューディールの旗手、たとえばナオミ・クラインの著作を読めばいい。彼女は、明確に資本主義に明日はないと考え、それを乗り越えるためのステップとして「グリーン・ニューディール」を論じている。
そう思ったら、斎藤幸平氏は、ナオミ・クラインの『地球が燃えている』を絶賛して推薦しているではないか。ならば、本書において、ナオミ・クラインではなく、トーマス・フリードマンを代表的な論客のようかのようにしたフェイク論法でグリーン・ニューディールを批判したことを謝罪すべではないだろうか。
私も、欧米でグリーン・ニューディールなんて言われ出す8年前から、エコロジカル・ニューディール(発案者は故力石定一氏)として同種のことを論じているが、斎藤氏と同様、グリーン・ニューディールで地球が救えるとなんて思っていない。さらにその先が必要だと思っている。しかし、不可欠で重要なファースト・ステップなのだ。それを批判しても何も生まれない。
まずは化石燃料なしでも生活を成り立たせるための技術とインフラが一通り出揃わなければ、その先には進めない。その技術とインフラの整備のために、まずは全力で投資を集中させよと言っているのだ。その間は、その投資によって経済成長する。最終的には脱成長すべきと思うが、当面は脱化石燃料革命を達成するための技術や社会インフラへの投資が必要である。
それが出揃って、脱成長が可能になる。化石燃料なしで生きられるようになれば、成長なんかしなくても、人びとが安心して暮らせる基盤があるのだから、資本主義は崩壊しようがマイナス成長になろうが苦にならないだろう。しかし、化石燃料依存症という深刻な病気を終わらせるための移行段階を経ずして、「脱成長コミュニズム」なんて言ってみたことろで、それこそ社会のカタストロフィしか生み出さないだろう。
マルクス的な独善性からは何も生まれない。まずは人の名前に「主義」とつけて崇拝しようとする態度から脱却することだろう。
本の内容を簡潔に述べれば、晩年のマルクスは、『資本論』までに自ら構築した理論の誤りに気づき、成長神話を捨て、エコロジーの原則に立脚して、循環型で自然と調和していた資本主義以前の農村共同体を評価し、それを発展させる形での「脱成長コミュニズム」という境地に達していたということ。そして、その晩年のマルクスのビジョンを活かして未来社会を構想しようということである。
マルクスのビジョンは革命の前に地球を滅ぼす
『資本論』までのマルクスは、明らかに生産力至上主義者であり、成長賛美論者である。またマルクスは、プロレタリア革命を起こすために、農村共同体を解体して民衆のプロレタリア化を押し進めるという「資本の本源的蓄積過程」は徹底的に推し進められるべきとし、それが歴史の必然であると考えていた。
地球上すべての地域の、自然と共生したライフスタイルを持っていた農村人口が、生産手段の全てを失い、寄る辺のないプロレタリアートの大群になって析出されるのが歴史法則だというのだから、はっきり言ってマルクスの考えは、新自由主義者のそれと同じである。すべての労働者が正社員ですらない派遣社員になるのが理想郷と考える新自由主義者とマルクスの、いったい何が違うのかといえば、その後に革命が起こって別のユートピアが出現するのか否かというだけである。
そのような「資本の本源的蓄積過程」なるものを進めれば、プロレタリア革命など起こる前に、地球そのものが、人類が生存不可能な状態にされ、人類は滅び去るだろう。それゆえ、斎藤氏は従来の「マルクス主義」と呼ばれているものを乗り越えねばならないと考える。それはよい。
晩年のマルクスと農村共同体
晩年のマルクスは生産力至上主義的な考えを捨てていた。著者が力説する通り、それは事実であろう。資本主義以前の農村共同体を解体するのではなく、むしろそれを維持し、発展させる形で、共産主義社会に至ることが可能だと考えるようになっていた。
これはロシアのナロードニキの女性革命家のヴェーラ・ザスーリチに宛てた手紙の中でなどで論じているビジョンである。本書も、この手紙やマルクスのノートなどを手掛かりに晩年のマルクスの思想的大転回を明らかにしようとしている。
私は農学部出身であり、東南アジアの熱帯林地域で農村共同体やコモンズの研究もしていたから、いまから25年も前の大学院生時代にマルクスのザスーリッチへの手紙などは読んでいた。それを読んで「晩年のマルクスはずいぶんまともなになっていたのだな」とは思った。しかし、「だから何なの?」という感じであった。
亡くなる直前の老人が、過去の自らの誤りを認めて改心したところで、その晩年の思想については何も著作を残していない。体系だって何も論じていないのだ。そんなものを掘り下げようとしたところで、未来を展望する力にはならない。それに「マルクス主義」と呼ばれる彼の思想は、『資本論』までの著作によって知られ、認識されている。晩年のそれではない。
それにマルクスは文献の中だけで、共同体の研究を行っているので、共同体に対する理解に誤りが多いのだ。それゆえアジアの農山村で、現実に存在する「共同体」の機能を実証的に研究した方がはるかに有益だと、大学院時代の私は思った。だから文献に拘泥せずに野外へ出て研究を行った。
だいたいマルクスが、ロシアのナロードニキとの論争を経てそのような境地に達成したのなら、当のナロードニキの再評価でもした方がよいのではないか。ナロードニキの思想家のピョードル・クロポトキンも、晩年のマルクスが到達したという「脱成長コミュニズム」と親和的な思想を述べている。日本だったら、エコロジーに基づく共同体主義の思想家として安藤昌益でも再評価すべきだろう。
晩年のマルクスが断片的に述べた思想については、自然生態系を無視して議論を進めてきた経済学者にありがちな成長神話を捨て、「エコロジズム」に至った一事例として取り上げればよい。「これこそマルクス主義だ」などと大げさに言ってはいけない。実際、それほどの価値ある思想とは思えない。
自由放任主義でマルクスとは対極的と見なされるジョン・スチュアート・ミルも、後年に成長神話を批判するようになり、経済成長しない「定常状態」を理想と考えるようになっていた。ミルのそれも、晩年のマルクスが至った境地とそれほど遠くない。つまりマルクスもミルも、自然生態系との共生のために成長神話を捨てるに至った経済学者の一人程度に位置づければよい。
晩年のマルクスも、せいぜい「エコロジズム」の先駆者の一人程度に等身大の評価をし、過大評価せず、これからの世代が発展させていくべきヒントを与えてくれた程度に位置付ければよいのだ。というのも「マルクス主義」の名を冠しただけで、運動に分断と対立を生むことになる。それこそ資本主義の延命を利する利敵行為になりかねないからだ。
著者の「コモン」理解は観念論
マルクス本人は文献の中だけで「共同体」の研究をしているので、人びとの生活の場である現実の「コモン」に対する理解が浅い。その理解の浅さというか観念性を、著者の斎藤氏も踏襲している。たとえば「本源的蓄積が始まる前には、土地や水といったコモンズは潤沢であった。・・・共同体の構成員であれば、誰でも無償で必要に応じて利用できるものであった」などと述べている(242頁)。これは現実を知らないことからくる、観念的ユートピアの表明でしかない。
著者は、資本主義以前は連綿として、「潤沢なコモン」が続いていて、コモンズの解体の中で資源の希少性が高まったかのように述べているが、明白な間違いである。資本主義以前であっても、資源は希少化していた。資本主義以前も、それぞれの時代によって、コモンはあったりなかったり、そのルールも強まったり弱まったりしていたのだ。
「コモン」は、資源の希少化にともなって生成される。たとえば日本の農山村共同体の入会林の管理慣行なども、江戸時代の中期以降に発達したのだ。薪炭材や刈敷などが潤沢に得られた中世には、入会林など存在しない。江戸時代初期に人口密度が高まり、列島の中での自給圏内での成長が限界に達し、資源が希少化し、村落間で、さらに村落内で資源利用をめぐる紛争が頻発化したからこそ、厳密な境界やルールを持つコモンズとしての入会林が生成されていったのだ。
灌漑用水だって潤沢になど得られなかったからこそ、コモンとして管理された。それはたえず紛争を生み出す緊張関係を伴うものだった。川の上流と下流で、命がけの灌漑用水の奪いあいがあった。資源が希少だからこそ「コモン」が発生したのであって、潤沢だから発生したのではない。
的外れなグリーン・ニューディール批判
本書はSDGs批判とグリーン・ニューディール批判から始まる。冒頭いきなり「SDGsは大衆のアヘンである」から始まるのである。私は「マルクス主義こそ大衆のアヘンである」と言い返したい。
本来は味方につけるべきものを罵倒して敵に回してしまうのが、マルクス本人の独善性であり、性癖であった。著者は、従来の「マルクス主義」と呼ばれていたものを乗り越えたいようなのだが、味方にすべきものまで敵に回すような物言いをするところは、「マルクス主義」そのものであるといえる。
グリーン・ニューディール批判にしても、批判対象がトーマス・フリードマンなのだから的外れこの上ない。トーマス・フリードマンは、新自由主義の旗手として活躍してきたのであって、グリーン・ニューディールの旗手でも何でもない。フリードマンは、新自由主義が旗色悪くなってきたので、グリーン・ニューディールに迎合的なことを言い出しているだけの単なる変節漢でしかない。
まともなグリーン・ニューディールの旗手、たとえばナオミ・クラインの著作を読めばいい。彼女は、明確に資本主義に明日はないと考え、それを乗り越えるためのステップとして「グリーン・ニューディール」を論じている。
そう思ったら、斎藤幸平氏は、ナオミ・クラインの『地球が燃えている』を絶賛して推薦しているではないか。ならば、本書において、ナオミ・クラインではなく、トーマス・フリードマンを代表的な論客のようかのようにしたフェイク論法でグリーン・ニューディールを批判したことを謝罪すべではないだろうか。
私も、欧米でグリーン・ニューディールなんて言われ出す8年前から、エコロジカル・ニューディール(発案者は故力石定一氏)として同種のことを論じているが、斎藤氏と同様、グリーン・ニューディールで地球が救えるとなんて思っていない。さらにその先が必要だと思っている。しかし、不可欠で重要なファースト・ステップなのだ。それを批判しても何も生まれない。
まずは化石燃料なしでも生活を成り立たせるための技術とインフラが一通り出揃わなければ、その先には進めない。その技術とインフラの整備のために、まずは全力で投資を集中させよと言っているのだ。その間は、その投資によって経済成長する。最終的には脱成長すべきと思うが、当面は脱化石燃料革命を達成するための技術や社会インフラへの投資が必要である。
それが出揃って、脱成長が可能になる。化石燃料なしで生きられるようになれば、成長なんかしなくても、人びとが安心して暮らせる基盤があるのだから、資本主義は崩壊しようがマイナス成長になろうが苦にならないだろう。しかし、化石燃料依存症という深刻な病気を終わらせるための移行段階を経ずして、「脱成長コミュニズム」なんて言ってみたことろで、それこそ社会のカタストロフィしか生み出さないだろう。
マルクス的な独善性からは何も生まれない。まずは人の名前に「主義」とつけて崇拝しようとする態度から脱却することだろう。














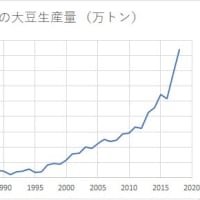

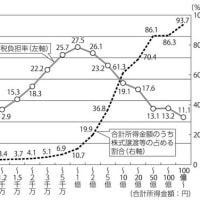



私は、大学の教養科目で左派の社会学者の方と接する機会が何度かあったのですが、「肌色」は人種差別的な言葉だから「薄橙色」を使うべきだとか、「外人」は排外主義的な言葉だから使用するべきではないとか、そういった「言葉狩り」的な主張を耳にして、「『夷狄』のような明らかに排外主義的な言葉ならともかく、それくらいは別にいいではないか。『外人さん』と親しみを込めて言ったりするし、小説や脚本に『薄橙色』と書いて、読む人にすんなりと伝わるのか?」などと思ったものでした。
一方、インターネットに目を向けてみると、アニメや漫画を愛好する、いわゆる「オタク」の人々は、なぜか表現規制に反対してきた枝野氏が党首の立憲民主党(もちろん、一枚岩ではないので、全党員が規制反対派というわけではないでしょうが)を攻撃し、憲法レベルで表現の自由を脅かす自民党を支持している傾向が見られます。
これはおそらく、リベラル=表現規制派、というイメージが先行しているためでしょう。
(自民党の麻生氏が「アニメ好き、漫画好き」というキャラで売っているのもあるでしょうが)
無論、差別やヘイトスピーチは許されるべきではないと私も思いますが、「政治的に正しくない表現は、どんなに些細なものでも全て規制、矯正してやる」といった姿勢では、無駄に反感を買い、敵を増やすだけではないかと私は思います。
おっしゃる通りだと思います。私も学生時代から、「左派」の不寛容性をイヤほど味わってホトホトあいそがつきました。そして、その不寛容性のかなりの部分、マルクスのパーソナリティそのものに起因すると考えています。
左派は「脱マルクス」しない限り再生しないでしょう。アメリカのサンダース支持の左派たちも、社会主義とは言っても、別にマルクスになんてこだわりませんから。サンダース本人も、社会主義は強調しても、マルクス主義なんて決して言わない。マルクスが運動に分断をもたらす思想でしかないことをよく分かっているのだと思います。
雑誌『世界』2020年11月号の斎藤幸平氏の論考を見て、グレタという名前をポジティブに牽いているのがうさんくさいという印象がのこっておりました。
書名から資本主義経済社会を人類学的視点から見る試みかと想像して多少興味はもっておりましたが、そうではないと御記事で知りながら、もてはやされるワケを知りたいと三度読みました。
斎藤幸平氏の脱成長という措定は、企業用語と化してウンザリされはじめたSDGsへの肘打ちとあわせて微妙によい落としどころ突き、書名との相乗効果で見事に売れ線に乗っています。里山論連想まで動員する腕利きのガス抜き商業ジャーナリストです。感心しました。
生産力の発展拡大と歴史の発展をリンクさせる生産力史観の言語的オリジンは、旧訳聖書『創世記』なのでしょう。生産力と生産関係が対応関係にあるという歴史的認識から、定量的な生産力が生産関係を決定する、定量的生産力の発展拡大が生産関係を変革する、という措定を引き出すのは強引ではないでしょうか。この公理を転覆する人類学的研究が現れると期待します。脱成長と逃げるのではなく。
あえて言えば、生産関係がそれに対応する生産力をもたらすという仮説の措定がむしろより自然であり、資本主義的生産関係は資本主義的生産力をもたらす、とするのが眼前に見てきた事実に適合します。
資本主義的生産力とはGNPであれGDPであれ、総生産の計算によるとされて、この定量的評価がすべてを支配するのが世界の現実です。資本主義の発展によって二度の世界大戦が人類史上はじめての総力戦となり、計算された生産力すなわち総生産が決定的なキィとして躍り出て現在に至るわけです。
納税による国家支出と、最終的に消費者につけが回ってくる企業設備投資を含めて、消費者大衆が事業者企業に支払う貨幣総量が総生産であると認識しています。これが資本主義的生産力であって、事業化されない家事、介護は度外視され、貨幣取引外の人間的活動は生産にはなりません。
生産関係が変化すると、生産力の定性的内容が対応して変化するのではないでしょうか。生産関係が何によって変化してきたのか、何によって変化するのか、それは経済学ではなく人類学の課題であると直感しているのですが。