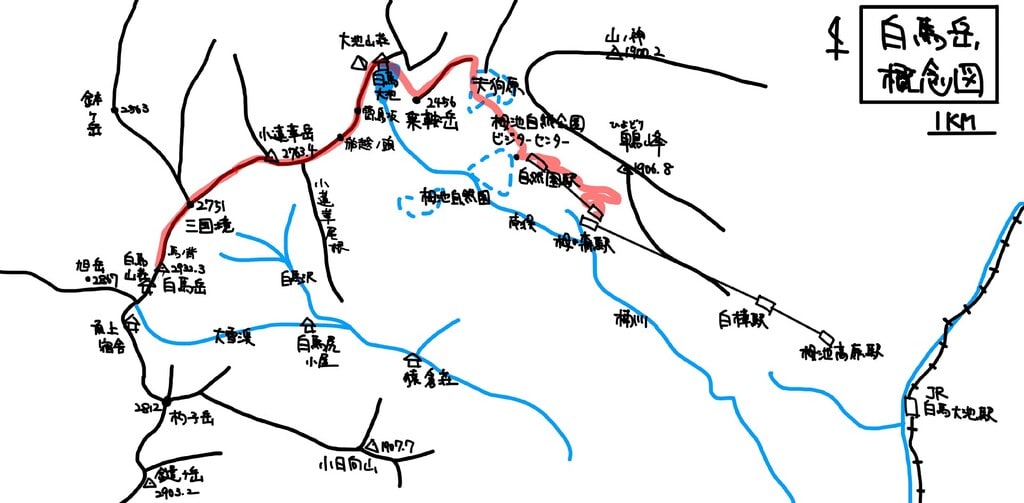2/15(土) 天気:快晴
09:10 中の湯 着
09:25 発
11:10 河童橋
12:40 明神
14:15 徳沢 着
18:30 就寝
岩井先頭。17日以降寒波で天候が荒れる予報のため、前日に決めたとおり徳沢より上の2220m地点程度まで行くことを目標に中の湯を出発した。快晴で雲ひとつなく、気温も-5℃程度で登山者多き。上高地トンネルを抜けてアイゼンを履き、河童橋からわかんに履き替えた。河童橋以降は登山者とほぼすれ違わなかった。トレースはあった。河童橋まで1時間半、そこから徳沢まで2時間の予定だったが竹田のスピードが上がらず、徳沢で幕営することにした。徳沢は我々以外なし。徳沢を拠点にアタックすることに決定し、3時起き4時発として18:30に就寝。
2/16(日) 天気:快晴
03:00起床
03:48徳沢発
04:06竹田撤退(18min後)
07:10長塀山
07:55現在地確認
08:13蝶ヶ岳山頂着
08:40蝶ヶ岳ヒュッテ発
09:30蝶槍
10:15蝶ヶ岳ヒュッテ着
10:30蝶ヶ岳山頂
12:48徳沢帰幕
前日のヤマテンで、午前中の天候は安定する見込みだが午後以降の天候が怪しいという情報を得ていたため、徳沢から直接蝶ヶ岳までのアタックを行った。コースタイム的に蝶槍まで行くのは厳しいと考え、アイゼンは持たず軽量化を優先した。前日の快晴で別パーティが蝶ヶ岳アタックをしており、夜に雪があまり降らなかったこともあってトレースはかなり明瞭だった。雪の深さは膝ほどであったが、トレース上は雪が踏み固められていて非常に歩きやすかった。
隊列は前から岩井-竹田-山本の順で出発。登山口から数分で急登が現れる。この時点で既に竹田のペースが上がらず、1分ほどおきに立ち止まってしまったりしていた。
行動開始から18分、竹田から「このままだと山頂が踏めないだろうから自分だけ撤退したい」との報告を受ける。コースタイム上では12時までに山頂に辿り着けるかギリギリであった。
幸いまだ登山口からあまり離れていなかったため、体調不良その他の異常がないことを確認して竹田だけ先にテント場に戻ってもらう判断をした。
その後岩井と2人で急登を登り続ける。基本的にはトレースが残っているが一部消えてしまっている場所もあったため、ピンクテープや消えていないトレースを探して進んだ。先頭は適宜交代しながら行動した。
その後も地図を見ながら進んでいたが、樹林帯を進んでいくうちに現在地がはっきりしなくなる。トレースが残っていることやピンクテープが稀にあることから進行方向に不安はなかったが、赤旗を置くポイントをこの時点で通り過ぎてしまっていた。急登を登り切って2000m付近の広場へ。そこで別の登山者とすれ違う。テントも広場にあった。その後トレースが消え、ピンクテープを頼りに樹林帯を登り続ける。そのうちに空が白んできたため視界が開け、ルーファイの難易度は下がった。
登り始めてから約3時間半、長壁山に到着する。10mほど初めての下りがあったため、この先が長壁山のコルなのではないかと岩井と話し合うも、夏道のコースタイムが3時間であったため、2100mの広場がここなのではないかという結論に。テント跡もそこで発見した。
長塀山のコルから少し歩くと頂上から下ってきた別の登山者とすれ違う。蝶ヶ岳ヒュッテにテント泊をしていたとのことだった。少し視界が開けてきたため、YAMAPを参考にして現在位置を確かめると妖精の池付近にいることがわかり、自分たちが想像の倍近いペースで進んでいたことが明らかになった。
少し進むと確かに蝶ヶ岳の山頂が見え、現在位置が正しいことが確認できた。ルーファイミスを反省しつつ、そのまま山頂へ。山頂付近は強風のためか雪が少ししか積もっておらず、ハイマツが一部地面を構成していた。山頂碑で写真を撮った後ヒュッテへ。ヒュッテは冬季小屋があり、北岳の池山小屋のように中でテントが張れる大きさだった。トイレもあったので非常に使いやすい幕営場所だと感じた。
ヒュッテで岩井と話し合い、ワカンではあるが蝶槍へ行ってみようという結論に。サングラスを外してゴーグルをつけ、ワカンでの歩行が危険そうな箇所があれば引き返すことも視野に入れ、ヒュッテを発った。
蝶槍までの稜線は明瞭で、幅も道中ずっと余裕があった。行動中徐々に風が強くなり、最終的には20m/s近い風が吹いていた。風に飛ばされぬよう慎重に歩を進め、蝶槍へ到着。雲一つない晴天で非常に景色がよかった。
その後ヒュッテに引き返し、休憩をとったのちに徳沢へ降りる。帰りもずっと晴れておりスムーズに行動できた。
2/17、アタック(山本-竹田) 天気:晴れのち雪
▪️行程
4:40 徳沢 / 1562 m
7:35 長塀山 / 2565 m
8:00 妖精ノ池 / 2615 m
8:30 蝶ヶ岳山頂 / 2677 m
11:25 徳沢
▪️詳細
3:00起床。昨夜に比べ外は寒かったが、風はなく星が見えるほど天気が良かった。午後から天気が悪化することをヤマテンで把握していたため、10:00時点あるいは天気が悪化した段階で撤収する取り決めをして山に登った。ワカンを装着し、山本(CL)が先頭で、竹田が次に続いた。
取り付きから東に伸びる登山道(1526 - 2256 m)は、トラバース気味の登りや斜度が50度以上あると思える程の急登が続いた。トラバース道は、尾根の傾斜が大きいため足を掬われれば一気に数十mは滑落するように思われた。急登は、キックステップかつ手(ピッケル)を使わないと足元の雪が崩れて登れない程だった。一方、雪が締まっていた(登山客で踏み固められた後、ほとんど降雪がなかった)ことと、トレースが明瞭であったため、前日に比べペースは落ちていたものの全体的な行動時間に支障はきたさなかった。前述の急登は2000m付近にある広場までで、それ以降は比較的緩やかな登りが続いた。積雪は登山靴が完全に埋没するくらいにはあったため、ワカンの雪上歩行の練習には丁度よかった。4:00(1700m付近)、4:30(1800m付近)、5:30(2000m付近)で6〜7分程の休息を取った。
ある程度行動したところで、針路が東から北東に切り替わった(2256 - 2565 m)のと同時に、日が昇り始めた。東の空(松本方面)は以前として快晴が続いたが、西の空(高山方面)は薄い雲が覆うようになっていった。長塀山に近づくにつれて傾斜は緩やかになり、樹林は次第に低くかつ疎になっていった。トレースは引き続き明瞭に残っていた。途中、先日長塀山でテン泊していたというソロの登山者とすれ違った。6:30(2300m付近)、7:30(長塀山付近)で6〜7分程の休息を取った。
長堀山から妖精ノ池への道は、50m程降ってコルを通過し、再び登る形で続いた。長塀山の標札は雪で埋没していたが、登り一辺倒の登山道に現れた急な降りの手前のピークを山頂であると考えると良い。そのピークからは蝶ヶ岳の山体がよく臨めた。50m程の降りではトレースが掻き消されていたため、往路で唯一、若干の道迷いを起こした。妖精ノ池まで緩やかな登りが続くが、しばしば斜面をトラバースする箇所が散見された。妖精ノ池もまた目印になる人工物がないため、盆地状かつ東側に開けた雪原が見えたらそこに辿り着いたと考えて良い。危険箇所として、長堀山付近の尾根の東側に雪庇が発達していたことが挙げられる。西側の樹林帯に逃げるように通過されたい。池に着く頃にはいよいよ天気が怪しくなり、空は一面雲に覆われ、雪がちらつき始めた。
妖精ノ池の後もしばらくは低い樹林帯を歩いた。森林限界は2660m付近で、山頂(2677m)の極手前であった。森林限界を抜けた後は一気に冷たいブリザードが吹き付け、蝶槍は見えず、赤い屋根の蝶ヶ岳ヒュッテだけがかろうじて確認できた。山頂までは積雪と埋没したハイマツのミックス帯が続いた。その際、ツリーフォールおよび躓きに注意されたい。山頂は開けており、標札が3つもあった。証拠写真を撮るためにグローブを脱いだが、十数秒後には完全に手先の感覚が無くなる程外気温は低かった。また少しの滞在で眉毛、睫毛、髭のありとあらゆる毛が凍りついた。山頂の気温はマイナス20℃以下、風速は20m/s以上はあったように思える。
登頂後、一気に視界が悪くなったため、写真を撮り終えた後、急いで樹林帯まで退避ないし下山を始めた。途中、ホワイトアウトで先頭の姿が見えなくなるアクシデントがあったが、樹林帯がすぐそこだったため事なきを得た。樹林帯は比較的風が穏やかであったが、それでも往路に比べ格段に風雪が強くなり、トレースは薄くなるか完全に掻き消されていた。復路はそのあるかないかのトレースと赤旗・ペンキ(◯、×、→)を頼りに慎重に降った。基本はトレースを頼りに降ったが、しばしばそれを見失い、その度にトレースあるいは目印を協力しながら探した。途中、1700m付近で完全に目印を見失い、YAMAPを参考にした。復路は8:40(森林限界)9:50(2200〜2300m付近)に休息を取った。
2/18 天気:小雪
05:00 起床
07:18 徳沢 発
11:55 中の湯 着
岩井先頭。ゆっくりと準備をし7時発の予定だったが凍ったテントに苦難し18分ほど遅れる。微かなトレースあり。主に赤旗を頼りに進んだ。河童橋に来るひとはいるにはいた。