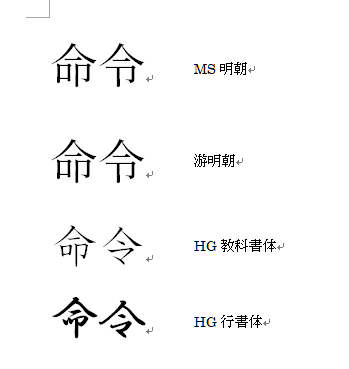渋谷のスクランブル交差点は、何かと人が集まる場所のようです。サッカーの日本代表の試合がある毎、若者は渋谷に繰り出し、歩行者用信号が青になるたび四方から集まってハイタッチをして喜びを表現していました。サッカーに限らず大晦日やハロウィンにも人が集まり、集まるだけでなく、一通り大騒ぎをするのが恒例のようになりつつあります。今回の、平成から令和への幕開けも、人はスクランブル交差点を目指し、カウントダウン前から大熱狂に包まれました。熱狂している人の殆どは、天皇制とか歴史を紐解いて国の成り立ちをどうとか…といった事には無関心で、ただ何かあると騒がなければ損…としか考えていないようで、後には大量のごみが残されたようです。
世界でも独自の元号を持つ国は、日本だけだと聞き及びます。当然、元号不要論も耳に入ります。新聞の多くは西暦年をメインに記述し、元号は括弧書きのようです。他国の人と話すにも、元号は西暦年に置き換える必要があります。生年月日を西暦年で記述する人も増えています。が、多くの日本人は、西暦年と和暦年の2種を、器用に変換し使い分けているようです。現代は、元号とイデオロギーは完全に乖離しており、和暦も無色透明で、ある種の国が危惧するような事は殆ど存在しないかと思われます。
日本人にとっての「元号」は、単に「そこにあるもの」。当たり前のように存在しているもののように思います。それでも、元号にはある種の効用があるように思います。それは、過去を一掃する事のできる節目としての効用です。西暦は、イエス・キリストが生まれたとされる年の翌年を元年としています。ADはAnnno Dominiの略称で「主の年に」という意味を持つのだそうです。それ以来、歴史は綿々と続いており、年始にはこれまでを一掃する「新しい」感があるにせよ、「とき」に区切りはありません。それに対して、日本は諸外国の年始よりも「正月」を特別なものとしてとらえる感覚が強いようですし、改元には連綿と続く日々を突然リセットして、白紙の気持ちに戻す感が強くある気がします。日本人は、昨日までを「白紙に」、これまでを水に流すことが上手なのかも知れません。それはある意味では無責任で、ある意味では前向きな日本人のバイタリティーのようにも思われます。
丁寧に生きたいと思います。
世界でも独自の元号を持つ国は、日本だけだと聞き及びます。当然、元号不要論も耳に入ります。新聞の多くは西暦年をメインに記述し、元号は括弧書きのようです。他国の人と話すにも、元号は西暦年に置き換える必要があります。生年月日を西暦年で記述する人も増えています。が、多くの日本人は、西暦年と和暦年の2種を、器用に変換し使い分けているようです。現代は、元号とイデオロギーは完全に乖離しており、和暦も無色透明で、ある種の国が危惧するような事は殆ど存在しないかと思われます。
日本人にとっての「元号」は、単に「そこにあるもの」。当たり前のように存在しているもののように思います。それでも、元号にはある種の効用があるように思います。それは、過去を一掃する事のできる節目としての効用です。西暦は、イエス・キリストが生まれたとされる年の翌年を元年としています。ADはAnnno Dominiの略称で「主の年に」という意味を持つのだそうです。それ以来、歴史は綿々と続いており、年始にはこれまでを一掃する「新しい」感があるにせよ、「とき」に区切りはありません。それに対して、日本は諸外国の年始よりも「正月」を特別なものとしてとらえる感覚が強いようですし、改元には連綿と続く日々を突然リセットして、白紙の気持ちに戻す感が強くある気がします。日本人は、昨日までを「白紙に」、これまでを水に流すことが上手なのかも知れません。それはある意味では無責任で、ある意味では前向きな日本人のバイタリティーのようにも思われます。
丁寧に生きたいと思います。