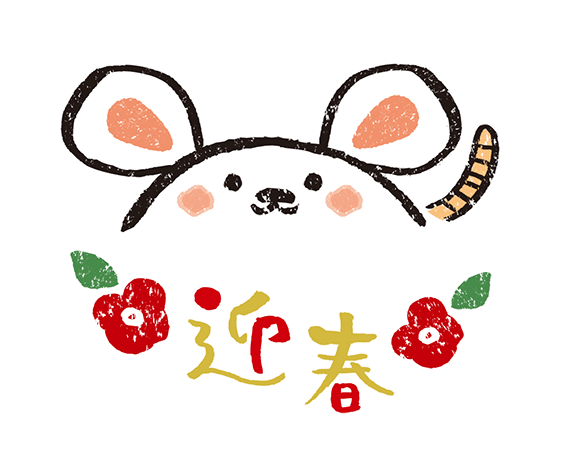随分、ず~いぶん、間が空いてしまいました。その間、度々ご訪問くださった方々、どうしたのかな?と心配をいただいた方々、申し訳ありませんでした。こんな拙いブログですが、ほんの少し社会と繋がっている窓口として、大切にしてきた場所なので、「いずれ更新」と閉じずに放置しておりました。
詳しくは伏せますが、家族が入院しており、なんやかや…と諸事情に振り回されている数か月で、ブログを更新する余裕が無かったというのが本音です。歳は重ねたくないものです。が、仕方ありませんね。これからは自分自身も含めて、段々坂道を下っていく時期です。急こう配に加速度がついて転がり落ちないようにしなければ…。「どう生きるか?」は、「どう人生を終えるか?」と同義であることを、考えさせられます。
そうこうしている間、世の中は「コロナ」一色でした。緊急事態宣言が再発令されて、昨年に続いて日常生活が制限される中、個人的な事情も相まって、パソコン講座から長く離れることになった日々でもあります。離れていればそれはそれなりに…日常は回りますし、禁断症状(笑)もそれほどありません。このままフェードアウトすることもできそうな気分ではありますが、私にとって「パソコン講座」は天職だと感じたものでもありますから、もう少し細々と続けてみようかと、今リベンジ講座を計画中です。
昨年来のコロナ禍で、リモートが進んで来ました。いち早く大学などの講義がリモートになり、企業の在宅勤務もそれなりに形が整って来たところでしょうか。昨年は小学校などが長く授業ができない期間がありましたが、コロナ対策とやらをしたうえで再開した後、今回の緊急事態宣言期間には、オンライン授業を導入する学校も聞くようになりました。スポーツは無観客試合とやらで実施、オリンピックやパラリンピックはその最たるものでした。コンサートなどを実施する機会も無くなり、オンラインライブといった苦肉の策も現れているようです。何やら、コロナとオンラインが妙に共振している部分があります。
人が集まることができないわけで、それを補うのがオンライン。顔を合わすことなく、情報をやり取りすることができる技術は、オンライン会議やオンライン授業という形で、随分コロナの時代を救ってくれました。
…が、対面とオンラインは同等の事ができるのか?というと、多分、それは否。対面が上でオンラインが下とか、オンラインが上で対面が下とか、そういう問題でなく、異質なもの別のものだという感覚です。だからオンライン授業で対面授業と同じことをする必要は無いし、オンライン授業が対面授業を100%補えるものでもないのだと思います。逆を言うなら、対面授業はオンライン授業を超えるものでもないし、いずれは対面授業に戻るのがベストなわけでも無いのではないでしょうか。
パソコン講座も「リモート」の時代になっていくのかも知れません。遠隔操作で他人の画面を操ることができる時代です。技術と環境さえ整えば、参加者の画面を遠隔操作で操って見せながら、説明することも可能です。…が、きっと対面でなければ伝えることができないものがあるから。人の心や気持ちを受け止めることができるのは、やはり「目の前」に居るから…なのだと。コロナが残す負の産物を乗り超えることができるのは、いつでしょうか。
更新の頻度の復活は、まだ難しいと思っています。が、たまに気が向いたらつぶやいているかもしれません。気ままにお付き合いください。
詳しくは伏せますが、家族が入院しており、なんやかや…と諸事情に振り回されている数か月で、ブログを更新する余裕が無かったというのが本音です。歳は重ねたくないものです。が、仕方ありませんね。これからは自分自身も含めて、段々坂道を下っていく時期です。急こう配に加速度がついて転がり落ちないようにしなければ…。「どう生きるか?」は、「どう人生を終えるか?」と同義であることを、考えさせられます。
そうこうしている間、世の中は「コロナ」一色でした。緊急事態宣言が再発令されて、昨年に続いて日常生活が制限される中、個人的な事情も相まって、パソコン講座から長く離れることになった日々でもあります。離れていればそれはそれなりに…日常は回りますし、禁断症状(笑)もそれほどありません。このままフェードアウトすることもできそうな気分ではありますが、私にとって「パソコン講座」は天職だと感じたものでもありますから、もう少し細々と続けてみようかと、今リベンジ講座を計画中です。
昨年来のコロナ禍で、リモートが進んで来ました。いち早く大学などの講義がリモートになり、企業の在宅勤務もそれなりに形が整って来たところでしょうか。昨年は小学校などが長く授業ができない期間がありましたが、コロナ対策とやらをしたうえで再開した後、今回の緊急事態宣言期間には、オンライン授業を導入する学校も聞くようになりました。スポーツは無観客試合とやらで実施、オリンピックやパラリンピックはその最たるものでした。コンサートなどを実施する機会も無くなり、オンラインライブといった苦肉の策も現れているようです。何やら、コロナとオンラインが妙に共振している部分があります。
人が集まることができないわけで、それを補うのがオンライン。顔を合わすことなく、情報をやり取りすることができる技術は、オンライン会議やオンライン授業という形で、随分コロナの時代を救ってくれました。
…が、対面とオンラインは同等の事ができるのか?というと、多分、それは否。対面が上でオンラインが下とか、オンラインが上で対面が下とか、そういう問題でなく、異質なもの別のものだという感覚です。だからオンライン授業で対面授業と同じことをする必要は無いし、オンライン授業が対面授業を100%補えるものでもないのだと思います。逆を言うなら、対面授業はオンライン授業を超えるものでもないし、いずれは対面授業に戻るのがベストなわけでも無いのではないでしょうか。
パソコン講座も「リモート」の時代になっていくのかも知れません。遠隔操作で他人の画面を操ることができる時代です。技術と環境さえ整えば、参加者の画面を遠隔操作で操って見せながら、説明することも可能です。…が、きっと対面でなければ伝えることができないものがあるから。人の心や気持ちを受け止めることができるのは、やはり「目の前」に居るから…なのだと。コロナが残す負の産物を乗り超えることができるのは、いつでしょうか。
更新の頻度の復活は、まだ難しいと思っています。が、たまに気が向いたらつぶやいているかもしれません。気ままにお付き合いください。