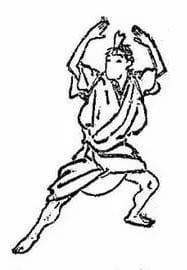今朝の日テレ「シューイチ」では「日本のおみやげ文化」について取り上げていた。そして「おみやげ文化」が始まったのは江戸時代中期から後期にかけて起きた「お伊勢参り」ブームによるものだと解説していた。
「お伊勢講」によってやって来た参詣者にとって、村に残った人たちへ手ぶらで帰るわけにもいかなかったのだろう。しかし、鉄道が敷かれた明治以降はともかく、江戸時代の移動手段は専ら徒歩。たとえば熊本から「お伊勢参り」へ行くには片道だけでひと月を要する。保存がきかない食べ物は持って帰れないし、乏しい予算では買えるものも限られていただろう。そこで「伊勢暦」などとともに「荷物にならない伊勢土産」としてが喜ばれたのが「伊勢音頭」。伊勢に滞在している間に宿や花街で聞き覚えた「伊勢音頭」を故郷へ持ち帰るのである。こうして「伊勢音頭」は日本全国に伝播し、祝い歌・祭り歌・踊り歌・座興歌・宴席歌・労作歌などとして様々な形に変化しながら唄い継がれた。

歌川広重「伊勢参宮 宮川の渡し」
この「荷物にならない伊勢土産」である「伊勢音頭」をモチーフに、本條秀太郎さんが俚奏楽として創作したのがこの「俚奏楽 伊勢土産」。
「伊勢音頭」は数多の民謡の中でも人気が高く、下の映像もアクセス数は常に上位にランクされる。
「お伊勢講」によってやって来た参詣者にとって、村に残った人たちへ手ぶらで帰るわけにもいかなかったのだろう。しかし、鉄道が敷かれた明治以降はともかく、江戸時代の移動手段は専ら徒歩。たとえば熊本から「お伊勢参り」へ行くには片道だけでひと月を要する。保存がきかない食べ物は持って帰れないし、乏しい予算では買えるものも限られていただろう。そこで「伊勢暦」などとともに「荷物にならない伊勢土産」としてが喜ばれたのが「伊勢音頭」。伊勢に滞在している間に宿や花街で聞き覚えた「伊勢音頭」を故郷へ持ち帰るのである。こうして「伊勢音頭」は日本全国に伝播し、祝い歌・祭り歌・踊り歌・座興歌・宴席歌・労作歌などとして様々な形に変化しながら唄い継がれた。

歌川広重「伊勢参宮 宮川の渡し」
この「荷物にならない伊勢土産」である「伊勢音頭」をモチーフに、本條秀太郎さんが俚奏楽として創作したのがこの「俚奏楽 伊勢土産」。
2020.2.2 くまもと森都心プラザホール 第55回熊本県邦楽協会演奏会
三味線・唄 本條秀美
三味線 本條秀咲・蒲原サヤ子・松本美恵子・高木テイ子・平田三枝子
立石松子・渡辺幸子・麻生美子・前田璃奈
唄 原田靖子・斉藤省子
三味線・唄 本條秀美
三味線 本條秀咲・蒲原サヤ子・松本美恵子・高木テイ子・平田三枝子
立石松子・渡辺幸子・麻生美子・前田璃奈
唄 原田靖子・斉藤省子
「伊勢音頭」は数多の民謡の中でも人気が高く、下の映像もアクセス数は常に上位にランクされる。
2012.5.26 熊本城本丸御殿 春の宴
振付:中村花誠
立方:ザ・わらべ
地方:(唄)本條秀美
(三味線)本條秀美社中
(囃 子)中村花誠と花と誠の会
振付:中村花誠
立方:ザ・わらべ
地方:(唄)本條秀美
(三味線)本條秀美社中
(囃 子)中村花誠と花と誠の会


















 今日の「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK-G)は富山県砺波市からの放送。富山県を中心に石川県、福井県の北陸地方の民謡が紹介された。全国的に有名な「越中おわら節」や「こきりこ節」「山中節」など、この地方はまさに民謡の宝庫と言えそうだ。今日演奏された曲目は
今日の「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK-G)は富山県砺波市からの放送。富山県を中心に石川県、福井県の北陸地方の民謡が紹介された。全国的に有名な「越中おわら節」や「こきりこ節」「山中節」など、この地方はまさに民謡の宝庫と言えそうだ。今日演奏された曲目は
 昨年はとうとう能を見る機会がなかった。仕舞や舞囃子は何度か見たのだが、装束を着けた正式な能は見ることができなかった。今年も正月の松囃子は藤崎八旛宮の初詣の時に見たのだがどうなることやら。
昨年はとうとう能を見る機会がなかった。仕舞や舞囃子は何度か見たのだが、装束を着けた正式な能は見ることができなかった。今年も正月の松囃子は藤崎八旛宮の初詣の時に見たのだがどうなることやら。