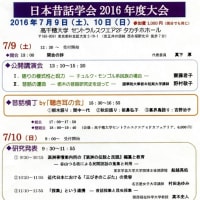奈良の人々は「古事記」の物語をどう伝えてきたのでしょうか?
今日はその事例として「井氷鹿姫」を取り上げましょう!
記紀神話に、神武天皇が熊野から吉野に入り、井氷鹿/井光(いひか)という人物に出会っている。
「古事記」ではこう伝えている。
尾のある人、井より出て来たりき。その井に光ありき。
ここに「汝は誰ぞ」と問ひたまへば、
「あは国つ神、名は井氷鹿(いひか)と謂ふ」と答へ曰しき。
こは吉野首(よしののおびと)等の祖なり。
また、「日本書紀」ではこう伝えている。
人有りて、井の中より出でたり。光りて尾有り。
天皇問ひて曰く「汝は何人ぞ」。応えて曰く
「臣は是れ国神なり。名を井光(いひか)と為す」。
此れ即ち吉野首部(よしののおびと)が始祖なり。
記紀神話はよく似た話で、井光は穴の中から現われ、しっぽが生えていたと伝えています。
古事記では「井戸」が光っていたとするのに対して、日本書紀では、光っていたのは「井光の体」です。
なぜ、井戸が光っていたのでしょう?
その井戸は掘ったら、水銀が出てきたので、上から見ると、光っていたのでしょう。
さて、記紀神話、いわゆる文献では以上のように記載されているのですが、
土地の人々は、どのように語っているのでしょうか?
比較民話研究会の私どもが吉野山で1994年春に調査した話では
次のように語られていました。
井光の井戸
むかし、神武天皇が九州から東に向かって進んできて、吉野山を越えて行かはってんて。
そのとちゅう、山の中腹に大きな杉の木があって、根もとのとこに井戸があってん。
神武天皇がその井戸のとこを通りかかると、井戸の中からものすごい光がさして来てんて。
みながびっくりしてるとな、光の中からしっぽのある人が出てきて、神武天皇の前にひれふしたんやて。
神武天皇が、「お前は何ものか」て聞かはったら、その人は、
「私は、この吉野山に住む吉野首(おびと)というものです。
天皇の道案内をしてさしあげようと思って、お待ち申し上げておりました」いうねんて。
神武天皇は喜んで、吉野首に道案内してもろて、また東に向かって行ったいうことや。
その井戸は今もあって、近くに井光山(いびかりざん)いうお寺と、井光神社いうてちいちゃい祠があるねん。
原話:『奈良県吉野町民間説話報告書』
再話:村上郁
私どもの聞いた別の話ではこう語っています。
この井戸には井氷鹿姫が住んでいたのです。
その証拠に井光神社が奈良県吉野郡川上村井光にあり
祭神は「井氷鹿姫」だそうです。
庶民の伝える話はロマンチックですよね。

(挿絵:マスダ ケイコ)
杉の根元に井戸があり、そこを天皇が通りかかり、
井氷鹿姫が井戸の中から現れ、天皇に水を差し出し、言葉をかわしたというのですから。
万葉集以来、日本文学の恋の舞台の伝統的なシーンのひとつは
「木の生えた泉のほとりで男女が愛の言葉を交わす」
なんですからね!
今日はその事例として「井氷鹿姫」を取り上げましょう!
記紀神話に、神武天皇が熊野から吉野に入り、井氷鹿/井光(いひか)という人物に出会っている。
「古事記」ではこう伝えている。
尾のある人、井より出て来たりき。その井に光ありき。
ここに「汝は誰ぞ」と問ひたまへば、
「あは国つ神、名は井氷鹿(いひか)と謂ふ」と答へ曰しき。
こは吉野首(よしののおびと)等の祖なり。
また、「日本書紀」ではこう伝えている。
人有りて、井の中より出でたり。光りて尾有り。
天皇問ひて曰く「汝は何人ぞ」。応えて曰く
「臣は是れ国神なり。名を井光(いひか)と為す」。
此れ即ち吉野首部(よしののおびと)が始祖なり。
記紀神話はよく似た話で、井光は穴の中から現われ、しっぽが生えていたと伝えています。
古事記では「井戸」が光っていたとするのに対して、日本書紀では、光っていたのは「井光の体」です。
なぜ、井戸が光っていたのでしょう?
その井戸は掘ったら、水銀が出てきたので、上から見ると、光っていたのでしょう。
さて、記紀神話、いわゆる文献では以上のように記載されているのですが、
土地の人々は、どのように語っているのでしょうか?
比較民話研究会の私どもが吉野山で1994年春に調査した話では
次のように語られていました。
井光の井戸
むかし、神武天皇が九州から東に向かって進んできて、吉野山を越えて行かはってんて。
そのとちゅう、山の中腹に大きな杉の木があって、根もとのとこに井戸があってん。
神武天皇がその井戸のとこを通りかかると、井戸の中からものすごい光がさして来てんて。
みながびっくりしてるとな、光の中からしっぽのある人が出てきて、神武天皇の前にひれふしたんやて。
神武天皇が、「お前は何ものか」て聞かはったら、その人は、
「私は、この吉野山に住む吉野首(おびと)というものです。
天皇の道案内をしてさしあげようと思って、お待ち申し上げておりました」いうねんて。
神武天皇は喜んで、吉野首に道案内してもろて、また東に向かって行ったいうことや。
その井戸は今もあって、近くに井光山(いびかりざん)いうお寺と、井光神社いうてちいちゃい祠があるねん。
原話:『奈良県吉野町民間説話報告書』
再話:村上郁
私どもの聞いた別の話ではこう語っています。
この井戸には井氷鹿姫が住んでいたのです。
その証拠に井光神社が奈良県吉野郡川上村井光にあり
祭神は「井氷鹿姫」だそうです。
庶民の伝える話はロマンチックですよね。

(挿絵:マスダ ケイコ)
杉の根元に井戸があり、そこを天皇が通りかかり、
井氷鹿姫が井戸の中から現れ、天皇に水を差し出し、言葉をかわしたというのですから。
万葉集以来、日本文学の恋の舞台の伝統的なシーンのひとつは
「木の生えた泉のほとりで男女が愛の言葉を交わす」
なんですからね!