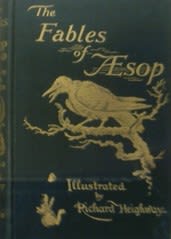今年の「奈良民話祭り」も終わり、新年を迎えようとしています。
このブログも開設後9ヶ月になります。
今までは奈良の民話、奈良の伝承文化について綴ってきましたが、
今後はグリム童話など世界の語りの文化に話題を広げます。
そこで今日は何にしようかな?と思案していたら、
窓から我が家の庭に目を向けると、なんとこの寒さの中
バラが健気に咲いているではないか!
(背後には南天の赤い実もみえるでしょ。)

そこで思いついたのが、グリム童話「いばら姫」です。
グリム兄弟の兄ヤーコプは、25歳のとき、
当時22歳であったマリー・ハッセンプフルーク嬢から
「いばら姫」の話を聞き書きしている。
その聞き書き原話を訳して載せましょう。
ある王さまと王妃さまには子どもがひとりもいませんでした。
ある日のこと、王妃さまが水浴びしていると、
一匹のざりがにが水から陸(おか)に這い上がってきて、言いました
「あなたは、まもなく娘を得ることになるでしょう。」
すると、その通りになりました。
喜んだ王さまは盛大な祝宴を催しました。
この国には、十三人の妖精がいましたが、
王さまは金の皿を十二枚しか持っていなかったので、
十三番目の妖精は、招くことができませんでした。
妖精たちは、王女にあらゆる徳や美を授けました。
さて、祝宴が終わりに近づいたとき、十三番目の妖精が来て言いました
「お前たちは私を招かなかったね。そこで、予言しでおくが、お前たちの娘は、
十五歳になったら指につむをさし、それで死ぬでしょう。」
ほかの妖精たちはできるかぎり、これをやわらげようと思って言いました
「王女は、百年の眠りにおちるだけにしましょう。」
けれども、王さまは、国じゅうのつむをすべて処分するようにという命令を出し、
その通り行なわれました。
そして王女が十五歳になったある日のこと、両親は外へ出かけていましたが、
王女は城の中を歩きまわったあげく、ある古い塔にたどりつきました。
その塔には、狭い階段が通じており、やがて王女は小さな戸のところへ来ました。
その戸には黄色い鍵がささっており、王女がそれを回して小部屋に入ると、
そこでは、ひとりのおばあさんが亜麻を紡いでいました。
王女はおばあさんをからかい、自分でも紡いでみようとしました。
すると、王女はつむに刺さり、すぐに深い眠りにおちてしまいました。
ちょうどその瞬聞に、王さまと廷臣たちが帰ってきたので、
お城の中のものはみんな、みんな、壁のはえまでが眠りはじめました。
そして、城全体のまわりには、いばらの垣根が生え広がり、
城のものは何も見えなくなりました。
それから、長い長い年月がたって、ひとりの王子がこの国にやってきましたが、
あるおじいさんがその王子に自分の祖父から聞いて覚えている話を語り聞かせました。
「これまで多くの人々がいばらを通り抜けて行こうと試みたけれど、
みんな、いばらにひっかかつてしまつた」というのです。
ところが、この王子がいばらの垣根に近づと、
いばらはみな花のようになって道をあけ、王子が通りすぎると、
また、いばらにもどりました。
さて、王子が城の中へ入ると、眠っている王女にキスをしました。
すると、みんなは眠りからさめました。そしてふたりは結婚しました。
もし、ふたりが死んでいなければ、まだ生きています。
皆さんはこの話は、よくご存知なので、すっと読めたでしょう。
でも最後の「もし、ふたりが死んでいなければ、まだ生きています。」は
なんだか、変ですよね。でもこれは、ドイツの口伝えの昔話で
よくでてくる結末句なのです。
まあ、日本の昔話の「お話、こっぷりこれでおしまい」にあたります。
このブログも開設後9ヶ月になります。
今までは奈良の民話、奈良の伝承文化について綴ってきましたが、
今後はグリム童話など世界の語りの文化に話題を広げます。
そこで今日は何にしようかな?と思案していたら、
窓から我が家の庭に目を向けると、なんとこの寒さの中
バラが健気に咲いているではないか!
(背後には南天の赤い実もみえるでしょ。)

そこで思いついたのが、グリム童話「いばら姫」です。
グリム兄弟の兄ヤーコプは、25歳のとき、
当時22歳であったマリー・ハッセンプフルーク嬢から
「いばら姫」の話を聞き書きしている。
その聞き書き原話を訳して載せましょう。
ある王さまと王妃さまには子どもがひとりもいませんでした。
ある日のこと、王妃さまが水浴びしていると、
一匹のざりがにが水から陸(おか)に這い上がってきて、言いました
「あなたは、まもなく娘を得ることになるでしょう。」
すると、その通りになりました。
喜んだ王さまは盛大な祝宴を催しました。
この国には、十三人の妖精がいましたが、
王さまは金の皿を十二枚しか持っていなかったので、
十三番目の妖精は、招くことができませんでした。
妖精たちは、王女にあらゆる徳や美を授けました。
さて、祝宴が終わりに近づいたとき、十三番目の妖精が来て言いました
「お前たちは私を招かなかったね。そこで、予言しでおくが、お前たちの娘は、
十五歳になったら指につむをさし、それで死ぬでしょう。」
ほかの妖精たちはできるかぎり、これをやわらげようと思って言いました
「王女は、百年の眠りにおちるだけにしましょう。」
けれども、王さまは、国じゅうのつむをすべて処分するようにという命令を出し、
その通り行なわれました。
そして王女が十五歳になったある日のこと、両親は外へ出かけていましたが、
王女は城の中を歩きまわったあげく、ある古い塔にたどりつきました。
その塔には、狭い階段が通じており、やがて王女は小さな戸のところへ来ました。
その戸には黄色い鍵がささっており、王女がそれを回して小部屋に入ると、
そこでは、ひとりのおばあさんが亜麻を紡いでいました。
王女はおばあさんをからかい、自分でも紡いでみようとしました。
すると、王女はつむに刺さり、すぐに深い眠りにおちてしまいました。
ちょうどその瞬聞に、王さまと廷臣たちが帰ってきたので、
お城の中のものはみんな、みんな、壁のはえまでが眠りはじめました。
そして、城全体のまわりには、いばらの垣根が生え広がり、
城のものは何も見えなくなりました。
それから、長い長い年月がたって、ひとりの王子がこの国にやってきましたが、
あるおじいさんがその王子に自分の祖父から聞いて覚えている話を語り聞かせました。
「これまで多くの人々がいばらを通り抜けて行こうと試みたけれど、
みんな、いばらにひっかかつてしまつた」というのです。
ところが、この王子がいばらの垣根に近づと、
いばらはみな花のようになって道をあけ、王子が通りすぎると、
また、いばらにもどりました。
さて、王子が城の中へ入ると、眠っている王女にキスをしました。
すると、みんなは眠りからさめました。そしてふたりは結婚しました。
もし、ふたりが死んでいなければ、まだ生きています。
皆さんはこの話は、よくご存知なので、すっと読めたでしょう。
でも最後の「もし、ふたりが死んでいなければ、まだ生きています。」は
なんだか、変ですよね。でもこれは、ドイツの口伝えの昔話で
よくでてくる結末句なのです。
まあ、日本の昔話の「お話、こっぷりこれでおしまい」にあたります。