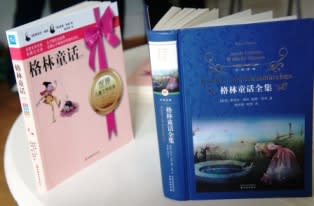『グリム童話』刊行200年記念国際シンポジウム
「グリム童話200年のあゆみ―日本とドイツの架け橋として―」が
先週土曜日10月20日午後、東洋大学にて開催されました。
500名を超える参加者があり、盛会のうちに終了しました。
<基調講演 1 〉 マールブルク?「だがこの町自体はひどく醜い」
―グリム兄弟と故郷ヘッセンとの相反的関わり―
ハルム=ペア・ツィンマーマン(チューリヒ大学教授)
<基調講演 2 〉文字から図像へ
―19~20世紀における『子どもと家庭のためのメルヒェン集』挿絵の歴史―
ベルンハルト・ラウアー(グリム兄弟博物館館長)
<シンポジウム>『グリム童話』研究がつなぐ過去と未来
パネラー:溝井裕一、野口芳子、竹原威滋
司会:大野寿子、田中雅敏
詳しい報告が東洋大学の下記のサイトに載っていますので、ご覧ください:
東洋大学『グリム童話』刊行200年記念国際シンポジウム

ラウアー館長の講演「グリム童話の挿絵の歴史」の映像の一コマです。
ラウアー氏の講演は次の日曜日10月28日武庫川女子大のグリムシンポジウムでも聴けますので、
関西方面の方は 是非来てくださいね。下記のサイトをご覧ください。
武庫川女子大・グリムシンポジウム「グリム童話とジェンダー」
シンポジウムの大役を果たし、ほっとして、東京でもう一泊して
六本木の国立新美術館で美術展「リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝」を見てきました。

展覧会のポスターです。
右の女の子の絵は画家ルーベンスが描いた5歳の愛娘の肖像画です。
さすが巨匠ルーベンスの絵だけあって、かわいい娘の表情をバッチリ捉えていますね。

国立新美術館は、黒川紀章の設計による斬新なガラス張りの建物です。
帰りの新幹線から夕闇せまる富士山を見ることができました。

緊張と安らぎの東京滞在の3日間でした。
「グリム童話200年のあゆみ―日本とドイツの架け橋として―」が
先週土曜日10月20日午後、東洋大学にて開催されました。
500名を超える参加者があり、盛会のうちに終了しました。
<基調講演 1 〉 マールブルク?「だがこの町自体はひどく醜い」
―グリム兄弟と故郷ヘッセンとの相反的関わり―
ハルム=ペア・ツィンマーマン(チューリヒ大学教授)
<基調講演 2 〉文字から図像へ
―19~20世紀における『子どもと家庭のためのメルヒェン集』挿絵の歴史―
ベルンハルト・ラウアー(グリム兄弟博物館館長)
<シンポジウム>『グリム童話』研究がつなぐ過去と未来
パネラー:溝井裕一、野口芳子、竹原威滋
司会:大野寿子、田中雅敏
詳しい報告が東洋大学の下記のサイトに載っていますので、ご覧ください:
東洋大学『グリム童話』刊行200年記念国際シンポジウム

ラウアー館長の講演「グリム童話の挿絵の歴史」の映像の一コマです。
ラウアー氏の講演は次の日曜日10月28日武庫川女子大のグリムシンポジウムでも聴けますので、
関西方面の方は 是非来てくださいね。下記のサイトをご覧ください。
武庫川女子大・グリムシンポジウム「グリム童話とジェンダー」
シンポジウムの大役を果たし、ほっとして、東京でもう一泊して
六本木の国立新美術館で美術展「リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝」を見てきました。

展覧会のポスターです。
右の女の子の絵は画家ルーベンスが描いた5歳の愛娘の肖像画です。
さすが巨匠ルーベンスの絵だけあって、かわいい娘の表情をバッチリ捉えていますね。

国立新美術館は、黒川紀章の設計による斬新なガラス張りの建物です。
帰りの新幹線から夕闇せまる富士山を見ることができました。

緊張と安らぎの東京滞在の3日間でした。