今日のブログは、新刊情報です。
6年前に刊行された丸山顕徳編『奈良伝説探訪』の続編が出ました。
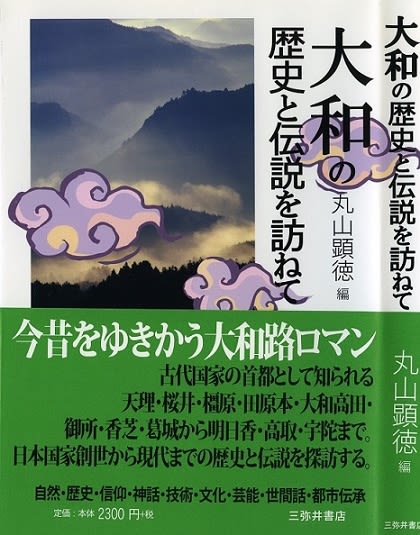
丸山顕徳編『大和の歴史と伝説を訪ねて』(三弥井書店)です。
先ずは、奈良新聞の書評を載せましょう:
----奈良新聞---書評より--------------------------
「奈良伝説探訪」の続編で、前作は奈良市が中心だったが、
本著は天理、桜井、橿原、香芝、葛城、御所、宇陀など
県内中和地域を中心に日本国家創世から現代まで、
36の大和の伝説・伝承が紹介されている。
丸山花園大教授が編者で、執筆陣は多彩だ。
「静御前のふるさと」(鈴鹿千代乃神戸女子大教授)や
「本居宣長の歩いた道」(藤原享和立命大教授)ら関西の専門家が
結集して奈良に眠る伝説を解説。
泉武(高松塚壁画館)、軽澤照文(東登美ケ丘小教諭)、
角南聡一郎(元興寺文化研究所)、上島秀友(日本ペンクラブ会員)、
藤井稔(天理高教諭)ら県内の研究者も参加している。
「この書を携えて大和路の歴史ロマンの源泉を訪ねてほしい」と丸山教授。
伝統・伝承のいわれや歴史的背景は知ってそうで知らない場合が多い。
歴史好きのみならず、文学、民俗学に興味のある人、散策好きなど
幅広い層に読んでもらいたい本といえるだろう。`(山)
(三弥井書店、税別2300円)
------------------------------
【目次】
Ⅰ 大和平野の中南部を歩く
田原本町・橿原市・明日香村・高取町
1橘寺の二面石/2明日香の亀石と亀形石造物/3神武天皇陵と国源寺/
4六御県/5小子部の里/6茂古の森/7藤原の里/8大和猿楽四座/9今井町の今西家/
10近世の山城・高取城/ 11芝村騒動と耳成山/12香久山と耳成山の狐の民話
Ⅱ 大和平野の東方を歩く
天理市・桜井市・宇陀市
13大神神社と本殿/14黒塚古墳と三角縁神獣鏡/15大和神社と大国魂神/
16石上神宮と神剣/17長谷寺縁起/18業平の姿見伝説/19物語の作者/
20三輪の玄賓僧都伝説/21初瀬街道/22布留郷ナモデ踊りの由来/
23本居宣長の歩いた道/24泥海からはじまる世界/25三輪そうめん/
26三輪の酒/27山の辺の道
Ⅲ 大和平野の西方を歩く
葛城市・大和高田市・御所市・香芝市
28ノミノスクネとタイマノケハヤ/ 29タイマノケハヤと良福寺の腰折田/
30大国主の約束した王城守護と鴨氏の神社/31大津皇子の二上山墓と薬師寺龍王社/
32当麻寺と浄土信仰/33奥田の蓮池/34吉祥草寺の大トンド/35静御前のふるさと/
36野口神社の汁掛祭と蛇綱曳き
---------------------------
奈良の民話を語りつぐ会の皆さん、奈良の民話に関心のある方は
是非、読んでくださいね!
今日のブログは、新刊情報でした。
奈良もあと少しで桜も開花、春ですね!
では、来週末にブログでお会いするまで、お元気で!!
6年前に刊行された丸山顕徳編『奈良伝説探訪』の続編が出ました。
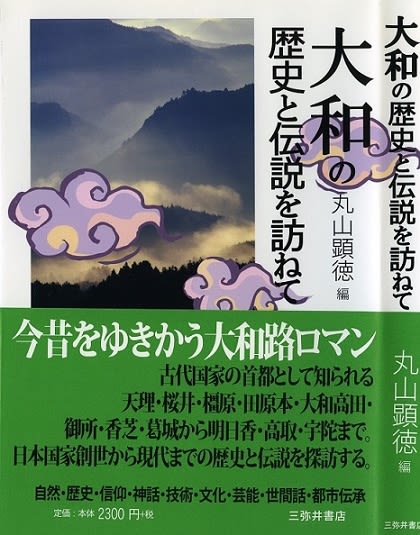
丸山顕徳編『大和の歴史と伝説を訪ねて』(三弥井書店)です。
先ずは、奈良新聞の書評を載せましょう:
----奈良新聞---書評より--------------------------
「奈良伝説探訪」の続編で、前作は奈良市が中心だったが、
本著は天理、桜井、橿原、香芝、葛城、御所、宇陀など
県内中和地域を中心に日本国家創世から現代まで、
36の大和の伝説・伝承が紹介されている。
丸山花園大教授が編者で、執筆陣は多彩だ。
「静御前のふるさと」(鈴鹿千代乃神戸女子大教授)や
「本居宣長の歩いた道」(藤原享和立命大教授)ら関西の専門家が
結集して奈良に眠る伝説を解説。
泉武(高松塚壁画館)、軽澤照文(東登美ケ丘小教諭)、
角南聡一郎(元興寺文化研究所)、上島秀友(日本ペンクラブ会員)、
藤井稔(天理高教諭)ら県内の研究者も参加している。
「この書を携えて大和路の歴史ロマンの源泉を訪ねてほしい」と丸山教授。
伝統・伝承のいわれや歴史的背景は知ってそうで知らない場合が多い。
歴史好きのみならず、文学、民俗学に興味のある人、散策好きなど
幅広い層に読んでもらいたい本といえるだろう。`(山)
(三弥井書店、税別2300円)
------------------------------
【目次】
Ⅰ 大和平野の中南部を歩く
田原本町・橿原市・明日香村・高取町
1橘寺の二面石/2明日香の亀石と亀形石造物/3神武天皇陵と国源寺/
4六御県/5小子部の里/6茂古の森/7藤原の里/8大和猿楽四座/9今井町の今西家/
10近世の山城・高取城/ 11芝村騒動と耳成山/12香久山と耳成山の狐の民話
Ⅱ 大和平野の東方を歩く
天理市・桜井市・宇陀市
13大神神社と本殿/14黒塚古墳と三角縁神獣鏡/15大和神社と大国魂神/
16石上神宮と神剣/17長谷寺縁起/18業平の姿見伝説/19物語の作者/
20三輪の玄賓僧都伝説/21初瀬街道/22布留郷ナモデ踊りの由来/
23本居宣長の歩いた道/24泥海からはじまる世界/25三輪そうめん/
26三輪の酒/27山の辺の道
Ⅲ 大和平野の西方を歩く
葛城市・大和高田市・御所市・香芝市
28ノミノスクネとタイマノケハヤ/ 29タイマノケハヤと良福寺の腰折田/
30大国主の約束した王城守護と鴨氏の神社/31大津皇子の二上山墓と薬師寺龍王社/
32当麻寺と浄土信仰/33奥田の蓮池/34吉祥草寺の大トンド/35静御前のふるさと/
36野口神社の汁掛祭と蛇綱曳き
---------------------------
奈良の民話を語りつぐ会の皆さん、奈良の民話に関心のある方は
是非、読んでくださいね!
今日のブログは、新刊情報でした。
奈良もあと少しで桜も開花、春ですね!
では、来週末にブログでお会いするまで、お元気で!!















