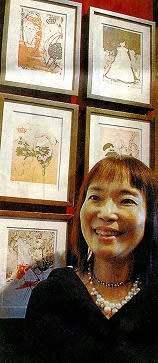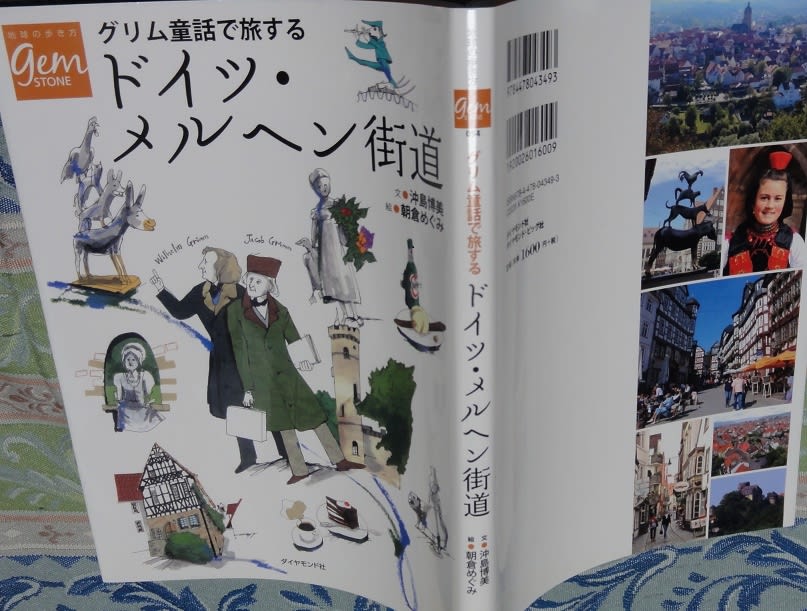皆さま。
お元気ですか?
今日は、とても面白い本が刊行されましたので、ご紹介します。
皆さまは、きっと子供も頃、お正月には双六をして遊んだことがおありでしょう!
双六の起源や江戸時代の庶民文化として人気のあった双六の歴史などを考察した本を紹介しましょう!

桝田静代著「絵双六 ― その起源と庶民文化」
A4版 巻頭図版8頁 本文372頁
発売:京阪奈情報教育出版
定価:本体 ¥10,000 税別
桝田さんは「絵双六の研究」について博士論文を書かれ、
学位をおとりになりました。
博士(文学):梅花女子大学大学院児童文学研究科後期博士課程2011年修了
今回、専門書ではありますが、一般の方々にも理解できるように図版なども多用し
分かり易い文体で執筆され、出版されました。
目次から各章のタイトルを挙げましょう。
第1章:絵双六の表現と構造に曼荼羅的世界を見る
― 浄土双六から一般的な双六まで ―
第2章:「名古屋版双六集」考
― シリーズ化して絵双六の世界観を楽しんだ蒐集家たち ―
第3章:江戸後期出版文化における竜宮イメージ
― 絵双六「新板竜宮飛双六」をめぐって ―
第4章:江戸版「春興手習出精雙六」考
― 絵双六に俳諧一枚擦りの趣向を見出す ―
第5章:江戸版「莟花江戸子数語録」考
― 描かれた子どもの姿に見る画題と写実性―
第6章:振分双六「新販女庭訓振分雙六」考
― 幕末期の女性たち その多様な生き方 ―
タイトルからもその内容が推測できますね。
「絵双六」というのは、ほんとうに奥が深いです。
曼荼羅の世界、江戸時代の寺子屋、子どもの遊び、当時の女性の生き方、竜宮世界、
いろんな分野を反映しているのですね。
しかもゲーム感覚で人生を体験していき、生きる力を与えてくれる!
桝田さんは双六を求めて、日本中を歩き回られ、閲覧の許可を得て、著作権をクリアーして
出版に至られたご苦労、本当に敬服しております。
全国の公共図書館、大学図書館の基本図書として備えられることを願っております。
皆さまも、購入されるか、
図書館にリクエストして
是非、手に取って読んでみてください。
今、「妖怪ウオッチ」というゲームが流行っていますが、このブームは
江戸時代の庶民が愛した双六文化を今に受け継いでいるのではないでしょうか?

では、来週までお元気で! 御機嫌よう!
お元気ですか?
今日は、とても面白い本が刊行されましたので、ご紹介します。
皆さまは、きっと子供も頃、お正月には双六をして遊んだことがおありでしょう!
双六の起源や江戸時代の庶民文化として人気のあった双六の歴史などを考察した本を紹介しましょう!

桝田静代著「絵双六 ― その起源と庶民文化」
A4版 巻頭図版8頁 本文372頁
発売:京阪奈情報教育出版
定価:本体 ¥10,000 税別
桝田さんは「絵双六の研究」について博士論文を書かれ、
学位をおとりになりました。
博士(文学):梅花女子大学大学院児童文学研究科後期博士課程2011年修了
今回、専門書ではありますが、一般の方々にも理解できるように図版なども多用し
分かり易い文体で執筆され、出版されました。
目次から各章のタイトルを挙げましょう。
第1章:絵双六の表現と構造に曼荼羅的世界を見る
― 浄土双六から一般的な双六まで ―
第2章:「名古屋版双六集」考
― シリーズ化して絵双六の世界観を楽しんだ蒐集家たち ―
第3章:江戸後期出版文化における竜宮イメージ
― 絵双六「新板竜宮飛双六」をめぐって ―
第4章:江戸版「春興手習出精雙六」考
― 絵双六に俳諧一枚擦りの趣向を見出す ―
第5章:江戸版「莟花江戸子数語録」考
― 描かれた子どもの姿に見る画題と写実性―
第6章:振分双六「新販女庭訓振分雙六」考
― 幕末期の女性たち その多様な生き方 ―
タイトルからもその内容が推測できますね。
「絵双六」というのは、ほんとうに奥が深いです。
曼荼羅の世界、江戸時代の寺子屋、子どもの遊び、当時の女性の生き方、竜宮世界、
いろんな分野を反映しているのですね。
しかもゲーム感覚で人生を体験していき、生きる力を与えてくれる!
桝田さんは双六を求めて、日本中を歩き回られ、閲覧の許可を得て、著作権をクリアーして
出版に至られたご苦労、本当に敬服しております。
全国の公共図書館、大学図書館の基本図書として備えられることを願っております。
皆さまも、購入されるか、
図書館にリクエストして
是非、手に取って読んでみてください。
今、「妖怪ウオッチ」というゲームが流行っていますが、このブームは
江戸時代の庶民が愛した双六文化を今に受け継いでいるのではないでしょうか?

では、来週までお元気で! 御機嫌よう!