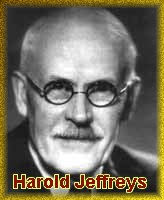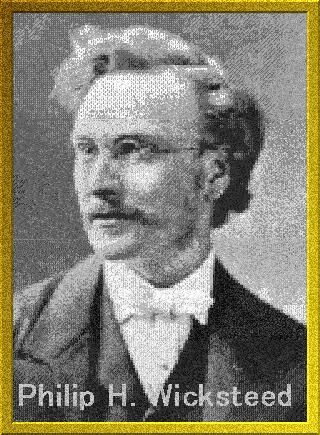マイロン・ショールズ(Myron S. Scholes)は、1941年、カナダ、オンタリオ州ティミンズ(Timmins)に生まれた。この地は、恐慌前は金鉱で賑わっていた所である。
父は歯科医、母は叔父とともにデパート・チェーンを経営していた。叔父の死によって相続問題に苦しんだという。一〇歳のとき、五〇〇マイル南のハミルトン(Hamilton)に移る。一六歳のとき、母が癌で死ぬ。さらに本人も、目の角膜を傷つけ、視力を損なってしまった。活字を読めなかったので、よい聞き手となり、抽象的思考になじむようになったという。二六歳のとき、角膜移植に成功して視力を回復する。
ビジネスにいそしむ母方家族の影響を受けて、一〇代の頃から利殖に興味をもつようになっていた。高校時代と大学には最初は母、後には父の口座を使って株式に投資していた。株価形成の理屈に興味をもち、成功した投資家の著作を読み耽っていた。
地元のマックマスター大学(McMaster)でシカゴ学派の教授、マッキーバー(McIver)の感化を受けて、ジョージ・スティグラー(George Stigler, 1911~91)、ミルトン・フリードマン(Milton Friedman, 1912~2006)の著作に親しんだ。そして、一九六二年、シカゴ大学の大学院に進む。ここで、博士コースにいたマイケル・ジェンセン(Michael Jensen)やリチャード・ロル(Richard Roll)と出会う。
いずれもファイナンス理論の大家として著名になった人であり、ショールズは、自伝で、彼らは長年の親友であり、理論的には最大の影響を受けたと述懐している。
シカゴ大学大学院に入学した後の最初の夏、彼は、コンピュータ・プログラムの経験がないのに、学部長のロバート・グレイブ(Robert Graves)の好意で、中級のコンピュータ・プログラマーの職を得た。職を得てすぐに、教授連からプログラム作成を依頼されたが、もちろん、まったくそうした要望に応えることはできなかった。学部長に相談したが、他にプログラマーはいないと諭されて、大学の側のコンピュータ施設に通うように命じられた。四か月半でかなりのことをマスターし、すっかりコンピュータの虜になってしまった。
もし、シカゴ大学にコンピュータ・サイエンス学科があれば、自分はコンピュータ学者になっていただろうと彼は述懐している。
コンピュータの専門家になってからは、シカゴ大学のファイナンス理論を専攻する学者たちから多くのことを学んだ。彼にプログラムを依頼していた教授陣には、レスター・テルサー(Lester Telser)、ピーター・パシジアン(Peter Pashigian)、マートン・ミラー(Merton Miller)、ユージーン・ファーマ(Eugene Fama)がいた。
ミラーは、手元にプログラマーとしてのショールズを必要としていたこともあって、ショールズに博士コースへの進学を勧めた。ミラーとファーマのファイナンス経済学、スティグラーの情報経済学、フリードマンのマクロ経済学が、彼を興奮させていたという。
株式市場における相対的資産価格、裁定取引が株主の代理人としての経営者の法外な儲けをどの程度阻止できるかが、彼の研究テーマであった。博士論文は、取引される証券の需要曲線に関するものであった。
証券ごとに異なるリスク・リターンを組み込む複数株取引の方が、個別的株の売買市場よりも大きくなる可能性を彼は信じていた。情報をもつ人による大取引が、市場に新しい情報をもたらして、証券価格を変化させるということも理論化すべき局面であった。ミラーとは、リターンに影響するリスクの計測とリスク間の格差の効果に関する研究を行った。
博士論文がほぼ完成した一九六八年秋、彼は、MITの経営学スローン・スクール(the Sloan School of Management at MIT)の助教授に採用された。
そこには、ポール・クートナー(Paul Cootner)、フランコ・モジリアニ(Franco Modigliani)、ステュアート・マイヤーズ(Stewart Myers)がいた。スローンの一年目に、アーサー・リトル(Arthur D. Little)のコンサルタントをしていたフィッシャー・ブラック(Fischer Black)と出会い、以後、彼らは共同研究を続けた。
一九六九年にポール・クートナーがスローンを去ったが、ロバート・マートン(Robert Merton)が加わった。マートン、ブラック、そしてショールズの三人がチームを組んで資産価格とデリバティブ価格のモデル化に携わった。
マートンとの共同研究が中断するというマイナスを覚悟して、彼は、シカゴ大学のビジネス・スクールに移った。一九七四年である。一九七二年にブラックがシカゴ大学教授に転身していたからである。ところが、一九七四年、マートンが、ブラックをMITに呼び戻していた。ショールズは、シカゴに留まり、証券取引に及ぼす課税の影響を研究していた。どうも、ブラックがモデル開発の核心であったと思われる。
一九八三年スタンフォードのビジネス・スクールとロー・スクールのスタッフになる。一九九〇年ソロモン・ブラザーズ(Salomon Brothers)の特別コンサルタントになる。ここで、デリバティブ取引に協力した。スタンフォードでの職を兼任したままであった。そして、一九九四年、LTCMに参加する。一九九八年再婚したと自伝で述べてはいるが、LTCMの破綻のことは、まったく触れていない(http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/scholes-autobio.html)。
LTCMの破綻については、『金融ビジネス』(二〇〇七年夏号)のインタビュー記事で語っている。まず、自分がリーダーでなく、旧ソロモンのトレーダーたちが実権を握っていたこと、彼らが「市場の方向性に賭ける」戦略を採用してしまっていたからであるとショールズは説明した。
「市場の方向性に賭ける」というのは、ショールズによれば、β(ベータ)と称されるもので、市場の動きを予測して証券を売買するもので、マクロを中心としたヘッジ・ファンド業者が行っていることで、システマティック・エクスポ-ジャーとは区別される(同、三二~三三ページ)。要するに単純な手法である。鳴り物入りで創設され、自らが資金調達に邁進したTCMをこのインタビューでは単純なファンドとして切り捨てている。
LTCM破綻後、ショールズは、プラチナム・グローブ・アセットマネージメント・エルピー(Platinum Grove Asset Management, L.P. =PGAM) を設立して、その会長になっている。
自分の作った新しいこの会社は、ω(オメガ)という手法をとるもので、市場が上がるとか下がるとかを予測するのではなく、どちらかといえば「受け身的に動く」もので、リスクをヘッジしたいという顧客のリスクをとって仲介することにより、付加価値を高める方法、つまり、「リスク移転」のビジネスを戦略の中心に置いていると説明する(同、三二~三三ページ)。
そして、一九九八年のアジア通貨危機などのひどい逆風が吹く場合もある、そうした事態における市場は正規分布ではなくファット・テール(fat tail)、つまり、裾野が広い分布をしている、この点を考慮して、ファンドが対処できるロスの大きさを、自分の主催するファンドは、つねに計測していると語った(同、三三ページ)。
個々の投資家は自分のリスクは把握しているのであろうが、世界全体の総和としてのリスク量は把握するのが難しい。これは「集計問題」(aggregation problem)と呼ばれているものである。彼は言う。
「クルマが事故を起こしたからといって、皆が運転をやめるわけではありません。市場は常に動き、そこから、われわれは常に何かを学んでいます。まったく心配がないなら、世界は極めて退屈なものになってしまう。むしろ失敗は次の成長をもたらす。理論と経験が相まってテクノロジーの発展があるのです。結局、ファイナンスの価値は何かと言えば、コストを減らすこと。規制当局も市場に対して、常に規制をすることの恩恵とコストを天秤にかけている。社会の発展、消費者あるいは貯蓄者にとって、金融工学は利益をもたらしていると思っていますよ」(同、三四ページ)。
金融はコストを減らすのに資するべきである。これは正しい。しかし、ここで想定されているのは何のコストだろうか。今日のようにファンドが猛威を奮えば、企業は買収に怯えて長期的な企業戦略を採用できないでいる。あるいは、資金調達に非常な困難を覚えている。ファンドは、金持ちの金融取引コストを下げるのに貢献しているのは確かであろうが、社会における生産と生活のコストを逆に増加しているのではないだろうか。
彼は、ファンドが流動性を供給するプラスの役割をはたしているという。
「グローバルな市場には、年金、企業、ヘッジファンドなどさまざまな投資家のニーズがあるわけですが、何らかの理由で、彼らがポートフォリオを組み替えたいと考えた場合、すぐに、買い手が現れるとはかぎりません。一定の期間、リスクをヘッジしたい人(hedger)とリスクを取る投機家(speculator)との間に立って保有し、流動性を供給する仲介者が必要です」(同、三二ページ)。
ここでイメージされている「流動性」とは市場をスムーズに機能させることであり、けっして、生産に必要な資金を供給するという意味で使われているわけではない。流動性という言葉が、ケインズ的な意味での「生産に必要な資金供給」からは大きく離れた使われ方をしているのである。
流動性を、ショールズ的に解釈したのは、ロバート・C・マートンも同じである。LTCM設立に必要な資金を調達するのに、米国大手証券会社の協力を得ることに困難を覚えていたメリー・ウエザーが、資金調達用の外部向け看板として、当時の金融工学界の最高峰、ハーバード大学教授のマートンを入社させたのである。マートンは、教え子のエリック・ローゼンフェルト(Eric Rosenfeld)に請われてソロモンの顧問をしていたこともあり、学会から金融界に移ることにさして抵抗感がなかったようである。
マートンは、時間を細かく分割し、時間の流れに沿って株式オプションの「適正価格」のモデル化に成功した。マートン自身はこれを「連続時間型ファイナンンス」と呼んでいた。
マートンが華麗な数式で証明してみせたブラック=ショールズ・モデルは、一九七三年五月に発表された。一か月前の四月、シカゴ・オプション取引所が開設されている。これは、はたして偶然であろうか。効果があるタイミングを見計らって発表されたのではないだろうか。事実、テキサス・インスツルメント(Texas Instrum,ents)は、『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙につぎのような広告を打ったという。
「これからは、わが社の電卓でブラック・ショールズ・モデルの計算ができます」(Lowenstein, Roger[2000]、邦訳、五九ページ)(ローウェン
スタイン自身は、その事実をBernstein Peter L.[1996]から得ている)。
フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ両氏が発表したオプション価格の評価モデルの基本的考え方は、リスクを避けうるポートフォリオの構築が可能であるというものである。