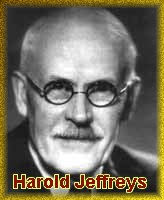息子との格差の大きさに奇異を感じるが、市場を通すのではなく、予言が実現され得るとしたのは、ロバート・コックス・マートンの父、ロバート・キング・マートン(Robert King Merton, 1910~2003)であった。
父のキングは「自己実現的予言」(self-fulfilling prophecy)という表現を生み出した人である。この父は、その他にも、「お手本」(role model)、「意図せざる結果」(unintended consequences)という、後に人々の日常会話にも登場するポピュラーな言葉を作った人として知られている。
主としてコロンビア大学で教鞭をとった。キングの父は、東欧ユダヤ系移民労働者であった。フィラデルフィアで育った。フィラデルフィアのテンプル大学(一九二七~三一年)、ハーバード大学(一九三一~三六年)を卒業後、しばらく、ハーバード大学で教えた後(一九三九)、一九四一年からコロンビア大学に移り、一九七四年には、この大学の最高の名誉である「大学の教授」(University Professor)になる。
全米科学アカデミー(the National Academy of Sciences)会員に推挙された最初の社会学者(sociologist)であり、スウェーデン、英国の外国人アカデミー会員にも選ばれた。一九九四年には、社会学者として初めて「全米科学賞」(the US National Medal of Science)を受けた。
そもそも、「社会学」(sociology)は、フランスのオーギュスト・コント(Auguste Comte, 1798~1857)の命名になるものある。

コントは、人間社会を「あるがままに、実証主義的に」描く学問の必要性を主張し、そうした学問を「社会学」と称した。
それまでは、社会を描く学問は「あるべき姿」にこだわりすぎた。コントは、「あるべき姿」と「あるがままの姿」の両者を探求することが重要であるとした。彼が造語したフランス語の"sociologie"は、ラテン語の「社会」(socius)とギリシャ語の「学知」(logos)を合わせたものである。コントの理論は、生物進化に社会の進化をなぞらえた「社会有機体説」であった。
第二次世界大戦後、社会学は米国の三人の学者を中心として発達してきた。


タルコット・パーソンズ(Talcott Parsons, 1902~1979)、アルフレッド・シュッツ(Alfred Schütz, 1899~1959)、そして、キング・マートンであった。
パーソンズは、「社会学的機能主義」という人間社会の大理論を、シュッツは、「現象学的社会学」の小理論を、そして、キングがその中間である「中範囲の理論」を作ったのである。
パーソンズは、「諸部分の総和からなるが、諸部分には還元されない独特の全体存在=システム」論を展開した。
それは、システムの内部か外部かという軸と、目的か手段かという軸の二つの軸が織りなす「適応」(adaptation)、「目標達成」(goal-attainment)、「統合」(Integration)、「型の維持」(pattern-maintenance or latency)からなるAGIL図式(四つの頭文字をとったもの)を分析手法に採用した。

パーソンズは、ノーバート・ウィーナー(Norbert Wiener, 1894~1964)の「サイバネティクス」(cybernetics)論を援用した。勢い(馬)と制御(騎手)をキーワードとしたシステム論を社会に適用しようとしたのである(Parsons, Talcott[1937], [1977])。
ただし、パーソンズの理論には、人間の内面を無視した客観的機能主義の傾向が強かった。それへの反発からシュッツは、人間世界の意味を重視した。
意味とは象徴である。これはこれで、大きな進歩を社会学にもたらしたものであったが、細かい小さな事例調査という物足りなさを生み出すものであった(Schütz, Alfred[1932])。
マートンは、一般的大理論を作るのではなく、経験的な検証ができる範囲という中間的なものに理論を限定させるべくきだとした。
マートンは、当事者の期待通りに結果を得ることができた「顕在的機能」(manifest function)と、意図してなかった結果をもたらした「潜在的機能」(latent function)とを区分し、さらに、役に立つ=貢献する機能を「順機能」(eufunction)、害を与えたり阻害する機能を「逆機能」(disfunction)と呼んで区分した。
マートンの理論の特徴は、先験的に物事を決めつけない点にある。そして、意図せざる結果の分析こそ、社会学の課題とした。つまり、不確実性がもたらす不確実な諸結果に機能分析の意義を見出そうとしたのである。
たとえば、人間関係がぎくしゃくしている共同体の人々が、干ばつに悩んで雨乞いの儀式を大々的に行ったとしよう。雨は降らなかった。したがって、「顕在的機能」はこの雨乞いにはなかった。しかし、共同体の成員はお陰で仲良くなった。つまり、意図しなかった結果という「潜在的機能」をこの行為がはたしたのである。
パーソンズが多用してきた「機能的統一性」も疑う必要があると父マートンは言う。部分が全体にとって一定の機能をはたすからといって、部分相互が役にたつように配列されているわけではない。部分間の対立を無視して安易に全体の調和を云々すべきではないと、彼は言う。
パーソンズの「機能的普遍性」という考え方も危険であると、彼は言う。部分のすべてが機能をもつという仮定が「機能的普遍性」の考え方にはあるが、部分によっては、機能せず、機能しても逆機能になっている可能性があることを排除してはならないと、父マートンは言う。
パーソンズの、「機能的不可欠性」は、ある部分がなくてはならない機能をもつという仮定であるが、これも疑わしい。ある部分を不可欠な要素であると決めつけることは危険である。不可欠だとされた部分が、まったく機能していないという可能性すらあるからである。
先決機能を社会のある部分に当てはめてはならない。社会全体が目指す理論を試みることは危険である。したがって、理論とは、経験的に検証可能な中範囲に自己限定されるべきだとマートンは言う。
マートンの理論を分かりやすく説明するには、「あこがれの集団=準拠集団」(reference groups)、「比較されたときの不満=相対的剥奪感」(relative deprivation)、「予言の自己実現」という三つの比喩が有効である。
「あこがれの集団=準拠集団」とは、タレントになりたい若者が、芸能界の「業界用語」を使って、芸能人の風体を真似するという、よく見られる光景をイメージしたものである。タレント志望の若者にとって、芸能界が「準拠集団」である。準拠集団は、その集団に憧れる外部の人間にとって生き甲斐をもたらすという「順機能」をもつ。しかし、あまり過度にのめり込みすぎると、そうした人々は現在属している集団との不適合を起こすという意味での「逆機能」をもつ可能性もある。
「比較されたときの不満=相対的剥奪感」は、潜在的機能の代表例である。米軍の中で、空軍の将兵の昇進がもっと早いという客観的な事実があるのに、昇進に対する将兵の不満は空軍でもっとも強いという調査結果がある。なまじ昇進が早いという現実では、昇進に対する期待感は他の軍よりも大きくなる。このときに昇進が遅れると不満が非常に大きくなるというのである。期待の大きさに比べてそれが実現しないときの落胆が「相対的剥奪感」とされる。良い職場であるがゆえに、こうしたマイナスの不満を呼び起こしてしまうので、これは「潜在的機能」の一つである。
さて、「予言の自己実現」が、マートン理論の精髄をなす。ある筋が、「どこそこの銀行が危ない」という噂を流したとしよう。この噂が増幅して、その銀行が取り付け騒ぎに巻き込まれる。そして、実際に倒産してしまうこともある。逆の事態もある。選挙で、絶対に当選するとの噂が流された候補者が実際には落選してしまうことも結構事例としてある(Merton, Robert King[1949])。
予言が実現されることもあれば、意図せざる逆の結果を生むこともある。つまり、将来は不確実性に満ち、結果も不確実なのである。
このように、人の行動が思わぬ結果をもたらすという局面に社会学の存在理由を見出した父に反して、市場は予測できる範囲で合理的に動くはずであるとした子マートンは、市場の痙攣に弾き飛ばされた。
演繹理論と分析しか科学として見ない父ミルから、帰納理論と叙述に人間性を復活させようとした子ミルへの流れとは正反対の成長を、子マートンは、潜在的機能として担ってしまったのである。