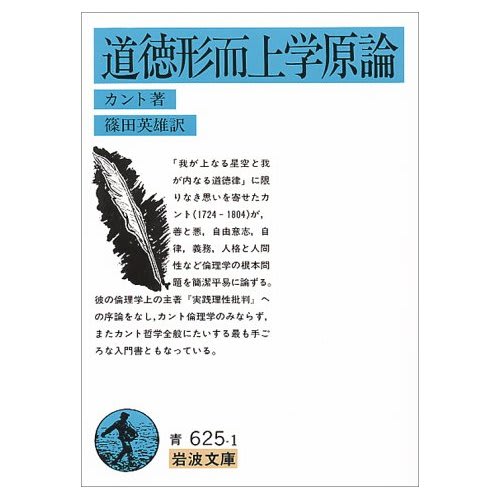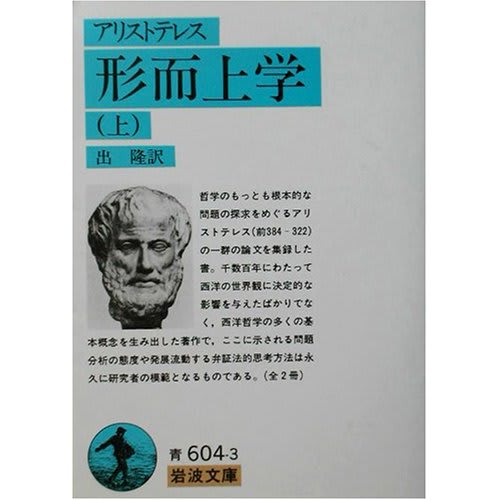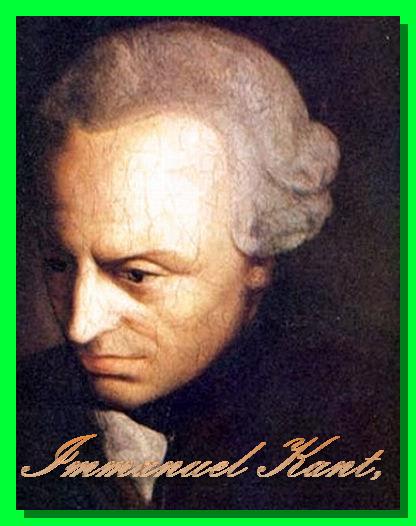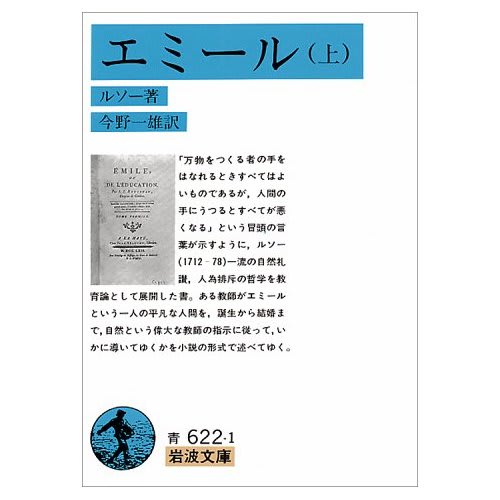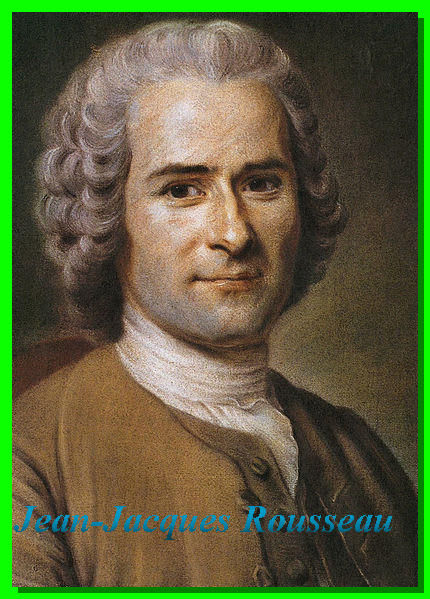本山美彦(京都大学名誉教授)
1 「形のあるもの」と「形のないもの」
ものを考える方法には二種類あるとカントは理解している。形のあるものに拘り続けて考え抜く方法と、形には拘らず考え方そのものの道筋を追う方法である(1)。
形のあるものに拘り続けるものとして、カントは物理学を挙げている(Kant, Immanuel[1785]、邦訳、五ページ)(2)。物理学は自然の法則を考える学問である。自然は形があるのでそれを研究する物理学がこの部類に入れられるのも当然であろう。物理学が自然学とも呼ばれてきたのもそのためである。
ところがカントは、倫理学をもこの部類に入れている。倫理とは形がないのではないか?それなのにカントはなぜ倫理を形のあるものとして理解したのであろうか?
カントは、形の中に経験を含めている。経験とは現実世界を生きていくさいに出会うことなので、現実世界の産物として形があるものと位置付けられるのであろう。経験から人の意志が生成されてくる。その意味で意志は形をもつ。意志を研究する倫理学はその意味において形をもつ領域の学問である(同、五~六ページ)。
ただし、意志は自然とは異なる。自然は物理的な法則に従っているという点で自らの意志をもたない。つまり、自分の外に存在する法則によって拘束されている。人の意志は自然の法則に拘束されていない「自由な」存在である。この意思の「自由」がカント哲学では最重要の位置を占めている。
人の意志が自由な存在であるといっても、自由があらゆるものから拘束されていないというわけではない。人の意志には、「そうなるべきもの」(ゾルレン、sollen)という拘束がある。「あるもの」を「なるべきもの」にさせる法則がある。その法則とは「道徳」である。道徳に従う人の意志が「なるべきもの」を創り出す。法則を研究するということにおいて、自然の法則を研究する物理学(自然学)と道徳哲学は同じである。
カントが面白いのは、道徳哲学が「そうあらねばならない」といったことのみを研究するのではなく、必ずしも「そうならない」という事態が発生する理由も研究対象にしなければならないといい切った点にある(同、七ページ)。
形のないものを研究するのが「論理学」である。それは、ものの考え方を経験知に拘束されずに「考え方」全体(思惟一般)を整理するものである(同、六ページ)。
以上の説明によって、カントは、古代ギリシャ哲学が「物理学」、「倫理学」、「論理学」の三つに分かれていた理由を読者に理解させた。
カントは、古代ギリシャ哲学が三つに分類されることの妥当性を説明した後、「哲学」(フィロソフィ)と「形而上学=純粋哲学」(メタフィジクス)との区別に進む。
古代ギリシャの哲学は「フィロソフィ」である。しかし、これからの哲学者は、その「フィロソフィ」を「メタフィジク」(純粋哲学)にまで高めるべきである。「純粋」という言葉を、カントはあらゆるものにの適用できるという意味で使用している。経験的な部分だけに留まるのではなく、経験から超え出た「アプリオリ」によって導かれる普遍妥当性を目指すのが「純粋哲学」=「形而上学」(メタフィジク)であるとカントは理解する(同、七~八ページ)。
2. 『道徳形而上学原論』の邦訳による上記の該当個所
『道徳形而上学原論』の邦訳者、篠田英雄の訳は正確である。随所に配置されている訳者解説も素晴らしい。私は、カントの数ある訳書では篠田訳をもっとも重宝している。しかし、意訳がタブーである学術書の宿命で、哲学の訳書の文章は例外なく晦渋である。カントの邦訳も例外ではない。そのこともあって、哲学の門外漢がカントの邦訳を読む苦労はあまりにも大きい。以下、前節で依拠した篠田の邦訳を掲載させて頂く。ポイント毎に個条書きにする。
①(物理学、倫理学、論理学といった古代ギリシャ哲学の)「区分は、哲学というものの本性にかんがみてしごく適切であり、これに区分の原理を付け加えさえすれば、格別訂正すべき点はないと言ってよい」(同、五ページ)。
②「いっさいの理性認識は─実質的であって、なんらかの対象を考察するものであるか、それとも形式的であって、対象の差別にかかわりなく、悟性や理性そのものの形式と、思惟一般の普遍的規則を攻究するものであるか、二つのうちのいずれかである、この形式的哲学は、論理学と呼ばれる、これに対して実質的哲学は、一定の対象と、これらの対象が従っているところの法則とを研究するものであるが、この哲学はまた二通りに分かれる、これらの法則は自然の法則であるか、それとも自由の法則であるか、両者のいずれかだからである。そして自然の法則に関する学は物理学であり、また自由の法則に関する学は倫理学である、なお物理学は自然学とも呼ばれ、また倫理学は道徳学とも呼ばれる」(同、五~六ページ)。
③「論理学は、経験的部分を含むことができない。それは─思惟の普遍的、必然的法則の根拠は、経験から得られたものであってはならないということである。もしそうだとしたら、そのような学は論理学ではないだろう、およそ論理学は、悟性あるいは理性にとって、いっさいの思惟に例外なく通用し、またこれらの思惟において直接に証示されねばならないような規準でなければならない」(同、六ページ)。
④「これに反して自然哲学と道徳哲学とは、いずれも経験的部分をもつことができる、自然哲学は、経験の対象としての自然に対して、また道徳哲学は人間の意志に対して、それぞれその法則を規定せねばならないからである、なおここで人間の意志とは、自然によって触発される限りにおける意志を指している」(同、六~七ページ)。
⑤「ところで自然哲学の規定せねばならない法則とは、いっさいのものがそれに従って生起するような法則である。また道徳哲学の規定せねばならない法則とは、いっさいのものはなるほどそれに従って生起すべき(sollen)であるが、しかし、道徳哲学においては、この生起すべきものが実際にはしばしば生起しないこともあるような場合の諸条件をも併せ考えるのである」(同、七ページ)。
⑥「およそ哲学が、経験から得られた根拠にもとづく限り、そのような哲学は経験的哲学と呼ばれてよい。しかしア・プリオリな原理にもとづいてのみその緒論を述べるところの哲学は、これを純粋哲学と呼ぶことができる。ところでこの純粋哲学が、まったく形式的な学であれば、論理学と呼ばれるし、またもっぱら悟性の一定の対象を論じるような学であれば、それは形而上学と呼ばれるのである」(同、七~八ページ)。
以上が、前節の叙述で依拠した元の邦訳である。訳は正確である。しかし、内容を理解することは容易ではない。このような文章を晦渋な文というのであろう。私などは、この種の文章に接する度に読むことを放棄したくなる。しかし、放棄できないのは、晦渋な文章を理解しないことには、論理思考が身に付かないと信じるからである。事実、内容的には珠玉そのものである。カント哲学の邦訳書をパソコンの操作入門書(マニュアル)になぞらえるとまことに訳者に失礼ではあるが、私はどうしても、初めてパソコンに取り組んだときのマニュアルの文章の意味不明さに悲鳴を上げたことを思い出す。それでもマニュアルを手放さなかったのは、ただパソコンを使いこなしたかったからである。
注
(1) このような俗っぽい表現をすれば哲学の専門家の眉をひそめさせることになることは重々承知している。私は日本の哲学者たちが日本の近代社会に果たした貢献を心より尊敬している。しかし、私は、松岡正剛の次の言葉に共感を覚える。
「(参考)アリストテレスの全著作については岩波の全17巻の全集がすべてで唯一であるが、その他いろいろ翻訳が単立しているほか、中公の「世界の名著」や筑摩の「世界古典文学全集」のたぐいでも主要なものが読める。解説書も田中美知太郎、出隆、西谷啓治、藤井義夫をはじめ、戦前からけっこうな量が出ているものの、本書の岩波文庫版『形而上学』の出隆の解説がそうであるように、一般読者には何を書いているのかほとんどわからないものが多い。では、何か適当な解説書があるかというと、これが見当たらない。いろいろ遊んでいるうちに何かを発見するしかないはずである」(「松岡正剛の千夜千冊、思構篇、二九一夜、二〇〇一年五月一四日、『アリストテレス、形而上学、上・下』岩波文庫、一九七九年、http://1000ya.isis.ne.jp/0291.html)。
(2) カントの原著は「アカデミー出版、カント全集」(Immanuel Kants Gesammelten Werken)が標準的に使用されている。これは全二二巻からなり、著書が一~九巻、書簡が一〇~一三巻、手記が一四~二〇巻である。ただし、本稿では、異なる版も使用している。
引用文献
Kant, Immanuel[1785], Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Immanuel Kants Gesammelten
Werken, Band IV. 邦訳、カント、篠田英雄訳『道徳形而上学原論』岩波文庫、
二〇一二年(第七〇刷)(一九六〇年第一刷、一九七六年第二〇刷改訳)。