世界を支配するIC技術
そのICというものが世界を支配すると思います。必ずこれは軍事技術に応用されます。つまり、戦争の現場にどの程度必要物資を送るか、これは「ロジスティック」と言います。日本語でいう「兵站業務」をICが果たします。そうすることでどの地域にどれだけの武器が流れて今どこに集積しているか。こういったことが把握できるようになります。
何よりも恐いのは私達が監視されるようになることです。これからは例えば携帯電話を駅でかざすと目的地へどういうルートで進めばよいかが携帯電話に入ります。便利になったなあと思います。けれどもこれは逆に言えば、私がどこにいるかが当局に見られていることになります。あるいは皆さん、カーナビを使っていらっしゃるでしょう。あのカーナビはスイッチを切ることができないことをご存知でしょうか。切っているように見えるけれども、あれは全部発信されているのです。だから、我々がどこにいるかがカーナビでわかる。
日本産業界も武器開発へ
まあ、考えたくないけれども、本格的に監視される世界に私達は突入しているのです。その時アメリカ方式とか日本方式とかフランス方式とか各国毎に方式が変わっていたら困ります。ペンタゴンで統一することになる。そうしますとそういう企業に群がっていくでしょう。誇り高き三菱重工といえどもそれからはずれたら巨大マーケットを失います。ですから今、必死になって三菱は食い込もうとしている。そのためには武器三原則は邪魔だ、共同開発させてほしい、イージス艦の一部を我々にも作らせてほしいと。こういう方向へどんどん持っていかざるを得ない。そういう意味でも日米軍事同盟の一体化というのは、悲しいことながら産業界の方で一体化が進んでいると思わざるを得ない。これが現代版軍産複合体だということです。
宣伝映画のすごい影響力
その状況を分かりやすく説明しますと、まず映画で宣伝します。もう腹が立ちます。「海猿」というのでしたか、海上保安庁の宣伝映画を見たのですが、かっこいいですよ。上手に作りますよ。次第にその気になっちゃうのです。それで海上保安庁の人に聞いたら、「すごく今年は受験者が増えました」と言っていました。あるいは六本木ヒルズの前に突然戦車が現れるのです。東名高速度道路を富士駐屯地から戦車が走ってくるのではないのです。それこそばらばらに部品にはずし、六本木ヒルズの前に集めて、そこでみるみる組み立てて戦車ができる。こういう宣伝をあちこちでしていくのです。
そうしますと私達はああいう職業がかっこよくなるのです。ゴルゴ13(超一流のプロ狙撃者が主人公の劇画)、麻生外務大臣なんかゴルゴ13の愛読者だと平気で言うでしょう。そんなことをやって結局私達は暴力を使うかっこいい職業として見るのです。こういった方向に次第に私達は洗脳されていくのです。
「労働の流動化」という首切り
「労働の流動化」は、いまでこそ当局にとってありがたい便利な言葉です。私は経済学をやめたいくらいこの言葉が嫌いです。つまり首切りの自由化のことなのです。それを「労働の流動化」というのです。皆さんは本気でそう思いますか。やはり一生かけて成し遂げる仕事にみんなあこがれるわけです。しかし皆さん、今では中華鍋のない中華料理店、火のないレストランとかがあるのをご存知ですか。それこそ許せないのです。どこを見ましても店長だけが社員で後はみんなパートタイマーです。
「労働の流動化」で何が腹が立つかと言いますと、昔の日本の経営者はどんなにつらいことがあっても従業員の首は切らなかった。戦後の大変な労働争議、革命前夜であった労働争議、その労働争議を潜り抜けてきて日本的労使一体化路線にやっと来た。その時に労働組合に対する恩義があって首は切らない、ということが長いこと続いてきたのです。
これをいつの間にか、日本は労働賃金の硬直化で結果的に日本人の消費が伸び悩んだとか、護送船団方式とか文句を言われています。ふざけるなと言いたくなるのです。アメリカに文句を言われる前までは、日本には21の都市銀行があって一つもつぶれなかったのです。しかも5.5%の利子があったのです。それが今は、都市銀行は3行くになってしまって利子は0.1%になったのです。何が金融の自由化だ、護送船団方式に戻せと言いたい。
皆さんお気づきですか。最近の若い男の子達は、女の子に金を払わせている。飲みに行っても女の子に払わせる。なぜかというと、女の子はかわいいからパートで使ってもらえる。男の子は就職先がない。まずないのです。仕方なく女の子のヒモになっていく。こういうように男の子に就職先がないという社会。
こういう社会に先ほどの軍事的なものがポッと来たらどうでしょう。ちょうど戦後すぐで我々は生きるのが精一杯の時に突然暴力団が流行ったのと同じように、今の日本でもそういった土壌ができているのだと知っておいてほしい。おそらく若者達がそちらに流れていく可能性は否定できないと思います。ますます境界線はあいまいになってきています。
4、ICタグで世界支配をもくろむペンタゴン
ICタグは儲かる
何度も言いますが軍事というのはものすごく儲かるのです。具体的にいいますとICタグをご存知でしょうか。あの世界貿易センタービルが燃えた時に、ほんとうに勇気のある消防士達がビルに入ったのです。彼らは死を覚悟していたのです。だから自分達は後で見つかるように一生懸命ヘルメットに自分の名前を書いていた。
それを見ていたある起業家がICタグを思いついた。1ミリ程度の小さなICつまり集積回路を皮膚に埋め込んでしまうと、人物が誰であるかが認知される。そこで開発されたのが、今流行しているICタグです。
広島ではまだないのかもしれませんが、関西では「ICOCA」、あるいは関東では「SUICA」とか、こういうものを通すだけで認知されます。ICの中にすべての情報が取り込まれていき、それが読み取り機により一瞬ですべてがそこで分かるということです。例えばスーパーで読み取るバーコードがあります。あれもアメリカが開発したのですが、商品をいちいち通さなければなりません。ICタグを全ての商品に植え付けたら、カートを押すだけですべての計算が済む。カードを渡すだけで一瞬で取引は終わるということです。あるいは入庫するときも出庫するときも瞬時で数量を把握できる。
一番恐ろしいのは、私達が例えばヘアークリームを買って家で開けて使った。その時にそのヘアークリームのメーカーは、この製品は広島のどの地区で今開けられたということが分かる。こういうことなのです。これがICタグなのです。
ペンタゴンの命令でICタグ開発
このICタグの開発を命令したのがペンタゴン、つまり国防総省です。ペンタゴンが使うアメリカの国防費はものすごい額です。日本の国家予算にほぼ匹敵する年間40兆円ぐらい。そしてアメリカ以外の世界の全ての国の軍事費を合計したよりもアメリカ一国の軍事費の方が上なのです。古今東西、これだけの軍事予算を費やしている国はまずないのではないかと思います。
逆に言えばものすごくおいしい蜜がそこにあるということなのです。企業にとっては、ペンタゴンと取引することがどれだけ大きな意味を持つかは明らかでしょう。そしてペンタゴンの命令でICタグの開発をやる。ペンタゴンに出入りする業者はそれを義務付けられている。同時に民間にノウハウを蓄積させるために世界最大のスーパーマーケットであるウォルマートにICタグの開発を依頼したのです。結局ウォルマートでは、最初にテキサスのダラスで納入業者がICタグ取り付けを義務付けられた。そして今年に入ってそれが全米のウォルマートで義務付けられている。
アメリカ方式の押しつけ
そして、その次にそれを世界的に普及させていかなければならないということになり、今、日本でどの方式を採用するかの対立がある。経産省はアメリカ方式、つまりMIT(マサチューセッツ工科大学)方式を日本に採用させようとしている。それに対してわが日本には東大教授だった坂村健さんのICタグがあり、方式が違うのです。それをアメリカ方式にしろということになった。坂村さんが負けたのはこれで2回目なのです。 ご存知ですか。日本人は独創性がなく物真似ばかりすると我々もそう信じこまされていますが、嘘です。独創的なものを作ればすべてアメリカによって叩き潰されるのです。
日本にはトロン方式というのがあったのです。そのトロン方式は坂村さんが開発したのです。それを松下電器が普及したのです。松下が普及して、小学校段階からこのトロン方式を学ばせようとしていたらアメリカがいちゃもんをつけてきた。カーラ・ヒルズという女性のアメリカ通商代表(USTR)が文句をつけてきて、けしからんと中止させられてしまった。生産も取りやめになった。 そして松下の不買運動が起こった。かわいそうに松下は、パソコンで先行していたのに、それを禁止されたのです。あの打撃は大きかった。それを世間の人は、「松下は松下幸之助が天皇になりすぎて技術開発をさぼったのだ」と言った。よくもかわいそうなことを言うなあと思いますが、寄ってたかって潰されたのです。そしていつの間にかあっという間にウィンドウズです。この様に独創的なことをやって、そのマーケットが奪われそうになったらアメリカに叩き潰されるのです。
坂村さんはいい人です。坂村さんが毎日新聞に寄稿していて、それを読んで私は涙が出てきました。彼は書いています。「日本人はグローバル・スタンダードを作るのが下手だ。実はフランスで寿司を食べて美味しかったけれどその寿司屋には日本政府の認定証がない。せめて日本のコシヒカリ(実は、わが福井がコシヒカリを開発したのです。越の国の光、魚沼ではないのです)を使ったら5つ星だとか、カリフォルニア米を使えば4つ星とか認定制度を作るべきである。認定制度を作らないがために、寿司は下手したら安物のブランドという形で転落する可能性がある」と。
坂村さんは精一杯に、「国家たるものは世界的なブランドを作るためにあるのではないのか。私は2回も開発し、トロンとICと2回とも叩き潰された。その間、国家は何をしてくれたか」との訴えを彼らしく奴隷の言葉で寿司を例にとって政府批判をやったものだから、私は一遍にファンになりました。坂村さんはすごくいい人だと思ったのです。
3、現代版「軍産複合体」の恐ろしい構造
ビン・ラディン一族を顧客とする父ブッシュ

私は、9・11テロは怪しいとにらんでいるのです。ペンタゴンに飛行機が突っ込んだ時にはちょっと穴が開いただけなのに、世界貿易センタービルは、飛行機がぶつかっただけで崩れるなんてことはまずありえないだろうと思っているのです。モノスゴイスピードで突入して行ったのにビルの中に機体が止まったなんて、そんな不思議なことが起こるのだろうか。普通は突き抜けて行くのと違うのだろうか。私は、「あれは陰謀だ」と勝手に捉えているのですけれども。
その日の朝に、親父ブッシュ(ブッシュ現米大統領の父)説明下でカーライルの投資相談が行なわれていたのです。そして、そのお客さんがビン・ラディン一族であったのです。ビン・ラディン一族はサウジアラビアの最大の事業家で大富豪です。少なくともモスク建設の100%はビン・ラディン一族が握っています。
我々がオサマ・ビン・ラディンと言う時に、簡単にビン・ラディンと言ってしまうのですがこれは失礼です。ビン・ラディンというのはファミリーネームのことであってオサマというのがファーストネームなのです。ほんとうはテロリストという言葉を使いたくないのですが、テロリスト「オサマ・ビン・ラディン」と言うのです。このビン・ラディン一族がそこで投資相談をブッシュ元大統領から受けていた。その時9・11テロがあった。
9・11テロは怪しい
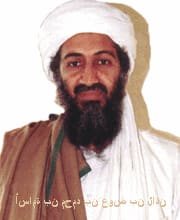
でも不思議なことには、あの時に即座に彼らは全部いなくなった。オサマ・ビン・ラディンが黒幕だと言われていた時、犯人の血縁者、一族郎党が集まっているのですから普通なら留め置きです。サウジアラビア人だというけれども、国籍がそうなのであって彼らのほとんどはカナダやテキサスに住んでいるのです。それがかわいそうにチャーター機でサウジアラビアのリヤドまで連れて行かれたのです。
けれども不思議なのは、飛行機テロが起こったのならば戒厳令で民間航空はすべてストップされるはずです。それなのにいち早く飛ばされて国外脱出できただけでも怪しいと思わなければいけない。事情聴取も全然していないといったことで私は陰謀説に本当に傾いています。
アイゼンハワーが警告した軍産複合体
話があちこち飛びますが、どうしてこうなってしまったのであろうか。まず、皆さんご存知のアイゼンハワー(通称アイク)が大統領を辞めるときに、初めて「軍産複合体」(military-industrial complex)という言葉を作りました。それまでトラクターメーカーだった。そのトラクターメーカーであった会社が、アメリカが戦争に参加するようになっていつの間にか武器メーカーに変わって行った。そして多くのアメリカ人達がそういった軍需産業に雇われるようになっていった。軍需産業である限り、儲けようと思えばどこかで戦争を吹っかけてしまう。「わがアメリカは軍産複合体の儲けが大きくなるようにすることで、しなくてもいい戦争に巻き込まれる恐れがある。だからいち早くアメリカ人はそういった軍産複合体が大きくなることを阻止しなければならない。これはアメリカ市民の義務なんだ」と語り、そしてアイゼンハワー自身は原子力開発を止めるとまで言っていたのです。
ところがベクテルの社長ジョン・マコーンがアイゼンハワーの政権にいて原子力委員長であったのです。ベクテルは世界の原子力発電の8割を設計しました。わが日本の巨大産業である三菱重工といえどもベクテルの設計図どおりに下請けしただけのことです。さらにケネディーが暗殺された時にマコーンはCIAの長官だった。私はこれも怪しいと思っています。少なくともアイゼンハワーのようなアメリカの良心がありながら、良心を持った人達は何らかの形で押さえつけられるか追放されていった、という非常に恐ろしい仕組みがアメリカの社会にビルトインされているということです。
(画像はすべて「ウェキペティア」から-編集者)
3、現代版「軍産複合体」の恐ろしい構造
戦争が一番儲かる
同じことが現在もっと大規模に行なわれているのです。悲しいことに戦争が一番儲かるのです。少なくとも、きちんとした国家の軍隊は堕落していない。しかし、いい加減な国家というのは、いい加減という差別的用語はいけないけれども、ほんとに自国を売り物にしている。アメリカの会社に対して、ダイヤモンドの採掘権を与えるから、その代わりに我々の治安を維持するためにあなた方の民間の警備会社を貸してくれ、ということを平気でやるのです。多くのアメリカあるいはイギリスの軍事請負会社というのは、武力的に言えば貧しい途上国の国軍よりも兵器も戦闘能力も上なのです。そういう連中が戦争を請け負ってしこたま儲けていくということです。
当然といってはおかしいですが当然の成り行きなのです。昔のように正面線で軍隊と軍隊が衝突していくということはまずない。今の戦争は必ず暗殺である。少なくとも政治的指導者は暗殺しなければならない。暗殺していくときに暗殺の資金はどこから出るのだろうかと私は疑っているのです。いろんなところに麻薬とかいろんな覚醒剤があるけれども、果たして当局のお目こぼしなしに、ああいったものがアフガニスタンから日本へ来るだろうかと思います。アヘンの70%はアフガニスタンから来ているのです。その間いろんな国を通って行かなければならないと考えたときに、私はかなり怪しいと思います。
そういった非合法の戦争をしていく資金源は非合法な稼ぎ方をしているだろうし、非合法の人員は民間軍事会社から調達しているだろう。現在そういった形で世界的な軍事編成が変わってきているのではないだろうか。
戦争がらみの企業集団
問題は、そこですごいワンセットの集団が出来上がっているのではなかろうかということです。まず金融会社が巨大事業を受注してきて自分の関連会社に生産させていく。そしてその関連会社が出て行くときに、その関連会社を警備する警備会社も連れて行く。そういう意味では、すべての一番後ろにはアメリカのペンタゴン(国防総省)がいて、ペンタゴンの認可の下でワンセットの戦争がらみの企業集団が形成されている。多国籍企業は平和の顔をしておりますけれども、まず汚らしい表面に出せない裏家業的な事を平気でしなければいけない。ただ戦争するだけじゃなく、お金と物と暴力とのワンセットを備えた一群の企業集団ができている。そして、それの後押しというか連係プレイをペンタゴンが保障している。そういった軍産複合体というものがほんとにできているのだ、と私達は理解しなければいけないと思います。
典型例はカーライル
正直なところ固有名詞を挙げるのはだんだんと恐いのです。ほんとに『民営化される戦争』を書いた時に、「1人で飲むなよ、やられるぞ」と言われました。ほんとに恐いのですが、例えばカーライルという会社があるのです。ここは主として、武器を売る宇宙産業、ミサイル産業といったところに融資、融資というよりもM&Aによる企業の吸収・合併を後押ししている会社です。軍産複合体の大元締めと考えてもいいと思います。
その大元締めの会社で親父ブッシュの元大統領がアジア担当だったのです。中国、朝鮮半島、日本の担当だった。実は親父ブッシュは自分の子供達3人を就職がなかった頃にカーライルに面倒を見させておりました。さすがに世間の批判が厳しくなってアジア担当の役職を辞任しましたけれども。これだけでも、カーライルは非常に大きな影響力を持っただろうなと想像できます。そのカーライルが今流行のMD(ミサイル防衛)に関与してきているのです。
続いて2番目の論点に入ります。アメリカが世界で戦争をしています。先に結論から言います。アメリカと日本は志を同じくするのだから日米一体化しなければならないのだ、というのは断固拒否。具体的には、わが日本は戦争をしていない。アメリカは世界で戦争をしている戦時国家なのです。戦争している国と戦争していない国とは同じだというのは、ふざけるなと言いたくなります。戦争していない国は戦争している国とは握手してはいけないのだ、我々は一切の戦争に加担しないのだ、ということが一番大事なことなのです。
アメリカは所得格差最大の貧しい国
アメリカ兵についての問題から始めたいのですが、世界で戦争をしているアメリカと言うときに、ここにも私達が大きな誤解を持ちます。アメリカでは徴兵制をしているのだ、いやいやながら戦争に取られているのだろうと理解しがちです。そうではないのです。アメリカでは兵隊さんは自発的に応募してきているのです。これはすごいことなのです。アメリカという坩堝の中で典型的な誇り高きアメリカ人が生まれてきて、世界の平和のために我々は血を流すのだと言って、志に燃えて応募してきているのだろうか。そうではないと思うのです。ここが現在の戦争の悲惨なところです。
世界では、先進国の中ではですけれども、アメリカは最も貧しい国なのです。この貧しさの定義はというと、すべての所得、つまりビル・ゲイツからホームレスの一番貧しい人達までの所得をずらーと並べて平均値の所得を取ります。その平均値所得以下の人達が全人口のうち何%を占めるのかというのが貧しさの指標なのです。その中でダントツに1位はアメリカです。そして、わが日本がほぼ近い2位です。
つまり、今の所得格差が大きいということはそういうことなのです。ビル・ゲイツは全アメリカ人のサラリーマンの半分の所得をすべて独り占めしています。そのビル・ゲイツ1人がおり、他が貧しいという社会を豊かな社会というのか。それは貧しいということなのです。豊かな社会というのはみんなそこそこの平均値であること。家も小さい、みんな平均値だけれどもまあ飢え死にしなくて済むというのが豊かな社会なのです。1人の大金持ちを持ってきて、それがGDP(国内総生産)を上げても意味がない。人々の所得がそこそこに平均的で格差のない社会。これが豊かな社会なのです。アメリカが最も貧しいと言いました。最も貧しいがゆえに、アメリカではすべてがお金です。大学へ行くのもお金です。
社会的認知を得るために軍隊へ
そうなれば誰でも大学に行けないでしょう。大学に行くには奨学金が必要でしょう。アメリカではその奨学金というときに、果たして単なる書類審査だけで通るだろうか。少なくとも地区の顔役あるいは教会の牧師の推薦がいるであろう。少なくとも社会的に認知されなければ奨学金そのものが当たらない、となります。そうしますと、貧乏人が大学へ行くために得る一番大きな社会的認知といったら何かといえばイラクに戦争に行くことである。そうすることによって市民として認知されていく。ましてやただでさえ白い目で見られているメキシカンとか、日本人、中国人、朝鮮人といったアジア人にとって。アジア人は大体、受験勉強は得意なのです。そうすると東部の大学では、あまり表門の試験ばかりでやるとアジア人ばかり通ってしまう。だからアジア人排斥で逆差別しなければいけない、という議論が真剣に交わされている。少なくとも人種的な差別というのは依然としてある。そういった中で大学へ行こうと思えば、市民として認知されなければいけない。認知してもらうための最も手っ取り早い方法が軍隊に行くことである、と考えたらいかがでしょう。
軍隊で心に深い傷
しかし、軍隊へ行っても、自らが分裂します。認知されるために人をどんどん殺してくる。実はアメリカのちゃんとした陸軍士官学校のテキストにあるのですが、人は目が合うと殺せないのです。だから、ドンパチやっているのはみんな空へ向かって撃っているのです。それでは弾薬をいくらつぎ込んでも埒があかないというので、テレビゲームのようにミサイルを撃ち込む。相手が死ぬ場面はミサイルを撃った本人にはわからない。こういうことをどんどん技術化していくのです。しかし、少なくとも市街戦を演じたら分かる。殺戮です。自分で相手を殺すわけです。その心に非常に傷を受けた人間が国へ帰ってきて大学生になって、「今から勉強するぞー」と思っても果たしてやっていけるだろうか。要するに自分が認知されたいがために戦争に行く。しかし戦争に行ったがために自分の心はズタズタになって引き裂かれたようになる。その連中を誰が面倒を見るのだろうか。
帰国後の仕事は軍事請負企業で
つまり、私達がいわゆる広域暴力団とかに「暴力団帰れ!帰れ!」と言いますけれども、よく見たら彼らは日本国内において差別されている連中ではないか。彼らがまっとうな就職先がなければアウトローの世界に行くのを認めるわけじゃないけれども、私は同情します。
同じようにアメリカで戦争に行って帰ってきた若者達がきちんとした大学に行き、きちんとした企業へ就職することができるのだろうか。まあ多くの人はそうするかもわかりませんが、かなりの人達はそこに何らかの精神的な負い目、異常をきたすでしょう。そうすると逆に人殺しの技術をもったそういう人達を雇うとんでもない会社が出てくる。これが民営化された戦争の意味なのです。
つまり、戦争に明け暮れる国で若者の心が傷つくがゆえに若者の就職斡旋機関として企業が戦争請負業をしていくのです。あっちこっちでたくさんの紛争が起こっている時に、果たして企業が丸腰で行くでしょうか。この広島市内で、この平和な社会では企業はほんとに丸腰で生産と販売をしています。これが紛争地区のコンゴで、イラクで、アフガニスタンで企業活動をしなければならない時に、果たして丸腰で行くだろうか。その時には当然警備専門家を携えて行くであろう。そして、石油を掘ったり、パイプラインを作ったりする仕事を受注する会社は、必ずそういった武器の携行を許された警備会社も連れて行くであろう。
過去にこのような例はどこの国でもあったのです。わが日本も満州を平和裏に取ったのではないのです。武力で奪い取ったのです。武力で奪い取って関東軍がずっと目を光らせてくれるわけではないのです。民間人が入植しても、いつ中国人に襲われるかわからない。だから満州開拓団というのは小銃を携えていたのです。村ごとに大砲を置いていたのです。要するにそういう軍事的な保障の下で侵略していったのです。
途上国のイニシアティブで発展を
そしてその結果「もはや戦後ではない」と言われたのが昭和31年、つまり1956年。これはすごいことですよ。「もはや戦後ではない」と言うのは、昭和11年(1936年)の工業水準に復帰したと。世界5大工業国家の一員に復帰したと。1945年に戦争で徹底的にやられ被災地となった日本は、当時の世界最貧国であったろうと思います。これがわずか11年で戦前の5大国に復帰できたのです。
このことのすごさを思い知らなければならないのです。つまり技術も人間も知識もあらゆるものがその国で根付き、普及しておれば、社会の発展というものは非常にスムーズに行くのだということです。逆に言えば、現在の途上国が先進国の力によって、企業によって分断されてしまっている。だから、1つの国の固まりではなくなりばらばらになって、いがみ合いをしてしまって、結局、現在の貧しさがあるのだということを理解してほしいのです。
だから今大事なことは、はっきり言って「多国籍企業は出て行ってくれ、自分達は自分達でやるから。その代わり自分達の生活できる分野の方に、皆さんお金を払ってくれ」と言うことです。つまり紅茶だったらそれこそ「広島市内でスリランカの紅茶ショップを出さしてほしい。マーケットで売らしてほしい」ということです。これがこれからの人類が取り組むべき課題だと思います。
何も日本人が偉そうにしてはいけないのですけれども、その時のモデルとして、あのとんでもない貧しさからわずか11年で復帰できたという日本の経験を、世界の人達に知らしむべきだと思います。しかし、先進国の企業や学者が途上国の人達に対し、俺達が教えてやるという態度を取ることはとんでもないことなのです。「ほっとってくれ」というのが、おそらく途上国が今後取り組むべきテーマになっていくはずです。私達もそれに備えてのいろいろな事を、私達の社会の中でシステムを変えていくことを模索する。私はこれが「グローバリゼーションを問う」という作業の最も大事な点だと思います。
要するに自分達の国で作り、自分達のイニシアティブで売り、その資本は自分達に回収し、その利益は自分達の社会改造に使っていく。間違っても先進国に横取りされてはいけないのだということです。こういったことの世界的なシステムが作り出されるはずであると私は思っています。そのために悲惨な戦争から学んだのだということを是非分かってほしいと思います
ちなみに私は広島でお話させて頂くのは非常にうれしいのです。実は私は神戸で生まれ、すぐ戦災で焼け出されまして、広島に疎開しに来ていたのです。疎開して来て、ついこの近くにおりまして、呉の広の近くなのです。そこで私は広島の原爆を見たと思っております。母親は「そんな馬鹿な、覚えているはずがない」と言うのですが。それは私がちょうど2歳位の時です。私は鮮明に覚えているつもりで、広島の原爆を本当に経験したつもりでおります。
広島に長いこと疎開させて頂きました。疎開というのはつらかったですよ。ほんとにこう小さくなって過ごさなくてはいけなかったのですが、疎開してから神戸に引き揚げてきた時には驚きましたね。天井のない貨車で帰ったのですが、長いこと20時間位かかってやっと神戸に着いて、三ノ宮駅に降りた時には立ちすくみました。何にもなかったですね。ほんとに瓦礫の山であった。
国産化はグローバリゼーションの反対
おそらくその時、私達は世界で最貧国であったと思います。それをわずか11年間で戻したのだということのすごさを分かって頂けるでしょうか。それを日本のすごさだとつまらんナショナリスト達は言うのです。私はそうではないと思います。少なくとも一つの国の一つの地域の人達が力を合わせれば、とんでもないスピードで生活水準は上がっていくと私は思っています。国産というのがキーワードだと思っています。グローバリゼーションというのはその反対なんです。それが人々をダメにしてしまっていると私は理解しているのです。
世の中の人々と仲良くしようというときは、自分達が作った物をお互いがリーズナブルな条件で交換していくことが仲良くするということです。よそ様の国にズカズカと入り込んで行ってよそ様の労働力を使って物を作るということは、とんでもないことなんです。そういったことは間違っているんだと、基本的に考えなければいけないと思います。
1、国産化が途上国発展の鍵
「グローバリゼーションを問う」作業とは
今年の4月から福井県立大学に勤めています。ブログで「消された伝統の復権」というタイトルで福井日記をほとんど毎日書いています。福井の風土を織り交ぜながら歴史で消し去られた人達の権威回復を書いており、楽しい読み物だろうと思っていますので是非ご覧になってください。初めは10人程度の読者しかいなかったのですが、アクセスする方が数百人程度に増えており喜んでいます。早く1日千人を超えることを目標としているところです。
「グローバリゼーションを問う」という時、どうしてグローバリゼーションということにこだわらなければいけないのか、反対しなければいけないのかについて簡単にお話したいと思います。グローバリゼーションは「地球的規模」という意味ですが、あんまりいい言葉ではないのですね。
分かりやすく言えば、例えば紅茶はスリランカで主に生産されるということを私達は知っている。あるいはコーヒーはジャマイカだと、天然ゴムはマレーシアだということは知っている。つまり、あらゆる特産品がそれぞれの国で作り出されていることは誰でも知っている。でも私達は、知識がそこで終わってしまうのです。もう少しきちんとお話しますと、紅茶が好きだという人が自動販売機で冷えた紅茶を買うという時、そこから一歩進めて考えてほしいのですね。この紅茶の生産地はスリランカなのに、ここの自動販売機で売られている紅茶はアサヒ飲料であり、キリンであり、あるいは伊藤園であるというように、いわゆる日本あるいは先進国の企業のブランド名で売られているのです。
ここが大事なんですね。つまり、力の強い国によって力の弱い国々は作らされ売らされ価格も決定されている。貧しい国の人々は厳しい労働を強制され一生懸命働くけれどもそこでの資本、利益、知識といったものが全体としてみんなに行き渡らない。儲けも技術もすべて一握りの外国の大きな企業に持っていかれてしまう。こういうことがこの世の中で正しいことなのだろうかと問うことが、「グローバリゼーションを問う」という作業のことなのです。 石油はサウジアラビアあるいはクウェートでとれるとか、日本はアラブ首長国連邦からたくさんの石油を輸入していることも知っている。けれども、ガソリンスタンドに、例えばクウェートでしたら「Q8」ですが、皆さん「Q8」のガソリンスタンドを見たことがあるだろうか。作らされているのは貧しい途上国で、生産物は先進国で販売し消費している。そういったルートを握っているのが先進国の一握りの企業である。そうしたことは少なくとも神様がお許しにならないだろうという問題の立て方。これが、「グローバリゼーションを問う」という作業なのです。
立地上の不公平を問い直す
私達日本人は平気で外国へ行きます。1万円札を持っていきます。両替してくれるものだと決めてかかっています。私達日本の銀行は世界各地に展開しています。そして日本には非常にたくさんの人々が世界中から来ています。でも果たして日本にタイの銀行があるのか、インドネシアの銀行があるのかと考えると、日本に来ている方々の母国の銀行が入っていることはありませんよね。一部は入っておりますけれども、こういう立地上の不公平というのは誰が見ても明らかなのです。 世の中というのは紛争が起こりあらゆる戦争が起こるけれども、結果的にはそれがプラスに転じてきた。その後には必ず平等な社会ができてきた。
つまり紛争は常に抑圧され虐げられた人々の反抗運動から起こっているのであり、その力によって権力側が譲歩していって次第に平等な社会ができてきたのです。しかし、その平等な社会ができた時に私達は生き抜いていけるのか。もし石油が完全に産油国側の力の下に服すことになった時に、石油だけに頼ってきた日本の社会が果たして現在のような大量消費社会を維持することができるのだろうか。私達は今の間にそういったことを想定して、心構えをし、社会が激変しないでソフトランディングする方法を指向していくのが文明人というものではないのか、という問題の立て方が必要です。
国産の低技術から復興開始
もしすべての技術が、すべての資本が、労働力が、知識が、あるいは防備が自分達の国だけで使われるとすれば、社会というのは意外に発展が早いのです。例えば、日本はアメリカに占領された。アメリカに占領されたけれども降って沸いたような幸運、隣の国の不幸を幸運と言うと失礼なようですけれど、朝鮮動乱が起こった。朝鮮動乱が起こったためアメリカはいち早く日本を復興させなければならなかった。いち早く日本を復興させて反共国家に仕立て上げなければならない時にアメリカがやったことは、日本を放置つまりほったらかすことであった。
当時は、皆様の地元の東洋工業(現在のマツダ)とか日産とかトヨタとか、日本の自動車会社には正直言ってろくな技術がなかった。アル・カポネが活躍した暗黒の時代のアメリカの映画を観ていたら、1930年代にはすでにセル一発でエンジンがかかるような車が走っていました。日本では私が運転免許を取る頃、つまり1960年代の頃は、私達はしょっちゅう車の前に回ってエンジンをかけるためにクランクを回していました。私ぐらいの年配の方なら分かってくださると思うのですが。セル一発ではエンジンはかかりませんでした。それほど日本社の技術が低かった。名神高速道路ができた時に、私が「京都-尼崎間をノンストップで走ったんだぞ」と言った時に友人たちは嘘だと言いました。つまり、当時は日本のトヨペットなんかは路肩に車を止めて、とにかくオーバーヒートしたラジエーターを冷やしていました。しかし、外車だけはスイスイ、スイスイ走っていました。
今の社会だったらその技術差が明らかな時には、アメリカの資本、アメリカの企業のビッグスリーが入ってきて日本で生産をするはずなんです。ところが当時の日本の置かれた状況は、朝鮮動乱で一刻も早く日本の産業を復興しなければならない時なので、アメリカのとった措置は日本に1社たりともアメリカの大企業を入れないことであった。 こういうことが非常に大事なのです。わが日本は非常に技術が低かった。でもすべて国産でやってきた。これは、アメリカと喧嘩してアメリカが入りたいのに俺達は絶対入れてやらない、というように日本政府が強い力を持っていたのではないのです。少なくともアメリカが長期戦略から考えて「アメリカの企業を入れたらだめだ。日本では日本に任せる」ということにしたのだと私は理解しています。ですから、あらゆる分野で国産が可能だったわけです。
「21世紀倶楽部」という組織がある。
その倶楽部が1996年10月31日、「第五回・リバティ・オープン・カレッジ」で、宮澤喜一・元首相の講演会を開催した。
題して、「二一世紀への委任、過去50年間の日本の選択を振り返る」という講演であった。同氏の講演は、占領というもののもつ理不尽さへの憤りが素直に吐露されていた。しかも、独立国家になったはずの日本政府の、対米関係は、占領期のそれと大差がないことを臭わす内容であった。
講演の内容の要約ではなく、講演のなかで対米関係における屈折した日本の位置に関して宮澤が感じたことを抜き書きしよう。
昭和20年8月17日、「東久邇稔彦内閣という、日本で初めてで、その後も例がない皇族首班の内閣ができ」た。
当時、「誰も戦争に負けたということがどういうことかがわかっていませんし、占領についてもどういうことかよくわかりませんでした。とにかく電気がついてうれしかった」。屈強な米兵がくるというので、婦女子の安全を図らなければならないから、政府が慰安所を作ることまで閣議決定をした。こんなヘンテコなことに日本人の意識が傾く有様であった。「そこいらが、まず占領というものではないかと思いました」。
「占領とは、文字通り政府がやること、箸の上げ下ろし一つにいたるまで、第一生命ビルに居るマッカーサーの指示を受けるのです。地方には軍政部があり、県庁の人はみんなそこへいって指示を仰ぎます。これ以上の屈辱はないのですが、そういう状況であって、それは行政府ばかりではありません。国会そのものに占領軍指令部の国会担当者が乗り込んできて、こうやれ、ああやれと指示をするのです」。
そうした屈辱の最たるものが、ある米国人に「日本の議会制度の確立に非常に寄与した」との理由で叙勲したことである。宮澤が総理大臣のときに叙勲をする書類が彼のところに回ってきた。しかし、その米国人は、「国会へ乗り込んできて、ああやれ、こうやれと指示をした男であった」。別に国会に貢献した人ではなかった。ただ、口やかましい人にすぎなかった。宮澤は皮肉を込めていう。「五十年経つとそういう指示が議会制度に寄与したことになるのだなと複雑な思いがしたものです」。
宮澤は断言する。「したがって、よい占領などは本来はあり得ない」と。
「日本政府という大組織があり、一方に占領軍という大組織があると、日米が対立するのは当り前ですが、そのうちに、たとえば、財政は財政同士、交通は交通同士で気持ちが通じてきますから、相手国との対立が自国の部門同士の対立になったりします」と日本政府機関の内情を説明する。
日本と米国との対立ではなくなる。米国内部の意見対立が日本内部の意見対立をだしていたのである。「組織とは時間が経つとそういうものですが、それをうまく利用したりして、何とかやってきました」。
米国の内部対立を利用して、日本の独自性を守ってきたという自負を宮澤は吐露した。まだ公開できない機密がそこにはあるのであろうが、独立後、米国の外圧を利用することが省庁の内部対立を調整する大きな手段となったことも、占領期から受け継いだ姿勢なのだろう。
「昭和二十四年頃には、もう占領はごめんだと日本は思うし、米国もマッカーサーが、『占領は長くやってはいけない』という哲学をもっており、当時の吉田茂総理大臣も早期に占領を終結させようと努力していました」。
そして、宮澤は、米国にはないが西欧には綿々としてある社会民主主義の伝統に敬意をもつ。宮澤自身は、市場中心主義者ではあるが、
「市場経済にはそれなりの欠陥があり、ことに世の中には貧しい人と富む人の間に財産の差、あるいは所得の格差がある。そういう貧富の差を再配分することが、そもそも政治の機能であるとソーシャルデモクラッツは考えます。ですから、高額所得者からは高い所得税をとるべきである。資産課税は厳しくすべきである。産業政策も労働政策もある程度は政府がしなければならない。それがために政府があるのであり、極端にいえば、市場経済でよいのなら政府は要らないのだという立場です」。
「そういう立場の政党が日本でどれくらい成功するかは別ですが、そういう政党が生まれてくるのなら、私はまことに理屈が合っているとは思います」。
そうした政党が日本に生まれるべきだと宮澤はいう。市場経済中心主義の政党と、市場経済の欠陥を是正する守備一貫した政策を打ちだせる社会民主党とが、日本で競い合い、国民の選択肢を増やすことが必要である。
「西欧をみても、高福祉・高負担がゆき過ぎると、保守党が税金を下げる政策を打ちだします。日本もそうであれば、有権者も政策の選択がしやすいだろうと思いますが、なかなかそうはなりそうにないので、心配をしています」。
宮澤が首相のときに、カンボジアPKO(平和維持活動)で、自衛隊をカンボジアに戦後初めて派遣した。戦闘行為ではなく、橋をかけたり道を直したり、いわゆる国づくりの手伝いをすることをPKOという。その活動で二人を亡くした。
「私は一生、これは自分の責任だと背負ってゆかなければならないのですが、しかし、自衛隊がいってあれだけの貢献をしたことは、国内でも評価されたし、国際的にも評判がよかったと思います。しかし、あれが日本のできる国際貢献の限度であるとも私は思っています」。
「つまりそれは、日本国憲法の下で、戦争前・戦争中の経験にかんがみて、『海外で武力行使をしてはいけない』という言葉に尽きると思います。たとえ国連の旗の下であっても、また、他国がわが国に攻めてきそうだから、こちらからでかけていってその出端をくじくといったような場合であっても、日本は海外で武力行使をしてはならない。これが戦後、我々が守ってきた規則であるし、これからも守らなければならないことだと私は思います」。
現在の自民党の閣僚と宮澤との格差は歴然としている。彼は、基本的には親米であり、けっして、米国から中立の立場をとる政治家ではないが、小泉体制以降、宮澤ですら政治の表舞台から追放されてしまったのである。これに、「姿なき占領」が本格化した証左である。
テレビの怖さも宮澤は、率直に認めた。
たとえば、ソマリアで部族間の争いがひどく、食料援助が届かないので、両方の部族を分けて届けるべく、国連は、多国籍軍を派遣した。しかし、米軍が部族間の争いに巻き込まれ、「米兵の死体が道を引きずられていくのがテレビに映りましたから、米国の国民がとても許せないということで、ソマリアから撤退してしまいました」。
「米国のクリストファー国務長官も、『いまの外交政策はテレビで決まる。テレビに何が映るかで、外交政策が左右されざるを得ない時代になった』と私によくいます。湾岸戦争のときも、当時のチェイニー国防長官が記者会見で、『CNNでみた」などというのですから、テレビの影響は大変なものだと思います。しかし、テレビの情報は総合的なものではありませんので、政府は報道があったらすぐに総合的な情報をとるように動かねばなりません」。
ソマリアで戦う米軍兵士の勇猛果敢な姿を描く映画がハリウッドで戦略的に製作されたことについて、私は以前、触れた。正しくは、テレビが外交政策を左右するのではなく、政府が自己の政策を実施しやすくするために、国民世論を誘導する狙いでテレビを利用するのである。「姿なき占領」の常套手段が権力によるマスコミの利用である。
ボスニア・ヘルツェゴビナでも国連軍が人質になっていて、国連の旗の下で軍事行動などできるものではない。その点、米国がもっとも痛切に感じているであろう。米国は、その点で、単独行動と他国の協力を求めるであろうとのニュアンスの発言をした後、日本では、「カンボジアPKOでおこなった程度が限度だと私は思います」と断言する。
「また、他国が日本を攻めてきそうだから、あらかじめでかけていって出端を挫くということは、まさに自衛の名の下で我々が第二次大戦中におこなったことですが、少なくとも我々が過去において自衛の名でおこなったことは少しも成功しませんでした。ですから、たとえどういう事情であれ、国外で武力行使をしてはならないのが鉄則だと私は思います」。
どんな事情があっても、「海外で武力行使をしないということを、我々はきちんと守っていかなければならないと思っています」というのである。
為替の完全自由化に対しても宮澤はそれが投機を刺激するからとの理由で批判的である。
「為替には、思わぬ事が起こるので、非常に怖いと思います。為替のスペキュレーション(投機)をやられると、大変なことになります。たとえば、今年(一九九六年)の二月にも英国の名門証券会社ベアリングス・グループがデリバティブ(金融派生商品)で失敗し、巨額損失を出して倒産しました。為替レートが投機の対象になるのは変動制になってからです。 コンピューターの進歩で瞬間的に投機が可能となり、それにデリバティブが加わると、毎日、一兆ドル単位で取り引きするようになります。どこの国の大蔵大臣も、『為替レートはファンダメンタルズ(経済の基本条件)を反映している』といいますが、相場がこう激しく動くと、それは大変に疑わしくなります。ファンダメンタルズがそう変わるわけはありませんからね。震災や不景気、政治が不安定といわれる日本の通貨が上がり、ニューヨーク市場で史上最高の株高をつけた好景気の米国の通貨が下がるわけを、きちんと説明できる人はいないでしょう。このようなことを、いつまでも放っておいてよいのかと思います。「投資はいいが、投機はいけません」などと私も大蔵大臣のときにいった憶えがありますが、通貨安定は二一世紀までに何とかしなければならない課題の一つです」。
少なくとも、宮澤は、金融面まで完全に市場に委ねるという米国流市場至上主義者ではない。古典的な「管理通貨体制」維持派である。
そうした政治家が、米国から遠ざけられるようになったことに、「姿なき占領」が表現されているのである。
箸の上げ下ろしにまで指令するのが占領である。社会の隅々まで日本は米国に占領されている。米国資本にとって、日本経済がおいしいものだからである。
医療問題についてこれまで大きな力をふるってきた厚生労働省の「中央社会保険医療協議会」(中医協)の委員構成が大幅に変えられ、中医協そのものの権限が剥奪される。
病院経営に営利会社が参入できるようになる。公的保険を適用しなくてもよい「自由診療」が可能になる。つまり、金持ちが高額医療を受けることができるようになる。逆にいえば、貧乏人でも受けることができていた公的保険の適用範囲が著しく制限されるようになる。
すべては、医療費の高騰を抑制するという建前の下で進められている医療改悪である。
確かに医療費は高騰傾向を示している。それでも、日本の医療費の対国内総生産(GDP)比で、他の先進工業国家にくらべてもっとも小さいという事実は語られない。むしろ、「公」の領域であった医療分野を、「私」の領域に開放しろという米国政府の要求に日本政府が屈したというのが、もろもろの改悪の本当の理由であろう。「官」から「民」へという流れは、日本では、営利の対象にしてはならなかった「公」の領域を、カネを儲けてもよい「私」の領域に移してしまえということである。そして、新たな領域で地歩を築く「私」とは、多くの場合、米国企業であり、米国のコンサルタントである。 政府・与党の「医療制度改革大綱」というものがある。それに沿う形で医療制度のなし崩し的改悪が進行している。
まず、中医協の委員構成が変えられる。これまでは、委員は四つの分野からだされていて、医療費を支払う側(支払側)が八人、診療側が八人、中立の立場にあるとされる公益側(学識経験者)が四人、専門委員が七人であり、支払側と診療側の委員は団体から推薦されていた。これが大幅に変えられる。まず団体推薦が廃止される。つまり、委員は厚生労働省が選ぶことになる。支払側と診療側がそれぞれ七人に減らされ、公益側を六人に増やすことになる。公益側が主導権を発揮することが決められた。そして、診療報酬改定にかかわる決定について、中医協の権限を剥奪し、官邸主導にすることが決定された。専門委員にも今後は、外資から選ばれるようになるであろう。
診療報酬は、「引き下げる」と明記された。
二〇〇八年度から七〇~七四歳の自己負担分を現行の一割から二割へと、じつに、二倍に引き上げることになった。七〇歳以上でも現役なみの所得のある人は、現行の二割から三割に自己負担分を引き上げられることになった。入院している高齢者の食費・居住費の負担増の方向で見直されることになった。
七五歳以上の高齢者向けの医療保険制度が他の世代から独立して二〇〇八年に新設されることになった。この新制度に関して、保険料の徴収義務だけが市町村に委ねられるが、運営は、都道府県単位で全市町村が加入する「広域連合」が担うことになった。
こうした改悪は、米国政府の意向を無視して判断されるべきではない。二〇〇六年六月に日米首脳会談があった。これに合わせて『二〇〇六年日米投資イニシアティブ』という報告書がだされた。
そのなかで、米国政府はドキッとさせられるようなことを日本政府に要求した。米国側は、「米国企業も医療改革の議論に積極的に関与」したいといってのけたのである。米国企業は、すでに、日本の医療サービス分野で大きな地歩を築いているのだから、医療改革の議論に参加させろというのである。
具体的には、株式会社などの営利会社が病院を経営できるように規制緩和をせよ、公的保険と自由診療とを組み合わす「混合診療」を拡大せよと要求した。
医療に営利を認めてしまえば、医療費の高騰は避けられないし、儲かる地域に病院が集中し、儲からない地域には病院がなくなってしまう怖れがあるとして、日本では病院株式会社が禁止されていた。しかし、米国の執拗で強い要求の前に、日本政府は譲歩して、「構造改革特区」に限って例外的に株式会社による病院経営を許可するようになった。しかし、これでは充分な展開ができないとして米国は、特区以外でも認可しろと日本政府に迫っているのである。
日本では、これまで、公的保険が適用される保険診療と、保険が適用されない自由診療との併用は原則的には、認められていなかった。保険診療を受けていた患者が、公的保険が適用されない自由診療を受けてしまえば、それまで受けていた公的保険の適用資格がなくなり、診療全体が自由診療として、患者は実費の全額を払わなければならなかった。これを認可せよというのである。
米国政府は、混合医療が、「医療支出を減らし、効率化を促し、さらに医療保険制度の財政上の困難を緩和しうるものである」と明言した。
そうではないだろう。医療費削減の建前の下、自由診療の分野に公的なものではない純民間ベースの医療保険を拡大させようとする米国医療保険会社の思惑が見え隠れするのである。
二〇〇六年報告書では、医療と並んで、教育も重点分野に挙げられた。教育もまた、カネを儲けてはならない「公」の領域であったのに、カネを儲けてもよい「私」の分野に移し替えられようとしている。安倍新政権が「教育改革」を目玉にしている背景に米国政府の圧力がないとはいいきれないのである。
日本のあらゆる領域が米国資本によって占領されようとしている。それは誰の目にもみえる剥きだしの力の行使ではなく、「構造改革」というスローガンの下で静かに進行するイデオロギー支配、つまり、「姿なき占領」なのである。
復帰しましたので、お手数ですがトラックバックしていただいた方、再度トラックバックをお願いいたします。
編集部
















