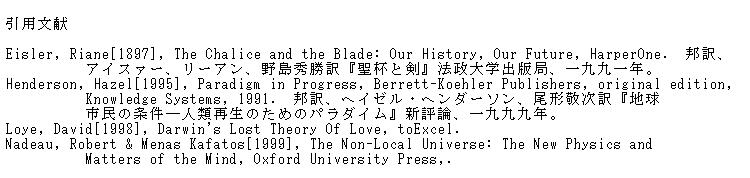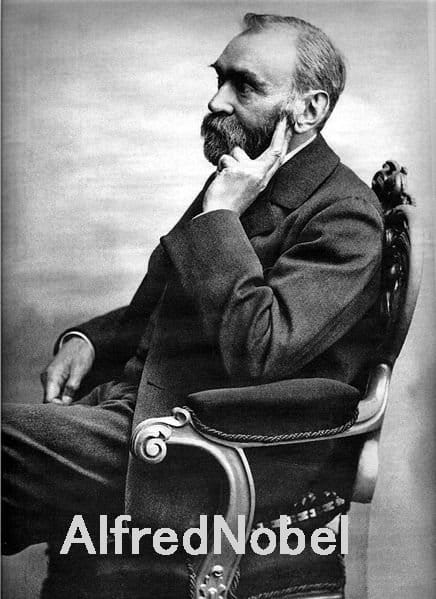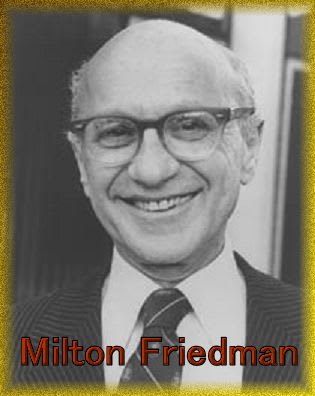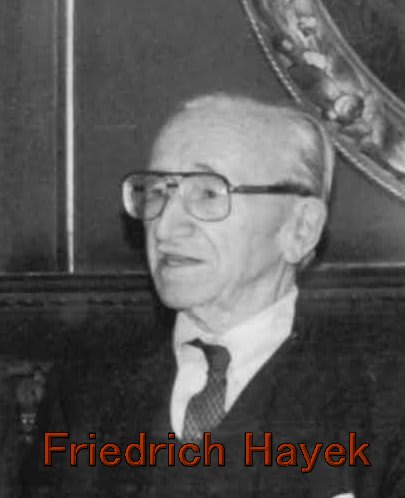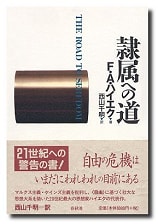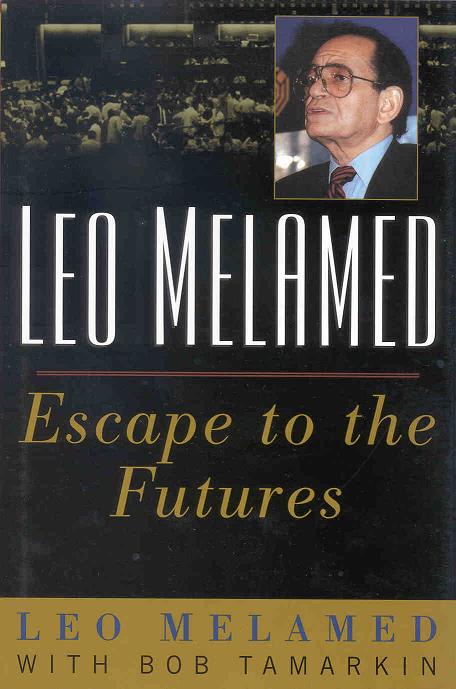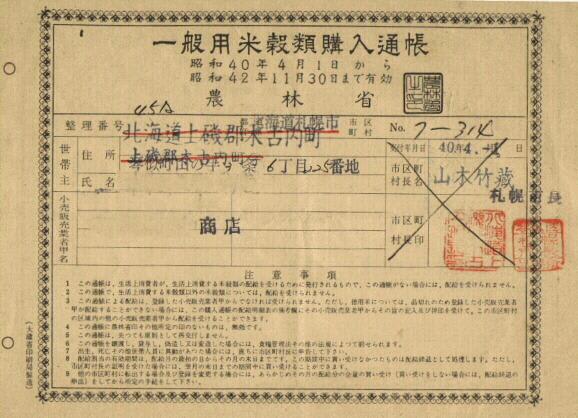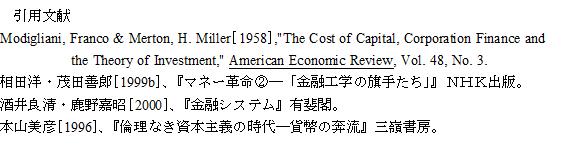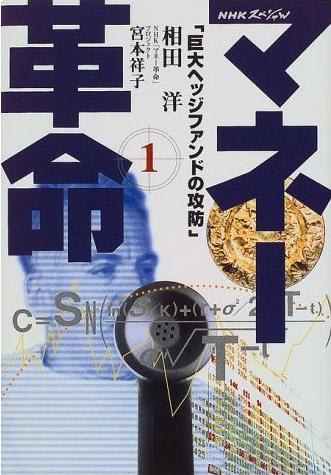日本学術会議の主催で、ノーベル賞一〇〇周年記念国際フォーラムが、二〇〇二年三月 一六日~一七日に東京大学安田講堂で、三月二〇日には国立京都国際会館で開催された。京都での準備は京都大学が引き受けることになった。たまたまの巡り合わせであるが、当時、私は日本学術会議第三部(経済・経営・会計)の第一八期の会員であり、京都大学経済学部に所属していたこともあって、準備委員と応接係を命じられた。大任ではあったが、ノーベル経済学賞に基本的な疑問を昔から抱いていた私には苦痛そのものであった。
スウェーデンとノルウェーから来日されたノーベル財団の派遣者には失礼な振る舞いをしなかったとは思うものの、当時の苦痛はいまでも夢に現れる。居並ぶ日本の歴代ノーベル賞受賞者を前にしての高山寺で前夜のご接待時での会話とか京都国際会館でのシンポジウム、その後の懇親会での会話は、赤面の至りで、いまでも、汗が噴き出る記憶である。
さて、ノーベル賞とは、言うまでもなく、ダイナマイトの発明者であるスウェーデンのアルフレッド・ノーベル(Alfred Nobel, 1833~1896)が、「前の年に人類に対して最大の便宜を与える貢献を行った人物」(to those who, during the preceding year, shall have conferred the greatest benefit on mankind)に年次の賞を与えるべく、遺言(遺言状の作成は一八九五年)によって、一八九六年に私財を寄付して財団を作ったことから始まっている。
ノーベルの兄たちは、バクー油田開発で成功して、ヨーロッパの石油産業を独占していた。ノーベル自身は発明家でダイナマイトの発明は一八六六年である。六三歳で生涯を閉じたが取得した特許は三五五件である。語学に堪能で露、仏、独、英語を自在に操ったという。
独身を通したアルフレッドノーベルの莫大な財産相続を期待していた遺族たちが、財団を無効としようとしたが、はたせなかった。
ノーベルの遺言によって、物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の各賞が設けられた。授賞式は、ノーベルの命日の一二月一〇日に行われる。一九〇一年の第一回授与式は、当時、スウェーデンとノルウェーが同盟関係にあったので、ストックホルムとオスロで行われた。しかし、一九〇五年以降、同盟関係が解消させられたので、平和賞だけがオスロで、他の賞はストックホルムで授与式がある。
選考は、物理学賞、科学賞、経済学賞(後述)については、スウェーデン王立科学アカデミー (Kungliga Vetenskapsakademien) が行う。これは、一七三九年に設立され、自然科学と数学の発展を目的とした活動を行っている。
生理学・医学賞は、カロリンス研究所(Karolinska Institutet)が行っている。この研究所は一八一〇年軍医養成を目的として設立され、ヨーロッパ最大の医学研究所である。
文学賞は、スウェーデン・アカデミー(Svenska Akademien)が審査する。これは、一七八六年に設立された。日本の学士院に相当する。
平和賞は、ノルウェー国会が選考する。
さて、ノーベル経済学賞である。正確に言えば、これはノーベル賞ではない。スウェーデン国立銀行(Sveriges Riksbank)が、一九六八年、設立三〇〇周年のために、ノーベルを忍んで設立した賞であり、正式には「アルフレッド・ノーベルを記念するスウェーデン国立銀行による経済科学賞」(Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)という。この「経済科学」という言葉が物議を醸したのであるが、後述する。
正式のノーベル賞ではないために、経済学賞の賞金はノーベル財団から支給されないが、選考方法や賞金額は正式の賞と同じで、賞金はスウェーデン国立銀行から支払われる。他の賞と同じく、共同受賞者は上限三名で、同じ受賞理由による。一九九五年二月、「経済科学」が「社会科学」と再定義され、政治学、心理学、社会学など経済学の隣接分野をも含むことになった。また審査員の五名は、以前は全員が経済学者であったが、そのときに、二人は非経済学者とすることになった。
ただし、一九九七年には、ノーベル文学賞の選考機関であるスウェーデン・アカデミーが経済学賞の廃止を要請している。二〇〇一年には、ノーベルの兄弟の曾孫(ひまご)、ピーター・ノーベル(Peter Nobel)ら四人のスウェーデンの人権派弁護士たちが、経済学賞は「人類に多大の貢献」をした人への授与というノーベルの遺訓にそぐわないとの批判を地元紙『ダーグブラデット』(Dagbladet)に寄稿した。親族は「ノーベルは実際、事業や経済が好きでなかった」とした上で、「経済学賞はスウェーデン中央銀行賞に改めるべきだろう」と指摘している(http://www.asahi.com/international/update/1128/012.html)。
さらに、経済学は「科学」ではないとピーターは、ヘイゼル・ヘンダーソン(Hazel Henderson)にも語ったという。これは、「インター・プレス・サービス」(InterPress Service=IPS)の二〇〇五年六月版に掲載されている。私自身も、先述の記念フォーラム前夜の懇親会で、審査委員から同じ話を聞かされた。
ヘイゼル・ヘンダーソンは女性の進化経済学者である。氏は、その著作(Henderson, H.[1995])に於いて、いまや、地球は産業主義社会の建設がもたらした負の遺産で満ち溢れ、この苦境から脱却するには経済構造や社会の価値観を根本から変化させる必要があると主張した。主流の経済学は、科学の名に於いて、偽装した政治を行ってきたという。経済学は、破綻、バブル、不況、エネルギー危機、資源の枯渇、貧困、貿易戦争、汚染、共同体の崩壊、文化と生物多様性の喪失など持続不可能なものを次々に作り出したことに責任を負うべきであると言うのである。
貨幣もまた世界を破壊した。一九八〇年代の金融の規制緩和が、巨大な世界的カジノを作り出し、毎日、一兆ドルを超える貨幣が世界中を荒らし回っている。しかも、その九〇%は投機的取引である。
現在は、世界的な貯蓄過剰社会であると言われるが、そのほとんどは金融「革新」(デリバティブ、ヘッジファンド)で積み上げられたドルである。これら、膨大な貯蓄が生産的に使用され、雇用を増やすために使われたことはない。ただ、見せかけの貨幣という数字を大きくしてきただけのことである。
そうした経済学批判でもって、氏は、ノーベル経済学賞を告発する。
一九六九年に設立された「スウェーデン銀行経済学賞」は経済学を制度化するものであった。自由貿易、民営化、変動相場、地球を駆けめぐるマネーを受け入れる門戸開放、等々を謳う「ワシントン・コンセンサス」(Washington Consensus)を叩き込まれた経済学者たちが、金融を不安定にし、過剰負債社会を生み出してしまった(Henderson, H.,"Abolish the "Nobel" in Economics―Many Scientists Agree!," http://www.hazelhenderson.com/editorials/abolishTheNobel.html) 。
同じ記事で、氏は、ピーター・ノーベルへのインタビューの内容を紹介している。ピーター・ノーベルはつぎのように語った。
「アルフレッド・ノーベルの手紙には、経済学賞を推奨する文言はない。スウェーデン国立銀行が、カッコーのように、自分の卵を世間で高い評判を取っている別の巣に置いたのである。スウェーデン銀行は、商標登録の侵害に近い罪を犯した。真のノーベル賞を略奪したもので受け入れがたい」。
「経済学賞の三分の二は米国の経済学者に与えられている。とくに、株式市場やオプションに投機するシカゴ学派に与えられている。これらの賞は、人類の状態と私たちの生存条件を改善するというアルフレッド・ノーベルが抱いていた目標とはなんの関係もない。それどころか正反対のものである」。
社説が掲載されている反対ページにある署名入りの囲み記事を「オプ・エド」(Op-Ed=Opposit Editorial)という。スウェーデンの有力紙、『ダーゲンズ・ナイヘテール』(Dagens Nyheter)の二〇〇四年一二月一〇日号、つまり、アルフレッド・ノーベルの命日にしてノーバル賞授賞式当日に、スウェーデンの数学者、マンズ・ロンロート(Mans Lonnroth)と、スウェーデン科学アカデミー会員、ピーター・ジャガールズ(Peter Jagers)の二人が「オプ・エド」記事を投稿した。経済学賞の範囲を広げるか、さもなくば、廃止すべきだとしたのである。とくに、二〇〇四年度の二人の経済学賞受賞者が数学の使用方法が間違っていると非難した。二〇〇四年度は、「動学的マクロ経済学への貢献、リアルビジネスサイクルの理論」という理由で受賞したのは、F・E・キドランド(Finn Erling Kydland、ノルウェー)とE・C・プレスコット(E.dward C. Prescott)であった。
彼らを選んだロイヤル・アカデミー・オブ・サイエンス(Royal Academy of Science)が出したステートメントで、彼らのモデルが経済の方向性を導き、そのモデルによって、ニュージーランド、スウェーデン、英国、ユーロ地域の貨幣政策が作成されたとある。
ヘンダーソンは言う。
スウェーデン銀行が、経済学を「科学」だとしたのは、経済学の政治性を、隠蔽するために、数学的な中立性を経済学がもっていることを強調したいからである。経済学が、政治的には中立であることを示したいからである。「価値フリー」(value-free)を装って政策を指導してしまうためである。
経済学は、三〇〇年に亘り人を欺してきた「蛇油」(Sneke Oil=街頭香具師が売りつける偽油=ガマの油)と同じものである。経済学の理論は証明不可能なものであるのに、世界の政策決定に関与し、為政者を植民地の人間にしてしまうのである。
ヘンダーソンは、多くの科学者にインタビューした内容を紹介している。
「マックス・プランク物理学研究所」(Max Planck Institute for Physics)のハンス・ピーター・ドゥール(Hans Peter Durr)教授。
「経済学は悪しき科学である上に、基礎的な仮定の多くが正しくない」。
そして、彼は、こうした間違った「科学」による経済学賞が四〇年間も続いたのは、科学者が他の領域の人たちを批判しないことをエチケットと見なしているからであると語った。
システム論、物理学者であるオーストリーのベストセラー作家、フリツォフ・カプラ(Fritjof Capra)は言う。
「意味合い、価値、摩擦、等々の次元が、現実の社会には究極的に重要である。この次元のものを含めない社会組織論は、いかなるものであれ、不十分である。残念ながら、今日の経済学の理論モデルのほとんどにこのことが当てはまる」。
カルフォルニア大学サンタ・クルーズ校(Santa Cruz)の数学者でカオス理論のラルフ・アブラハム(Ralph Abraham)教授。
「経済学賞は、社会科学のすべての視野を含むようなものに拡大されるべきである。数学のフィールズ賞(the Fields Medals)のような次元のものからは距離を置いたノーベル賞になるべきである」。
システム科学者で『聖杯と剣』(Eisler, R.[1987])のベストセラー作家、リーアン・アイスラー(Riane Eisler)も経済学が科学であることを否定している。
ヘンダーソンは言う。心理学者のデビッド・ロイ(David Loye)の『愛についてのダーウィンの忘れられた理論』(Loye, D.[1998]というベストセラーがある。「適者生存」(the survaival of the fittest)ということについて、ダーウィンはわずかしか触れていない。にもかかわらず、階級社会を当然視するビクトリア時代の英国には、この言葉がピッタリとフィットしたことによって、ダーウィンの言葉として独り歩きしたものである。この独り歩きした観念が経済学の「合理的経済人」(rational economic man)として採用されてしまった。他人との競争で自己の利益(self-interest)を最大にするという人間像がそれである。ロイの著書によれば、ダーウィンはそんなことを強調したのではなく、利他主義(altruism)、協同(cooperation)、結束(bonding)、分け合い(sharing)、信頼(trust)こそが人としての成功の基礎であるとダーウィンは主張していた(詳しくは、http://www.thedarwinproject.com)。
いまや、ロバート・ナドウ(Robert Nadeau)とか、メナス・カファトス(Menas Kafatos)など科学史の研究者でも、こうした実際に人類が生き延びてきた真の経緯を経済学は学び直すべきだと主張する人たちが増えてきた。