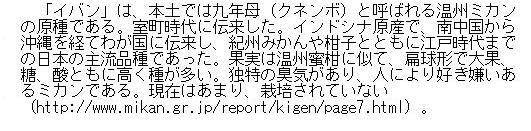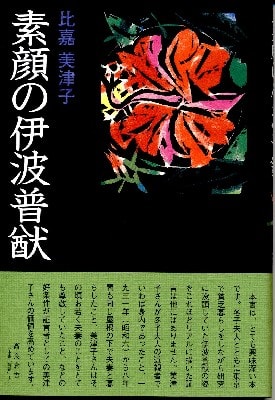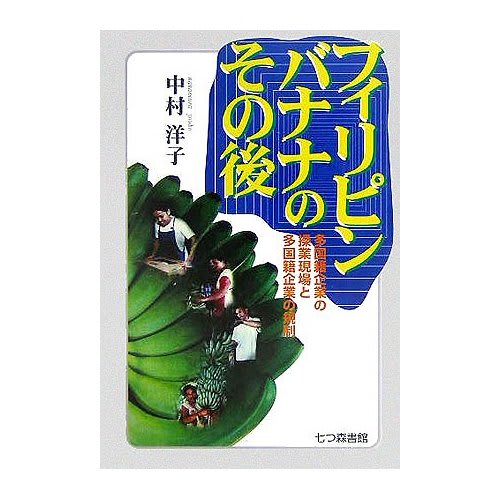現在もハワイの女性の正装であるムームーは、上半身裸が普通であった往時のハワイの女性が、キリスト教的に「淫ら」だとして、宣教師が普及させたものと言われている。宣教師の薦めで、ハワイ語もアルファベット表記にされた。
次ぎに移植された産業が、さとうきびプランテーションである。このさとうきびプランテーションがハワイを米国の植民地化にさせた主要な推進力となった。
1835年、ウィリアム・フーパーが、カウアイ島コロアでサトウキビの事業化に成功した。さとうきびプランテーションは、広大な土地、砂糖1ポンド(重量)につき1トンもの膨大な水、そして、安価な多数の労働力が必須である。ここに、米国人による土地収奪が本格化した。
1840年、憲法が制定され、政府ができる。
1848年 土地私有制度、「グレートマヘレ」法が導入され、ハワイ諸島全土が国王と245人の族長に分配された。土地の私有化が開始されたのである。これが外国人による土地取得の露払いになった。マヘレとは分配の意味である。
事実、1850年、配分された王侯貴族の土地を民間人に売ってもいいことになった。当然、資金力のある白人が土地を独占することになった。この土地が、さとうきびプランテーションとなったのである。
1850年、ハワイ王国の首都は、マウイ島ラハイナからオアフ島ホノルルへと遷都された。
プランテーションの拡大は、当然、低賃金労働力を必要とする。白人は、移民を導入しなければならなかった。最初、移民として中国人が導入された。
1852年、中国福建省と広東省から初の移民受け入れを開始した。
1863年、ニュージーランドからきたエリザベス・シンクレアが、カメハメハ4世からニイハウ島を10000ドルとピアノ1台で買い取った。
そして、
1868年、日本からも初の移民をハワイは受け入れた。移民開始の年号が明治元年なので、日本初のハワイ向け移民は、「元年者」と名付けられた。この日本初のハワイ向け移民は153名であった。ただし、この時の日本移民は不法出国であった。
この日本人移民は、徳川幕府と移民ブローカーとの協定で募集された移民だったため、発足直後の明治新政府は、そうした移民を認めず、移民達はパスポートすらもたない、いわば非合法状態であった。1日12時間働いて月給は4ドルであった。
1872年、カメハメハ5世の死去に伴い直系王家は途絶した。
1874年、ルナリロ王の病死に伴い、カラカウアが第7代国王に選出される。
そして、1876年、このカラカウア王の下で、「米国・ハワイ互恵条約」が締結された。これによって、ハワイの砂糖は無関税で米国に輸出できるようになった。さとうきび産業は飛躍的に増大し、王家を財政的に潤した。米国政府にとって重要なことは、王家を潤わすことによって、オアフ島真珠湾の軍事利用を獲得したことである。米国は、後の沖縄の軍事利用に匹敵するメリットをハワイで得たのである。
1878年、孫文がハワイに移り住む。
1881年、カラカウア王が日本を訪問して、天皇と会見、日本からの移民を要請した。その時、西欧諸国の政治的経済的侵略に危機感を感じていた王は、姪のカイウラニ王女と山階宮(後の東伏見宮依仁親王)との政略結婚によるハワイ王朝と天皇家との間の関係強化を画策したが、米国との関係悪化を懸念する日本政府は、この提案を丁重に断った。
1885年、ハワイ王の移民要請に応えて、日本から初の「官約移民」が出される。
1886年、「中国移民禁止法」が施行される。これに伴って日本からの移民が増加する。
1900年時点で、ハワイ人口の40%を日本人が占めるようになった。
1887年、米国人による準軍隊組織「ハワイ連盟」の威嚇の下、カラカウア王が「銃剣憲法」と呼ばれる新憲法にサインする。首謀者は、サンフォード・ドールであった。以下、ウィキペディアに依拠して、この悪質なドール一族のことを説明する。
サンフォード・ドール(Sanford Ballard Dole、1844年4月23日 - 1926年6月9日)は、米国メイン州ノリッジウォック(Norridgewock)出身の白人プロテスタント宣教師の子供として、ホノルルに生まれた。後のハワイのパイナップル王ジェームズ・ドールは従弟に当たる。ジェームズも同じく宣教師の息子としてマサチューセッツに生まれ、サンフォードを追ってハワイに移っている。
ドールは
1887年、米人系の経済人・政治家・さとうきび農場主らが結成した政治組織
、「ハワイ連盟」の武装蜂起に参加した。白人市民たちからなる民兵部
「ホノルル・ライフル連隊」の後ろ盾を得てカラカウア退位を迫ったハワイ連盟は、カラカウア王に退位を迫り、拒否されると、退位を強制しないが、その代わりに、内務大臣であった米国人、ロリン・A・サーストンが起草した
「新憲法」(銃剣憲法)を受け入れさせた。
この憲法はすべてのアジア系移民から一切の投票権を奪った。また投票権に収入や資産などの一定の基準を設けたため、貧しい人々は選挙権を剥奪され、一方でハワイ人エリートや富裕な米系・ヨーロッパ系移民の政治力が劇的に強まった。さらに憲法は王の権利を極小化し、枢密院や内閣の政治的影響力を高めた。
武力を背景にしたこの
「銃剣憲法」で、ハワイ王室と大多数のハワイ人は政治力を失い、白人農場主らを中心とする共和派が王国の実権を手にした。ドールはこの後に、カラカウア王によりハワイ王国最高裁判所の判事に任命されている。
1891年、サンフランシスコに向かう途上で風邪をこじらせたカラカウア王が死去。妹のリリウオカラニが後を継ぐ。そして、サンフォード・ドールは、女王の法律顧問に就任する。威嚇の下に就任したに違いない。
しかし、即位したリリウオカラニ女王は共和派と対立、王権を取り戻す新憲法を起案するなど王国政治は騒然となった。ドールら「共和派」は、ハワイ人たちの「王政派」勢力急伸に危機感を募らせた。
1893年1月16日、両派の衝突で混乱する中、
米国公使ジョン・L・スティーヴンスは米国海兵隊に出動を要請し、イオラニ宮殿を包囲させた。
1893年1月17日には共和派が政庁舎を占拠し、王政廃止と臨時政府樹立を宣言した(「ハワイ革命」、注、なんたる傲岸な命名であることよ!)。ドールが、結局臨時政府の大統領に就任した。臨時政府は王政転覆から48時間以内に、ハワイ王国と外交関係を結んでいた諸国から合法政府として承認された。
臨時政府は米国への併合を求めた。この時、日本政府は、珍しく日本人移民を擁護すべく、日本は海軍部隊をハワイに派遣してクーデター勢力を威嚇した。しかし、ハワイ王朝は幕を閉じた。
同年、グロバー・クリーブランドが米国大統領に就任したが、「マニフェスト・デスティニー」はすでに終わったと考える彼は、米国の領土拡張には消極的であった。彼はハワイでのこの「革命」に不快感を示し、元下院議員ジェームズ・ヘンダーソン・ブロントにハワイ内政の調査を依頼した。
1893年7月17日、『ブロント報告書』(Blount Report)が大統領に提出された。
報告書では、白人共和派が組織する
「治安委員会」(Committee of Safety)が、スティーヴンス公使と共謀して米国海兵隊をハワイに上陸させ、リリウオカラニ女王を武力で排除し、治安委員会メンバーからなるハワイ臨時政府を樹立する陰謀を進めていたことが、述べられていた。
この報告を基にクリーブランド大統領はスティーブンス公使を更迭した。新公使アルバート・ウィリスはリリウオカラニの復位と立憲君主制の確立、および女王による治安委員会メンバーの恩赦を求め、ドールらには臨時政府解散を求めた。
しかし、
1893年、11月16日、ウィリス公使との会合でリリウオカラニは、恩赦を拒否し、革命参加者への極刑を要求した。しかし、リリウオカラニは、1893年、12月18日のウィリス公使との会合では、考えを変えて、革命首謀者サンフォード・ドールとロリン・A・サーストンに対する処刑を取りやめた。臨時政府は12月23日、ウィリス公使からクリーブランド大統領の提案を示された。リリウオカラニの復位の提案であった。しかし、臨時政府はこれを拒否した。
そして、ハワイ問題は米国上院に審議が戻され、上院議員ジョン・テイラー・モーガンが新たに調査報告を依頼された。彼の
1894年2月26日の報告書(『モーガン報告書』、Morgan Report)は
、『ブロント報告書』とは対照的な内容だった。「革命」は現地の米国人が長年の王国の腐敗の結果起こした地元の問題であり、米国政府は関係がなく、海兵隊は米国民やその資産を守るためにのみ出動し、王政廃止には何の役割も果たさなかったと結論付けた。
臨時政府は、制憲議会を開き、1894年7月4日に「ハワイ共和国」樹立を宣言した。なんと、米国独立記念日を簒奪政権自立記念日にしたのである。
これは、メキシコから領土を奪った「アラモ砦」以来の米国の「民主主義の伝道者」の伝統であり、いまなおアフガニスタンで、イラクで起こし、そして、イランにも波及させようとする帝国主義的「民主主義の輸出」という悪行の共通項である。米国史を貫く、忌まわしい「ならず者国家」の悪しき伝統である。
ドールは、1894年から1900年までの間、ハワイ共和国初代にして最後の大統領を務めた。この間、ドールは、サーストンに、ワシントンD.C.でハワイ併合のためのロビー活動を行うよう任せた。
ドール政権は王政復古の試みによって幾度も危機に直面した。その最大のものは銃剣憲法制定後にも、たびたび反乱を起こした、先住ハワイ人の、ハワイ軍人ロバート・ウィリアム・ウィルコックスらが加わった王政派による1895年1月6日の武力蜂起であった。
しかし、王政派は速やかに鎮圧され、1月16日にはリリウオカラニが多くの銃器を貯蔵していたとして反乱の首謀者の容疑で逮捕され、イオラニ宮殿に幽閉された。
ウィルコックスら反乱首謀者らは内乱罪で死刑を求刑されたが、ドールは彼らに対する刑を減刑した。しかし、1月22日、約200人の命と引き換えにリリウオカラニは女王廃位の署名を強制され、ハワイ王国は滅亡した。
ドールは外交面でも成功した。ハワイ王国を承認していた国は結局すべてハワイ共和国を承認した。ウィリアム・マッキンリー大統領は、ドールに対し、ハワイ併合の暁には
「ハワイ準州」の最初の知事に任命すると約束した。
1896年 法律61号が布告され、ワイキキの土地使用権が白人投資家に渡り、リゾート開発が始まった。
ウィリアム・マッキンリー大統領は、ドールに対し、ハワイ併合の暁には「ハワイ準州」の最初の知事に任命すると約束した。
1898年7月4日(嗚呼!ここでもまた米国独立記念日に!)、米国下院はハワイ共和国併合とハワイ準州の設立を定めた「ニューランズ決議」(Newlands Resolution)を採択、7月7日にはマッキンリー大統領が署名した。8月12日にはハワイ編入が宣言され、ハワイ王国の国旗が降ろされ、星条旗が掲揚された。
1900年4月30日の「ハワイ基本法」(Hawaiian Organic Act)で準州に政府が成立すると、ドールは準州知事となった。
実質的には、ハワイは、従弟のジェームズ・ドールを代表とする、さとうきび農園主およびビッグ・ファイブ(5大財閥、Castle & Cooke、C.Brewer、Alexander & Baldwin、Theo Davies & Co.、Am Fac)に支配されることになる。
1901年、従弟の、ジェームズ・ドールがオアフ島ワヒアワでハワイアン・パイナップル社を設立。労働力確保のために1900年にプエルト・リコ、1903年に韓国、1907~31年にフィリピンから契約労働者が到着。そのほとんどがそのままハワイに住みついた。
同年、W.C.ピーコックがワイキキにモアナ・ホテルを建設する。
1903年、サンフォード・ドールは、連邦地裁判事の任命を受けるため辞任した。彼は判事職を1915年まで務めた。。
1921年 、ワイキキ環境整備プロジェクトが始まり、ワイキキ、アラモアナ、マッカリー地区の湿地帯が埋め立てられる。
1922年、ジェームズ・ドールがラナイ島のほぼ全域を買い取った。。
1925年、サンフランシスコ、ロサンゼルスとを4日半で結ぶ650人乗りの定期観光客船“マロロ号”が就航する。
1926年、アロハタワーが完成。この年、、サンフォード・ドールが、卒中で死去した。
1927年、ロイヤル・ハワイアン・ホテルができる。
1928年、リゾート用地確保のために始められたワイキキの水田や養魚池の埋め立てが完了し、地価が30倍以上に跳ね上がる。
1941年、太平洋戦争勃発。真珠湾が日本機動部隊の奇襲を受け、3435名の死傷者、戦艦8隻ならびに大型艦船10隻が沈没ないし大破、航空機188機が破壊される。
ハワイの日系人は、日本人会会長や僧侶など、日本人社会を代表する一部の人々を除き収容所に収容されなかった。これは当時、ハワイが正式な州でなかったこと、米国本土から離れていること、そして何より、当時の人口の4割程度を占める日系人を強制収容すれば、ハワイの社会や経済活動が崩壊しかねないという事実が影響したようである。それでも、約1000人の日本人が米国本土の強制収容所に送られた。
そうしたこともあってか、ハワイで生まれ育ち、米国の市民権をもつ日系の若者の多くは、自ら進んで志願兵となることで、米国に対する忠誠心を示そうとした。
1943年、ハワイ在住日系人のみで構成された第100大隊が北アフリカ戦線に投入され、その後イタリア戦にも参加する。この大隊が目覚ましい戦果を挙げたため、メインランド在住の日系人と合流して、第442連隊が編成された。同部隊の死傷率は、米国陸軍平均値の3倍であり、パープル・ハート(陸軍における最高位の戦傷章)をもっとも多く受勲している。
1959年、米国の50番目の州となる。 ハワイや、ロサンゼルスの日系人たちの中で、沖縄出身者たちが、米国の共産主義運動に傾斜したことの意味は限りなく重い。伊波普猷が、ハワイにおける沖縄出身者の境遇に沖縄の置かれていた現実を投影させたのも、むべなるかなである。