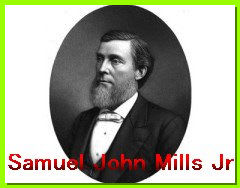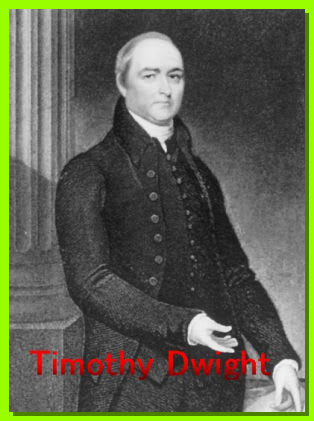海老名は豪語した。時の首相・大隈重信と朝鮮総督・寺内正毅(てらうち・まさき)の依頼によって、渋沢栄一(しぶさわ・えいいち)が音頭を取って、三菱、三井、古河財閥からの朝鮮布教の募金が実現したと(「日本組合教会第三〇回総会朝鮮伝道現況報告」、『基督教世界』一九一四年一〇月八日付、小川・池[一九八四]、二〇四ページに所収)。

一九一六年に寺内を継いだ長谷川好道(はせがわ・よしみち)も、寺内と同じく、組合教会に資金援助をしたことを次期総督・斎藤実(さいとう・まこと)への引き継ぎ文書の中で告げている(姜[一九六六]、五〇〇ページ)。

一九一八年末には、朝鮮における組合教会数一四九、牧師数八六人、信者数一万三〇〇〇人強、経費は二万五〇〇〇円強であった。同じ時期、本土の組合教会では、教会数一一三、信者数二万人程度、経費も一万六〇〇〇円程度であったことからすれば、組合教会は、本土よりも朝鮮で勢力を伸ばしていたことが分かる(松尾[一九六九]の表、参照)。
こうした組合教会の隆盛は、総督府などによる資金援助なしにはあり得なかったであろう。
組合教会全体が韓国併合に協力的であったわけではもちろんない。柏木義円(かしわぎ・ぎえん)、吉野作造など、朝鮮総督府や海老名弾正、渡瀬常吉を鋭く批判したクリスチャンもいた。それでも、海老名を首領とする組合教会の執行部は、総督府による朝鮮支配を支持していた。
渡瀬は、三・一独立運動を、天道教徒と外国人キリスト教宣教師によって扇動された暴動であると言ってはばからなかった(渡瀬常吉、「朝鮮騒擾事件の真相と其の善後策」、『新人』一九一九年五月号、姜[一九六六]、五三七~四一ページに所収)。
しかし、三・一独立運動は、日本の組合教会を朝鮮布教から撤退させるという効果を持った。三・一独立運動が勃発するまで、組合教会の朝鮮人信者は一万四〇〇〇人強いた。しかし、一九二一年、組合教会は朝鮮伝道部を廃止し、布教業務を新たに設立した朝鮮会衆派基督教会に信者を移管して、現地人に布教業務を委ねたが、移管に応じた朝鮮人は三〇〇〇人を切ってしまった。一挙に五分の一にまで激減してしまったのである(川瀬[二〇〇九]、九六ページ)。
おわりに
柏木義円の反戦論を紹介しておきたい。柏木義円は、現在の新潟県長岡市与板町にある浄土真宗大谷派に属する西光寺の住職の子として生まれた。新潟師範を経て東京師範を卒業した。群馬県碓氷郡土塩小学校教員時代にキリスト教に出会い、一八八〇年、同志社英学校に入学した。在学中、新島襄に「同志社の後事を託す」とまで言わしめたという。その後群馬県細野東小学校長を勤め、一八九七年、安中教会(18)の牧師となった。地味で寡黙な人であったらしい。一八九八年から三八年間続けた『「上毛(じょうもう)教界月報』(全四九五号)では、平和主義、人格尊重、思想言論の自由を掲げ、軍国主義的風潮の中で、否応なく戦争に突入していく世の中に警鐘を鳴らし、幾多の弾圧にも屈することなく戦争の「不当性」を現状分析に基づいて粘り強く訴えた人である(http://ojima3.com/yoita/person06.html)。
柏木は、朝鮮における日本人の狼藉ぶりを非難し、<このままでは、将来大変な事態が起ころう>と、すでに一九〇四年に書いている。<気の毒なのは韓人である。日本民族の膨張のための伝道ならばしない方がよい>とまで言い切った(柏木、「朝鮮伝道について」、『基督教世界』一九〇四年八月一一日付、姜徳相編[一九六六]、一四一~四二ページに所収)。
一九一四年には、正面から渡瀬常吉批判を展開している。要約する。<組合教会が日本国民の代表であると言うのは、あまりにも牽強付会なことである。日本人は、そもそも鮮人の指導者たる資格はない。鮮人をキリスト教化するよりも、日本人を教化する方が先決であろう。キリストの名を借りて、鮮人を日本国民に同化させるという政策は、彼らを反発させ、日本から離反させるだけである。渡瀬常吉が横暴な総督府を讃えるような文章を書いているが、そうしたことは、御用宗教に堕したという非難を受けるだろう。それはキリストの名を貶めるだけである>(柏木、「渡瀬氏の『朝鮮教化の急務』を読む」、『上毛教界月報』一九一四年四月一五日号、姜徳相編[一九六六]、三〇一~〇二ページに所収)。
三・一独立運動を「朝鮮人の韓国独立という妄想」であるとうそぶく渡瀬を柏木は非難した<日本人が愛国の運動をすれば尊くて、鮮人が同じことをすれば愚かなことであると言うのは、あまりにも得手勝手なことである>と(柏木、「渡瀬常吉君に問ふ」、『上毛教界月報』一九一九年一一月一五日号、姜徳相編[一九六六]、三一〇ページに所収)。
一九三一年、柏木は組合教会と総督府との癒着について書いている。要約する。<寺内朝鮮総督は、朝鮮のキリスト教会がほとんど西洋人の宣教師によって運営されていることを目の上のたんこぶと意識したのか、その向こうを張る意味で日本人の朝鮮伝道を保護しようとしたのであろう。長老派の日本基督教会の植村正久(まさひさ)に依頼したが断られ、組合教会の海老名氏にお鉢が回ってきた。渡瀬常吉がそれを担当することになり、総督府の機密費から匿名寄附として年額六〇〇〇円程度が提供された。さらに、総督府の肝いりで五〇万円の朝鮮教化資金が募集された。しかし、その寺内総督が亡くなり、長谷川総督も去り、公正な人である斎藤総督がその任に就くや、あたかも木から落とされた猿のように、組合教会は突き放されてしまった。組合教会は、朝鮮伝道部を廃止して、朝鮮教会に後事を託したが、その朝鮮教会すら放棄せざるを得ないであろう。朝鮮における一〇〇余りの組合教会、二万人と称した組合教会信者は、雲散霧消してしまったからである>(柏木、「組合教会時弊論」、『上毛教界月報』一九三一年五月二〇日号、富坂キリスト教センター編[一九九五]、九一ページに所収)。
<公明なる精神をもって、幾多の猜疑と誹謗を受けても、忍び難きを忍びて奮闘努力をしてきた>(組合教会、「三七回総会を迎ふ(続)─度重なる二三の案件」、『基督教世界』一九二一年九月二二日付、姜徳相編[一九六六]、二三八~三九ページに所収)が、結局は朝鮮布教から撤退するしかなかった。
こうして、組合教会も、朝鮮布教面では、神道、仏教と同じ運命を辿ったのである。