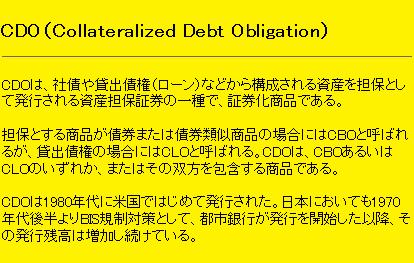恐慌の足音が聞こえる―投資銀行の消滅と日本経済への影響
はじめに
米国で、「金融経済安定化法案」(金融安定化法案)が〇八年一〇月三日に成立したにもかかわらず、世界的な株価暴落が止まらない。連日、戦後最大の下げ幅を記録したのが、法案成立後の〇八年一〇月の世界の株式市場であった。金融崩壊と実物経済の縮小がスパイラルを描き始めた。そして、素材価格の暴騰という典型的な世界的スタグフレーションが姿を整えつつある。その暴騰の火種を加えているのが、米国政府による巨額の資金散布である。
一 恐慌の荒々しい足音
経済指標と大荒れの相場が、世界の主要経済国のリセッションに結びつき始めている。金融危機が世界経済の危機に拡大している証拠が、毎日のように増えている。〇八年一〇月二日に発表された米国経済指標では、週間の失業保険新規申請件数が予想以上に増え、八月の製造業受注は予想をはるかに下回った。米サプライ管理協会(ISM)が〇八年一〇月一日に発表した九月の製造業景況調査では、製造業の活動が二〇〇一年以来の低水準に落ち込んだことが示された。
FRBが発表した一〇月一日までの一週間におけるコマーシャルペーパー(CP)市場の残高は、前週比九四九億ドル減少し一兆六〇七〇億ドルとなった。二〇〇一年にFRBが
統計を開始して以降では、最大の落ち込みだった (http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCKK4824.html)。
一方、上院を通過した修正金融安定化法案は、三日に下院で再採決された。しかし、この救済策を講じても、七〇〇〇億ドルの不良資産処理計画が、特効薬にはならないことがはっきりしてきた。恐慌がくるのが先か、システム改革が間に合うのか。間に合わないだろう思われる。
二 消滅した投資銀行
いま、米国で起こっていることは、「闇の金融機関」(shadow banking sysytem)の崩壊現象である。闇の金融機関とは、すべてを秘密にし、活動内容を表に出さない金融機関である。誰から出資を募り、どのような手口で儲け、どのような利益分配をしているかを絶えず隠す組織、つまり、闇の組織である。投資銀行がその代表である。
金融が自由化される以前には、銀行は、大衆から小口預金を預かり、それを企業に融資して、わずかばかりの利子差を収入源にするという旧い型の商業銀行であった。この種の商業銀行は、預金者が誰であり、どこに融資し、どのような利益分配をしているのかをすべて明らかにする義務を当局から課されている。データが公開されるという意味で、それは「パブリック」(public)なものである。その見返りとして、銀行が倒産の危機に瀕すれば、当局からの救済を銀行は期待できた。
これに対して、闇(影)の金融機関は、活動の自由を得るべく、金融監督当局の監視を嫌う。経営危機に瀕しても当局の庇護を受けないという約束事で、闇の金融機関は、活動内容を極力秘密にする。つまり、「プライベート」(private)である。こうした闇の金融組織の方が、金融を容易にし、リスクをより効率的に回避できると見なされていた。しかし、金融危機の発現によって、闇の組織の方がリスク軽減に優れているわけではなかった。真のリスクは隠され続けてきたのである。
FRBと財務省は、足並みをそろえて、危機に陥っている組織を救済しようとしている。膨大な公的救済資金が注がれた。しかし、それは、買収する組織を助けるだけのものであった。しかも、当局の救済に宛てられるべき資金は枯渇してしまっている。ファニーメイやフレデリックマックを救済しても、それが、米国の財政破綻を招くことになるであろうとの意識はない。救済資金は、空しく浪費されてしまう可能性がある(Krugman[2008])。
そもそも、短期の流動性を借りて、それをより長期の資産に転換するが、その資産はさらに流動化の度合いを深めるというのが、闇の組織の悪しき特徴であった。ローンを証券化し、その証券をさらに、別の形の証券化に組み替えるという際限なき手続きが闇の金融組織の常套手段であった(Roubini[2008a])。しかも、デリバティブを多用すれば、商業銀行の貸し付けに対して設定される自己資本比率の規制を迂回することができる(Tett & Davies[2007])。彼らは非預金組織なので、本来は、中央銀行からの資金援助など望むことができないものだったはずである。そして、彼らが消滅した。投資銀行主要五社のうち、二社が破綻し(ベアとリーマン、残り三社は、FRBの監督に服する商業銀行に衣替えさせられた(メリル、モルガン・スタンレー、ゴールドマン)た。巨大なヘッジファンドから出資者が資金を急激に引き揚げている。モルガン・スタンレーは、一〇月二日時点で、顧客のヘッジファンドからの預かり金の三分の一を解約された。眼前に展開しているのは、「闇でうごめく銀行システム」(shadow banking system)の音を立てての崩壊である。
三 倒産被害をモロかぶる日本の地方銀行
米国金融の痙攣は、サムライ債(円建て外債)を通じて、日本の金融機関に波及する。二〇〇八年九月までに発行されたサムライ債の金額は二兆五〇〇〇億円で、過去最高だった二〇〇〇年の二兆八五六七億円に迫っていた。ところが一転、リーマン破綻ショックでこの市場がパニックに陥っている。
大手邦銀は、リーマンに対する融資で推計二七億ドル(約二九〇〇億円)の債権をもっていたが、リーマンの破綻によって、その一部しか回収の見込みはない。大手以外の日本の金融機関ももリーマンが発行した一九五〇億円のサムライ債の大部分を保有していた。中堅地方銀行、生命保険会社、年金基金がそれである(Hall[2008])。
日本は、金融機関や企業が数日間で巨額の資金を調達できる世界でも数少ない市場の一つであった。欧米の信用市場では資金供給が激減し、日本市場がそれに代わる資金調達先として浮上していた。米小売り大手ウォルマート・ストアーズ(WMT)、スイスの金融大手UBS、ドイツの自動車大手ダイムラー(DAI)、オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ、本社:メルボルン)などが、サムライ債を発行していた。
その結果、サムライ債の発行額は、二〇〇八年に入って急増していた。新生証券の推計では、二〇〇八年八月までに発行されたサムライ債は約二兆四〇〇〇億円で、すでに、二〇〇七年通年の発行額二兆二五〇〇億円を上回った、二〇〇八年九月、米銀大手シティグループ(C)は過去最高額の三一五〇億円のサムライ債を起債した。
サムライ債の発行体の多くは格付けも高い有名金融機関や企業で、日本の投資家は安全な投資先と考えて債券を購入していた。しかし、この信頼も、もう通用しなくなった。リーマンのサムライ債は、アルゼンチン政府がサムライ債の償還不能に陥った二〇〇一年一二月以来、初めてのデフォルトとなった。投資家たちは、ほかの米証券会社が発行したサムライ債を売却して現金化し、これ以上の損失拡大の阻止に努めるようになった。そして、サムライ債の価格を当初の投資額の二割に設定する投資家も出始めている。全国一六四の信用組合を傘下にもつ、全国信用協同組合連合会(全信組連)は、リーマンのサムライ債に五五〇〇万ドル(約五八億円)を投資していた(BusinessWeek, September 19)。
いよいよ、日本でも信用収縮が本番になった。
文献
Hall, Kenji[2008], "Lehman Collapse Hits Japan Bond Market," BusinessWeek, September 19.
Krugman, Paul[2008], "Financial Russian Roulette," New York Times, September 14.
Roubini, Nouriel[2008], "NYU professor predicting a whale of a bear market," Financial Week,
February 28.
Tett, Gillian & Paul J Davies[2007], "Out of the shadows: How banking's secret system broke
down," Financial Times, December 16