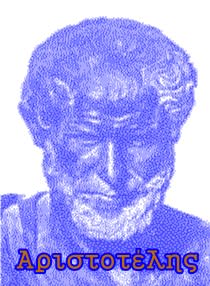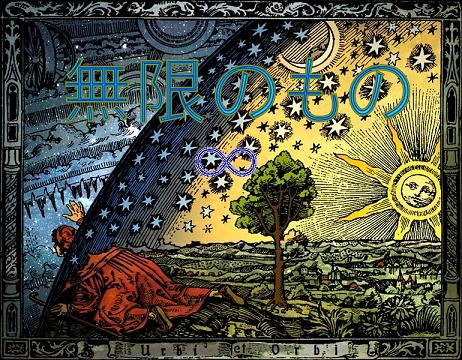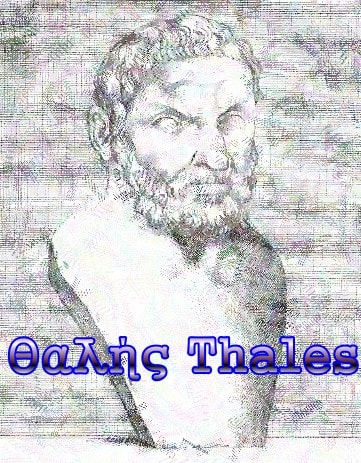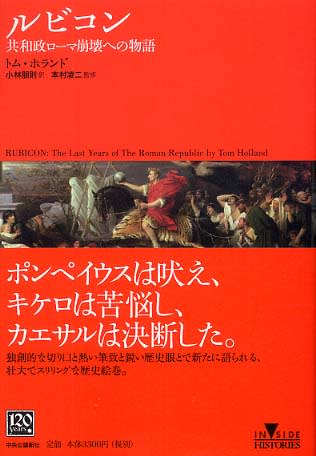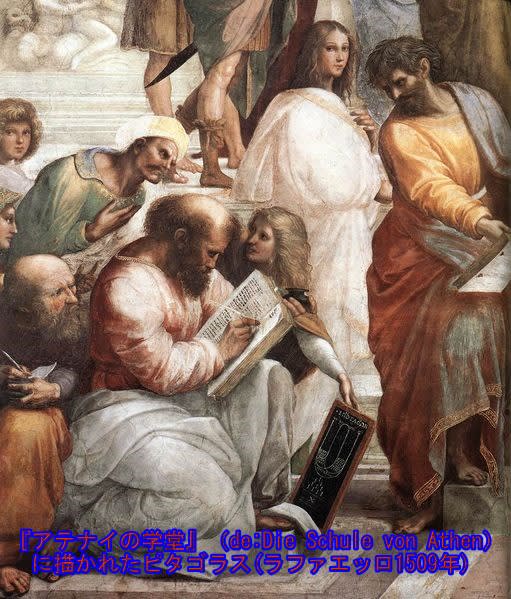以下は、
2003 ココロワークス Produced by 大阪商工会議所に依拠している。
越前大仏(臨済宗妙心寺派)と勝山城という大建造物を造った多田文化財団は、多田清の資財を基に設立された。
 多田清は明治 38 年、福井県勝山市で4人兄弟の末っ子として生まれた。
多田清は明治 38 年、福井県勝山市で4人兄弟の末っ子として生まれた。多田家は、この土地で代々続く庄屋で、かつては苗字帯刀も許された家柄であった。
父親の事業の失敗によって、清が3歳になる頃には代々受け継いだ豊富な山林や田畑をすべて散財し、逃げるようにして商都・大阪に移り住んだとされる。
大阪では明日の生活もままならなかったが、当の清は体格もよく、天衣無縫の腕白小僧であった。
気丈だった母親は、清に
、「お前は偉くなって、多田家を昔のように繁栄させるのだよ。そして、みんなで力を合わせて、銀行を創業した野村徳七さんのような立派な人物になるんだよ」と励ました。
野村徳七とは、
野村証券を創業した人物で、
同じ福井県出身であった。
清は、小学校を卒業すると、早くも丁稚奉公に出て、「少しでも身入りのいい職場を」と職を転々とした。職種を選ばす、自分の体を酷使して働き始めるようになる。原料工場での荷物運搬、運送会社での日雇い労働、さらには、20歳で広島の電信隊に徴兵されてからも、2年間、厳しい軍隊訓練のかたわら休日を利用して働いた。 彼は毎週土曜日に、訓練で疲れた体に鞭打って夜汽車に乗り、広島から神戸まで出ると、またそこから大阪港に来て
、沖仲仕の荷役労働を丸1日こなした。沖仲士と言えば、肉体労働の中でも最重労働である。毎日曜日に、清は港に姿を現した。
軍務のかたわら、勉学に励み、自動車修理の免状と運転免許まで取得した。清は除隊すると、早速、地元の大阪・市岡にある相互自動車(現、
相互タクシー)という小さなタクシー会社の一運転手となる。
タクシー運転手になると、清は少年時代からの親分気質を見込まれ、社内に自分たちの労働組合を組織する。さらに、関西方面の中央組織である大阪交通労働組合にまで出かけ、ストライキの指導までした。 入社3年後、労働組合は大阪交通労働組合のストライキに参加した。そこで、清たちは社長を前に、当時、多くのタクシー会社が実施していた名義貸制度(会社が名義を貸す代わりに、運転手から車庫賃を徴収するシステム)の不当性を訴えた。
席上、社長は、車庫を車で一杯にしてくれたら車庫賃を下げてもよいといった。「よく分かった。それなら、われわれの力で車庫をいっぱいにしよう」と清は約束した。 清の交渉態度に信頼を深めた社長は、さらに会社の経営を組合でやってくれないか、と申し出た。清、26歳のことである。
昭和6年11月6日、清ら 28名のタクシー運転手たちは、後に近代タクシー経営の一翼を担うことになる
相互タクシーの前身「相互共済購買組合」を立ち上げた。まさに労働者管理の「協同組合」の設立であった。
スタート時点から異例ずくめだった。当時のタクシー業界では、経営者が車両を1台も持たずに営業認可を得て、営業権を運転手に名義貸しする、いわゆる
「名義貸制度」の会社が多かった。それに対して
、「相互共済購買組合」はその名が示す通り、会社は同志的に集まった運転手たちが出資しあう共済組合であった。車両、ガソリン、タイヤ、自動車修理、すべてを共同購入するうえ、経営者が経営に関する責任の一切を負う「直営方式」を導入した。さらに、
経営方針には「運転手の生活安定」、「利益はすべて運転手へ」というスローガンを掲げ、会社の利益を労使で折半するという画期的な経営手法が取り入れられた。
清は、不足していた乗務員を広く募り、新車購入を計画。車両の購入には頭金を払っての月賦払いを活用し、組合員の稼ぎと新車購入の支払いを緻密に計算しながら毎月1~2台ずつ車両を増やし、拡大路線を敷いた。その結果、組合スタート時には 16 台しかなかった車両が、3年後には 70 台にまで増加した。
また、運転手の生活安定を経営方針に掲げた相互タクシーは、タクシー業界で初めて公休制を導入し、それまで業界が全く手をつけなかった従業員の福利厚生面にも革命的な進化をもたらした。 創業から5年後の昭和11年には、大阪・関目の地に3000坪の土地を購入し、車両100台を駐車できる大規模な車庫と従業員が居住できる社宅を建設して、“一大タクシー村”をつくり上げたの。手厚い従業員の保護と家族主義的経営が基本であった。他社が1~2年で新車を買い換える時代に、相互タクシーは4~5年もの長い間、車両を走らせることができた。
昭和12年には
日中戦争が勃発し、翌年には
国家総動員法が公布された。その戦時体制化にあって、中小のタクシー業者は経営に行き詰まり、次々に大手企業に身売りするようになる。
日中戦争で世間が日本の将来を案じている時、清は部下に
「タイヤをぎょうさん買っておけ」と命じた。そして、清はオイル不足を見越して、いちはやく
「木炭自動車」の研究に取り組み始めた。そのうち彼にも召集令状が届き、軍隊に入隊するが、それでも研究を諦めなかった。そして、ついに清は、多田式木炭車を完成させた。
時を経ずして、太平洋戦争に突入すると、清の予見通り、ガソリンは急激に不足し、ついにはガソリンの配給が完全にストップした。そして、ガソリン車休車命令が発令された。この時にはすでに相互タクシーは600台の木炭車が稼動できる体制を整えていた。部下に大量購入を命じたタイヤも急速に不足したが、清は倉庫一杯にあふれるストックを抱えて、同業他社との経営体力に大きな差をつけた。
また、一億総決起で戦意が最高の高まりを見せていた頃、清は会議で開口一番
、「今日から経理、営業部長らは中之島の図書館に通って勉強をしてもらいたい。ドイツが第一次世界大戦に負けた直後の経済状況を調べて、1週間後に報告書を出して欲しい」と言った。
「金、銀、の価値がどう変わるかも調べてくるんだ」と付け足した。
「戦後のインフレ対策は、山林を買う、土地を買う、平和産業の株を買う」というものだった。
清は、これらのインフレ対策をすぐに実行に移した。そして、山林は昭和38年頃までに京都府で58 山、大阪府で65山を買占め、平和関連産業の株購入に至っては昭和39年頃までに約6000株、93 銘柄に及び、当時の時価総額で約65 億円にも達した。
後に、木炭車の燃料確保に端を発した山林の買占めは、植林事業として受け継がれ、戦後の地価高騰時代には計算のしようもないほど莫大な資産となる。さらに、一流上場企業の株主となったことで、その受取配当金は半期で5億円にも上る多大な収入源となった。
こうした多田式経営は、ほどなくして経済界にも響き渡り、当時、経営の神様と言われた阪急の総帥・小林一三が、阪急バスの経営を頼み込んだという逸話も残っている。
紺の詰襟と制帽を着用する乗務員
「私が今日あるのは、あらゆる人達に有形無形の迷惑をかけ、そういう意味での借金をしてきたからだ。残された人生で、これらの借金を返してしまわなければ、人間としての価値はない」。
戦前に一タクシー運転手から起業し、一代で大阪を代表する一大タクシーグループを築き上げた清は、
晩年、「人生借金返済論」をしきりに説くようになる。
そして、その言葉通り、「社会に対する当然の恩返し」として数え切れないほどの寄付行為や慈善事業を重ねるが、その最後の仕上げとして構想したのが、父祖が眠る生まれ故郷に大仏を建立する事業だった。
清は、本社の敷地内のガレージを大仏工場に改造して、自ら大仏殿の設計や付属品の試作に取り組んだ。そして、実際に工事が始まると、天候に構わず1週間に一度は現場を訪れ、細部まで自分の目で確かめ、工事業者に厳しい注文を出した。
 昭和62年、実に1857日、延べ8万485人の作業により、大仏殿と五重塔、そして中国の国宝に指定されている装飾壁を再現した九龍壁が完成し、開眼落慶法要が執り行われた。
昭和62年、実に1857日、延べ8万485人の作業により、大仏殿と五重塔、そして中国の国宝に指定されている装飾壁を再現した九龍壁が完成し、開眼落慶法要が執り行われた。

越前大仏は身の丈17㍍、両脇に羅漢像と菩薩像を従え、3方を1281体もの仏像に囲まれた、座像では奈良の大仏をしのぐ日本一の大きさとなった。この大仏の完成により、清は地域社会への貢献を合わせた観光事業への進出を目指そうとしたのだった。 そんな折、清は突然、病に倒れる。病状は重く、長期の入院生活の中で、志半ばの清は事業を後継に託すことを決意する。そして、平成3年7月、ついに清は帰らぬ人となる。葬儀は、清自身が建設した大師山清大寺越前大仏で、しめやかに執り行われた。
 地縁・血縁の大きな財産が福井にはあったものと想像される。
地縁・血縁の大きな財産が福井にはあったものと想像される。