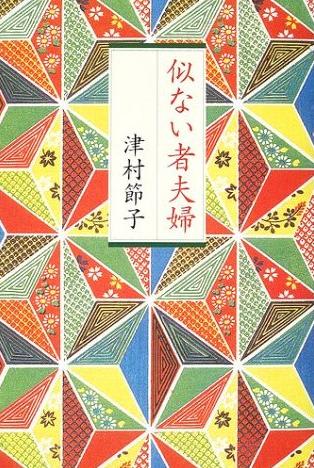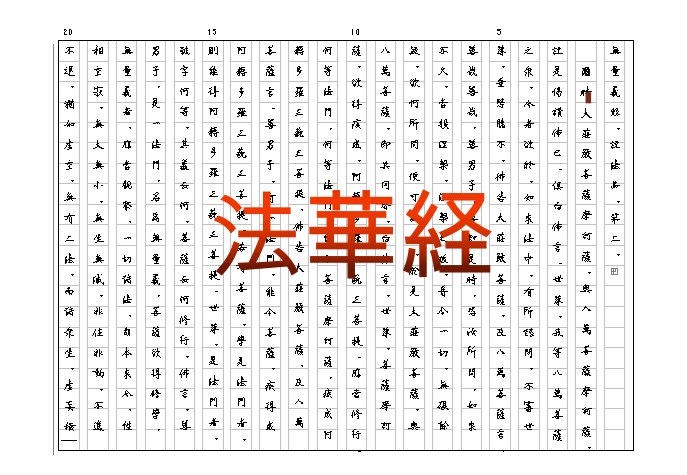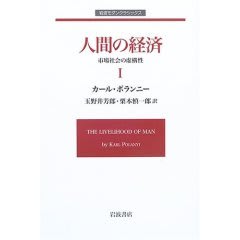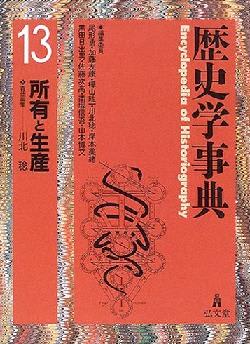津村節子は、1928年福井に生まれ、1965年『玩具』で芥川賞を取り、先日亡くなった吉村昭の伴侶であった。
『似ない者夫婦』(!?ー私の感想)の中の「私のルーツ」(!!!ー私の感想)に「福井の織物」がある。これは、私が日頃感じていることと同じである。
「福井の織物」というタイトルであるが、内容は京福電鉄の、あの痛ましい事故のことである。


京福電鉄は、京都の人には馴染みの深い叡電と嵐電の関連会社であった。
「あった」というのは、いまでは、越前鉄道(エチテツ)という第三セクターになっているからである。私は、福井駅に出るのに、いつもこの電車を使っている。
それに、永平寺町・坂井市のバスはすべて京福バスである。
これも、京都では、赤バスとして大原や比叡山に通じる郊外バスとして京都の人達に親しまれている。私の場合、とくに愛着が深くて、大事な私の若い後輩のご父君がこのバスの運転手をしておられて、大原の風景をよくその後輩から聞かされていた。下宿のある松岡で、京都で見慣れた赤バスが、けなげに走る光景は、棄てたものではない。ただし、一日、数本しか走ってくれない。
2000年12月17日、「本来なら東古市駅’いまの永平寺口ー私)が終点となる永平寺発の電車が、同駅を通過して、そのまま越前本線に乗り入れ、反対方向から来た福井発電車と正面衝突したのである」。「原因は、電車の制動力を車輪に伝える主ロッドが破断していたのだという(???-私の感想)。赤字のため老朽化した車輌を、十分と言えない安全装置のまま運行していたのである。東古市駅は、勝山方面と永平寺方面に分かれる分岐点である(???ー私の感想)」。
確かに、大変な悲劇であった。これを契機として、この鉄道の永平寺線が廃止された。
ずっと以前は、越前本線は勝山を超えて、遠く大野まで伸びていた。永平寺線も東古市を超えて丸岡まで伸びていた。それが、いまでは、勝山が終点、そして、丸岡線は廃止になっている。もったいない。越前平野を環状に被うこの鉄道がいまでもあれば、福井の産業はこうも衰退しなかったであろうに。
「福井県人は勤勉で、共働き率が高い。大野、勝山からお手伝いさんが引き続き来てくれているが(!!ー私の感想)、彼女らは全く無駄遣いせず、貯めたお金でまっ先に買うのは車である。各家の家族たちは一台ずつ車をもっていて、一家に五台もある家も少なくない。車が増えれば、電車に乗る人は少なくなる。利用者は通学の学生か、病院へ行く老人ぐらいにしぼられている。ダイヤは間引かれ、車輌も一輌になり、無人駅が増え、人員削減も行われ、福井ー東古市間に路線を縮小したいという申し入れも会社から出されるようになった。沿線の自治体は、”乗る運動”を展開し、恐竜エキスポの効果もあって、下げ止まりの傾向が見えてきた矢先であった。この度の事故が、京福電鉄にどういう効果をもたらすか、祈るような気持ちである」。
本当にそうである。せめて、わが県立大学と福井大学医学部が学生と教職員の自動車通学・通勤を禁止し、その代わりにバス・電車の増車を懇願して見るべきではないのか。それか、神戸や富山のような新しい交通システムを開発すべきではないのか。
福井県は家族当たり自動車保有率日本一などを自慢している場合ではない。
融雪の水道水の噴射で全身ずぶぬれになる私のような歩行者は、水しぶきあげて平気で疾走する車が地獄の使者に見えて、忌々しくなる。公共交通システムの整備がないかぎり、福井は産業はおろか、人間のコミュニケーション能力を際限なく低カさせるであろう。
一人、車で大学に来て、また人と会話することもなく、ノン・アルコールでまた一人、家路に車で帰る生活から他者が心に住みつく環境は生じないであろう。このまま行けば、我が大学の学生諸君は、いつかは、無感動、無表情の表情になりかねない。なんとかしなければ大変なことになる。打倒!車社会。
福井の車社会の悪口をもうひとつ。ねずみ取りがないのか、とてつもなく、猛スピードで車が走り、車間距離も取らず、嫌みで接近してくる。最低の交通マナーである。携帯、くわえタバコ、片手運転。女の子まで!ライトはアップ、信号で止まってもライトを消さない。本当に嫌になる。