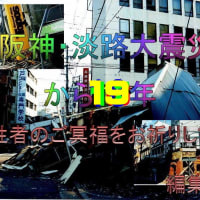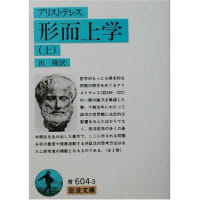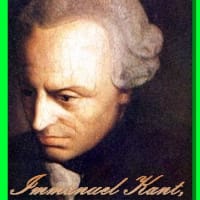市場とは、個々人の営利行為の集合体である。個々人が自己の判断に基づいて行動するが、個人の行動は、それぞれ異なって現れる。市場とは異なる多くの行動を合わせて表現するものである。市場が発信するシグナルを見て、個々人はその行動を修正する。それがまた市場に反映される。
そして、再度の個々人の行動の修正がおこなわれる。そうした繰り返しが市場の内容である。それゆえに、市場は、異なる諸個人の判断の開きをある点に収斂させる機能を結果的にもつ。
金融でいえば、市場は、債券価格の開き具合を調整する場として意識されている。市場によって最終的に示される価格を先取り的に理解して、価格差が収斂する前に、本来の価格から離れてはいるが、いずれ市場の力によって本来の価格に収斂していく債券を売買することで利益を得るのが債券の売買である。
予想の範囲内での価格差、その価格差が収斂していく方向に売買の方向を合わせることによって、利益は生み出される。予想の範囲内での収斂であるために、その過程によって得られる利益は微々たるものでしかない。微々たる利益を大きくするために、レバリッジが働かされる。
いまはバラバラの動きをしているが、いつかは、均衡点に向かう流れが生まれる。そうした動きに売買を合わせることが合理的かつ安全な投資行動である。
しかし、市場には、均衡化作用とともに、パニックを生み出す作用をも合わせもつ。今の流れに不信感をもつようになるとき、人は他の人とは正反対の行動をとる。そして、市場が、そうした行動をする人の数が多いことを示すシグナルを人々に送る。人はそれをみて慌てる。多くの人々がいままでの行動を大きく修正しようとしている。この認識が、いまの状態から逃避しようとのパニックを生み出す。それがまた市場に反映される。こうして、パニックが増幅される。このように、パニックを生み出し、増幅させる作用をも市場はもつ。
ところが、どうしたことか、債券売買という金融の世界では、市場の二つの作用のうち、前者、つまり、均衡化作用をもつ市場の側面のみに照準が合わされてきた。
安全な投資という局面がここにあるので、関心が市場の均衡化作用に向かうのは、当然であるが、それにしては、強引ともいえる高いレバリッジを効かすとき、後者、つまり、パニックを増幅する作用をもつ市場の存在への恐怖心は、いつでも、もたれるべきではあった。そのときには、ファンドを解散させればいいとの思いがあるからなのかは知らないが、少なくとも、債券売買に関する投資理論では、後者の存在は無視ないしは軽視され、市場とは均衡をもたらし、価格差のない方向に収斂させるものであるとの信念のみが信仰のように語られてきた。
リスク(危険)は統計的な確率で表現することができるが、確率が存在しないものがある。これが「不確実性」(uncertainty)であるとしたのは、フランク・ナイト(Frank H. Knight,、1885~1972)であった。一九二〇年代から四〇年代までシカゴ大学で教鞭を取り、同大学の「テニュア」(tenure=終身在職権)であった。

ジェイコブ・バイナー(Jacob Viner, 1892 ~1970)、ヘンリー・シモンズ(Henry Simons, 1899~1946)とともに、経済学におけるシカゴ学派の創設者とされている。


大学側からの厚遇は、ハーバード大学のヨーゼフ・シュンペーター(Joseph Schumpeter, 1883~1950、LSE(London School of Economics)のライオネル・ロビンズ(Lionel Robbins, 1898~1984)に並ぶものであった。
ミシガン大学、テネシー大学を経て、コーネル大学で学位を取得。コーネル大学講師、シカゴ大学講師、アイオア大学准教授を経て、一九二八年にシカゴ大学教授、一九五〇年アメリカ経済学会会長になった。
彼は、確率として把握可能な分散を「リスク」(risk)と定義し、確率的にも把握できない分散を「不確定性」(uncertainty)としてリスクと区別した(Knight, F.[1921])。これは、「ナイトの不確実性」と呼ばれる。
将来を予測するということは、不確定な状態下でどの程度の「確かさ」で期待が生じるかを当てる作業である。これには、三つの可能性がある。
一つは、数学的に先験的に確率として予見できるもので、「先験的確率」というタイプに属するものである。たとえば、二つのサイコロを振って、目の和が一〇になる確率は数学的に出てくる。その確率の範囲で将来は予測される。
二つは、統計的に検証できるもので、「統計的経験的確率」という種類に属するものである。たとえば、来年の出生率とか、平均寿命の予測などがこれに属する。予測は経験的に検証されている数値に基づいておこなわれる。
三つは、数学的確率も経験的検証もできないもので、一回限りの発生で、繰り返されないものを予測することである。そもそも予測を可能にするようなデータが存在しないので、予測はあくまでも「推定」でしかない。数学的先験的確率も経験的統計的確率も存在せず、「大数の法則」も作用しない。そうしたことの発生を予測することである。
この第一と第二のタイプが「リスク」であり、第三のタイプが「不確実性」である。つまり、第三のタイプは、「なにが起こるかは予測できない」といった事象を扱う。ナイトは、この三つ目のタイプが、経営者が対応しなければならないものなのであり、経営者の報酬とはこの行動に対するものであるとした。
「大数の法則」とは、統計上の母集団の平均値とこの母集団から無作為に抽出された標本の平均値とを比較し、標本が大きくなればなるほど、標本の平均値は母集団の平均値(真の平均値)に近づくというものである。
真の平均値と標本の平均値との誤差の大きさは正規分布に従うものとして統計的には処理されている。
統計的に面白いのは、母集団が正規分布になっていない場合でも、無作為標本の標本平均は、標本が十分に大きくなれば真の平均との誤差が正規分布をなすということである。母集団が正規分布であろうとなかろうと、誤差は正規分布に従うという数学上の定理は「中心極限定理」と呼ばれる。この定理がLTCMなどの投資を客に信頼させる理論として多用されたのであるが、これは、上で見たナイトの「リスク」の範囲内でのことでしかない。
第三のタイプの「不確実性」は考慮外に置かれ、実際には、アジア通貨危機、ロシアのデフォールト危機という第三のタイプの不確実性に見舞われ、一瞬にしてLTCMは吹き飛ばされてしまったのである。
現実は、起こりうる確率など計算できない不確実性に満ちている。したがって、将来への行動の決断は、確率ではなく、経営者の主観的楽観に依存するしかない。そしてその楽観はしばしば現実に裏切られる。したがって、企業社会はつねに過剰生産と過少生産との間で揺れ動かざるを得ない。これがケインズの「不確実性」理解であった。
ナイトのいう不確実性はまだ破局を意味していない。しかし、ケインズになると、社会の激動・恐慌などの存在を認知しているのである。

ナイトは、コーネル大学時代のハーバート・J・ダベンポート(Herbert J. Davenport, 1861~1931)からもっとも大きな影響を受けている。



ダベンポートは、ジェヴォンズ(William Stanley Jevons, 1835~1888)、ウィックスティード(Philip H. Wicksteed, 1844~1927)、オーストリー学派などの限界理論に、ヴブレン(Thorstein Veblen, 1957~1929)の人間行動の心理を相対的に扱う手法を組み合わせた「米国心理学派」(American Phychologicak School)の創始者である。ナイトは、限界理論を奉じてはいたが、けっして数理主義者ではなかった。
非常に論争好きの学者ではあったが、いろいろな学派から積極的なものを採用する、J・S・ミル(John Stuart Mill, 1806~1873)のような偉大な折衷主義者であった。

たとえばワルラス派からは市場の複数理解を受容したが、彼らの数学への傾斜を非難した。
オーストリー学派からは代替コスト理論を評価したが資本理論を退けた。マーシャル学派からはその文学的香りを受け継いだが実質コスト理論を批判した。リカードウ学派からは社会階層論を受容したが彼らの客観主義的傾向を非難した。マルクス学派の資本主義に対する倫理的批判を受け入れたが労働価値説は退けた。制度学派からは社会制度のもつ意味を重視したが、彼らの経験主義的な歴史観は批判した。歴史とは感得するもので、なぞるものではないとしたのである。
ナイトは、経済学だけでなく、哲学、社会学、歴史学を重視した。
そして、資本主義の倫理の喪失を生涯を通じて批判していた。とくに、「競争の倫理」(一九二三年、Knight[1923])では、資本主義は、人々が必要とするものを生産しないで、資本主義が生産するものへの需要を作り出すだけであるという強烈は資本主義批判を行った。
「もっとも自由でいる人ですら経済環境の産物である。この環境は人の欲求と必要を形成してしまい、市場で売れる生産物を人に作らせて人に与える。こうして、資本主義は、人の機会をもほとんど管理してしまうのである」(同)。
ナイトは続ける。まるでマルクスを彷彿とさせる資本主義への厳しい告発である。
曰く。市場は独占を生む。市場が効率的であるというのは嘘である。市場は社会に有益な産物を供給していない。限界生産力説は道徳的に誤った含意をもたらす。所得は生産要素に帰属しているとこの理論は説くが、実際に所得を得るのは要素ではなく要素の所有者である。したがって、生産設備の所有者が所得を得る権利をもつと軽々に弁護されてはならない。所有とは相続されたもの、幸運で手に入れたもの、努力で獲得できたものの複合的な所産でしかないからである(同)。
こうして、彼は「弁護論的経済学」(apologetic economics)を侮蔑したのである。しかし、彼は経済過程に権力が介入することには反対していた。
経済は複雑にして不安定なものである。そうした複雑性に対処するには、政府の経済計画は単純すぎる。権力の経済過程への介入は、なにもしないよりも危険である。したがって、自由放任(レッセフェール=Laissez-faire)が望ましい。これは、レッセフェールが有効に機能しているからではない。レッセフェールそのものが有効に機能しないのは明らかである。しかし、レッセフェールは個人の自由を最高善と見なし、それ以外のものを害悪と理解するから重要なのであると彼は主張した。


フリードマン(Milton Friedman, 1912~2006)やスティグラー(George J. Stigler, 1911-1991)たちがシカゴ学派の第二世代とされ、一九六〇年代の経済学を牽引したが、彼らとは明確に一線を画す道徳的経済学者であった。