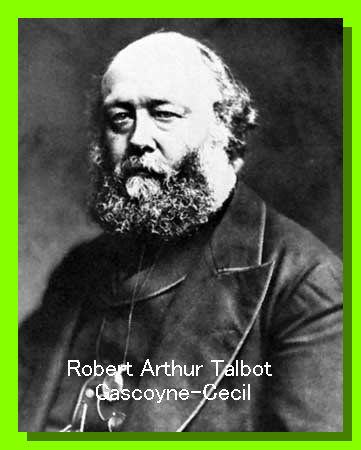二 日露戦争の奇襲攻撃
日露戦争開戦の一か月前、ロシア側の主戦派の一人と考えられていた政治家が戦争を回避しようと「日露同盟」案を準備しているとの情報を得ながら、日本政府が黙殺していたことを示す新史料を、和田春樹・東大名誉教授が二〇〇九年一二月に発見した。日露戦争についてはこれまで、司馬遼太郎の『坂の上の雲』で展開された「追いつめられた日本の防衛戦」とする見方が日本では根強い。しかし、この新資料が正しければ、これまでの通説は崩壊する。
和田名誉教授は、サンクトペテルスブルク(St. Petersburg)の.ロシア国立歴史文書館(Russian State Historical Archive)で、ニコラス二世皇帝(Czar Nicholas II)から信頼されていた非公式貿易担当大臣の主戦派政治家ベゾブラーゾフ(Aleksandr Bezobrazov)の署名がある一九〇四年一月一〇日付の「同盟」案全文を発見した。「同盟」案は、「ロシアが遼東半島を越えて、朝鮮半島、中国深部に拡大することは、まったく不必要であるばかりか、ロシアを弱化させるだけだろう」と分析、「ロシアと日本は、それぞれ満州と朝鮮に国策開発会社を作り、ロシアは満州、日本は朝鮮、の天然資源を開発する」ことなどを提案する内容のものであった。
ベゾブラーゾフが「日露同盟」案を準備していることを日本の駐露外交官の手で日本の外務大臣・小村寿太郎(じゅたろう)に打電された。一九〇四年一月一日のことであった。詳しい内容が、同月一三日、小村外相に伝えられた。日本の外務省は、その電文を駐韓公使館に参考情報として転電した。和田春樹は、この転送電文を、韓国国史編纂委員会刊行の「駐韓日本公使館記録」の中から見つけた。
当時の小村寿太郎外相は日露同盟案の情報を得ながら、一月八日、桂太郎(かつら・たろう)首相や陸海軍両大臣らと協議して開戦の方針を固め、同月一二の御前会議を経て、同年二月、ロシアに宣戦布告したのであると、共同ニュースは伝えた(共同、二〇〇九年一二月二日付。http://d.hatena.ne.jp/takashi1982/20091207/1260192623、和田[二〇〇九])。この文書の内容に沿ってロシアが動こうとしているとすれば、満州支配後にロシアが韓国領有に向かおうとしていたので、それを阻止すべく日本は韓国併合に出るしかなかったという司馬遼太郎的史観は崩壊するとの見方も出てきた(Japan Times, December 9, 2009)。
しかし、開戦が近いことは、ロシア当局も十分承知していたであろうし、一片の電報で日本が開戦を思い止まるなどと思うほど、ロシアの軍部、政府は甘くはなかったはずである。資料発見は大きな成果だが、この電文程度で、日本政府も開戦を中止したとはとても思われぬことである。
周知の史実であるが、少し、日露開戦前後のことを整理したおこう。
日本政府内では小村寿太郎、桂太郎、山縣有朋(やまがた・ありとも)らの対露主戦派と、伊藤博文、井上馨(かおる)ら戦争回避派とが対立していた。一九〇三年四月二一日、山縣の京都における別荘・無鄰菴(むりんあん)で伊藤・山縣・桂・小村による「無鄰菴会議」が開かれ、満洲については、ロシアの優越権を認めるが日本は韓国を確保すべく、日露開戦やむなしと述べたが(徳富編[一九三三]、五三九~五四一ページ)、実際には伊藤の慎重論が優勢であったと言われている
一九〇三年八月から開始された日露交渉で、日本側は朝鮮半島を日本、満洲をロシアの支配下に置くという妥協案、いわゆる満韓交換論をロシア側へ提案したが、ニコライ二世などの主戦派によってその提案は一蹴された。そして、一九〇四年二月六日、外務大臣・小村寿太郎が、ロシア公使に国交断絶を言い渡した。
一九〇四年二月八日、旅順港に配備されていたロシア旅順艦隊(第一太平洋艦隊)に対する日本海軍駆逐艦の奇襲攻撃に始まった。まだ、宣戦布告を日本側はしていなかった。日本艦隊は、同日夜、旅順港(Port Arthur)に停泊していたロシア艦隊の半数を拘束した。港外で哨戒の任に当たっていた二隻のロシアの駆逐艦が、日本の駆逐艦一〇隻から攻撃を受け、慌てて港内に逃げ込み、ロシア艦隊に急襲を知らせたが、日本の駆逐艦が船尾に張り付き、ロシアの哨戒艇や軍艦を包囲してしまった。ロシア艦隊の乗組員たちは飲酒のために上陸していて、なす術がなかった。東郷平八郎(とうごう・へいはちろう)率いる日本艦隊は、機雷を港外に配置し、ロシア艦隊の脱出を妨害した。それは、後の真珠湾攻撃で米国が抱いたものと同じ憤激をロシア側に与えた( http://constantineintokyo.com/2009/12/22/112/)。
宣戦布告前の奇襲攻撃は韓国でも行なわれた。二月八日、日本陸軍先遣部隊の第一二師団が仁川(Incheon)に上陸した。日本海軍の巡洋艦群が、同旅団の護衛に当たった。日本の艦隊が、仁川港に入港する際に、偶然出港しようとしたロシアの航洋砲艦・コレーエツ(Koreets)が、すれ違う時に儀仗隊(ぎじょうたい=捧げ銃の敬礼を行なう役目を担う隊)を甲板に並べて敬意を表した。しかし、日本の水雷艇が魚雷攻撃をかけ、コレーエツは、慌てて一発砲撃して引き返した。
そして、二月九日、仁川港に停泊中のロシア太平洋艦隊所属の艦船に退去勧告を行ない、退去しない場合は攻撃を加える旨を日本艦隊が伝えた。ところが、この退避勧告によって仁川港から出航したロシア艦隊は、待ち構えていた日本艦隊に砲撃され、一等防護巡洋艦・ヴァリャーグ(Varyag)は大破し、仁川港に引き返し、乗組員を上陸させた後、「コレーエツと共に自沈した(http://homepage2.nifty.com/daimyoshibo/mil/jinsen.html)。後に、ヴァリャーグは引き上げられ、二等巡洋艦・宗谷として日本海軍に編入された。