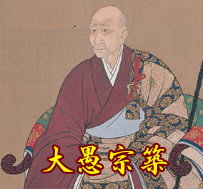福井県立大学の学章は白樫に鶫(つぐみ)が駐まっているデザインである。
シラガシ(白樫)は、ブナ科コナラ属の常緑広葉樹である。本州中南部から四国、九州に自生、また、朝鮮南部にも分布している。辺心材の区分は不明瞭で、材の色調は全体に淡黄色を帯びた灰褐色を呈す。柾目面には虎班が現れ、板目面には著しい樫目が見られる。 木質は国産材の中では極めて重硬で強靭である。そのためもあって、切削などの加工や乾燥は困難である。器具材、車両材、船舶材、機械材、枕木、薪炭材などに用いられ、特殊用途としては鉋台や農工具の柄、櫓などもある。
あまり大径木にはならない。街路樹としてよく見かける高木である。葉っぱが細長いのが特徴であり、ギザギザ状である。
材が白いカシの木なので「白樫」というが、見た目の樹皮は黒いので「黒樫」とも呼ぶ。表面はすべすべである。秋になるドングリは細めである。
「白橿」とも書く。別名 「黒樫(くろかし)」
あしひきの
山道(やまぢ)も知らず
白橿の 枝もとををに 雪の降れれば
(万葉集・柿本人麿)。
福井県立大学のホームページの説明によれば、「しらかし」をマークに入れたのは、「勇気と力」を学生にもってもらいたいとの願いを込めているという。 大学祭は「白樫祭」と称されている。素直な人たちである。
鶫は、福井県が県鳥に指定した鳥である。大学のホームページでは、「ここで学んだ学生たちが勇気をもってつぐみのように飛翔する国際人に育ってほしい」という願いと、「研究においては国際水準を、教育においては全人類的視野を養成する」との決意が込められています、とある。
福井県の花「水仙」は昭和29年に指定、県木「松」は昭和41年に指定、さらに冬の味覚「越前がに」が平成元年、県魚に指定された。そして、県鳥「つぐみ」が昭和42年に指定されている。
県鳥「つぐみ」は再指定された2代目の鳥で、初代の鳥は「こうのとり」だった。初代は昭和39年の指定だが、すでに絶滅しつつあったため、再び県民からの公募で「つぐみ」に決まったものである。
つぐみは日本に渡来する代表的な冬鳥で、全長約20cm前後の小鳥である。シベリア北部で夏を過ごし10月頃、日本に飛来して福井県をはじめ中部以南の日本各地と中国で越冬する。毎年晩秋になると約100万羽が福井県に来る。
日本海の荒波を超えて渡ってくる勇気と厳しい寒さに耐えるたくましい生命力が、県民性に共通し学ぶところが多いことから、県鳥として指定されたという。
かつては冬の味覚として捕獲し食用にされた時代もあったが、昭和22年に捕獲が禁止されたことから、国境をもたない渡り鳥をあたたかく迎え、密猟の悪習を根絶しようという、やさしい県民の気持ちがこめられていると福井ではいわれている。
大学の学章を紹介したついでに学歌も紹介しよう。少なくともそんじょそこらのありふれた校歌ではない。
(音声(MP3)「福井県立大学」HPより)

なんと美しい歌詞か。
作詞者は清水哲男、あの詩人の清水哲男なのか、同姓の別人なのかは知らない。わかればまた紹介する。
とにかく詩情溢れる秀歌である。
すごいでしょう。本当にすごい。
悩みがいとしく、哀しみがまぶしい。
なんという感性。
そうなのだ。悩み悲しむことこそが青春なのだ。
そうだったのだ。
わが大学の学長は歴代農学者であった。
通じるものがある。いのちの深さに。