岸本芳也「米国発明法の特許防衛戦略」を読みました。
著者は、米国特許実務家として有名な方で、私も企業勤務時代にお話を伺ったことがあります。
2011年9月16日に成立した米国発明法は、先願主義への移行をはじめ、付与後異議申立制度の導入や訴訟における無効抗弁の制限、米国特許商標庁の財政・組織改革規則制定に至るまで、37項目にも及ぶ広範な大改正となりました。
この本は、米国発明法の大改正について実務者が押さえておくべき重要ポイントについて、特許実務家、企業の知財・法務部員ならびに事業部の意思決定者が、戦略的・実務的に活用できるように説明されています。
この本には、「米国発明法の概略」「先願主義への移行」「その他の主な改正」「防衛手段とそれを阻止する手段」「USPTOの審査と裁判所の審理の相違」「付与後異議申立制度」「査定系再審査」「付与前情報提供」「申立人における付与後異議申立のメリットと留意点」「特許権者の付与後異議申立への対応戦略」「付与前情報提供のメリットと留意点」「弁護士の助言・鑑定の活用による防衛戦略」「特許権者による補充審査の活用」について分かりやすく書かれています。
何といっても実務的な留意点が書かれていること分かりやすい理由の一つでしょう。
私が特に役に立ったのは、「USPTOの審査と裁判所の審理の相違」の中の「立証基準の相違」ですね。
日本では、あまり意識することがないのですが、USPTOでは証拠の優越、裁判所では明白かつ確信を抱くに足る証拠と、立証基準が異なっており、裁判所で特許の有効性が否定されるケースは日本と比べてかなり少ないのが現状です。
このように、米国と日本との相違を理解して対応する能力が実務家には不可欠ですね。
ご一読をお薦めします。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
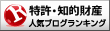
特許・知的財産 ブログランキングへ
著者は、米国特許実務家として有名な方で、私も企業勤務時代にお話を伺ったことがあります。
2011年9月16日に成立した米国発明法は、先願主義への移行をはじめ、付与後異議申立制度の導入や訴訟における無効抗弁の制限、米国特許商標庁の財政・組織改革規則制定に至るまで、37項目にも及ぶ広範な大改正となりました。
この本は、米国発明法の大改正について実務者が押さえておくべき重要ポイントについて、特許実務家、企業の知財・法務部員ならびに事業部の意思決定者が、戦略的・実務的に活用できるように説明されています。
この本には、「米国発明法の概略」「先願主義への移行」「その他の主な改正」「防衛手段とそれを阻止する手段」「USPTOの審査と裁判所の審理の相違」「付与後異議申立制度」「査定系再審査」「付与前情報提供」「申立人における付与後異議申立のメリットと留意点」「特許権者の付与後異議申立への対応戦略」「付与前情報提供のメリットと留意点」「弁護士の助言・鑑定の活用による防衛戦略」「特許権者による補充審査の活用」について分かりやすく書かれています。
何といっても実務的な留意点が書かれていること分かりやすい理由の一つでしょう。
私が特に役に立ったのは、「USPTOの審査と裁判所の審理の相違」の中の「立証基準の相違」ですね。
日本では、あまり意識することがないのですが、USPTOでは証拠の優越、裁判所では明白かつ確信を抱くに足る証拠と、立証基準が異なっており、裁判所で特許の有効性が否定されるケースは日本と比べてかなり少ないのが現状です。
このように、米国と日本との相違を理解して対応する能力が実務家には不可欠ですね。
ご一読をお薦めします。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
特許・知的財産 ブログランキングへ














