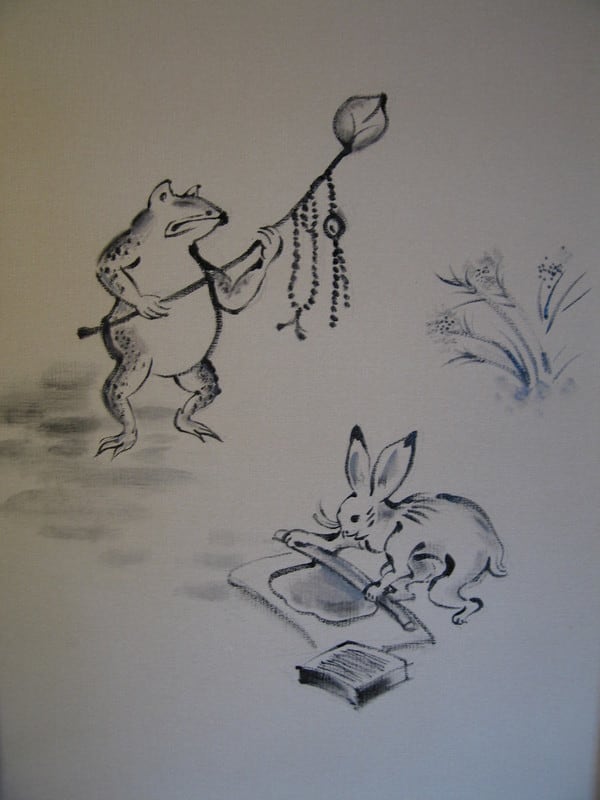静岡というローカルエリアで活動していると、知り合いの知り合いが知り合いだったりして、世間は狭いと実感すること、しばしばです。それでも時々、この分野の人と、あの世界の人が、どーして知り合いなんだぁ?と笑っちゃうしかないよな経験があるから不思議です。個人で仕事をしていると、どこで、どんなつながりが生きてくるかわかりません。だからこそ、出会いの一つひとつを大切にしたいと思うのです。
最近不思議だったのは、私のライフワークである地酒の関係者と、映像作品『朝鮮通信使』が、なぜかつながったこと。1年前、クランクインを目前に、平日の午後から夜にかけて予定されていた大井川の川越遺跡のロケで必要な数のエキストラが集まらず(運悪く、その日に山田洋次監督の『母べえ』大井川ロケがあり、島田フィルムコミッション関係者はほとんど出はらっていたのです・・・)、困っていたスタッフを見かねて、私は島田・藤枝地区の地酒関係の知人に片っ端から電話をかけ、『若竹』の醸造元・大村屋酒造場の松永今朝二社長と、『喜久酔松下米』の酒米農家・松下明弘さんが協力してくれることになりました。松永社長は、「今夜、島田の主だった人たちが集まる若竹サロンがあるから、宣伝しに来なさい」と誘ってくれ、その足で蔵へ飛んだ私は、一晩で10人のエキストラを確保することができました。

その中に、松永社長の中央大学の後輩で、3年前、しずおか地酒研究会の若竹訪問で“相撲甚句”を披露してくれた社労士の見城邦男さんがいました。三保、駿府公園、大井川すべてのロケのエキストラにエントリーしてくれ、「大河ドラマのエキストラにも出たことがあるんだ、時代劇なら任せておけ」と頼もしいお言葉。

一方、松下さんは「平日体が空いているのは、どうせ俺たち農家ぐらいなもんだと思って声掛けてきたんだろう?」と皮肉を言いながらも、知り合いの農家に声をかけ、2人で川越遺跡の撮影に参加してくれました。
どの撮影も、大変な寒さの中、薄着の衣装で長時間拘束され、「終電に乗れなかったらどうしてくれるんだ」と苦情もあったみたいですが、今は「ああいう経験は2度とないなぁ」と笑って話してくれます。寒い思いは一時でも、映像は永遠に残りますものね!
その後、脚本の監修でお世話になった金両基先生と松下明弘さんが、なぜか知り合いで、先生宅で酒を酌み交わしたことがあると知り、びっくり。「うちでは変わり者が集まる訳のわからん飲み会を時々やるんだ。その中のメンバーが連れてきたんだよ」と金先生。「彼から、貴女の名前を聞いてビックリしたよ。やっぱり変わり者つながりなんだな」。・・・このときばかりは、変わり者呼ばわりが、なぜか褒め言葉に聞こえ、作品完成後は、松下さんの有機コシヒカリと喜久酔松下米をセットでお贈りし、先生と奥様に大いに喜んでいただきました。

見城さんが、3年前、しずおか地酒研究会の若竹訪問で相撲甚句を披露したとき、そのリーダーとして参加してくれたのが石川たか子さん。先月まで浅間神社の静岡市文化財資料館で相撲人形コレクション展を開いたほどの相撲通で、静岡の名士・粋人が集うシズオカ文化クラブの会長として活躍されています。
実は、10数年前、映像の仕事に、ちょこっとだけ関わったことがあります。それが、たか子さんが社長を務める㈱丸伸のプロモーションビデオで絵コンテを描く仕事でした。丸伸のロングセラーである可動式本棚“ブックマン”の洋服ラック版“ドレスマン”を紹介するもので、たか子さんとはこの時知り合い、同じ中学・高校の大先輩だと知り、それ以来、何かと目をかけていただいています。
シズオカ文化クラブに初めて参加したのは、数年前、同クラブが、松下さんの米作りを撮り続け、ドキュメント写真の登竜門といわれる土門拳奨励賞を受賞したフォトグラファー多々良栄里さんの作品鑑賞&喜久酔松下米を味わう会を企画したときでした。私は、栄里さんと松下さんを引き合わせた縁で招待され、なかなか呑む機会のない松下米40を存分に呑ませてもらいました。
栄里さんに松下さんを引き合わせたのは、2人が写真家&農家として新たな挑戦に踏み出した頃のこと。円熟したプロ同士のセッションというよりも、若く、荒削り状態の摩擦や共鳴が互いに反映されるのではないかと思ったのですが、作品は、円熟味さえある完成度の高いものとなり、それが観る者・味わう者に深い感動を呼びました。年齢やキャリアじゃない、2人が出会うべくして出会って、自然に生まれたんだ、人生にはそういう出会いがあるんだ・・・としみじみ思いました。
多々良栄里さんの土門拳奨励賞受賞作品『松下くんの山田錦』。パソコン上では真価が十分伝わらないかもしれませんが、未見の方はぜひご覧ください。映画『吟醸王国しずおか』でも使わせてもらえたら、とひそかに願っています。
そして今月、シズオカ文化クラブに再び招かれることになりました。
このブログでも紹介した通信使ラベルの酒・白隠正宗大吟醸を呑みながら、『朝鮮通信使』を鑑賞する会を企画してくれたのです。なんだか、ホントに、私のためだけに催される会みたいで恐縮です・・・。
“地酒の女神が映画を作った?!”~『朝鮮通信使』鑑賞とゆかりの地酒賞味/3月25日(火)18時30分から、静岡市産学交流センターB-nest 6階プレゼンテーションルームにて。酒代&おつまみ代2000円。申込み・問合せは18日までに、シズオカ文化クラブ事務局 TEL 054-271-3111(財団法人満井就職支援財団内、担当・内田)まで。

駿府公園東御門で、黒子衣装で人型の絵を持って寒さをこらえてくれた見城さん。大井川川越遺跡で通信使の薄い衣装を着て何度も行進させられた松下さん。2月15日の通信使上映会&トークセッションに来てくれた栄里さん。そして「大御所四百年祭の年度中になんとか上映会を!」と奔走してくれた石川たか子さん。
みなさんの存在は、人と人の出会いや縁をつなぎ続けることの大切さ、会社の肩書きや所属先を持たないフリーランサーにとって、人脈が何よりの財産であることを教えてくれます。感謝の気持ちで一杯です。
朝鮮通信使で新たに出会った人、これから出会う人とも、こういうつながりを持ち続けられたら、と願わずにいられません。