おまたせしました。4月6日しずおか地酒サロンの松崎晴雄さん講座の続きです。

全国新酒鑑評会100年の副産物のもう一つは、新しい産地を発掘したということです。
明治末にスタートした鑑評会ですが、当時の代表的な銘醸地といえば灘と伏見ですね。東京市場でも認知されており、一般の人には「上方の酒は上物」と浸透していましたし、そういう一般感覚からすれば、鑑評会でも当然、灘や伏見の酒が上位に来るだろうと思われていました。
ところがフタをあけてみたら、広島が圧倒し、明治終わりから大正時代にかけ、上位3位を独占するぐらいの勢いをみせ、東京でも取引が始まりました。鑑評会で優秀な成績をとると東京市場で酒が売れるということが認知され、今でも続いています。
この100年を見ると、まず広島。そして9号酵母の発祥の地・熊本ですね。熊本は江戸時代まで、清酒造りが温暖な気候に向かないからという理由で禁止されていたのです。今でも熊本ときくと清酒よりも焼酎のイメージのほうが大きいでしょうか。肥後藩では貴重な米を清酒にしても、腐らせてしまうのではまずいということで、清酒造りの代わりに赤酒という、灰を混ぜてアルカリ化したものを造らせたのです。
明治になって清酒造りが許されるようになると、江戸時代のハンディを取り戻そうと、熊本の酒蔵が共同出資して熊本県酒造研究所を設立し、9号酵母の開発に結び付いた。酒どころとしては後発組だったからこそ、先行する産地に追い付け追い越せで努力をし、南の吟醸産地として浮上したというわけです。
秋田県も今でこそ東北を代表する銘醸地ですが、昔はそうでもなく、全国新酒鑑評会によって産地として認められてきました。
静岡県も四半世紀前に鑑評会を舞台に“吟醸王国”としての地位を得ました。鑑評会にかける蔵元や研究者の意気込みが、産地形成につながったといえるでしょう。鑑評会とは、単にモノを造って評価するだけの場ではない、何か造り手を突き動かすものがあって、その晴れ舞台になる場といいますか、そこにかける人々の情熱のようなものが違った次元で昇華する舞台なのでは、と思っています。
地方銘酒は鑑評会によって百花繚乱に華開き、静岡県が果たした役割も大きかったといえるでしょう。酒造りの後発県でも、頑張れば一流の銘醸地になるという励みになったと思います。
さて今日は酒米のお話もしようと思います。ここ30年ぐらいの代表的な品種として山田錦や五百万石、さらに近年開発された品種―静岡県の誉富士も含まれますが、一覧表にまとめてみました。
一般米で酒造りにも利用されている品種もまとめてみました。酒造りに使われている米の7割は、実は一般米で、酒造好適米は3割程度なんです。
戦前に造られていた古い品種を復活させた米も増えていますね。漫画「夏子の酒」のブームも手伝ったと思います。その土地の酒造りのルーツを探るという、酵母とは違ったかたちの、地酒本来の姿を探求した成果だといえます。
地酒といいながら、兵庫県産山田錦と9号酵母を使った標準的な吟醸酒が多いのも事実です。原材料というところから、その土地の風土性を探る、ワインのような流れがあってもいいと思います。
米の難点は、大きな味の違いがないということです。目隠してきき酒すると、ワインならメルローやカベルネソービニオンの違いぐらいはわかるんですが、日本酒の場合はなかなかそういきません。しかも日本酒に使われる米は200~300種類あるといわれます。
米よりも違いが解りやすいのが酵母です。静岡の酒の味を特徴づけているのが静岡酵母だというわけです。仮に秋田、長野、静岡の酵母の違いできき酒したら、当てられる自信はまあ、あります。
鑑評会では1品あたり20~30秒程度できき酒しますので、短時間で訴えかけるものがあれば、当然印象に残ります。よほど欠点がない限り上位にくるでしょう。香りが高い酵母がどんどん増えてきた背景にはこういう理由もありました。
酵母は確かにわかりやすいのですが、行きすぎると香りがきつくなる。きき酒は短時間で吐いて判断しますが、飲酒の際、行きすぎた香りの酒では長時間呑み続けることはできません。
最近の酵母でいえば、福島県のうつくしま煌めき酵母というのがあります。1種類ではなく3種類ぐらいの酵母の総称で、デビューして2年ぐらいの新しい酵母で、香りの小・中・大とそろっているんですね。県として産地イメージを高める意味で、総称統一したようです。
バイオテクノロジーの発達で、天然の花や植物から酵母を採取し、酒造りに活用したものも増えていますね。東京農大でも花酵母を15種類ぐらい出していますね。カーネーション、しゃくなげ、なでしこの酵母が知られています。酵母開発は日本酒のトレンドを占う意味で一つの重要なファクターであることは間違いありません。
吟醸酒はどうしても香りを追い求める酒ですから、香りの出る酵母はこれからも開発され続けて行くと思いますが、非常に酸の出る超辛口酒用の酵母や、色を出す酵母等、日本酒の多様性を広げて行く意味でますます盛んになると思います。
ただし、吟醸酒の王道を行く、きれいで呑みやすい酒になるスタンダードな酵母があって、特殊な酵母も存在するわけです。静岡の時代があり、秋田や長野の時代があり、今またトレンドが変わっている。各県でも次世代型の造り方に移っています。
米の世界でも、味の出やすい米、精米をおさえてもきれいな米など、いろいろな米も出てきます。酵母ほど簡単に開発はできませんが、山田錦は誕生してから80年もロングセラーを誇っており、この間、山田錦を超える米はなかなか出てきません。全国に1600社ほどある日本酒の酒蔵のうち、1000社は山田錦を使ったことがあるでしょう、それだけ広範囲で使われている米は、他にはありません。
あと20年すれば山田錦は誕生一世紀になるわけで、農家にも酒造会社にとっても膨大なデータが蓄積され、扱いやすくなっているといえます。はたして21世紀中に山田錦を超える米が登場するのか、今世紀中の最大のテーマといえるかもしれません。山田錦と同じような米では意味がないので、まったく異なった切り口で、山田錦を超える米が登場するのか、期待したいところです。
このように、日本酒は古いようで新しい酒です。つねに新しい技術が投入され、日々進化し続けていて、ときには元に戻ったりする。そんなところに日本酒の面白みがあるような気がします。
新しいといえば、ワインのコンペティションに日本酒部門ができたり、アメリカでは2001年から全米日本酒コンテストというのも行っています。日本から5人、アメリカから5人、計10人で日本の鑑評会とまったく同じやり方で審査します。
また毎年、2蔵ぐらいずつ海外でミニブルワリーが誕生し、日本語の話せないブルワリーマスターが日本酒を一生懸命造っています。彼らも出来たら鑑評会に出品したいと言っています。技術者としては同じマインドなんですね。いずれ、日本酒のワールドカップみたいな世界規模のコンペティションが開かれて、「今年は南米代表の蔵が優勝した」なんてニュースが世界中を駆け回ることを想像すると楽しいですね。
山田錦を超える米の誕生、日本酒のワールドカップ。この2つが今世紀中に実現できるかどうか、どうかみなさんも興味を持って見守ってください。(文責/鈴木真弓)
最後の「今世紀中に実現できるか、山田錦を超える米の誕生&日本酒のワールドカップ」という夢のあるお話、ガツンと来ましたねえ!!また受講生に配っていただいた、各県別・時代別の酒米&酵母の一覧表、松崎さんが長年のリサーチのもとで独自に創り上げた大変貴重な資料です。本当にありがたいです。こういうの、本来は酒米農家や酒販店主やきき酒師等、酒を業務にする人たちのほうがよっぽど参考になるんじゃないかあ。消費者のほうがどんどん知恵を付けてしまうようで怖い(笑)。

2次会の日本酒BAR佐千帆は、定員10人の店に30人押し込んで、みなさん立ち呑み状態でガマンしてくれました。カウンターの中に回って給仕役を務めてくれた『正雪』の望月正隆さん、『喜久醉』の青島孝さん、『白隠正宗』の高嶋一孝さん、ありがとうございました。3人がカウンターで接客する姿、お宝モノだったと評判でしたよ。
無理を受け入れてくださった長沢佐千帆さん、本当にありがとうございました
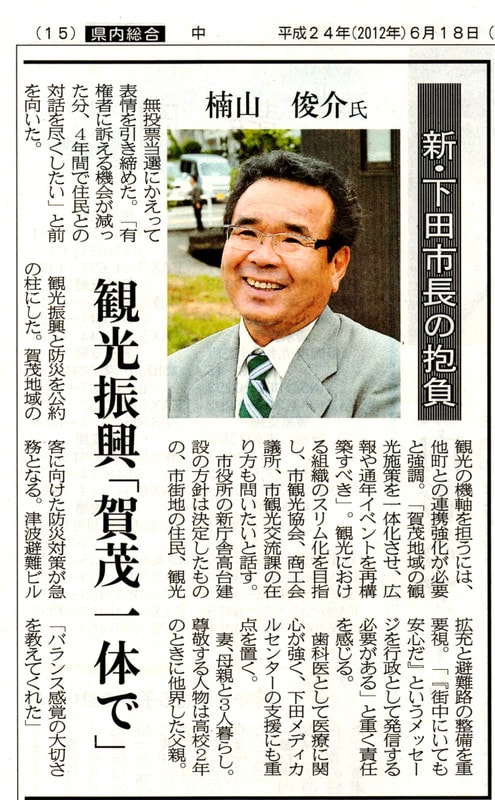














 偶然、列で一緒になった知り合いと「アップルの新機種の発売当日に、徹夜して並ぶ人の気持ちがわかるねえ」と笑い合いました。並ばなくても買えるのに並んでしまう、並ぶのがちっとも苦ではないって心理・・・ファンの性(サガ)なんですね。
偶然、列で一緒になった知り合いと「アップルの新機種の発売当日に、徹夜して並ぶ人の気持ちがわかるねえ」と笑い合いました。並ばなくても買えるのに並んでしまう、並ぶのがちっとも苦ではないって心理・・・ファンの性(サガ)なんですね。



 松崎さん、ご参加のみなさま、本当にありがとうございました。
松崎さん、ご参加のみなさま、本当にありがとうございました。