2019年5月20日に発行された日本経済新聞紙の朝刊一面に掲載された見出し「副業解禁、主要企業の5割 社員成長や新事業に期待」を拝読しました。
この記事のリードでは「働き方改革の一環として、企業が副業を解禁する動きが進んでいる。日本経済新聞社が東証1部上場などの大手企業にアンケートを実施したところ、回答を得た約120社のうちの約5割の企業が従業員に副業を認めていることが分かった」と報じています。
こう答えた大手企業側には外部の企業や個人のビジネスノウハウを吸収し、人材育成や新事業の開発につなげたいとの期待が大きいと分析しています。
ただし、日本ではこれまであまり無かった「複数の職場で働く従業員の労務管理などの課題も残る」と伝えています。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「副業解禁、主要企業の5割 社員成長や新事業に期待」と伝えています。
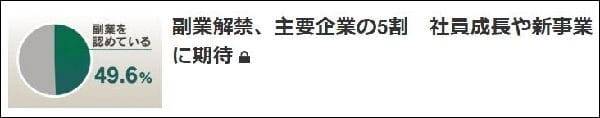
この日本の大手企業実が従業員の副業を解禁し始めた背景には、優秀な従業員は魅力ある仕事を求めて転職する方も増えています。
逆に、大手企業は不採算事業を整理する際に、従業員が転職しやすくなるという背景の事情もあります。
日本の1980年代以降の高度成長期の終身雇用制度が揺らぎ始め、実際に優秀な従業員ほど、転職する傾向が高まっています。
その半面、既存事業も市場が変化し、成長が鈍ったり、縮小するものも増えています。
こうした成熟化した事業を、従業員の副業などの複眼視点などによって、優れたリストラアイデアによる事業内容の改革もあり得ます。
一企業に終身雇用によってしがみつく時代ではないということです。
今回の主要企業による従業員の副業解禁の裏では、同じ日の別の面では、見出し「氷河期世代、職なお不安定内」という記事が載っています。
正社員になれなかったフリーターなどの方々が約90万人の方々が不安定な生活にあえいでいると報じています。
独自の職能面でのスキルを持たない方々には厳しい状況です。
政府の「働き方改革」という呼び方による変革によって、実際には終身雇用制度から実力主義に変わり始めているとも感じています。
従業員の実力を測るツールの確立が重要になります。
この点は、65歳以上の高齢者の従業員に対しても、同じことがいえます。
この記事のリードでは「働き方改革の一環として、企業が副業を解禁する動きが進んでいる。日本経済新聞社が東証1部上場などの大手企業にアンケートを実施したところ、回答を得た約120社のうちの約5割の企業が従業員に副業を認めていることが分かった」と報じています。
こう答えた大手企業側には外部の企業や個人のビジネスノウハウを吸収し、人材育成や新事業の開発につなげたいとの期待が大きいと分析しています。
ただし、日本ではこれまであまり無かった「複数の職場で働く従業員の労務管理などの課題も残る」と伝えています。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「副業解禁、主要企業の5割 社員成長や新事業に期待」と伝えています。
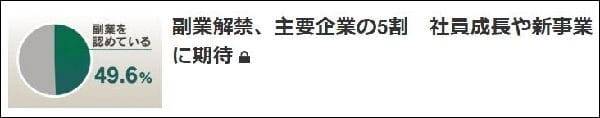
この日本の大手企業実が従業員の副業を解禁し始めた背景には、優秀な従業員は魅力ある仕事を求めて転職する方も増えています。
逆に、大手企業は不採算事業を整理する際に、従業員が転職しやすくなるという背景の事情もあります。
日本の1980年代以降の高度成長期の終身雇用制度が揺らぎ始め、実際に優秀な従業員ほど、転職する傾向が高まっています。
その半面、既存事業も市場が変化し、成長が鈍ったり、縮小するものも増えています。
こうした成熟化した事業を、従業員の副業などの複眼視点などによって、優れたリストラアイデアによる事業内容の改革もあり得ます。
一企業に終身雇用によってしがみつく時代ではないということです。
今回の主要企業による従業員の副業解禁の裏では、同じ日の別の面では、見出し「氷河期世代、職なお不安定内」という記事が載っています。
正社員になれなかったフリーターなどの方々が約90万人の方々が不安定な生活にあえいでいると報じています。
独自の職能面でのスキルを持たない方々には厳しい状況です。
政府の「働き方改革」という呼び方による変革によって、実際には終身雇用制度から実力主義に変わり始めているとも感じています。
従業員の実力を測るツールの確立が重要になります。
この点は、65歳以上の高齢者の従業員に対しても、同じことがいえます。



















