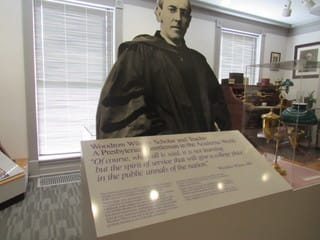数日前のこと。夜10時少し前に、
路灯ひとつない1車線のクネクネな山道を走って救急隊員訓練を終えた長男を迎えにいったさい、
がつん、ががががと、車の右側をガードレールにぶつけてしまいました。
真っ暗な路肩に止めて、
車内のライトをたよりに、ダメージを確かめます。
ガードレールはなんともないようです。
車には、3箇所ほどの凹みと横一直線に落書きしたような塗装のはがれ。

実はこの車、
先月、これまで17年間乗っていた車がとうとう動かなくなったので、
2週間ほど前に購入した新しい車(中古)。
長年、「年季の入った車」に乗っていたものですから、
ぴかぴかの車に子供たち、
「この車が、う、家のものなんて、なんだか信じられない・・・」
と夢見心地になるほど喜んでいたんですが。
この夜以来、家族みな、私の運転を心配します。
少し曲がり方が急でも、止まり方がちょっとスムーズでなくても、
後部座席や助手席から、「ママ、大丈夫?」と身を乗り出します。
それで、ふと気がつくと、
自分も何だかちょっとぎこちなくなっていて、
普段より、肩やハンドルを握る手にも力がはいっています。
それで、「ちょっと待った」、と立ち止まってみました。
こちらは、車社会。
親の仕事といえば、シッターさんを雇うなどの状況にない限り、
学校から様々なアクティビティーまで、
「送り迎え」が大きな位置をしめます。
私も、子供の数が増えるほど、職業を聞かれるならば、
思わず「運転手です」と答えたくなるほど、
ハンドルを握る毎日です。
もともと抜けているところがあるので、
これまで米国で16年近くかなりアクティブに運転してきて、
何度か、「あ、危ない」というスレスレの思いはしてきたのですが、
それでもありがたいことに事故はなく、
車にこれほどダメージをうけたのも、今回初めてのこと。
これって、
事故を起こす確率としては、
とても低いんじゃないかなと。
しかも今回は、
幅の少し広くなった買ったばかりの慣れない車で、
真っ暗闇の鹿うようよする夜の細山道を行き、
その上、寝不足気味で体調も万端ではありませんでした。
こうした「ちょっと特殊で難しい条件下」での出来事。
ということで、子どもたちと、
「1回の失敗」がどれほど周りや自分に影響を与えるか
といった話をしていました。
失敗は改善のためにあるのだからと、
まずは最大限学ぶ。
今回の事故は、
・新しい車の幅に慣れる。
・夜の山道は‘細心の注意を払う。
・体調を整えて運転
といったことを今後気を付けるようにする。
あとは、
これまでの大部分を占める「できてきたこと」を思い出していこうねと。
16年間、おかげさまで無事故でこれたことを思い返し、
「安全運転できる」と落ち着いて運転していけばいいんだよねと。
上の子たちとは、
「ネガティビティー・バイアス」の話しも。
100ポジティブでも1ネガティブだと、
その1ばかり頭から離れなくなってしまうという傾向。
(ネガティブなことに引きずられない、「ネガティビティー・バイアス」の緩和)
「フェア」に全体を眺めていきたいです。
それは、子どもの失敗に対しても、同じなんですよね。
「また失敗しやしないか!」と逐一身を乗り出すよりも、
まずは改善点を明確にする。
そのあとは、
これまでの大部分を占める「できてきたこと」について声をかけてやり、
「ほら、でもこんなにもできてきてるじゃない?」
と自信を取り戻してやる。
ぎゅっと力の入った身体を緩めてやる。
その大切さを、身をもって、
なるほどなあと体感したここ数日でした。
みなさん、安全運転でいきましょうね。良い日を!