LSA(学習支援員)養成講座は、安藤壽子先生にスタートを切っていただきました。
「学級で困っている子どもたち ~気づきの手がかり」です。
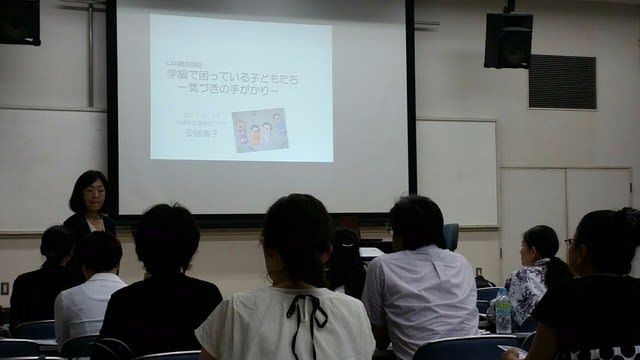
安藤先生は講義のスタートで、まず、会場の皆さんの声を聴くことから始められました。
「あなたはどういうお立場で何に困っていますか?」と・・・
学習サポーターをなさっている方は「自分が子どもにやってあげたいことと、教師や学校が求めるものの食い違い」について話されました。
支援員さんは「困っている子どもたちをほめて自信をつけてあげたい」、でも担任は「注意してやめさせてほしい、横についてできるようにしてほしい」
保護者をなさっている方は、「学校で理解してもらえず辛い思いをしてきたこと」を、当事者の方は「こんな支援があればよかったこと」を・・・。
安藤先生のお話の中で、心に残ったことがたくさんあります。その中から少し箇条書きで記してみたいと思います。
・「この子困っているな」という気づきは、子どもが好きで真剣にかかわっていると、知識がなくても感じ取れるものである。
・認知の特異性から生じている表面的な行動は、表面的な行動だけに注目して改善しようとしても難しい。
・今だけでなく、長期的なこれから先のことを考えた支援が必要。
(先生は小3になったら、そろそろ将来のことを考えましょうと話しているとか、この子の能力をできるかぎり高めていくために何をするか。「自分で考えてそれを表明する力」「理解してもらうために解説する力」「思考力」をどう育てるか )
・「様子を観察」「声に耳を傾ける」「気持ちを感じ取る」前から受け止めて後ろから支える
・脳機能からいうと前頭葉の働き(思考する・行動を抑制する・コミュニケーションする・意思決定する・情動の制御をする・記憶のコントロールをする・意識・注意を集中する・注意を分散するなど)が弱い子どもたちが多いが、それよりの大事なののは、その奥にある「生きたい!」「おもしろい!」「認められたい!」「達成感を味わいたい!」「充実したい!」という思い。このモチベーションをどう上げていくか?!
・先生だって支援が必要。
・支援員はつなぐ存在・・・子ども同士をつなぐ・子どもと先生をつなぐ・ときには保護者と先生も)
何に困っているのか
何が苦手なのか(嫌いなのか)
何が得意なのか(好きなのか)
なぜそうするのか(特性? 環境?)
伝えたいメッセージは何か(シグナル)
・「何ができないか」ではなく、「何ができるか」「どうすればできるか(同条件を変えればできるか)」を考えて支援していくことがたいせつ。

★
学級の中で困っている子どもたちは、実際には
読みや書きがたどたどしかったり、
不器用で運動会のダンスの振付をまちがってしまったり、
姿勢が悪かったり、
コミュニケーションが苦手で手が出てしまったり、
感覚過敏でうるさい声に耐えられなかったり、
給食が食べられなかったり・・・
でも、これらの困っていることは問題行動と思われて、それを正そう、なくそうと知られがちです。
支援員さんは 本当に黒子でありながら、重要な役割を担っていることを考えさせられました。
「学級で困っている子どもたち ~気づきの手がかり」です。
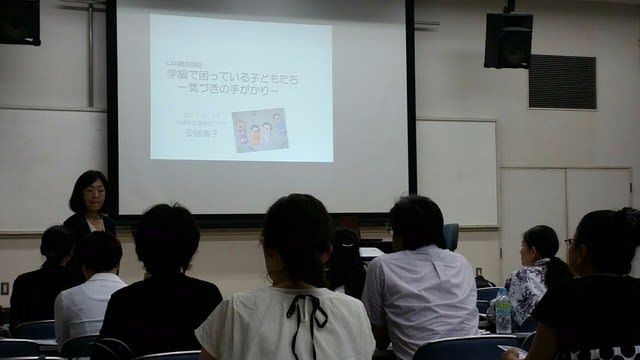
安藤先生は講義のスタートで、まず、会場の皆さんの声を聴くことから始められました。
「あなたはどういうお立場で何に困っていますか?」と・・・
学習サポーターをなさっている方は「自分が子どもにやってあげたいことと、教師や学校が求めるものの食い違い」について話されました。
支援員さんは「困っている子どもたちをほめて自信をつけてあげたい」、でも担任は「注意してやめさせてほしい、横についてできるようにしてほしい」
保護者をなさっている方は、「学校で理解してもらえず辛い思いをしてきたこと」を、当事者の方は「こんな支援があればよかったこと」を・・・。
安藤先生のお話の中で、心に残ったことがたくさんあります。その中から少し箇条書きで記してみたいと思います。
・「この子困っているな」という気づきは、子どもが好きで真剣にかかわっていると、知識がなくても感じ取れるものである。
・認知の特異性から生じている表面的な行動は、表面的な行動だけに注目して改善しようとしても難しい。
・今だけでなく、長期的なこれから先のことを考えた支援が必要。
(先生は小3になったら、そろそろ将来のことを考えましょうと話しているとか、この子の能力をできるかぎり高めていくために何をするか。「自分で考えてそれを表明する力」「理解してもらうために解説する力」「思考力」をどう育てるか )
・「様子を観察」「声に耳を傾ける」「気持ちを感じ取る」前から受け止めて後ろから支える
・脳機能からいうと前頭葉の働き(思考する・行動を抑制する・コミュニケーションする・意思決定する・情動の制御をする・記憶のコントロールをする・意識・注意を集中する・注意を分散するなど)が弱い子どもたちが多いが、それよりの大事なののは、その奥にある「生きたい!」「おもしろい!」「認められたい!」「達成感を味わいたい!」「充実したい!」という思い。このモチベーションをどう上げていくか?!
・先生だって支援が必要。
・支援員はつなぐ存在・・・子ども同士をつなぐ・子どもと先生をつなぐ・ときには保護者と先生も)
何に困っているのか
何が苦手なのか(嫌いなのか)
何が得意なのか(好きなのか)
なぜそうするのか(特性? 環境?)
伝えたいメッセージは何か(シグナル)
・「何ができないか」ではなく、「何ができるか」「どうすればできるか(同条件を変えればできるか)」を考えて支援していくことがたいせつ。

★
学級の中で困っている子どもたちは、実際には
読みや書きがたどたどしかったり、
不器用で運動会のダンスの振付をまちがってしまったり、
姿勢が悪かったり、
コミュニケーションが苦手で手が出てしまったり、
感覚過敏でうるさい声に耐えられなかったり、
給食が食べられなかったり・・・
でも、これらの困っていることは問題行動と思われて、それを正そう、なくそうと知られがちです。
支援員さんは 本当に黒子でありながら、重要な役割を担っていることを考えさせられました。



















