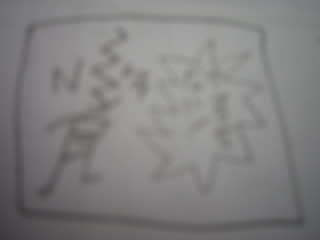~LIVE・ライブ 「PALETTE ~十人十色~ 」のお知らせです~
 星槎国際高等学校立川学習センターでは、
星槎国際高等学校立川学習センターでは、「様々な活躍の機会ときっかけをを子どもたちのために」
というテーマの一環として、
「ブラストビート(会社運営体験プログラム)」
に挑戦しました。
 ブラストビートとは・・・
ブラストビートとは・・・国際的な高校・大学生向けの社会起業体験プログラム
今回は実際に模擬的な会社組織を作り、音楽ライブ(ロックコンサート)を
催行します。
 基本その全てを生徒が行います。
基本その全てを生徒が行います。 運営については、準備段階からNPOブラストビートのスタッフが
運営については、準備段階からNPOブラストビートのスタッフが指導や相談に関わります。
立川学習センターの生徒が社長となって臨んだライブ企画運営会社名は
 「Colors(カラーズ)」
「Colors(カラーズ)」












***星槎国際高等学校(立川学習センター)3年生、
Colors (カラーズ)社長から***
はじめまして、ブラストビート Colors 社長です。
僕はこの活動を始めてから、人とのつながりを感じられるようになりました。
それくらい僕らがこのライブに向けて走ってきた8ヶ月間は密度の濃いものでした。
もちろん、
僕ら高校生にとっては初めての連続で折れそうにもなったりもしたんですけど、
その度に先生方や周りの人たちに助けてもらい、「自分はひとりじゃない」と感じ、
それと同時に
自分に今までなかったような感謝の気持ちや責任感も少しずつ芽生えました。
こういう機会を与えて下さったからには、
来てくださった皆さんに「良かった」と言ってもらえるような
悔いの残らないライブをお届けしたいと思います。
ぜひ足を運んでいただき、
十人十色な僕らがひとつになって作り上げた
"PALETTE"をお楽しみください!






日時:7月30日(金)18:00~20:00(予定) 開場17:30
場所:国立リバプール 東京都国立市中1-17-27関口ビル B1
JR中央線国立駅南口下車大学通り徒歩3
http://www7.plala.or.jp/LIVERPOOL/
価格:高校生以下 前売1,300円 当日1,800円
大 人 前売1,800円 当日2,300円
小学生未満 無料
別途、ドリンク代(200円)頂戴します

 高校生によるミニ音楽会社 「Colors」とは?
高校生によるミニ音楽会社 「Colors」とは?
ブラストビートを日本に導入するにあたり、パイロットプログラムとして
初めて設立された高校生によるミニ音楽会社です。
「Colors」という社名の由来は、「ライブはいろんな色があってこそできる。」
という想いから付けられました。
「一人ひとり、悩みも、考え方も、笑顔も違う。
だからこそ、お互いのColorを混ぜずに重ねることで、
エンターテイメントという虹を描いていく」
というのを掲げ、資金ゼロ・経験ゼロ・おまけに人間関係も一からというところ
から会社設立からアーティスト探し、ライブ企画運営を行っています。
「Colors」ブログ、はコチラ
 ライブタイトル「PALETTE」とは?
ライブタイトル「PALETTE」とは?
これは一人ひとり違う色を「PALETTE」に持ち寄れば、
どんな絵も描けるという想いから付けられました。
 寄付について
寄付について
ブラストビートでは収益の25%以上を慈善事業団体に寄付することになっていて、
僕らはみんなで持ち寄った10個の候補の中から「アグラサーラ協力基金」に
寄付しようということになった。
この「アグラサーラ」には学校の先生が関わっているのもあり、
いろんな話を聞く機会に恵まれ、そういった話を聞く中で、
僕たちは今、日本という国で、どれだけ恵まれた環境にいるかを知り、
国は違えども同じ"今"を生きているバングラデシュの子どもたちの未来に
少しでも光が見える手助けになれば、と思い寄付しようと決めました。

皆様のお越しを心よりお待ちしています