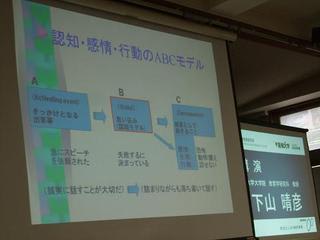星槎教育研究所主催 2011『不登校・ひきこもりへの理解と対応(青年期・成人期)』を立川アイムホールをメイン会場として、
北海道から九州まで、全国17か所をTV会議システムで結んでお送りしました。
年明けでお忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。
★
今回のセミナーは
第1部:近藤直司先生による講演
『青年期の社会的ひきこもり~対応と予防のために~』



・ひきこもり問題の背景
・精神医学的背景
・支援方法 等
社会的ひきこもりの背景にある問題、ケースに基づく特徴・支援方法など具体的にお話していただきました。
第2部:梅永雄二先生による講演
『社会的ひきこもりからの就労~発達障害のある人の自立』




↑帯広会場の就労支援員とTV会議システムを用いた双方向のやり取りの様子
・発達障害のある人の離職理由
・発達障害者のライフスキル
・就労支援 等
ひきこもりから就労に成功した事例なども交えて具体的にお話していただきました。
一部ですが、受講者の感想を紹介します。
★
【第1部感想】
■ひきこもり要因と対応の関係が良くわかりました。ありがとうございました。(元教員)
■今後の対応について考え直す良い機会となった。また、学童期の不登校児童との関わりの上で「今できること」「しなければならないこと」を常に考えていきたいと思っている。(保育士)
■ひきこもりと障害との関係がよくわかりました。本日教えていただいた様々なことを、今後の仕事に実践の場で試し生かしていきたいと思います。(高校教員)
■ひきこもりについて、学んだことがなかったので、初めてこのような会に参加して学ぶことができて良かったです。ひきこもりの中には背景に発達障害があることを知れて良かったです。(中高教員)
■成因論から対応・予防まで総論を聞くことができて良かったが、時間があれば各論を聞きたかった。特に、本人や保護者の相談例や対応例について。(中高教員)
■具体的な相談の経験に基づいた話が聞けて良かった。(中学教員)
■まだ、社会的にひきこもりの主因の一つである発達障害に対する理解がないということがよくわかった。今後さらに周知を徹底していく必要がある。(高校教員)
■広汎性発達障害とひきこもりにこんなにも関連があることに驚きました。(中高教員)
■分かりやすい講演でした。私が勤務している学校でも、不登校の生徒がいます。対人関係による恐怖のためです。少しでも問題を解決していくためには、丁寧にコツコツと積み重ねていき、ご両親と学校の信頼関係を築きあげていきたいと思います。(特別支援学校支援員)
■予防が出来るなら・・・どんな人間でもまず、その人を理解しようと努力する姿勢が大事だと思います。人間として生まれたら、社会とかかわらないで生きるのは難しい。どんな形であっても社会と関わっていけるのがBest!なのだと思います。(支援員)
■就労をベースに支援をしているため、医療の視点から幅広いお話を聞けて大変勉強になりました。(支援員)
■質疑応答の時間に出ていた「関係機関につなげる」の難しさを感じています。親も本人も受け入れられないけれど、生活、就労について不安を持っている人に対する支援の部分をもう少し詳しく聞きたかったです。第1群~3群の分けは分かりやすかったです。(カウンセラー・支援員)
■根気強く、丁寧に一つ一つ積み重ねていくことが大切であると実感しました。同時に支援体制を固めること、関係機関との連携を取ることの重要性と難しさも感じました。一人ひとりの事例にケースバイケースで対応、支援しながらいかに全体としての支援体制を強化していくかが課題であると思いました。(就労支援員)
■ひきこもりの要因や支援についての基本について非常に理解しやすい内容でした。対応よりも、今後は予防が重要であるとともに、現在私たちが行なっている支援のほかに、家族支援のノウハウを作っていくことが大切なように感じました。(支援員)
■たくさん事例と経験、知識も豊かで視野も広く素晴らしい内容でした。HSPという概念があればと感じました。(医師)
■とても理解しやすく勉強になりました。どうもありがとうございました。(医療職)
■すぐに薬物療法をすすめるのが精神科医だと思っていたので、薬物療法以外の対象の人が3分の2もいるという事実と、そのことを知っている精神科医がいることに少し安心しました。(相談員)
■非常によかったです。仕事をしている身には深い講義でした。(支援員)
■現在、まだまだ未開の土地で開拓しているようなひきこもりの対応だということに驚きを感じました。不登校になる子がわが子の周りでもどんどん増えて、学級でも当たり前に思っている状況が社会にもつながるとはかなり深刻な問題だと思います。見過ごしてはいけませんね。(支援員)
■ひきこもりはやり方により、復帰できることがわかった。(支援員)
■ガイドラインの存在を知ることが出来たのが大きな収穫となりました。予想はしていましたが、原因が複雑でそのために対応も複雑だとわかりました。(塾講師)
■広汎性発達障害とパーソナリティ障害のことがよくわかりました。途中で関係が切れてしまう(来なくなる)ことが非常に残念です。無力感がありました。支援や相談窓口を知らない人が多いと思うので、もっと敷居の低い窓口がもっと皆に知られるようになれば良いなと感じました。(塾経営者)
■かなり詳細なケース等と治療援助方針を3群に分けて説明していただき理解しやすい講習でした。(保護者・カウンセラー)
■目立たない広汎性発達障害についての詳しい話はなかなか聞けないので良かったです。精神科医でもわからない場合がかなりあると思われます。「発達障害ではありません」といわれて、では、この状態はどういうことになるか、そこまで家族のケアが大切だと思います。(不明)
■本人が障害を受け入れてくれると少しずつ変わっていくような気がしました。バランスをよく見て親として支援していこうと思います。もっと早く障害を知っていればと思いますが、わかったことをよしと思ってやっていきます。セミナーを受けてとてもよかったです。(保護者)
■発達障害のことが少し理解できた気がします。ありがとうございました。(保護者)
■早期に発達障害を見逃さず、その人に合った適切な支援・環境整備が重要だと思う。(会社員)
■「早期発見、適切な対応を小さな時から」「社会の発達障害への理解」「良いネットワーク」「気長に」対応で大切なこととして学びました。(保護者・支援員)
■最後に近藤先生の告知に関するお話に感動しました。(保護者)
★
【第2部感想】
■ライフスキルの話はとてもよかった。良い考え方を知りました。もっともっと広く知らせたい考え方だと思いました。(小学校教員)
■ASの手帳の活用については感動しました。(元教員)
■仕事上は、児童期までの子どもたちの関わりだけであり、青年期、成人期の支援などについては、法制上の事など、全く知らないと言って良い状況である。梅永先生のわかりやすいお話で少し知ることができた。これからも、発達障害児者のとぎれない支援などについて機会があれば学んでいきたい。(保育士)
■なかなか厳しい道のりであると思いました。高校で仕事をしていますので、就労の最前線にいるわけですが、教えていただいたことを生かして何とか子どもたちのために道を切り開いていきたいと思いました。(高校教員)
■様々な事例を聞けて良かったです。今回の講話を受けて、どのような支援がよいのか自分でも考えていきたいと思いました。また、このような就労支援をもっと保護者にも伝えていきたいと思いました。(中高教員)
■SSTすらまだ広まっていない状況の現実の中で、ライフスキルの考え方も同時に広めていく必要性と痛感した。と同時に、各自の障害特性と状況に応じて、求められるスキルは違うこと、オーダーメイドの支援が必要であることを理解すべきだと感じた。東京には様々な社会資源があるが、アセスメントや適切で有効的な支援ができていないと思う。(中高教員)
■就労の観点から発達障害を考えさせられ、学校教育でのカリキュラムを見直す良いきっかけになると思う。(中学教員)
■第一にライフスキルを身につけることが対人関係スキルに先立って重要であるということがわかった。第二に注意深い観察に基づいたアセスメントをもって、支援の方法を明確化しなければならないと感じた。(高校教員)
■就職支援体制について良くわからなかったので、今回知ることができて良かった。(中高教員)
■とてもわかりやすい講演でした。勉強でもそうですが、目標を持たせることが大事なんだなぁと思いました。とても勉強になりました。ありがとうございました。(特別支援学校支援員)
■何回か大人の発達障害テーマの講演を聞き、「困っているのは自分だけじゃない」と元気になれる反面、(日常で理解されない)社会はまだまだ生きにくいなあ・・・と。(支援員)
■個々に合わせた職務のマッチングや職場ごとの工夫の事例など大変勉強になりました。(支援員)
■ソーシャルスキルよりもライフスキルという考え方は、いいなと思いましたし、できないことは支援を受けていいというのも今後に生かしていきたいです。事例もとても参考になりました。(カウンセラー・支援員)
■環境整備と周囲の理解が発達障害のある方の自立や就労において一番配慮すべき点であることがわかりました。本人を変えるのではなく、環境を変える、環境に働きかけるという先生のお言葉が印象に残りました。(就労支援員)
■発達障害を持つ方々の就労について、仕事に就き生活をしていく上で必要となるスキルと旧来言われているようなSSTとの間の差異があり、まさに実践的なスキルであると感じました。発達障害者の就労支援に向けた、企業への働きかけなどを支援していく必要性を感じました。(支援員)
■就労支援についての新たな知識や考え方を学べました。大人のLDの問題を取り上げてくれたのが良かったと思います。DVDを購入し、皆と一緒に再度見たいと思います。(医師)
■SSTについてのお考えやライフスキルについての内容がためになりました。(医療職)
■とてもわかりやすかったです。いろいろな事業所があって、いろいろな雇用の仕方があるのでよくわからなくなっていたけれど、情報が整理されていてよかったです。(相談員)
■就労に特化した興味深い情報でした。(支援員)
■非常に面白かったです。もっと時間をかけて聞きたかったです。(相談員)
■就労にとどまらず、発達障害の人への支援の心構えをいろいろ知ることができました。できないことはできるようにすると考えていましたが、できないことはできないことと受け入れて、どう支援するかを考える。液体と固体との例えが目からうろこでした。発達障害があっても個性として受け入れられる職場が普通になってほしいです。(支援員)
■正しい支援をすれば、満足できる就労が可能であることがわかった。(支援員)
■ひきこもりについて大変理解が深まりました。今後の就労支援に役立てたいと思います。(支援員)
■環境次第で発達障害もかなり薄まるということがわかりとても勉強になりました。結局は「人」が鍵なんですね。(塾講師)
■自閉症スペクトラムの勉強中です。自閉症の人たちの支援にさらに興味をもちました。(塾経営者)
■ハードスキルとソフトスキルの講義は「目からうろこ」でした。「100人の友達より1人での自立」という言葉が印象に残りました。DVD鑑賞もできて良かったです。(保護者・カウンセラー)
■企業説得をすることはとても大事だと思う。又、こういう仕事ができそうですと、特徴等を企業に伝えることの大事さを感じています。(保護者)
■精神障害者手帳を取得するのは、なかなか勇気がいることで、本人自身が納得するまで時間がかかるんだろうと想像します。(不明)
■受講して大変良かったです。お話を聞いて、とても勇気が出ましたし、親として出来ることをしっかりやっていこうと思います。本当にありがとうございました。(保護者)
■企業に発達障害とは、どういうものかわかってもらうことが大切だと思う。目標設定の時は、その人の得意分野・好きなことを知った上で設定すると良いと思う。(会社員)
■たらいまわしにしない!そのためのネットワーク理解の共有が大切ですね。(保護者・支援員)
■雑談も入って楽しいお話でした。発達障害でも生きていけると少し希望が見えた気がします。(保護者)
★
昼休憩に
学習障害の「ディスレクシア(難読症)」と取り上げた映画ドキュメンタリー映画
『DXば日々--美(び)んちゃんの場合』(谷光章監督)の予告を上映しました。
発達障害のひとつ「ディスレクシア」を抱えて大人になった一人の女性の生きづらさ・困難さを日常生活を通して描いています。障害をユニークな個性としてとらえ、明るく前向きに生きる彼女の姿を通して、
障害とは何か?
教育とは何か?
生きるとは何か?
について考えるきっかけになればと思います。このブログでも紹介していますので、詳しくはこちらをご覧ください。
全3回シリーズのセミナーが今回で無事終了しました。多くの方にご参加いただき、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
北海道から九州まで、全国17か所をTV会議システムで結んでお送りしました。
年明けでお忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。
★
今回のセミナーは
第1部:近藤直司先生による講演
『青年期の社会的ひきこもり~対応と予防のために~』



・ひきこもり問題の背景
・精神医学的背景
・支援方法 等
社会的ひきこもりの背景にある問題、ケースに基づく特徴・支援方法など具体的にお話していただきました。
第2部:梅永雄二先生による講演
『社会的ひきこもりからの就労~発達障害のある人の自立』




↑帯広会場の就労支援員とTV会議システムを用いた双方向のやり取りの様子
・発達障害のある人の離職理由
・発達障害者のライフスキル
・就労支援 等
ひきこもりから就労に成功した事例なども交えて具体的にお話していただきました。
一部ですが、受講者の感想を紹介します。
★
【第1部感想】
■ひきこもり要因と対応の関係が良くわかりました。ありがとうございました。(元教員)
■今後の対応について考え直す良い機会となった。また、学童期の不登校児童との関わりの上で「今できること」「しなければならないこと」を常に考えていきたいと思っている。(保育士)
■ひきこもりと障害との関係がよくわかりました。本日教えていただいた様々なことを、今後の仕事に実践の場で試し生かしていきたいと思います。(高校教員)
■ひきこもりについて、学んだことがなかったので、初めてこのような会に参加して学ぶことができて良かったです。ひきこもりの中には背景に発達障害があることを知れて良かったです。(中高教員)
■成因論から対応・予防まで総論を聞くことができて良かったが、時間があれば各論を聞きたかった。特に、本人や保護者の相談例や対応例について。(中高教員)
■具体的な相談の経験に基づいた話が聞けて良かった。(中学教員)
■まだ、社会的にひきこもりの主因の一つである発達障害に対する理解がないということがよくわかった。今後さらに周知を徹底していく必要がある。(高校教員)
■広汎性発達障害とひきこもりにこんなにも関連があることに驚きました。(中高教員)
■分かりやすい講演でした。私が勤務している学校でも、不登校の生徒がいます。対人関係による恐怖のためです。少しでも問題を解決していくためには、丁寧にコツコツと積み重ねていき、ご両親と学校の信頼関係を築きあげていきたいと思います。(特別支援学校支援員)
■予防が出来るなら・・・どんな人間でもまず、その人を理解しようと努力する姿勢が大事だと思います。人間として生まれたら、社会とかかわらないで生きるのは難しい。どんな形であっても社会と関わっていけるのがBest!なのだと思います。(支援員)
■就労をベースに支援をしているため、医療の視点から幅広いお話を聞けて大変勉強になりました。(支援員)
■質疑応答の時間に出ていた「関係機関につなげる」の難しさを感じています。親も本人も受け入れられないけれど、生活、就労について不安を持っている人に対する支援の部分をもう少し詳しく聞きたかったです。第1群~3群の分けは分かりやすかったです。(カウンセラー・支援員)
■根気強く、丁寧に一つ一つ積み重ねていくことが大切であると実感しました。同時に支援体制を固めること、関係機関との連携を取ることの重要性と難しさも感じました。一人ひとりの事例にケースバイケースで対応、支援しながらいかに全体としての支援体制を強化していくかが課題であると思いました。(就労支援員)
■ひきこもりの要因や支援についての基本について非常に理解しやすい内容でした。対応よりも、今後は予防が重要であるとともに、現在私たちが行なっている支援のほかに、家族支援のノウハウを作っていくことが大切なように感じました。(支援員)
■たくさん事例と経験、知識も豊かで視野も広く素晴らしい内容でした。HSPという概念があればと感じました。(医師)
■とても理解しやすく勉強になりました。どうもありがとうございました。(医療職)
■すぐに薬物療法をすすめるのが精神科医だと思っていたので、薬物療法以外の対象の人が3分の2もいるという事実と、そのことを知っている精神科医がいることに少し安心しました。(相談員)
■非常によかったです。仕事をしている身には深い講義でした。(支援員)
■現在、まだまだ未開の土地で開拓しているようなひきこもりの対応だということに驚きを感じました。不登校になる子がわが子の周りでもどんどん増えて、学級でも当たり前に思っている状況が社会にもつながるとはかなり深刻な問題だと思います。見過ごしてはいけませんね。(支援員)
■ひきこもりはやり方により、復帰できることがわかった。(支援員)
■ガイドラインの存在を知ることが出来たのが大きな収穫となりました。予想はしていましたが、原因が複雑でそのために対応も複雑だとわかりました。(塾講師)
■広汎性発達障害とパーソナリティ障害のことがよくわかりました。途中で関係が切れてしまう(来なくなる)ことが非常に残念です。無力感がありました。支援や相談窓口を知らない人が多いと思うので、もっと敷居の低い窓口がもっと皆に知られるようになれば良いなと感じました。(塾経営者)
■かなり詳細なケース等と治療援助方針を3群に分けて説明していただき理解しやすい講習でした。(保護者・カウンセラー)
■目立たない広汎性発達障害についての詳しい話はなかなか聞けないので良かったです。精神科医でもわからない場合がかなりあると思われます。「発達障害ではありません」といわれて、では、この状態はどういうことになるか、そこまで家族のケアが大切だと思います。(不明)
■本人が障害を受け入れてくれると少しずつ変わっていくような気がしました。バランスをよく見て親として支援していこうと思います。もっと早く障害を知っていればと思いますが、わかったことをよしと思ってやっていきます。セミナーを受けてとてもよかったです。(保護者)
■発達障害のことが少し理解できた気がします。ありがとうございました。(保護者)
■早期に発達障害を見逃さず、その人に合った適切な支援・環境整備が重要だと思う。(会社員)
■「早期発見、適切な対応を小さな時から」「社会の発達障害への理解」「良いネットワーク」「気長に」対応で大切なこととして学びました。(保護者・支援員)
■最後に近藤先生の告知に関するお話に感動しました。(保護者)
★
【第2部感想】
■ライフスキルの話はとてもよかった。良い考え方を知りました。もっともっと広く知らせたい考え方だと思いました。(小学校教員)
■ASの手帳の活用については感動しました。(元教員)
■仕事上は、児童期までの子どもたちの関わりだけであり、青年期、成人期の支援などについては、法制上の事など、全く知らないと言って良い状況である。梅永先生のわかりやすいお話で少し知ることができた。これからも、発達障害児者のとぎれない支援などについて機会があれば学んでいきたい。(保育士)
■なかなか厳しい道のりであると思いました。高校で仕事をしていますので、就労の最前線にいるわけですが、教えていただいたことを生かして何とか子どもたちのために道を切り開いていきたいと思いました。(高校教員)
■様々な事例を聞けて良かったです。今回の講話を受けて、どのような支援がよいのか自分でも考えていきたいと思いました。また、このような就労支援をもっと保護者にも伝えていきたいと思いました。(中高教員)
■SSTすらまだ広まっていない状況の現実の中で、ライフスキルの考え方も同時に広めていく必要性と痛感した。と同時に、各自の障害特性と状況に応じて、求められるスキルは違うこと、オーダーメイドの支援が必要であることを理解すべきだと感じた。東京には様々な社会資源があるが、アセスメントや適切で有効的な支援ができていないと思う。(中高教員)
■就労の観点から発達障害を考えさせられ、学校教育でのカリキュラムを見直す良いきっかけになると思う。(中学教員)
■第一にライフスキルを身につけることが対人関係スキルに先立って重要であるということがわかった。第二に注意深い観察に基づいたアセスメントをもって、支援の方法を明確化しなければならないと感じた。(高校教員)
■就職支援体制について良くわからなかったので、今回知ることができて良かった。(中高教員)
■とてもわかりやすい講演でした。勉強でもそうですが、目標を持たせることが大事なんだなぁと思いました。とても勉強になりました。ありがとうございました。(特別支援学校支援員)
■何回か大人の発達障害テーマの講演を聞き、「困っているのは自分だけじゃない」と元気になれる反面、(日常で理解されない)社会はまだまだ生きにくいなあ・・・と。(支援員)
■個々に合わせた職務のマッチングや職場ごとの工夫の事例など大変勉強になりました。(支援員)
■ソーシャルスキルよりもライフスキルという考え方は、いいなと思いましたし、できないことは支援を受けていいというのも今後に生かしていきたいです。事例もとても参考になりました。(カウンセラー・支援員)
■環境整備と周囲の理解が発達障害のある方の自立や就労において一番配慮すべき点であることがわかりました。本人を変えるのではなく、環境を変える、環境に働きかけるという先生のお言葉が印象に残りました。(就労支援員)
■発達障害を持つ方々の就労について、仕事に就き生活をしていく上で必要となるスキルと旧来言われているようなSSTとの間の差異があり、まさに実践的なスキルであると感じました。発達障害者の就労支援に向けた、企業への働きかけなどを支援していく必要性を感じました。(支援員)
■就労支援についての新たな知識や考え方を学べました。大人のLDの問題を取り上げてくれたのが良かったと思います。DVDを購入し、皆と一緒に再度見たいと思います。(医師)
■SSTについてのお考えやライフスキルについての内容がためになりました。(医療職)
■とてもわかりやすかったです。いろいろな事業所があって、いろいろな雇用の仕方があるのでよくわからなくなっていたけれど、情報が整理されていてよかったです。(相談員)
■就労に特化した興味深い情報でした。(支援員)
■非常に面白かったです。もっと時間をかけて聞きたかったです。(相談員)
■就労にとどまらず、発達障害の人への支援の心構えをいろいろ知ることができました。できないことはできるようにすると考えていましたが、できないことはできないことと受け入れて、どう支援するかを考える。液体と固体との例えが目からうろこでした。発達障害があっても個性として受け入れられる職場が普通になってほしいです。(支援員)
■正しい支援をすれば、満足できる就労が可能であることがわかった。(支援員)
■ひきこもりについて大変理解が深まりました。今後の就労支援に役立てたいと思います。(支援員)
■環境次第で発達障害もかなり薄まるということがわかりとても勉強になりました。結局は「人」が鍵なんですね。(塾講師)
■自閉症スペクトラムの勉強中です。自閉症の人たちの支援にさらに興味をもちました。(塾経営者)
■ハードスキルとソフトスキルの講義は「目からうろこ」でした。「100人の友達より1人での自立」という言葉が印象に残りました。DVD鑑賞もできて良かったです。(保護者・カウンセラー)
■企業説得をすることはとても大事だと思う。又、こういう仕事ができそうですと、特徴等を企業に伝えることの大事さを感じています。(保護者)
■精神障害者手帳を取得するのは、なかなか勇気がいることで、本人自身が納得するまで時間がかかるんだろうと想像します。(不明)
■受講して大変良かったです。お話を聞いて、とても勇気が出ましたし、親として出来ることをしっかりやっていこうと思います。本当にありがとうございました。(保護者)
■企業に発達障害とは、どういうものかわかってもらうことが大切だと思う。目標設定の時は、その人の得意分野・好きなことを知った上で設定すると良いと思う。(会社員)
■たらいまわしにしない!そのためのネットワーク理解の共有が大切ですね。(保護者・支援員)
■雑談も入って楽しいお話でした。発達障害でも生きていけると少し希望が見えた気がします。(保護者)
★
昼休憩に
学習障害の「ディスレクシア(難読症)」と取り上げた映画ドキュメンタリー映画
『DXば日々--美(び)んちゃんの場合』(谷光章監督)の予告を上映しました。
発達障害のひとつ「ディスレクシア」を抱えて大人になった一人の女性の生きづらさ・困難さを日常生活を通して描いています。障害をユニークな個性としてとらえ、明るく前向きに生きる彼女の姿を通して、
障害とは何か?
教育とは何か?
生きるとは何か?
について考えるきっかけになればと思います。このブログでも紹介していますので、詳しくはこちらをご覧ください。
全3回シリーズのセミナーが今回で無事終了しました。多くの方にご参加いただき、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。









































 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・