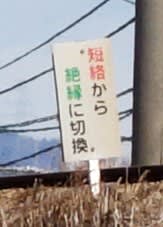JRの線路脇や電柱に設置された標識について、書いてみました。一昨日に採り上げた「撮り鉄」をした周辺で撮った、線路標識です。
昨日、これらについて書こうとしていたのですが、この分野は詳しくないので、まとめることが出来ませんでした。結局、調べてわからないところはそのままにして、書きかけ記事のようになりました。
「速度制限標識」です。左の写真は、60km/h以下で走行すること。中は、左角上下が黒いので、左方向へ進む場合は45km/h以下で走行 (分岐制限) という意味で、まっすぐは無視できます。右は、R=500のRは円の半径(曲線半径)のことで、この先は半径500mの長さのカーブなので、80km/h以下で、となります。



「気笛吹鳴標識」です。「×」印で、警笛を鳴らす必要がある場所に、設置されます。

「信号喚呼(かんこ)位置標」です。黄色い三角形(黒い丸の中に書かれている)で、前方の信号機の表示を (声を出して) 確認する位置を示すものです。


表示は、場内信号機の場合は「場」、出発信号機の場合は「出」、中継信号機の場合は「中」、遠方信号機の場合は「遠」、閉塞信号機の場合は、中に閉塞番号が書かれている、とのことです。


「電車線区分標」 エアセクションを設置した位置を示しています。エアセクションは、「ここから」の表示です。


エアセクションとは、電車を走らすには架線 (トロリ線) が必要で、多くの列車を走らす線区は、何区間かに分けて架線を繋ぎ、(数kmごとにある) 変電所から電気を送電して対応しています。変電所が変わるごとに、2つの架線がオーバーラップさせて (数mほど?) 設置している場所を、言っています。
(車両がセクション内で止まると、両方の架線とパンタグラフが接触する「短絡」の状態になり、断線したりしますので、原則として停車してはならない、ことになっています)
「エアセクションゾーン標・クリア標」 エアセクションの通過を確認するための標識です。
黄色地に赤の横線の下に×は、エアセクションは「ここまで」の表示です。

そのあとに続く、エアセクションゾーン標は、2,4,6,8,10,12まであるようですが、〇もあって、これが最終? なのでしょう。



「短絡から絶縁に切換」の標識です。 エアセクションに入りますので、パンタグラフによって短絡してしまわないように絶縁にするように、と運転士に向けたものと思われますが。(パンタグラフからの配線をオフにするのか? 普通に走行していれば、問題はないと思うのですが? 保線作業用車両に向けたものなのかも) このへんのところは、よくわかりません。
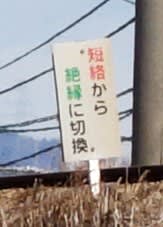
昨日、これらについて書こうとしていたのですが、この分野は詳しくないので、まとめることが出来ませんでした。結局、調べてわからないところはそのままにして、書きかけ記事のようになりました。
「速度制限標識」です。左の写真は、60km/h以下で走行すること。中は、左角上下が黒いので、左方向へ進む場合は45km/h以下で走行 (分岐制限) という意味で、まっすぐは無視できます。右は、R=500のRは円の半径(曲線半径)のことで、この先は半径500mの長さのカーブなので、80km/h以下で、となります。



「気笛吹鳴標識」です。「×」印で、警笛を鳴らす必要がある場所に、設置されます。

「信号喚呼(かんこ)位置標」です。黄色い三角形(黒い丸の中に書かれている)で、前方の信号機の表示を (声を出して) 確認する位置を示すものです。


表示は、場内信号機の場合は「場」、出発信号機の場合は「出」、中継信号機の場合は「中」、遠方信号機の場合は「遠」、閉塞信号機の場合は、中に閉塞番号が書かれている、とのことです。


「電車線区分標」 エアセクションを設置した位置を示しています。エアセクションは、「ここから」の表示です。


エアセクションとは、電車を走らすには架線 (トロリ線) が必要で、多くの列車を走らす線区は、何区間かに分けて架線を繋ぎ、(数kmごとにある) 変電所から電気を送電して対応しています。変電所が変わるごとに、2つの架線がオーバーラップさせて (数mほど?) 設置している場所を、言っています。
(車両がセクション内で止まると、両方の架線とパンタグラフが接触する「短絡」の状態になり、断線したりしますので、原則として停車してはならない、ことになっています)
「エアセクションゾーン標・クリア標」 エアセクションの通過を確認するための標識です。
黄色地に赤の横線の下に×は、エアセクションは「ここまで」の表示です。

そのあとに続く、エアセクションゾーン標は、2,4,6,8,10,12まであるようですが、〇もあって、これが最終? なのでしょう。



「短絡から絶縁に切換」の標識です。 エアセクションに入りますので、パンタグラフによって短絡してしまわないように絶縁にするように、と運転士に向けたものと思われますが。(パンタグラフからの配線をオフにするのか? 普通に走行していれば、問題はないと思うのですが? 保線作業用車両に向けたものなのかも) このへんのところは、よくわかりません。