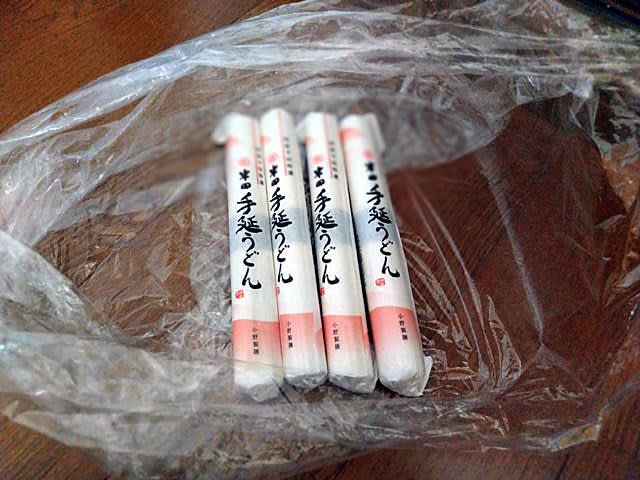近所の道の駅に立ち寄ったら、珍しくポポーが売られていた。
3年ぶりの出会いなので迷わず購入。

ポポーは熟すと2~3日で黒っぽく変色し、いかにも「傷んでいる」という姿になってしまう。
だから、普通の流通ルートに乗せられることがなく、幻のフルーツと呼ばれている。
生産者が直接持ち込む農産物直売所では、今日のようにポポーの出品に出会うことがある。
知られた果物ではないし、見た目が悪い上にすぐに黒ずんで傷んだようになるから、売れ残る可能性も高いと思う。
過去に3回、道の駅の直売所で買っているが、どれも1パックだけの在庫だった。
写真のポポーは見栄えしないが、今まで買った中では一番きれいである。
ポポーは生食が主で、果肉はクリーム状、バナナとマンゴーを混ぜたような味で「森のカスタードクリーム」とも呼ばれているらしい。
良い香りがあるが、その香りが強いので好き嫌いが分かれるかもしれない。
.