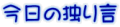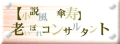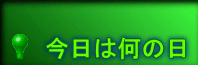■【小説風老いぼれコンサルタントの日記】 2月25日 ◆乾燥対策の加湿器がまさかの・・・ ◇江戸っ子の「御御御汁」??? ◇夕刊紙を購読しない人が多い
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
2月25日 乾燥対策の加湿器がまさかの・・・
乾燥対策として多くの人が加湿器を利用します。
ところが、加湿器のタンク内のカビや細菌により、『アレルギー性肺炎(加湿器肺)』という病気を引き起こすそうです。
症状は、痰は出ないものの咳や発熱など、一見すると風邪と似た症状です。肺全体にカビが広がり、抗菌薬では、効果がみられないそうです。怖いことに、重症化すると呼吸不全をおこし、ひどい場合には命にも関わります。
毎日、水を交換するのは当然ですが、こまめなメンテナンスが不可欠です。取説をもとに、正しい手入れが必要ですね。
*
かねてから興味を持っていた江戸庶民の生活、江戸から学ぶことが多く、時々気分転換に、江戸に関する書籍を手に取ります。
とりわけ故杉浦日向子女史の本は、江戸風物詩を手に取るように語ってくれます。
◆ 江戸っ子の「御御御汁」??? 4
江戸では、汁物はご飯の時にしか付きません。ご飯は、炊きたての銀しゃりのことで、朝食にしか食べません。すなわち汁物は、朝だけで昼夜に付かないのです。最も昼はほうじ茶で冷や飯を食べ、夜はお茶漬けですので知るものはなくても済んだのです。
「汁物」、すなわち「お味噌汁」ですが、江戸では「おみおつけ」と言いました。もともとは「つけ」すなわち「汁」と言っていたのです。それを丁寧に表現しようと「御汁(おつけ)」と言うようになりました。その「御汁」をさらに丁寧に表現しようと「御汁」に「御」をつけます。御汁に御をつけるので、これを「みおつ汁」すなわち「御御汁」というようになりました。これでもかという江戸っ子気質で、「御御汁」に「お」を重ねて「御御御汁」すなわち「おみおつけ」となったのです。
では、なぜ江戸っ子は、このように丁寧な表現にしたのでしょうか。ひとつには、江戸っ子の負けず嫌いが言葉にも出て来たといえます。ご飯だけではやはり不充分で、一日の活力を御御御汁に求めたので、具は二種類以上を入れました。
具だくさんな御御御汁ですので、どちらかというとけんちん汁のような汁物だったのです。どんぶりというか大きなお椀で御御御汁を食べたのです。
江戸では、すまし汁はあまり食べなかったようです。すまし汁は、明治以降の汁物のようです。

■ 「杉浦日向子の江戸塾」バックナンバー ←クリック
杉浦日向子女史の江戸塾は、江戸時代のエコ生活から飽食時代を迎えている我々に大きな示唆を与えてくれます。

■【今日のおすすめ】
【経営コンサルタントへの道】6. 経営コンサルタントになるための資格取得 3 特別推薦制度の活用で近道
コンサルタント・士業として独立起業することは勇気が要ることです。
どの様な資質を備えている人が、成功する確率が高いのでしょうか、経営コンサルタント歴半世紀の経験からお話しています。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】と【きょうの人】などをご紹介します。
この欄には、発信日の【今日は何の日】などをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930

■【知り得情報】
政府や自治体も、経営環境に応じて中小企業対策をしています。その情報が中小企業に伝わっていないことが多いです。その弊害除去に、重複することもありますが、お届けしています。
*
◇《調査》価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果
エネルギー価格や原材料費、労務費などが上昇する中、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境を作るため、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」として設定されています。政府は、業界団体を通じた価格転嫁の要請等を実施しています。
来月3月を前に、折衝準備をしてはいかがでしょうか。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
出典:e-中小企業庁ネットマガジン

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
◆ 夕刊紙を購読しない人が多い 225
近年、新聞を購読しない人が増えています。
スマホで用が足りてしまうからです。
夕刊を取らない人も増えています。
2月25日は、「夕刊紙の日」でした。
夕刊のメリットのひとつが、朝刊に比較して、海外の記事が新鮮であるということです。
海外と時差があるために、海外からニュースが入っても朝刊発行に間に合わないからです。
それと夕食後、ゆったりとした気分の時に、政治・経済といった硬い記事や三面欄よりは家庭欄のような記事を見る方に適しているのです。
なぜ、夕刊を取らない人が増えてきたのかという理由のひとつが、夕刊の記事欄のスペースが減り、読むところが少なくなってきているからではないでしょうか。
上述のようにゆったりした気分で読む記事がないのです。
その上、夕刊の記事と朝刊の記事がダブってしまっていて、夕刊で読んだ記事がまた朝刊に載っているということがしばしばあります。
テレビが普及し、夕刊のニュースの速さは当然のこと色あせてしまっています。
さらに年寄りには、紙の薄さが難儀です。
髪が薄くてページをめくれないのです。
このままでは、海外と同様に夕刊は廃れてしまいます。
内容にもっと工夫が必要ではないでしょうか。
http://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/3dde0a1805c131c75e920de76ec26532
(ドアノブ)

■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。
明細リストからだけではなく、下記の総合URLからもご覧いただけます。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17
>> もっと見る

■【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記 バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a8e7a72e1eada198f474d86d7aaf43db
© copyrighit N. Imai All rights reserved
![]()