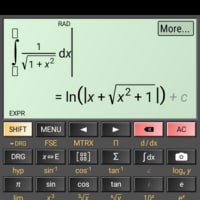今年の水稲は減反のため作付けしておりません。例年は転作で大豆を作付けするのですが、赤字幅が増すので完全に休耕することにしました。休耕と言っても作物の作付をしないだけであって、何もしなくても自然と草々は繁殖してきます。特に稗などを放置しておくと来年水稲栽培すると稗が大繁茂し、夏の盛りに稗取りという重労働をさせられることになります。
そこで除草作業を軽減する方法を調べておりますと”高刈り”という除草法があることを知り、なるほどと思い試してみることにしました。
一般には草刈りと言えば草刈り機で地際で刈ることであると理解されております。地際で刈れば見た目にも綺麗になりますし、草が生えてくる期間も長くなると思われております。私もそのように考えて地際で刈ってきました。更には除草作業をするとき、根から抜きなさいと教えられてもきました。ですから、できるだけ短く刈ること、できれば根から抜いてしまうことが理想だと思っていたのです。
ところが、高刈りは根元から5~10㎝のところで刈りましょうという方法です。それはイネ科の草は根元に生長点があり、地面に広がるように成長する草は先の方に生長点があるとのことで、地際で刈ると地面に広がるように成長する草は絶えてしまい、イネ科の草は直ぐに再生し、結果イネ科の草が優勢になってしまうということです。
高刈りすることで地面に広がるように成長する草を温存し、イネ科の高くなった部分を抑制し、日当たりのよくなった下部の草が繁茂し表土を被いイネ科の草の発芽を抑制でき、結果イネ科優勢とならないようにできるというものです。
確かに自然農においても草は根から抜かず、作物の初期成長に必要な場合に草の上部を刈り、その場で草マルチにすることで他の草を抑制する方法がとられます。これと似たような草管理の方法だと理解しました。
休耕田においては、すでに存在する稗の種子を発芽させ、新たなる種子ができる前に刈り取ることで土中に含まれる稗の種子を減少させることが目標となります。ですから他の草々は少々繁茂しても構いませんので、できるだけ草刈りの回数を多くした方が効果が高くなります。ですから回数を重ねるためには、一回当たりの作業量を減らすことは重要な要素になります。それには高刈りが最も適するのではないかと考えた次第です。
次の画像は高刈り3回目をして12日後のものです。既に稗が結実しております。稗の繁殖力恐るべしです。これらを放置しておくと来年の水稲は目も当てられないような事態になってしまいます。


次の画像は高刈り実施後のものです。地際に生えていた草が顔を覗かせております。



実際高刈りをやってみますと地際刈りに比べると作業時間が1/3程度となりました。作業の疲労度も相当に軽減されます。また、ナイロンコードの減りも激減しました。
ただ、イネ科の草の抑制につながっているかどうかは不明です。前回の草刈りからたったの12日で稗が結実したり、稗が低い位置で穂を作るように変化するなど色々と問題がありそうです。
とりあえず今年はこれでやってみて、来年の水稲栽培における稗の状況を見てみたいと思います。
そこで除草作業を軽減する方法を調べておりますと”高刈り”という除草法があることを知り、なるほどと思い試してみることにしました。
一般には草刈りと言えば草刈り機で地際で刈ることであると理解されております。地際で刈れば見た目にも綺麗になりますし、草が生えてくる期間も長くなると思われております。私もそのように考えて地際で刈ってきました。更には除草作業をするとき、根から抜きなさいと教えられてもきました。ですから、できるだけ短く刈ること、できれば根から抜いてしまうことが理想だと思っていたのです。
ところが、高刈りは根元から5~10㎝のところで刈りましょうという方法です。それはイネ科の草は根元に生長点があり、地面に広がるように成長する草は先の方に生長点があるとのことで、地際で刈ると地面に広がるように成長する草は絶えてしまい、イネ科の草は直ぐに再生し、結果イネ科の草が優勢になってしまうということです。
高刈りすることで地面に広がるように成長する草を温存し、イネ科の高くなった部分を抑制し、日当たりのよくなった下部の草が繁茂し表土を被いイネ科の草の発芽を抑制でき、結果イネ科優勢とならないようにできるというものです。
確かに自然農においても草は根から抜かず、作物の初期成長に必要な場合に草の上部を刈り、その場で草マルチにすることで他の草を抑制する方法がとられます。これと似たような草管理の方法だと理解しました。
休耕田においては、すでに存在する稗の種子を発芽させ、新たなる種子ができる前に刈り取ることで土中に含まれる稗の種子を減少させることが目標となります。ですから他の草々は少々繁茂しても構いませんので、できるだけ草刈りの回数を多くした方が効果が高くなります。ですから回数を重ねるためには、一回当たりの作業量を減らすことは重要な要素になります。それには高刈りが最も適するのではないかと考えた次第です。
次の画像は高刈り3回目をして12日後のものです。既に稗が結実しております。稗の繁殖力恐るべしです。これらを放置しておくと来年の水稲は目も当てられないような事態になってしまいます。


次の画像は高刈り実施後のものです。地際に生えていた草が顔を覗かせております。



実際高刈りをやってみますと地際刈りに比べると作業時間が1/3程度となりました。作業の疲労度も相当に軽減されます。また、ナイロンコードの減りも激減しました。
ただ、イネ科の草の抑制につながっているかどうかは不明です。前回の草刈りからたったの12日で稗が結実したり、稗が低い位置で穂を作るように変化するなど色々と問題がありそうです。
とりあえず今年はこれでやってみて、来年の水稲栽培における稗の状況を見てみたいと思います。