四月二十九日(水) 雨曇
四月二十八日(火)~ 四月三十日(木)の三日間、皇大神宮内宮において「春の神楽祭」開催。
本来なら野外の神宮神苑にて開催されるのだが、二十九日(水)は”清めの雨”にて参集殿内能舞台にて開催された。

雨天の為、参集殿にての開催となる。 せっかく脚立を用意してきたのに・・・、とぼやいても仕方ない。
11:00開催まで時間があり、小腹が空いたので、おかげ横町「豚捨」にてコロッケを一個食す。
おはらい町をブラブラしながら、10:40に参集殿へ戻ったら拝観席が満員・・・。
とりあえず、知らぬ顔して最前列席横の通路に座り込み撮影場所を確保。
あまり良いポジションではなかったが、最後列からの撮影に比ぶれば上等と思うしかない。
待機の間、尻が冷える・・・。
☆ 雅楽とは?
今日雅楽と呼ばれている音楽は、飛鳥・奈良時代から平安時代の初めにかけて、支那大陸や朝鮮半島などから日本に伝来した音楽と、我が国で古来より行われた音楽(神楽歌など)の総称。
雅楽は、その伝来や舞の有無によって管弦・舞楽・催馬楽(さいばら)・朗詠・国風歌舞(くにぶりのうたまい)などの別がある。
支那や朝鮮では王朝の交代などに伴って早くに途絶えたが、我が国に伝来した雅楽は宮中の儀式や社寺の祭礼に用いられて、今日まで連綿として伝承されている。
○ 外国から伝来した雅楽
*支那・印度に由来した「左方」または「唐楽」。
舞がないものを「管弦」、 舞があるものを「舞楽」 左舞(さまい)
*朝鮮に由来した「右方」または「高麗楽」。
舞がある「舞楽」 右舞(うまい)
○ 日本に在来した雅楽
舞がない 和歌を用いる「催馬楽」、漢詩を用いる「朗詠」
舞がある「国風歌舞」(神楽歌・東遊など)
☆ 舞楽について
雅楽に舞が伴うものを舞楽。 舞楽は左方の舞(左舞)と右方の舞(右舞)に分けられる。
左舞は唐楽ともいい、支那・印度方面から伝来したものを指す。
奏楽は三管三鼓といって、笙(しょう)・篳篥(ひちりき)・龍笛(りゅうてき)・鞨鼓(かっこ)・太鼓(たいこ)・鉦鼓(しょうじ)の六楽器編成で、赤色を基調とした装束を用いる。
右舞は高麗楽ともいい、朝鮮方面から伝来したものを指す。
奏楽も左舞とは異なり、笙を用いず、龍笛に代わって高麗笛を、鞨鼓に代わって三ノ鼓を用いる。
装束は緑色を基調としている。
左舞・右舞ともに外来の舞楽だけでなく、これに倣って日本で作られた舞楽もある。
楽曲を奏する所役を管方といい、襲装束(かさねしょうぞく)と呼ばれる装束を着けて鳥甲(とりかぶと)を被る。
管方の筆頭である鞨鼓の所役は襲装束の上に赤い袍(ほう)を着ける。
本日の神楽は、「振鉾」(えんぶ)、「散手」(さんじゅ)、「胡蝶」(こちょう)、「長慶子」(ちょうげいし)。
「振鉾」 左方 一人舞 右方 一人舞
舞楽にあたり初めに奏される。
古代支那の故事に由来し、左方と右方の舞人が鉾を振り大地を鎮め安じて、天下太平を言祝ぐめでたい舞楽。
鉾で天地を厭うことから「厭舞」(えんぶ)と称されたものが、鉾を振ることから「振鉾」の字を充てるようになったと思われる。
転じて舞台を祓い清める舞楽とされている。
舞人は襲装束という出で立ちで、左方は赤の袍に金色の鉾、右方は緑の袍に銀色の鉾を執って舞う。







「振鉾」、優雅な舞である。
「散手」 左方 一人舞
神功皇后が新羅との戦の折、大和の率川明神(いさかわみょうじん)が船の舳先に現れ、指揮をとって敵軍を打ち破った時の姿を模して作った曲といわれ、仁明天皇の御代 (833~850)に、舞を大戸真縄が、曲は大戸清上が作ったと伝えられている。
また一説に、釈迦誕生の時に、師子頬王が作ったともいわれる。
舞楽の次第は、まず龍笛の奏する新楽乱声で舞人が舞台に登台し、登場の舞である「出手」(でるて)を舞い、舞台中央に鉾を置く。 続いて三管による緩やかな「序」という調子も豊かな「破」が奏される。
今回は「破」のみ演奏。 鉾を持って後方から前方へ駆けだしてくる様や、舞台の四方を鉾で突く所作が特徴的。
その後再び龍笛の新楽乱声が奏され、舞人は「入手」(いるて)を舞い舞台を降台。
舞振りは勇壮活発であり、勇ましい武将の姿を表現している。
舞人は赤色の袍に毛縁の裲擋装束(りょうとうしょうぞく)を着け、太刀を佩き、手には鉾を持つ。
顔には朱塗りの赤ら顔の面を被り、牟子(むし)を着け、その上に龍が玉を抱いている姿を模した甲を被る。























気合い溢れる素晴らしい舞であった。 武道の足裁き、腰の使い、無駄のない迫力ある動作に圧倒された。
撮影後には全身汗まみれ、まるで舞人と格闘している感覚であった。
次回のブログで「胡蝶」を記載予定。
それでは、また。 ごきげんよう。
四月二十八日(火)~ 四月三十日(木)の三日間、皇大神宮内宮において「春の神楽祭」開催。
本来なら野外の神宮神苑にて開催されるのだが、二十九日(水)は”清めの雨”にて参集殿内能舞台にて開催された。

雨天の為、参集殿にての開催となる。 せっかく脚立を用意してきたのに・・・、とぼやいても仕方ない。
11:00開催まで時間があり、小腹が空いたので、おかげ横町「豚捨」にてコロッケを一個食す。
おはらい町をブラブラしながら、10:40に参集殿へ戻ったら拝観席が満員・・・。
とりあえず、知らぬ顔して最前列席横の通路に座り込み撮影場所を確保。
あまり良いポジションではなかったが、最後列からの撮影に比ぶれば上等と思うしかない。
待機の間、尻が冷える・・・。
☆ 雅楽とは?
今日雅楽と呼ばれている音楽は、飛鳥・奈良時代から平安時代の初めにかけて、支那大陸や朝鮮半島などから日本に伝来した音楽と、我が国で古来より行われた音楽(神楽歌など)の総称。
雅楽は、その伝来や舞の有無によって管弦・舞楽・催馬楽(さいばら)・朗詠・国風歌舞(くにぶりのうたまい)などの別がある。
支那や朝鮮では王朝の交代などに伴って早くに途絶えたが、我が国に伝来した雅楽は宮中の儀式や社寺の祭礼に用いられて、今日まで連綿として伝承されている。
○ 外国から伝来した雅楽
*支那・印度に由来した「左方」または「唐楽」。
舞がないものを「管弦」、 舞があるものを「舞楽」 左舞(さまい)
*朝鮮に由来した「右方」または「高麗楽」。
舞がある「舞楽」 右舞(うまい)
○ 日本に在来した雅楽
舞がない 和歌を用いる「催馬楽」、漢詩を用いる「朗詠」
舞がある「国風歌舞」(神楽歌・東遊など)
☆ 舞楽について
雅楽に舞が伴うものを舞楽。 舞楽は左方の舞(左舞)と右方の舞(右舞)に分けられる。
左舞は唐楽ともいい、支那・印度方面から伝来したものを指す。
奏楽は三管三鼓といって、笙(しょう)・篳篥(ひちりき)・龍笛(りゅうてき)・鞨鼓(かっこ)・太鼓(たいこ)・鉦鼓(しょうじ)の六楽器編成で、赤色を基調とした装束を用いる。
右舞は高麗楽ともいい、朝鮮方面から伝来したものを指す。
奏楽も左舞とは異なり、笙を用いず、龍笛に代わって高麗笛を、鞨鼓に代わって三ノ鼓を用いる。
装束は緑色を基調としている。
左舞・右舞ともに外来の舞楽だけでなく、これに倣って日本で作られた舞楽もある。
楽曲を奏する所役を管方といい、襲装束(かさねしょうぞく)と呼ばれる装束を着けて鳥甲(とりかぶと)を被る。
管方の筆頭である鞨鼓の所役は襲装束の上に赤い袍(ほう)を着ける。
本日の神楽は、「振鉾」(えんぶ)、「散手」(さんじゅ)、「胡蝶」(こちょう)、「長慶子」(ちょうげいし)。
「振鉾」 左方 一人舞 右方 一人舞
舞楽にあたり初めに奏される。
古代支那の故事に由来し、左方と右方の舞人が鉾を振り大地を鎮め安じて、天下太平を言祝ぐめでたい舞楽。
鉾で天地を厭うことから「厭舞」(えんぶ)と称されたものが、鉾を振ることから「振鉾」の字を充てるようになったと思われる。
転じて舞台を祓い清める舞楽とされている。
舞人は襲装束という出で立ちで、左方は赤の袍に金色の鉾、右方は緑の袍に銀色の鉾を執って舞う。







「振鉾」、優雅な舞である。
「散手」 左方 一人舞
神功皇后が新羅との戦の折、大和の率川明神(いさかわみょうじん)が船の舳先に現れ、指揮をとって敵軍を打ち破った時の姿を模して作った曲といわれ、仁明天皇の御代 (833~850)に、舞を大戸真縄が、曲は大戸清上が作ったと伝えられている。
また一説に、釈迦誕生の時に、師子頬王が作ったともいわれる。
舞楽の次第は、まず龍笛の奏する新楽乱声で舞人が舞台に登台し、登場の舞である「出手」(でるて)を舞い、舞台中央に鉾を置く。 続いて三管による緩やかな「序」という調子も豊かな「破」が奏される。
今回は「破」のみ演奏。 鉾を持って後方から前方へ駆けだしてくる様や、舞台の四方を鉾で突く所作が特徴的。
その後再び龍笛の新楽乱声が奏され、舞人は「入手」(いるて)を舞い舞台を降台。
舞振りは勇壮活発であり、勇ましい武将の姿を表現している。
舞人は赤色の袍に毛縁の裲擋装束(りょうとうしょうぞく)を着け、太刀を佩き、手には鉾を持つ。
顔には朱塗りの赤ら顔の面を被り、牟子(むし)を着け、その上に龍が玉を抱いている姿を模した甲を被る。























気合い溢れる素晴らしい舞であった。 武道の足裁き、腰の使い、無駄のない迫力ある動作に圧倒された。
撮影後には全身汗まみれ、まるで舞人と格闘している感覚であった。
次回のブログで「胡蝶」を記載予定。
それでは、また。 ごきげんよう。










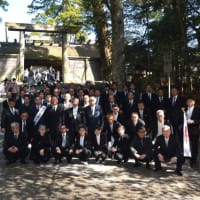















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます