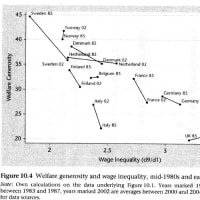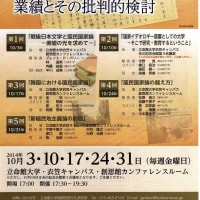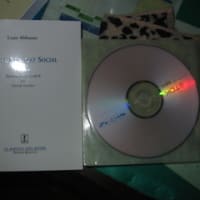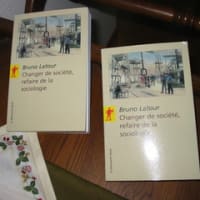| Collins Cobuild Pocket English Grammar (Collins Cobuild Grammar) |
| クリエーター情報なし | |
| HarperCollins UK |
昨今は、日本の社会学でも英文で文章を書くことが求められることがある。私自身は、そうしたことの専門家でも、得意でもないのだが、使えるツールとしていくつかの書籍を紹介させてもらえればと思う。
で、初めは、上の本。
この本、レベルとしては「中級学習者向け」となっているが、英語で書かれた英文法書なので、留学などで英語圏で語学を勉強している人の中で「中級」というレベルではないかと推察する。本の末尾には、アカデミックライティングの基本が載っていて、そういうレベルの人向けだろう。
これは思い込みかもしれないが、英語で書かれた英文法書は説得力があるように思われる。で、この本、ポケット版なので、外出時に文法事項を確認したい時に用いる本、という位置づけだろうか。
で、この本で興味深かったのは、アカデミックライティングの中で、アカデミックな文章では、非人称構文を多用すること、というアドバイスがあった。まあ、非人称構文や、それに伴って受け身なども用いることになるが、それによって自分の主観とは異なった印象を与えることができるようになる。
日本語で書かれた英文ライティングの本などでは、能動態を使うようなアドバイスが多くあるが、英語でも受動態が必要なところが有り、必要なところではそれを用いるべきなのである、といったところであろうか(ただし、この本であった説明ではないのだが、この辺の状況というか、用法の状況について説明すると、歴史的にはアカデミックな文章では、客観性が求められたため、非人称構文や三人称が用いられることが多かったのだが、近年というか現代では、その傾向が改まって、能動態を用いて能動的な文章を書くように変わったのだそうだ。こうした歴史的コンテクストを踏まえていないと、ちゃんとした英語も書けないと思うのだろうが、どうだろうか? そうした意味で、この種の文法書を携帯することは無駄なことでは無いと思われる)。