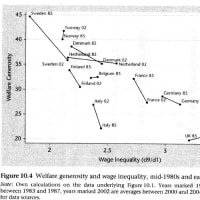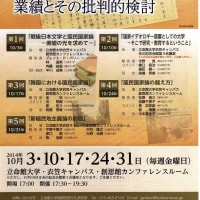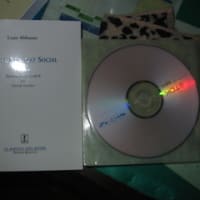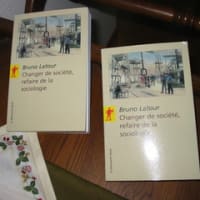たしか数年前ぐらいのことだったと思う。NHKのドキュメンタリー番組、NHKスペシャルで、NHK交響楽団の音楽監督だったアシュケナージに焦点を当てたドキュメンタリーが放送されていた。このドキュメンタリー、ソ連時代のロシアにおいて、いかに芸術家の自由が抑圧されていたのかを取材した番組だった。
アシュケナージとは、現在のロシア(当時はソ連)出身の音楽家で、その当初はピアニストとしてキャリアをスタートさせたらしい。第二回チャイコフスキーコンサートで優勝したのはよく知られているが、その後、音楽の幅を広げるために指揮をするようになったというのだとか。彼は、旧ソ連から逃れるために亡命したのだが、その番組では、ソ連共産党の抑圧的な支配下で、ショスタコービッチ等の芸術家がどのようにして創作活動を行ったのかに注目していた。
ソ連共産党は、芸術家の活動を常に監視していて、芸術には自由な表現手段はなかったというわけだが、この番組で、もっとも印象に残ったのは次のことであった。
スターリンは、難解な芸術作品を「ブルジョア的だ」と非難し、作曲家のショスタコーヴィチに、より「わかりやすい作品」を書くように迫ったようでである。つまり、音楽は大衆の役に立つものでなくてはならない、大衆を感動させるべきものでなければならない、というわけなのだとか。ショスタコーヴィチはその求めに応じて、スターリンのプロパガンダ映画に『ベルリン陥落』という曲を書く。ショスタコーヴィチのこの曲をして、アシュケナージは、「ショスタコーヴィチの曲のうち最低の部類に属する」と述べていた。「わかりやすい頭にわかりやすいメロディー……、」というように。
でも、難解な作品に対する「非難」は、何も東欧圏諸国に限った話ではない。日本でも現代的な作品には、そうした批判はつきもの。そしてそれは、芸術に限った話ではなく、社会学においても言えること(笑)。現在の日本の社会理論を巡る状況にも当てはまるような気がしてならない。
「難解」な話に対する拒否反応という点では、どこでも同じかもしれません。
社会学の現在の潮流について言えば、「難解な理論」は、何の役に立つのかさっぱりわからない、言葉をもてあそんでいるにすぎない……。こうした声は、社会学に限らず多く聞かれることだが、ある種のスターリニズム的な偏狭さを感じさせます。
無論、こうした「スターリニズム」の問題から、私自身逃れられているわけではない。というか、おおよそマルクス主義を標榜する者としては、このスターリニズムは、自ら引き受けねばならない問題であり、避けては通れないと思っている。そうした意味では、「難解な理論」を巡る現在の「スターリニズム的」状況についても、それについて「スターリニズム」というをレッテル張るだけで、批判した気になるつもりもないが……。
ただし、私が気にしているのは、「わかりやすければそれだけで役に立つ」という考えが、「わかりやすさの要求」の背後に見え隠れしているのではないか? ということ。「難解な理論は……云々」とそれを批判しても、こうした問題設定を見直さねば、徒労に終わるように私には思える。「難解な理論」のなかにも、「役に立つ」ものとそうでないものがあるわけで、こうした検討こそが求められるべきではないだろうか。それを抜きにして、「難解なものはすべてだめ」と安易に結論づけることは、非常に危険なようにも思われる。
アシュケナージとは、現在のロシア(当時はソ連)出身の音楽家で、その当初はピアニストとしてキャリアをスタートさせたらしい。第二回チャイコフスキーコンサートで優勝したのはよく知られているが、その後、音楽の幅を広げるために指揮をするようになったというのだとか。彼は、旧ソ連から逃れるために亡命したのだが、その番組では、ソ連共産党の抑圧的な支配下で、ショスタコービッチ等の芸術家がどのようにして創作活動を行ったのかに注目していた。
ソ連共産党は、芸術家の活動を常に監視していて、芸術には自由な表現手段はなかったというわけだが、この番組で、もっとも印象に残ったのは次のことであった。
スターリンは、難解な芸術作品を「ブルジョア的だ」と非難し、作曲家のショスタコーヴィチに、より「わかりやすい作品」を書くように迫ったようでである。つまり、音楽は大衆の役に立つものでなくてはならない、大衆を感動させるべきものでなければならない、というわけなのだとか。ショスタコーヴィチはその求めに応じて、スターリンのプロパガンダ映画に『ベルリン陥落』という曲を書く。ショスタコーヴィチのこの曲をして、アシュケナージは、「ショスタコーヴィチの曲のうち最低の部類に属する」と述べていた。「わかりやすい頭にわかりやすいメロディー……、」というように。
でも、難解な作品に対する「非難」は、何も東欧圏諸国に限った話ではない。日本でも現代的な作品には、そうした批判はつきもの。そしてそれは、芸術に限った話ではなく、社会学においても言えること(笑)。現在の日本の社会理論を巡る状況にも当てはまるような気がしてならない。
「難解」な話に対する拒否反応という点では、どこでも同じかもしれません。
社会学の現在の潮流について言えば、「難解な理論」は、何の役に立つのかさっぱりわからない、言葉をもてあそんでいるにすぎない……。こうした声は、社会学に限らず多く聞かれることだが、ある種のスターリニズム的な偏狭さを感じさせます。
無論、こうした「スターリニズム」の問題から、私自身逃れられているわけではない。というか、おおよそマルクス主義を標榜する者としては、このスターリニズムは、自ら引き受けねばならない問題であり、避けては通れないと思っている。そうした意味では、「難解な理論」を巡る現在の「スターリニズム的」状況についても、それについて「スターリニズム」というをレッテル張るだけで、批判した気になるつもりもないが……。
ただし、私が気にしているのは、「わかりやすければそれだけで役に立つ」という考えが、「わかりやすさの要求」の背後に見え隠れしているのではないか? ということ。「難解な理論は……云々」とそれを批判しても、こうした問題設定を見直さねば、徒労に終わるように私には思える。「難解な理論」のなかにも、「役に立つ」ものとそうでないものがあるわけで、こうした検討こそが求められるべきではないだろうか。それを抜きにして、「難解なものはすべてだめ」と安易に結論づけることは、非常に危険なようにも思われる。