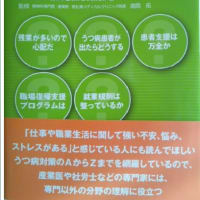多くの企業関係者の疑問です。「安全配慮義務、どこまでやればいいの?許されるの?」
当職も同様の疑問に悩む一人です。
参考判例として、川義事件(最三小判昭59.4.10)では、
「安全配慮義務の具体的な内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等、安全配慮義務が問題となる
当該具体的状況等によって異なる」としました。即ち、個別具体的に判断されますので、
安衛法などの一般的な基準を満たしているだけでは不十分なのです。
つぎに、参考になる判例を紹介します。
まず、既にご承知の、東芝(うつ病・解雇)事件(最二小平26.3.24判、差戻審・東高平28.8.31判)です。
判決では、「会社側は、労働者の申告がなくても、企業は労働者の心身の健康に注意を払う義務がある。」とされました。
さらに、最近の重要な事例を二つ紹介します。
ひとつは、判決ではありません。地裁の和解勧告なのですが、画期的です。
通勤時にも会社側に安全配慮義務があるとされた事案です。
過労事故死 通勤時も会社に安全配慮義務
毎日新聞2018年2月8日
和解成立 会社が遺族に謝罪、7590万円支払いへ
勤務先からバイクで帰宅途中に事故死した社員の遺族が、事故が起きたのは過重労働が原因だとして
会社側に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の和解が8日、横浜地裁川崎支部で成立した。
橋本英史裁判長は、会社には、通勤時にも社員が過労により事故を起こさないよう配慮する義務があると判断し、和解を勧告。
会社が遺族に謝罪し、約7590万円を支払うなどの和解条項に双方が合意した。
過労により労働者が通勤時に起こした事故で雇用主の賠償責任を認めるのは異例。
過労死防止法には「事故死」の規定はなく、原告側弁護団の川岸卓哉弁護士は「
過労事故死を未然に防ぐ社会規範になる」と評価した。
訴えたのは、植物装飾業「グリーンディスプレイ」(東京都世田谷区)の社員だった渡辺航太さん(当時24歳)の遺族。
渡辺さんは2014年4月24日朝、22時間弱の徹夜勤務後に原付きバイクで帰宅中、電柱に衝突して亡くなった。
渡辺さんの業務は深夜や早朝に及ぶため、会社はバイク通勤を認めていた。
和解勧告は、渡辺さんが疲労蓄積と睡眠不足のため「居眠り状態に陥って運転を誤り、事故を起こした」と指摘した上で、
「雇用主は、労働者の通勤に際し、過労で事故を起こさないよう注意する安全配慮義務を負う」と判断。
「事故の危険を認識できたのに、公共交通機関を利用するよう指示しなかった」と義務違反を認めた。
勧告は「過労死の撲滅は喫緊に解決すべき重要な課題で、社会全体の悲願だ」とも指摘。
和解条項には、同社が(1)休憩時間を確保する「インターバル」の導入(2)仮眠室の設置
(3)深夜タクシーチケットの交付--などの再発防止策を実施することが盛り込まれた。
ふたつめは、ティー・エム・イーほか事件(東高判平27.2.26)です。
これは、派遣労働者(A)が過重負荷のない業務に就業している際に、うつ病にり患し、その旨の診断書を
派遣先・派遣元に提出しないまま自殺した事案です。
高裁判決では、
〇会社側は、休暇・早退の頻度からAの健康状態を不安視し、事情を聴いているので、
会社側は、Aの体調不良を認識すことが出来ていた。
〇AやAの家族に単に「調子はどうか」などと抽象的に問うだけでは足りない。
体調不良を把握した以上、安全配慮義務の一環として、
・不調の具体的内容等(診断名、処方薬、通院先等)を調査する義務
・適宜、産業医等に面談させ、体調管理が適切に行われるよう配慮・指導する義務
があるが、通院先等を何ら把握せず、安全配慮義務を尽くさなかった。
結果、Aの慰謝料(の相続)を認容したが、自殺との相当因果関係は否定された(請求一部認容)判決となりました。
上記二つの事例は、安全配慮義務の範囲、あるいは限度が「際限なく」拡大しているように思えます。
では、どこまでやればいいの?一般的な解釈です。以下、優先順位で列挙します。
1.労働安全衛生法、労働安全衛生規則その他の法令
・法令遵守の最低基準のみならず、快適職場づくりなどの努力義務も含む
2.ガイドライン等(告示・指針・通達などの行政指針)
3.裁判例が確立した基準を、1.及び2.に従い、体制づくりに反映させる
4.社内規定の遵守(安全衛生管理規程、作業手順なども)
5.その他の積極的な災害防止対策(危険予知訓練、リスクアセスメントなど)
6.一般的基準からは予見できない具体的危険の抽出
7.本人とのコミュニケーション、管理監督者・部署・専門家間の連携など、関係当事者への積極的な働きかけ・活用
結論は、安全配慮義務の範囲、あるいは限度は、きりがない、
ここまでやっておけば、OKということはないのです。
即ち、冒頭の多くの企業関係者の疑問に対する答えは、「ない」というのが、正しいようです。