といっても日本酒の話。
「古酒」といっても日本酒の場合、熟成は年数に比例して進むわけではないらしいです。
最初の2,3年は順調に熟成が進むのですが、そのあとは酒質は低下の一途をたどるそうです。
ところが7年目あたりをボトムにして急に酒質がよくなる。ここを酒蔵では「解脱」というとか。
しかし世の中そんなに上手くいかず、またしばたらくしてピークを迎えるとまた低下が進み、30年目くらいに次のボトムが来るそうです。
それ以降に再度「解脱」するかは、日本酒の熟成のメカニズムが解明されたわけでないのでよくわからないとか。これは30年前の酒造は今ほど安定していなかったし古酒を造る酒蔵も多くなかったことによるらしいです。
このライフサイクルってなんとなくサラリーマンと似てますね。
最初は一生懸命働いて経験を積むんだけど、そのうち天狗になってくる。
30くらいでこれじゃいかん、と、ギアを入れ替えてがんばって一皮むける。
ただ、だんだん歳をとってきて体力・知力の衰えを経験だけではカバーできなくなったり、得たポジションを維持することに専ら能力を使うようになると「労害」「お荷物」になってくる。
という感じでしょうか。
そして、2度目のボトムでもう一ふんばりするとか別の味わいのある生き方をするというスタイルが一般化するかは、まだ団塊の世代がそこにさしかかったばかりなのでわからない、というところも似ています。
ちなみに、生酒や吟醸酒は吟醸香などを出すアミノ酸が熟成するとヒネた香りの元になってしまうので、古酒にはあまり向かないそうです。これもキャリアシステムとか採用基準を考えると示唆的です。
熟成が環境によって大きく変わるところは、日本酒(温度、タンク内か瓶内かetc.)も仕事も同じ。
ただ、仕事は自分のほうから環境を変えることができるので、酒でなく酒蔵の立場で試行錯誤ができるのが大きな違いです。
明確な方法論とか「キャリアパス」がないところが古酒の奥深さであり人生の醍醐味だ、と味わうのが大事ということですね。
最新の画像[もっと見る]
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
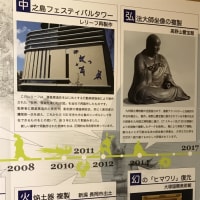 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
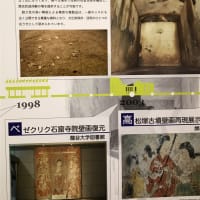 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
-
 大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前
大塚国際美術館+鳴門の渦潮
5年前















