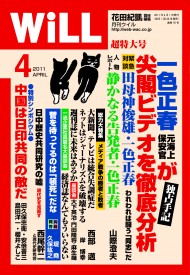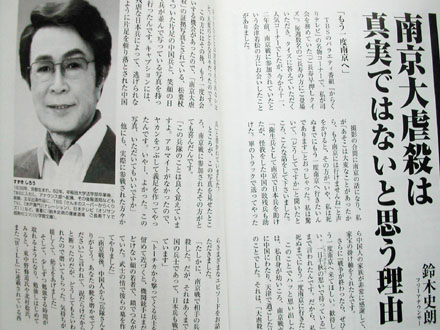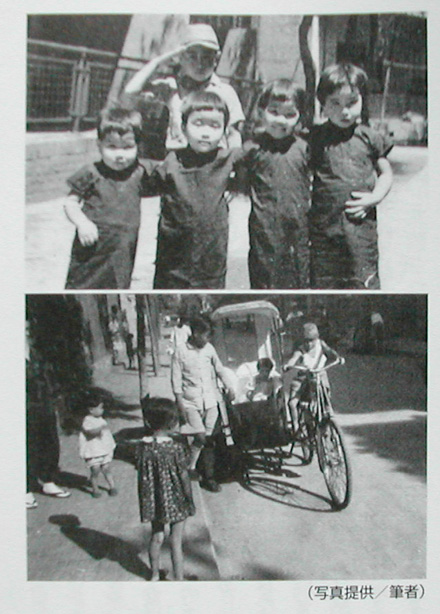前回サイタニのブログから転載した
の続きです。日本の歴史の中で、これほど厳重に守られ続いてきた天皇の万世一系の男系継承の伝統、もし今この伝統を現代のわれわれが破ってしまうならば、この伝統を死守するために中継ぎ役で女帝になり、時には婚姻や出産を諦めて、生涯独身で通した女帝達はいったいなんだったのでしょう。
この方々の献身は一途なものであったでしょう。その後は男系の血統を守るための血の伴走者たる閑院宮が立てられ、よくその伴走者の役目を果たし、女帝を建てる必要はなくなります。そうした宮家の制度はGHQに廃止されるまで続いていたのです。
今私達が考えることは、この廃止された宮家を復活させることではないでしょうか。この宮家は男系を維持しながらも、常に時の天皇の皇女との婚姻により、時の天皇との血の濃さを保って来ました。
天皇であること、それは生涯を国家と國民への献身で貫くという覚悟にほかなりません。今上陛下がどれだけ、日々の生活の隅々まで気を配って、その殆どの時間を、国民のためのご公務に、あるいは国民の幸福を祈るために、費やされているかを知れば、天皇となるには、無私であることの覚悟が、まず一番に必要とされる御位であり、重大な天命を受け入れることなのです。
竹田恒泰 著 「皇族たちの真実」より
女帝は中継ぎ役
我が国最初の女帝、推古(すいこ)天皇は、東アジアにおける女帝の先例となる。崇峻(すしゅん)天皇が後継者を指名する前に殺害されたことで、後継争いが起き、しかも有力な候補者が複数あったことから、その争いを避けるために、
推古天皇が即位することになった。
即位して間もなく厩戸皇子(うまやどのみこ)(聖徳(しょうとく)太子)が皇太子になったことから、推古天皇の即位と厩戸皇子の立太子は一体のものだったと考えられる。つまり、推古女帝の誕生は、後継争いを避けて政治的緩和をしつつ、次の皇太子を導き出すという役割を担ったことになる。
推古天皇の次の女帝である皇極(こうぎょく)天皇も後継争いを緩和するために 擁立された女帝であった。そして次の女帝、持統天皇は、継嗣たる我が子草壁皇子(くさかべのみこ)(天武(てんむ)天皇皇子)が即位に必要な年齢に成長するまでの間、中継ぎのために即位した女帝である。
結局、草壁皇子は若くしてこの世を去るが、その息子の珂瑠皇子(かるのみこ)「文武(もんむ)天皇」に皇位が伝えられた。持統天皇は生前譲位して太上(だいじょう)天皇(上皇(じょうこう))となった初めての天皇であり、初の年少天皇を成立させることになった。
次の女帝、元明(げんめい)天皇もまた、継嗣たる孫の成長を待っために中継ぎとして即位した女帝である。元明天皇は娘(元正(げんしょう)天皇)に譲位し、
継嗣たる孫を立太子させ、そして親子二代で継嗣の成長を待つ形になった。
孝謙天阜は弟の安積(あさか)親王(聖武(しょうむ)天皇の皇子)が庶系であったために、一定期間親王を皇太子とすることで、安全に皇位を継承させることをもくろみ、親王に先立って即位した女帝である。ここでもやはり中継ぎ役であった。
そして平安時代に入ると皇太子の制度が整い、中継ぎとしての女帝は必要なくなる。
しかし、これまで見てきた六方八代の女帝の足跡は、皇太子制度をつくる上で大きな影響を与えた。
その後江戸期に入って二方の女帝が現れたが、明正(めいしょう)天皇はわずか6歳で践祚した女帝だった。紫衣(しえ)事件とそれに引き続く春日局(かすがのつぼね)参内事件で幕府に激怒した 後水尾天皇が、不快感を顕(あらわ)に幼少の内親王を即位させたことで859年ぶりに女帝が成立した。これは 後水尾天皇の幕府に対する報復措置であった。
我が国最後の女帝となる後桜町天皇は継嗣たる甥の英仁(ひでひと)親王が成長するまでの間、天皇の位に就いた。明正天皇は特殊な例だが、そのほかの女帝は、皇位の後継争いを緩和する為、もしくわ継嗣の成長を待つために成立したのであり、いずれも「中継ぎ」としての役割を担ったものだった。
女帝の不文律
女帝が誕生した背景や役割はどれも異なっているが、一定の共通項が あるので、ここでまとめてみよう。
第一に、女帝は例外なく歴代天皇の男系の子孫であると指摘できる。 女系子孫や外部から嫁いで来た女性が天皇になったことはない。よって、 八方十代の女帝がありながらも、万世一系、つまり男系による皇統の継承は 途切れたことがない。
そして第二に、先帝の皇后が女帝になることを原則としている。 まさに推古天皇、皇極・斉明天皇、持統天皇は皇后であった。
元明天皇は皇太子草壁皇子妃であり、元正天皇に至っては皇后でも 皇太子妃でもなかったが、いずれにしても皇后、もしくはそれに 準ずるように格上げされてから即位となっている。
そのことからも、女帝は皇后であるべきだとの不文律が存在していた ことが分かる。ただし、その原則も未婚の内親王が即位した元正天皇の 例を以って変化し、以降の女帝は全て未婚の内親王となった。
また第三に、女帝はいったん即位すると、婚姻した例も、出産した 例もなく、これらを禁止した不文律が成立していた点を指摘しなくては いけない。女帝は、在位中はもちろんのこと、退位した後も未婚の立場を 貫き通さねばならない運命にあった。そしてこれは一つの例外もなく 守られている。皇統が男系によつて継承される以上、女帝の婚姻は 本人に婚姻の意思があつたとしても事実上不可能だった。
そして第四に、女帝の係累は即位することができないことが指摘できる 。元来女帝の擁立は、継承を巡る政治的緊張を緩和させるのが趣旨であり 、女帝の息子に皇位継承権があるならぱ決して緊張緩和にはならなかつた ことからも明らかである。女帝とはその係累の皇位継承を事実上否定 された天皇であった。
また、女帝は通常の天皇とは区別されていたことは注目すべきである。 女帝を「中天皇(なかつすめらみこと)と称して区別したこことや、 泉涌寺(京都市東山区)に江戸期の歴代天皇の肖像画が保存されて いるが女帝の肖像画だけがないこと、そして本来天皇が成人すると、 摂政(天皇に代わて政務を行なう役職)は関白(天皇の政務を補佐する 役職)に置き換えられるのだが、江戸時代の女帝には天皇の成人後も 摂政が置かれ続けたことが挙げられる。
八方の女帝にはそれぞれのドラマがあるが、結果的にはいずれも正当な 皇位の継承者となることなく、全て「中継ぎ」の役割を担つたことになる 。そして「中継ぎ」とはあくまでも「中継ぎ」であつて、皇統断絶の危機 に当たつての緊急避難ではない。
皇位継承者がいなくなつたとき皇統断絶の危機を回避するために
女性が天皇となつた例は一例もなかつたのだ。
閑院宮を天皇に
後桃園天皇崩御に伴う皇統の危機に際し、女帝を立てる以外の方法も洗いざらい先例が調べ上げられ、様々な方法が模索された。そしてついに朝廷は、傍系から即位した継体天皇と後花園天皇の先例に従うことを決めた。
先帝が遺(のこ)した唯一の内親王を女帝とせず、先例にあるとおり、たとえ遠縁であろうとも、いずれかの天皇の男系男子を世継ぎとした。天皇の近親に男系男子はいなかったものの、傍系であれば正真正銘の 天皇の男系男子が存在していたのである。
このとき世継ぎに選ばれたのは世襲親王家、つまり宮家の男子だった。朝廷は、閑院宮典仁(かんいんのみやすけひと)親王の第六王子でまだ満8歳の祐宮(さちのみや)を後桃園天皇の養子とした上で世継ぎとする旨を正式に取り決めた。祐宮というのは幼名であり、御名を「師仁(もろひと)」、後に「兼仁(ともひと)」と称した。
祐宮は第一一三代東山天皇の男系の曾孫に当たり、また先代の後桃園天皇とは七親等の遠縁に当たる。祐宮は生後間もなく聖護院宮忠誉(しょうごいんのみやちゅうよ)入道親王の元に預けられ、将来聖護院門跡を継ぐことが予定されていた。
現在は天皇の皇子であれば自動的に宮家を創設することになっているが、近世以前にはそのような習慣はなく、天皇もしくは四親王家の当主にならなかった親王は、宮家を創設せずに出家して門跡に入るのが原則であった。
出家した皇族が入る寺院は宮門跡といわれ、一種の寺院格式をなした。輪王寺(りんのうじ)、青蓮院(しょうれんいん)、聖護院、勧修寺(かんしゅうじ)、仁和寺(にんなじ)、知恩院(ちおんいん)などが江戸時代の宮門跡として知られている。
幕末になると、 青蓮院宮が還俗(げんぞく)して中川宮へ、また勧修寺宮が還俗して山階宮(やましなのみや)となるなど、明治2年(1869)までの間に、出家していた親王は次々と還俗を命ぜられ、宮門跡は廃止された。
後桃園天皇崩御翌月の11月8日、祐宮が世継ぎとなることを関白九条尚実(くじょうなおざね)が叡慮(えいりょ)〔天皇の考え」として発表した。この重大な発表があった日、祐宮は閑院宮邸から天皇の御所である禁裏御所に移り住み、皇位の証である剣璽(けんじ)(三種の神器のうちの剣と勾玉(まがたま))を受け継ぐ践祚の儀を済ませた。
この祐宮こそ光格(こうかく)天皇である。翌日の11月9日、朝廷はついに後桃園天皇が崩御したことを公にした。この運命の日より祐宮の生活は一変する。8歳の祐宮にとって、天皇になることの意味を理解することはできなかつたであろう。しかし、立派な僧侶になるための修行をしていた生活が、御所の中の生活に様変わりするのであるから、祐宮も戸惑ったに違いない。
何も知らない祐宮が初めて禁裏御所に入るところは、「ラストエンペラー」として知られる清朝の愛新覚羅溥儀(あいしんかくらふぎ)が幼少にして紫禁城に入る場面を紡佛とさせるものがある。
先帝の皇女を皇后に
光格天皇のように傍系から践祚した例は、一二四回繰り返されてきた皇位継承のドラマの中でも継体天皇、後花園天皇、そして光格天皇のわずか三例しか存在していない、いずれも皇室にとって危急存亡の秋であった。
ここで極めて重要な点を指摘しなくてはいけない。崩じた後桃園天皇の皇女欣子内親王が光格天皇の皇后とされたことである。これは、閑院宮出身の光格天皇と先帝との血縁を濃密にするための措置にほかならない。
新帝は閑院宮から擁立されたが、天皇家を置き去りにすることはなかつたのだ。皇位継承者が不在という局面で傍系から天皇を擁立したことは、皇位を男系継承させ、最も重要な伝統を守ったことになるが、一方で新帝と先帝が遠縁であるという問題を生じさせた。しかし、先帝の皇女が新帝の皇后になることにより、新帝と先帝との間の血縁を一挙に近づけることに成功した。
この方策にはモデルがあり、その先例に従ったものだった。それは継体天皇の例である。皇統断絶の危機の一つとして既に示した武烈天皇から継体天皇への皇位継承のとき、傍系の継体天皇は、武烈天皇の姉で仁賢天皇皇女に当たる手白香皇女を皇后としたことは既に述べたが、光格天皇が欣子内親王を皇后としたのは、この先例に従ったものだった。
ちなみに、手白香皇女は後に継体天皇の嫡子たる欽明天皇を出産したことも注目すべきである。それにより現在の天皇家の血筋は手白香皇女を通じて仁賢天皇以前から、また継体天皇の父系を通じて応神天皇以前から繋がっていることになるからだ。
祐宮が選ばれた理由
安永8年当時世襲親王家は四家あり、その中に多数の男子皇族がいた。誰を天皇にするべきかの選考を行なうに当たり、継体天皇を先例とし、先帝の皇女との婚姻が前提、もしくは優先されたと考えられる。すると侯補者はおのずとわずか数名の若年皇族に絞られることになる。
安永8年生まれの先帝の皇女との婚姻を考えると、年齢的に釣り合っている必要があり、また未婚者で、かつ宮家を継承する予定がないことが望ましい。またその頃、宮家の当主とならなかった男子皇族は出家して門跡寺院の門跡となることが慣習であったが、門跡を継いだ入道親王を還俗させるよりは、いまだ門跡を継いでいない若い皇族の中から候補者を選ぶことが優先されたと考えられる。安永8年に御桃園天皇が崩御した時の未だ門跡を継いでいない皇族男子は八方あった。
つづく
転載終わり