ご挨拶
新年明けましておめでとうございます
私の拙いブログ、お読みいただいている皆さまに心から感謝申し上げます。
これまで、時事問題を中心に日ごろ考え思ったことを、野猿や雉ぐらいしか訪問者の居ない山家住まいの徒然あれこれ書いてまいりましたが、何がどうなるわけでもなく虚しさが日に日にましてまいりました。
そこで、この頃、小説なるものを書いてみたくなり、二、三習作を試み、地元紙の新春文芸作品に応募したところ、敢えなく落選の憂き目をみました。
だが、せっかく一生懸命書いた作品、このまま捨ててしまいますのも惜しく、ここに恥を忍んで掲載させていただくこととしました。
ご一読くださいました方、何かご感想、ご教示をいただければ誠に幸いに存じます。
なにとぞよろしくお願い申しあげます。
「勝頼幻影」
ドンドン…、ドンドン…。マンションのドアを誰かが激しく敲いている。何だ!誰だ!こんな時間に…。幸一は布団の上に跳び上がるように腰を起こした。左脇で多恵子が掛け布団の襟元をぎゅっと握り締めながら「今頃誰…」と不安そうに幸一を見上げた。
もしかして…あいつ等では…。また激しくドアを敲く。玄関ドアの前へ小走りに身を寄せた。ドアの覗き穴から外を窺う。小さな球形の視界。パンチパーマにサングラスのいかつい顔が迫る。背後にも人影が動く。
「居るんだろう…。さっさとここを開けねーか…」
幸一は多恵子の傍へ走り戻った。
「あいつらだ。手形の取立てだ…。こんな時間に押しかけてくるなんて…。」
と今度は、ドアでキューンと悲鳴のような金属音がした。ディスクグラインダーか何かでドアに穴を開けるらしい…。
「警察に電話して…」
幸一が切羽詰って低く、短く云った。
多恵子が震える指で携帯のボタンを押した。グラインダーの狂ったような金属音とドアを蹴る音が激しく交錯する。幸一の大きな背中に身を寄せた多恵子の微かな震えが伝わる。
ほどなくパトカーのサイレンが近づいてきた。ドリルの音がやんだ…。外廊下を慌てて駆け去っていく靴音があっという間に消えた。
代わりに警察官がドアをノックした。
「どうしました」
幸一はドアを開けて狭い玄関に、外に立つ二人を招じ入れた。
「実は恥ずかしい話しですが、私の会社が倒産して、不渡り出してしまい、その取立ての嫌がらせです…。」
「それは大変ですね。とりあえず器物損壊で調書取らせてください…。」。
二人の警察官は現場のドアに付けられた傷跡を写真に撮るなどし、型どおりの調書を作成すると、今夜はまた直ぐ同じことはしないでしょう、何かあったらこのあたりをパトロールしているので通報するようにと、云い置いて戻っていった。両隣の部屋で何事かと様子を窺っている気配が伝わってきた。
翌朝、レンタカー会社に多恵子の名前で予約をいれ、二人は借りた車に身の回りの小物を詰めたバック二つを後部座席に、八王子インターから中央高速を西に向った。
前方の風景が左右に切り開かれていく。なだらかな山並みが明るい空の下に横にひろがり、山肌が柔らかな萌黄色に霞んでいる。
幸一は、ハンドルを手に、今度のことがなければ、多恵子と初めての少しばかり心浮くドライブだったのだが…と思う。それが、とんだ取立て屋からの逃亡ドライブとは…。彼女は隣のシートに深く身を沈めて座り、黙って前を見ている。何を思っているのだろうか。昨夜の騒ぎで、自分の長年勤めてきた会社の倒産という現実の厳しさ、そしてこれからどうなるのか不安で一杯なのだろうか…。
その気持ちを軽くほぐすように声をかけた。
「取りあえず、親父(おやじ)とお袋の墓参りでもしてみようかな…。春の彼岸にも行ってやれなかったし…。お参りすれば、何か好い智恵も湧くんじゃないかな…」
「そうねー。こうゆう時こそ、好いことかもね…」
幸一のその一言に多恵子はいく分気を軽くしたようだ。だが、また沈黙が続いた。
自然、幸一の頭には、昨夜の事態に至ったあれこれがフラッシュバックとなって浮かぶ。
叔父で専務の清水賢吉のしてやったと言いたげな高笑い。叔父は、父源三が腹違いの兄源太郎の事故死の後を、急遽周囲の反対を押し切り、愛人の子であり、しかも畑違いの市役所勤めを辞めさせ、認知してまで自分に後を継がせたときから面白くなかったのだ。
賢吉のやったことはともかく、その気持ちは理解できなくもなかった。叔父は、父源三が山梨の穴山の小さな集落の高等小学校を終え、八王子の大工棟梁の家に住み込み、二十四、五でそこを飛び出し、独立して戦後の焼け跡のバラック建築で大儲けし、三十そこそこで株式会社清水住建を設立して以来、十歳年上の兄を助けてきたのだ。会社はその後高度経済成長に平仄を合わせたように急成長した。その陰には賢吉の貢献も大いにあったのだ。だから、跡取りの源太郎が亡くなったあとは当然、自分が指名されるものと期待していたに違いない。それが、予想外の結果になったのだ。父は血筋を選んだのだ。
当時、幸一は若さからか、叔父の複雑な思いまで考える余裕はなかった。ただ、父から口説かれたとき、自分でも役所に入って十年余り、役所での仕事に飽き足りないものを感じていた。このままここで、ただ一回限りの人生終わっていいのだろうかと…。
大きな組織の中では、何一つとして、これは自分がやったという達成感がなかった。
それにまた、若くして職場結婚した妻の昌枝が、お互いの性格の違いから何かと衝突するようになり、加えて母との間でお決まりの嫁姑の衝突から、ある日一人娘の七才になった絵里を連れて家を出ていき、そのまま離婚した。その三年後に母も乳がんで亡くなり、幸一は母の遺した家に独り暮らしの身だった。
だから、父から、突然思いがけなくも後を継いでくれないかと云われたとき、これはこれで自分の人生の一つの転機かと思えた。そして、父の会社に入り、営業を担当して十年余り、一生懸命に働いてきた。新築ブームの蔭りから、いち早くリフォーム部門を立ち上げそれなりの業績もあげてきた。そんな、これからと云うとき、父が脳溢血で急逝した。
父亡き後、幸一は五十人余りの社員の生活を担う責任の重さを感じ、一層社業に励んだ。ところが父の三回忌を終えたばかりの、この正月明け、事態は急変した。
専務の清水賢吉が突然、会社の預金通帳とともに姿を隠した。あっというまに噂が四方に飛んだ。中小企業の清水住建にとってそれは致命的だった。たちまち銀行の貸付が閉鎖され、下請けへの手形が不渡りとなった。「支払いどうするんだ。金よこせ…」の電話の殺到…。
そんな中で、親しい知人が智恵をかしてくれた。少しでも手元の現金があったら他人名義の口座へ変えてしまえ。でないと丸裸になって動きがとれなくなるぞと。
咄嗟に多恵子の顔が浮かんだ。彼女は会社で総務関係の仕事を一人で切り盛りしていた。手が空くと、いつもさりげなく、コーヒーを淹れてくれたり、コンビニでお握りを買ってきてくれたりした。そんな多恵子に幸一は昌枝にない優しさを感じつつ、次第に心密かに惹かれていた。彼女は会社から二駅ほどの私鉄駅近くの小さなマンションに、何故か独りで暮らしていた…。
いつも地味な服装で、長めの髪を後ろでリボン止めしたポニーテールが、細面の奥二重の優しげな顔によく似合った。
事情を話して彼女に新規口座を作ってもらい、僅かにかき集めた売掛金の百数十万円を入金し、彼女名義でカードも作った。幸一にとってこれが当面の命綱だった。多恵子は、彼の身を心配して、私のところ二部屋あるのでよかったら暫くうちへ来ては…と申し出てくれた。それは、心身ともに疲労困憊していた彼にとって、地獄に仏だった。
「好いのかな…。迷惑かけるんじゃないかな…。」
「大丈夫。身体さえちゃんとしていれば…何とかなるんじゃーない。」
こうして、多恵子の好意に甘える形で2Kのマンションの一室に身を隠すことになった。最初は別々の部屋に寝ていた二人だが、周囲に追い詰められた状況の中でいつとはなくごく自然に身体を寄せて、寝床をともにするようにもなった。
これからどうすればいいのだろうか…。幸一は心の中で呟いた。
多恵子もすでに四十代半ば。これからの生活をどうしていくのか…。今度のことがなければ、規定の退職金も出せた。それがいまや、当座の給料さえ払えるかどうか…。
今や、多恵子の居候のような、紐のような自分。何がしてやれるだろうか…。
とふと思った。そうだ生命保険だ。絵理が生まれたとき、自分の万一に備えて、少ない給料の中から目一杯掛けてきた。確か三千万ほどだ。受取人は絵理だ。そのままにしてある。あの名義を替えてやろう…。今は、自分を支えてくれるのは多恵子一人だけなのだ…。
そして自分が死んでしまえばいいのだ。もう、何だか生きていくのに疲れた…。これからどうせ生きていたっていつ返せるか当てもない巨額の負債。債権者に追い回され、息をひそめて生きていくのだ…。そんな惨めな人生、真っ平ごめんだ。このへんで一思いに清算できるものなら、決して未練は無い…。
いや、今の多恵子には多少の未練はある。だが、男と女、一度身体を合わせてしまえば、後はお互い段々色褪せてしまうばかりではないか…。別れた昌枝とのように…。それなら今、多少ともお互いの温もりに愛着と未練が残るうちに、きっぱり思い切るのも…。
その死に場所はどこにしよう…。そうだ、いつか青梅街道を塩山へ抜けようとして、偶然迷いこんで怖い思いをしたあそこがいい。あの一之瀬林道の目も眩むような崖から谷底へ自分だけ車ごと突っ込もう。
あそこなら人知れず確実に死ねる…。この墓参りを終えたら、途中の中央線の駅で多恵子だけ何か理由をつけて降ろし、自分だけでそこへ向おう…。
こんなことを心中とつおいつしている間に車は穴山に近い韮崎インターに近づいた。
インターを出て途中のJAの売店で花と線香を買った。墓に詣でた。二人して手を合わせた。隣の多恵子は果たしてこの父の墓に何を語りかけたのだろうか…。多恵子にとって、父はどういう存在だったのだろうか…。身近な女性には直ぐ好意を抱いてしまう父だ…。
寺を出ると、春の日は真上にあった。薄い雲を通して真珠色の柔らかな陽光が二人を包む。二人は空腹を覚えた。寺のそばに簡素な鉱泉宿があった。休憩もどうぞとある。そこで軽い昼食を頼み、食後小一時間ほど仮眠した。レジをすますと、おかみが云った
「お客さま、新府のお花、見られました?今が一番見頃ですよ。お帰りに是非一目お立寄りになったらいかがですか…」と勧めた。
幸一は内心思った。「この世の花の見納めか…。それも好いな…」と。宿を出て教えられた道を南へ走った。新府城跡はすぐだった。城跡の案内標識の下に駐車場がある。
車を降りて二人は前方の杉や赤松に覆われ小高くなった丘に向かった。道路と直角にまっすぐな急傾斜の狭い石段の前にでた。その石段を登る。傾斜がきつい。幸一は後に続く多恵子に「大丈夫…」と声をかけた。「ええ,平気、平気」と元気に応えた。
ようやく上りきると正面に古びた社殿がある。その左側の広場には四角な本丸の低い土手沿いに植えられた十数本の桜が満開の花盛りだ。見上げる空を蔽いつくすかに広げた枝々から花びらが絶えまなく吹雪のように舞い落ちる。
その中を、花を見上げつつゆっくり歩む。古びた石の柵に囲われた一郭にでた。中には中央のひときわ太い石柱を挟んで横一列に数本の石柱が立ち、それぞれに彫られた人名がところどころ朽ちている。
そばの説明版を一読する。天正十年(一五八二)、三月三日、この城を捨てて滅んだ城主武田勝頼主従を記念するものだ。
旧暦の三月三日は、新暦の四月初旬、ちょうど今頃の桜と桃の花の季節だ。
勝頼はそのとき、まだ三十七歳。男盛りだ。その嫡子信勝は若干十七歳。勝頼夫人北條氏政の妹は、十九歳。それが皆、この城を出て旬日もたたない三月十一日、ここから四十キロ先の甲府盆地の出口、田野の地で悉く滅んだ。新羅(しんら)三郎義光以来二十代の名門武田家はここに滅亡したという。
幸一は、その悲運が今の自分の置かれている境涯に二重写しとなって身に沁み、勝頼の最後に深い共感と興味を覚えた。勝頼もまた正妻の嫡男としてではなく、義兄、義信の非業の死の後、急遽、父信玄により、周囲の反対を封じて後継ぎに指名されたのだ。その勝頼がどうしてまだ三十七歳という若さで滅びざるをえなかったのか…。
幸一の脳裏に解き明かしてみたい大きな謎が湧いた。その思いを抱きつつ周りを巡る。
記念碑の背後に出た。そこは城祉の北の境界だった。眼下は急峻な土手となり、眺望が大きく開けている。正面一面には淡いピンクの桃の花の絨毯。その果てに屹立した鑿(のみ)の刃を並べたような八ヶ岳連峰が青く霞んでいる。
目を左に移すと足元の大地が大きく引き裂かれ、崖下に釜無川が濃緑の細い流れに白く小さな波頭をきらめかせ、北から南へ流れ奔しる。その対岸には、どっしりとした山塊が連なり、見上げる頂には鳳凰三山の嶺々が残雪に白く輝いている。
幸一は、この景観を一望して、何故か久しく覚えたことの無い高揚した気分になった。
勝頼のことをもっと詳しく知りたくなった。勝頼のことを書いた本が読みたい。多恵子に提案した。さっきの宿でもう一泊していこうか…。俺、勝頼のことがもっと知りたくなった…と。陽はすでに西に傾いていた。幸一は財布からレシートを取り出し、先ほどの宿に電話した。お待ちしていますとのことだ。
宿に入る前に韮崎の街に出て、本屋を探し「新府城と武田勝頼」を買った。
宿でその夜、「先に休ませてもらう…」という多恵子をおいて、座敷の縁側の椅子でウイスキーグラスを手元に、ほとんど徹夜で拾い読みした。そして仕事用のノートパソコンを開き、インターネットで「勝頼落去の道筋」というページを見た。
あくる朝、宿を出ると、多恵子に話して、帰途、ネットでみた新府から勝頼主従最後の地、景徳院までたどってみることにした。
今朝も好天だ。昨日の新府城跡の前を過ぎ、七里岩ラインを南へ下る。韮崎インター手前が権現沢。そこを右折し果樹畑の中の曲がり道を走る。小さな塚がある。「回看(みかえり)塚」だ。傍の説明板に、ここで一行が塩川を挟んだ対岸の新府城の燃える煙に涙したとある。さらに南に走る。富士山が正面に大きく聳える。一行は、早暁、この富士をどんな思いで仰ぎみて過ぎただろうか。その先は竜地。富士を右に見つつ甲府市街へ…。途中、荒川を渡れば千塚。古府中、武田神社だ。なるほど、ここは背後を低い山で囲まれ前面には大きな川もない。大軍に攻められたらひとたまりもない。勝頼が無理を承知で急遽新府に築城した気持ちがわかる。一行はここで一休みし、石和で笛吹川を渡り、甲州街道を東に向ったという。春の日が暮れなずむ頃、甲斐大和の入口、大善寺に着く。ここまで約四十キロ、勝頼夫人、そのお付の侍女を伴なっての道中の難渋はいかばかりであっただろうか…。
大善寺には勝頼の乳母だった理恵尼が居て、勝頼一家を手厚くもてなし、その悲運を共に嘆いたという。勝頼一家にとってここでの夜がまさに人らしく過ごした最後の夜だったのでは…。この寺にはこのときの理恵尼の思いを綴った理恵尼記が遺されている。
そして翌日、一行はその先、駒場の宿(しゅく)で小山田の迎えを待った。だが迎えは一向にこない。七晩過ぎた。裏切られたのだ。
勝頼主従は一縷の望みを断たれ、最後の死に場所を求めて、武田家ゆかりの天目山醒雲寺を目指した。だがその時、手前の田野で、信長の大軍に追いつかれ、進退きわまり勝頼主従四十一人が自刃し、他に侍女ら二十七人が日川に入水して果てたという。
その田野の景徳院に着いた。夕闇が迫っていた。今朝からの「勝頼落去」の後追いで疲れがどっと出た。幸一はシートを倒して、多恵子に「少し寝かせて…」と背を伸ばした。
目の前に誰かが、小ぶりな石に腰を下ろしてじっとこちらを見ている。よく見ると鎧武者のようだ。左手に穂先のない槍を杖代わりに抱え込んでいる。兜のない頭髪はザンバラで青白い頬には黒っぽく血飛沫(しぶき)が点々と飛び散っている。右手は鎧の袖ごと斬りおとされて無い。その右足元にはやや小柄な鎧武者が倒れこんでいる。嫡子信勝だろうか。見ればこちらは首が無い。
幸一は「何だ、これは…。俺は一体どこに居るんだ…。」と小さく叫んだ。
目の前の武者が細い目をうっすらと開けて何か呟くのが聴こえた。
「儂(わし)は…、どこで読み間違えたんだ…。先ずは、父信玄の遺言『三年は吾が死を隠せ。その間、内を固めて外に出るなと…。』これに叛いたからか…。
二つには、重臣どもの反対を押し切り、長篠を奪還すべく大戦(おおいくさ)をしかけ、父信玄股肱の歴戦の強者(つわもの)の殆どを戦死させたからか…。
三つ目には、一族重臣の反対を押して古府中を捨て新府に城を築かせ皆を無理やり移らせようとしたからか…。
最後に、信長に攻め込まれ、一族に悉く裏切られるなかで、智将真田昌幸の上野岩櫃(こうずけいわびつ)のわが城へとの進言をしりぞけ、譜代の臣、小山田を頼り岩殿城への道を選んだからか…。
今、思い返せば、儂は後を継いで以来、二つに一つの場で全て負の方へ負の方へと選びとってきた…。それもこれも一門や譜代の重臣から軽く見られまいとして儂は焦った。儂は、自分で自分を崖淵(がけっぷち)へと崖淵へと、追い込んでいったのだ…。そして最後に儂の前途を断ち切ったのは、信長の父信玄への怨念だ。信長は信玄が突如同盟を破り、背後から襲い掛かったことを激しく怒り恨んだのだ。以来、信長は武田討滅を固く誓ったのだ…。」
そこまで語り終えると、勝頼らしき武者の首が前へがくりと落ち夕闇に消えた…。
同時に誰かの重苦しい呟きを聴いた…。
「お前は生きよ。お前は儂と違い、自らの定めにより誰かに死ぬように逼られてはおらぬ…。お前は生きられるのだ…。」
幸一は、襟元のひんやりとした渓谷の冷気で目ざめた。何か怖い夢を見たようだ…。彼は、傍らの多恵子に声をかけた。
「一日、すまなかったね。勝手に引っ張りまわして…。疲れたろう…。」
「ええ、少しね…。でも、好かった…。なんか歴史上の人って、遠い人と思っていたけど、こうして貴方と一緒にお話し聴きながら歩いてみて身近に感じたわ…。私、女だから、勝頼夫人にすごく同情しちゃう…。まだ十九歳だったんでしょ…。それが、勝頼が兄の北條氏政のところへ帰れというのに、あえて一緒の死を選んだんでしょ。勝頼は、無念な最後だったけど、でも最愛の夫人が一緒に死んでくれて救われたんじゃないかしら。
今日一日貴方と回ってみて、私、貴方についていこうと決めたの…。貴方が嫌でなければ…。私、父を知らないの。母はいくら訊いても何も云わずに亡くなったから…。」
「そうか…。俺たちお互いに二人きりなんだ。頼むよ…。苦労かけるけど…。今夜は久しぶりに景気よく一杯やろう。この先の嵯峨塩に鉱泉の一軒宿があるそうだ。」
多恵子は、幸一に日ごろの爽やかな表情が戻ったのを見て安心したように小さく頷いた。
夜の闇の奥に微かな宿の灯りが見えた。
新年明けましておめでとうございます
私の拙いブログ、お読みいただいている皆さまに心から感謝申し上げます。
これまで、時事問題を中心に日ごろ考え思ったことを、野猿や雉ぐらいしか訪問者の居ない山家住まいの徒然あれこれ書いてまいりましたが、何がどうなるわけでもなく虚しさが日に日にましてまいりました。
そこで、この頃、小説なるものを書いてみたくなり、二、三習作を試み、地元紙の新春文芸作品に応募したところ、敢えなく落選の憂き目をみました。
だが、せっかく一生懸命書いた作品、このまま捨ててしまいますのも惜しく、ここに恥を忍んで掲載させていただくこととしました。
ご一読くださいました方、何かご感想、ご教示をいただければ誠に幸いに存じます。
なにとぞよろしくお願い申しあげます。
「勝頼幻影」
ドンドン…、ドンドン…。マンションのドアを誰かが激しく敲いている。何だ!誰だ!こんな時間に…。幸一は布団の上に跳び上がるように腰を起こした。左脇で多恵子が掛け布団の襟元をぎゅっと握り締めながら「今頃誰…」と不安そうに幸一を見上げた。
もしかして…あいつ等では…。また激しくドアを敲く。玄関ドアの前へ小走りに身を寄せた。ドアの覗き穴から外を窺う。小さな球形の視界。パンチパーマにサングラスのいかつい顔が迫る。背後にも人影が動く。
「居るんだろう…。さっさとここを開けねーか…」
幸一は多恵子の傍へ走り戻った。
「あいつらだ。手形の取立てだ…。こんな時間に押しかけてくるなんて…。」
と今度は、ドアでキューンと悲鳴のような金属音がした。ディスクグラインダーか何かでドアに穴を開けるらしい…。
「警察に電話して…」
幸一が切羽詰って低く、短く云った。
多恵子が震える指で携帯のボタンを押した。グラインダーの狂ったような金属音とドアを蹴る音が激しく交錯する。幸一の大きな背中に身を寄せた多恵子の微かな震えが伝わる。
ほどなくパトカーのサイレンが近づいてきた。ドリルの音がやんだ…。外廊下を慌てて駆け去っていく靴音があっという間に消えた。
代わりに警察官がドアをノックした。
「どうしました」
幸一はドアを開けて狭い玄関に、外に立つ二人を招じ入れた。
「実は恥ずかしい話しですが、私の会社が倒産して、不渡り出してしまい、その取立ての嫌がらせです…。」
「それは大変ですね。とりあえず器物損壊で調書取らせてください…。」。
二人の警察官は現場のドアに付けられた傷跡を写真に撮るなどし、型どおりの調書を作成すると、今夜はまた直ぐ同じことはしないでしょう、何かあったらこのあたりをパトロールしているので通報するようにと、云い置いて戻っていった。両隣の部屋で何事かと様子を窺っている気配が伝わってきた。
翌朝、レンタカー会社に多恵子の名前で予約をいれ、二人は借りた車に身の回りの小物を詰めたバック二つを後部座席に、八王子インターから中央高速を西に向った。
前方の風景が左右に切り開かれていく。なだらかな山並みが明るい空の下に横にひろがり、山肌が柔らかな萌黄色に霞んでいる。
幸一は、ハンドルを手に、今度のことがなければ、多恵子と初めての少しばかり心浮くドライブだったのだが…と思う。それが、とんだ取立て屋からの逃亡ドライブとは…。彼女は隣のシートに深く身を沈めて座り、黙って前を見ている。何を思っているのだろうか。昨夜の騒ぎで、自分の長年勤めてきた会社の倒産という現実の厳しさ、そしてこれからどうなるのか不安で一杯なのだろうか…。
その気持ちを軽くほぐすように声をかけた。
「取りあえず、親父(おやじ)とお袋の墓参りでもしてみようかな…。春の彼岸にも行ってやれなかったし…。お参りすれば、何か好い智恵も湧くんじゃないかな…」
「そうねー。こうゆう時こそ、好いことかもね…」
幸一のその一言に多恵子はいく分気を軽くしたようだ。だが、また沈黙が続いた。
自然、幸一の頭には、昨夜の事態に至ったあれこれがフラッシュバックとなって浮かぶ。
叔父で専務の清水賢吉のしてやったと言いたげな高笑い。叔父は、父源三が腹違いの兄源太郎の事故死の後を、急遽周囲の反対を押し切り、愛人の子であり、しかも畑違いの市役所勤めを辞めさせ、認知してまで自分に後を継がせたときから面白くなかったのだ。
賢吉のやったことはともかく、その気持ちは理解できなくもなかった。叔父は、父源三が山梨の穴山の小さな集落の高等小学校を終え、八王子の大工棟梁の家に住み込み、二十四、五でそこを飛び出し、独立して戦後の焼け跡のバラック建築で大儲けし、三十そこそこで株式会社清水住建を設立して以来、十歳年上の兄を助けてきたのだ。会社はその後高度経済成長に平仄を合わせたように急成長した。その陰には賢吉の貢献も大いにあったのだ。だから、跡取りの源太郎が亡くなったあとは当然、自分が指名されるものと期待していたに違いない。それが、予想外の結果になったのだ。父は血筋を選んだのだ。
当時、幸一は若さからか、叔父の複雑な思いまで考える余裕はなかった。ただ、父から口説かれたとき、自分でも役所に入って十年余り、役所での仕事に飽き足りないものを感じていた。このままここで、ただ一回限りの人生終わっていいのだろうかと…。
大きな組織の中では、何一つとして、これは自分がやったという達成感がなかった。
それにまた、若くして職場結婚した妻の昌枝が、お互いの性格の違いから何かと衝突するようになり、加えて母との間でお決まりの嫁姑の衝突から、ある日一人娘の七才になった絵里を連れて家を出ていき、そのまま離婚した。その三年後に母も乳がんで亡くなり、幸一は母の遺した家に独り暮らしの身だった。
だから、父から、突然思いがけなくも後を継いでくれないかと云われたとき、これはこれで自分の人生の一つの転機かと思えた。そして、父の会社に入り、営業を担当して十年余り、一生懸命に働いてきた。新築ブームの蔭りから、いち早くリフォーム部門を立ち上げそれなりの業績もあげてきた。そんな、これからと云うとき、父が脳溢血で急逝した。
父亡き後、幸一は五十人余りの社員の生活を担う責任の重さを感じ、一層社業に励んだ。ところが父の三回忌を終えたばかりの、この正月明け、事態は急変した。
専務の清水賢吉が突然、会社の預金通帳とともに姿を隠した。あっというまに噂が四方に飛んだ。中小企業の清水住建にとってそれは致命的だった。たちまち銀行の貸付が閉鎖され、下請けへの手形が不渡りとなった。「支払いどうするんだ。金よこせ…」の電話の殺到…。
そんな中で、親しい知人が智恵をかしてくれた。少しでも手元の現金があったら他人名義の口座へ変えてしまえ。でないと丸裸になって動きがとれなくなるぞと。
咄嗟に多恵子の顔が浮かんだ。彼女は会社で総務関係の仕事を一人で切り盛りしていた。手が空くと、いつもさりげなく、コーヒーを淹れてくれたり、コンビニでお握りを買ってきてくれたりした。そんな多恵子に幸一は昌枝にない優しさを感じつつ、次第に心密かに惹かれていた。彼女は会社から二駅ほどの私鉄駅近くの小さなマンションに、何故か独りで暮らしていた…。
いつも地味な服装で、長めの髪を後ろでリボン止めしたポニーテールが、細面の奥二重の優しげな顔によく似合った。
事情を話して彼女に新規口座を作ってもらい、僅かにかき集めた売掛金の百数十万円を入金し、彼女名義でカードも作った。幸一にとってこれが当面の命綱だった。多恵子は、彼の身を心配して、私のところ二部屋あるのでよかったら暫くうちへ来ては…と申し出てくれた。それは、心身ともに疲労困憊していた彼にとって、地獄に仏だった。
「好いのかな…。迷惑かけるんじゃないかな…。」
「大丈夫。身体さえちゃんとしていれば…何とかなるんじゃーない。」
こうして、多恵子の好意に甘える形で2Kのマンションの一室に身を隠すことになった。最初は別々の部屋に寝ていた二人だが、周囲に追い詰められた状況の中でいつとはなくごく自然に身体を寄せて、寝床をともにするようにもなった。
これからどうすればいいのだろうか…。幸一は心の中で呟いた。
多恵子もすでに四十代半ば。これからの生活をどうしていくのか…。今度のことがなければ、規定の退職金も出せた。それがいまや、当座の給料さえ払えるかどうか…。
今や、多恵子の居候のような、紐のような自分。何がしてやれるだろうか…。
とふと思った。そうだ生命保険だ。絵理が生まれたとき、自分の万一に備えて、少ない給料の中から目一杯掛けてきた。確か三千万ほどだ。受取人は絵理だ。そのままにしてある。あの名義を替えてやろう…。今は、自分を支えてくれるのは多恵子一人だけなのだ…。
そして自分が死んでしまえばいいのだ。もう、何だか生きていくのに疲れた…。これからどうせ生きていたっていつ返せるか当てもない巨額の負債。債権者に追い回され、息をひそめて生きていくのだ…。そんな惨めな人生、真っ平ごめんだ。このへんで一思いに清算できるものなら、決して未練は無い…。
いや、今の多恵子には多少の未練はある。だが、男と女、一度身体を合わせてしまえば、後はお互い段々色褪せてしまうばかりではないか…。別れた昌枝とのように…。それなら今、多少ともお互いの温もりに愛着と未練が残るうちに、きっぱり思い切るのも…。
その死に場所はどこにしよう…。そうだ、いつか青梅街道を塩山へ抜けようとして、偶然迷いこんで怖い思いをしたあそこがいい。あの一之瀬林道の目も眩むような崖から谷底へ自分だけ車ごと突っ込もう。
あそこなら人知れず確実に死ねる…。この墓参りを終えたら、途中の中央線の駅で多恵子だけ何か理由をつけて降ろし、自分だけでそこへ向おう…。
こんなことを心中とつおいつしている間に車は穴山に近い韮崎インターに近づいた。
インターを出て途中のJAの売店で花と線香を買った。墓に詣でた。二人して手を合わせた。隣の多恵子は果たしてこの父の墓に何を語りかけたのだろうか…。多恵子にとって、父はどういう存在だったのだろうか…。身近な女性には直ぐ好意を抱いてしまう父だ…。
寺を出ると、春の日は真上にあった。薄い雲を通して真珠色の柔らかな陽光が二人を包む。二人は空腹を覚えた。寺のそばに簡素な鉱泉宿があった。休憩もどうぞとある。そこで軽い昼食を頼み、食後小一時間ほど仮眠した。レジをすますと、おかみが云った
「お客さま、新府のお花、見られました?今が一番見頃ですよ。お帰りに是非一目お立寄りになったらいかがですか…」と勧めた。
幸一は内心思った。「この世の花の見納めか…。それも好いな…」と。宿を出て教えられた道を南へ走った。新府城跡はすぐだった。城跡の案内標識の下に駐車場がある。
車を降りて二人は前方の杉や赤松に覆われ小高くなった丘に向かった。道路と直角にまっすぐな急傾斜の狭い石段の前にでた。その石段を登る。傾斜がきつい。幸一は後に続く多恵子に「大丈夫…」と声をかけた。「ええ,平気、平気」と元気に応えた。
ようやく上りきると正面に古びた社殿がある。その左側の広場には四角な本丸の低い土手沿いに植えられた十数本の桜が満開の花盛りだ。見上げる空を蔽いつくすかに広げた枝々から花びらが絶えまなく吹雪のように舞い落ちる。
その中を、花を見上げつつゆっくり歩む。古びた石の柵に囲われた一郭にでた。中には中央のひときわ太い石柱を挟んで横一列に数本の石柱が立ち、それぞれに彫られた人名がところどころ朽ちている。
そばの説明版を一読する。天正十年(一五八二)、三月三日、この城を捨てて滅んだ城主武田勝頼主従を記念するものだ。
旧暦の三月三日は、新暦の四月初旬、ちょうど今頃の桜と桃の花の季節だ。
勝頼はそのとき、まだ三十七歳。男盛りだ。その嫡子信勝は若干十七歳。勝頼夫人北條氏政の妹は、十九歳。それが皆、この城を出て旬日もたたない三月十一日、ここから四十キロ先の甲府盆地の出口、田野の地で悉く滅んだ。新羅(しんら)三郎義光以来二十代の名門武田家はここに滅亡したという。
幸一は、その悲運が今の自分の置かれている境涯に二重写しとなって身に沁み、勝頼の最後に深い共感と興味を覚えた。勝頼もまた正妻の嫡男としてではなく、義兄、義信の非業の死の後、急遽、父信玄により、周囲の反対を封じて後継ぎに指名されたのだ。その勝頼がどうしてまだ三十七歳という若さで滅びざるをえなかったのか…。
幸一の脳裏に解き明かしてみたい大きな謎が湧いた。その思いを抱きつつ周りを巡る。
記念碑の背後に出た。そこは城祉の北の境界だった。眼下は急峻な土手となり、眺望が大きく開けている。正面一面には淡いピンクの桃の花の絨毯。その果てに屹立した鑿(のみ)の刃を並べたような八ヶ岳連峰が青く霞んでいる。
目を左に移すと足元の大地が大きく引き裂かれ、崖下に釜無川が濃緑の細い流れに白く小さな波頭をきらめかせ、北から南へ流れ奔しる。その対岸には、どっしりとした山塊が連なり、見上げる頂には鳳凰三山の嶺々が残雪に白く輝いている。
幸一は、この景観を一望して、何故か久しく覚えたことの無い高揚した気分になった。
勝頼のことをもっと詳しく知りたくなった。勝頼のことを書いた本が読みたい。多恵子に提案した。さっきの宿でもう一泊していこうか…。俺、勝頼のことがもっと知りたくなった…と。陽はすでに西に傾いていた。幸一は財布からレシートを取り出し、先ほどの宿に電話した。お待ちしていますとのことだ。
宿に入る前に韮崎の街に出て、本屋を探し「新府城と武田勝頼」を買った。
宿でその夜、「先に休ませてもらう…」という多恵子をおいて、座敷の縁側の椅子でウイスキーグラスを手元に、ほとんど徹夜で拾い読みした。そして仕事用のノートパソコンを開き、インターネットで「勝頼落去の道筋」というページを見た。
あくる朝、宿を出ると、多恵子に話して、帰途、ネットでみた新府から勝頼主従最後の地、景徳院までたどってみることにした。
今朝も好天だ。昨日の新府城跡の前を過ぎ、七里岩ラインを南へ下る。韮崎インター手前が権現沢。そこを右折し果樹畑の中の曲がり道を走る。小さな塚がある。「回看(みかえり)塚」だ。傍の説明板に、ここで一行が塩川を挟んだ対岸の新府城の燃える煙に涙したとある。さらに南に走る。富士山が正面に大きく聳える。一行は、早暁、この富士をどんな思いで仰ぎみて過ぎただろうか。その先は竜地。富士を右に見つつ甲府市街へ…。途中、荒川を渡れば千塚。古府中、武田神社だ。なるほど、ここは背後を低い山で囲まれ前面には大きな川もない。大軍に攻められたらひとたまりもない。勝頼が無理を承知で急遽新府に築城した気持ちがわかる。一行はここで一休みし、石和で笛吹川を渡り、甲州街道を東に向ったという。春の日が暮れなずむ頃、甲斐大和の入口、大善寺に着く。ここまで約四十キロ、勝頼夫人、そのお付の侍女を伴なっての道中の難渋はいかばかりであっただろうか…。
大善寺には勝頼の乳母だった理恵尼が居て、勝頼一家を手厚くもてなし、その悲運を共に嘆いたという。勝頼一家にとってここでの夜がまさに人らしく過ごした最後の夜だったのでは…。この寺にはこのときの理恵尼の思いを綴った理恵尼記が遺されている。
そして翌日、一行はその先、駒場の宿(しゅく)で小山田の迎えを待った。だが迎えは一向にこない。七晩過ぎた。裏切られたのだ。
勝頼主従は一縷の望みを断たれ、最後の死に場所を求めて、武田家ゆかりの天目山醒雲寺を目指した。だがその時、手前の田野で、信長の大軍に追いつかれ、進退きわまり勝頼主従四十一人が自刃し、他に侍女ら二十七人が日川に入水して果てたという。
その田野の景徳院に着いた。夕闇が迫っていた。今朝からの「勝頼落去」の後追いで疲れがどっと出た。幸一はシートを倒して、多恵子に「少し寝かせて…」と背を伸ばした。
目の前に誰かが、小ぶりな石に腰を下ろしてじっとこちらを見ている。よく見ると鎧武者のようだ。左手に穂先のない槍を杖代わりに抱え込んでいる。兜のない頭髪はザンバラで青白い頬には黒っぽく血飛沫(しぶき)が点々と飛び散っている。右手は鎧の袖ごと斬りおとされて無い。その右足元にはやや小柄な鎧武者が倒れこんでいる。嫡子信勝だろうか。見ればこちらは首が無い。
幸一は「何だ、これは…。俺は一体どこに居るんだ…。」と小さく叫んだ。
目の前の武者が細い目をうっすらと開けて何か呟くのが聴こえた。
「儂(わし)は…、どこで読み間違えたんだ…。先ずは、父信玄の遺言『三年は吾が死を隠せ。その間、内を固めて外に出るなと…。』これに叛いたからか…。
二つには、重臣どもの反対を押し切り、長篠を奪還すべく大戦(おおいくさ)をしかけ、父信玄股肱の歴戦の強者(つわもの)の殆どを戦死させたからか…。
三つ目には、一族重臣の反対を押して古府中を捨て新府に城を築かせ皆を無理やり移らせようとしたからか…。
最後に、信長に攻め込まれ、一族に悉く裏切られるなかで、智将真田昌幸の上野岩櫃(こうずけいわびつ)のわが城へとの進言をしりぞけ、譜代の臣、小山田を頼り岩殿城への道を選んだからか…。
今、思い返せば、儂は後を継いで以来、二つに一つの場で全て負の方へ負の方へと選びとってきた…。それもこれも一門や譜代の重臣から軽く見られまいとして儂は焦った。儂は、自分で自分を崖淵(がけっぷち)へと崖淵へと、追い込んでいったのだ…。そして最後に儂の前途を断ち切ったのは、信長の父信玄への怨念だ。信長は信玄が突如同盟を破り、背後から襲い掛かったことを激しく怒り恨んだのだ。以来、信長は武田討滅を固く誓ったのだ…。」
そこまで語り終えると、勝頼らしき武者の首が前へがくりと落ち夕闇に消えた…。
同時に誰かの重苦しい呟きを聴いた…。
「お前は生きよ。お前は儂と違い、自らの定めにより誰かに死ぬように逼られてはおらぬ…。お前は生きられるのだ…。」
幸一は、襟元のひんやりとした渓谷の冷気で目ざめた。何か怖い夢を見たようだ…。彼は、傍らの多恵子に声をかけた。
「一日、すまなかったね。勝手に引っ張りまわして…。疲れたろう…。」
「ええ、少しね…。でも、好かった…。なんか歴史上の人って、遠い人と思っていたけど、こうして貴方と一緒にお話し聴きながら歩いてみて身近に感じたわ…。私、女だから、勝頼夫人にすごく同情しちゃう…。まだ十九歳だったんでしょ…。それが、勝頼が兄の北條氏政のところへ帰れというのに、あえて一緒の死を選んだんでしょ。勝頼は、無念な最後だったけど、でも最愛の夫人が一緒に死んでくれて救われたんじゃないかしら。
今日一日貴方と回ってみて、私、貴方についていこうと決めたの…。貴方が嫌でなければ…。私、父を知らないの。母はいくら訊いても何も云わずに亡くなったから…。」
「そうか…。俺たちお互いに二人きりなんだ。頼むよ…。苦労かけるけど…。今夜は久しぶりに景気よく一杯やろう。この先の嵯峨塩に鉱泉の一軒宿があるそうだ。」
多恵子は、幸一に日ごろの爽やかな表情が戻ったのを見て安心したように小さく頷いた。
夜の闇の奥に微かな宿の灯りが見えた。



















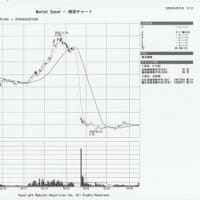
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます