
「アースマインド・・地球は人類の廃棄を意図し始めた」という、ポール・デヴェロー、ジョン・スティール、デヴィッド・クブリンという3人の共著の本のご紹介を続けます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
アイルランドでは、特定の日になると太陽光線が塚の内部の岩の彫刻にレーザーのような光線を投げかけたり、塚を取り巻く彫刻の上に影を伸ばす、新石器時代の遺跡が発見された。
ニューメキシコ州・チャコ・キャニオンにある石板の割れ目からは、太陽光線が、石に刻まれたらせんデザインに作用して、夏至・冬至・春分・秋分を正確に記録することが知られている。
この遺跡は、1000年以上前に滅亡したアナサジ族が残した。
古い土台の上に建っているが、現存するナバホ族の伝説によれば、それは本物の道ではなく、アナサジ族が「目に見えない者と一緒に旅をする」トンネルなのだという。
カリフォルニアの山脈や、他の南西部の州にはインディアンが謎の直線を残している。
これらの線のいくつかは、山頂から山頂まで、ずれもなく続いている。
なぜこれらが作られたのか、誰にも分からない。
メキシコでは、ユカタン半島や、さらに南下した地域に、マヤ族の直線の儀式用道路がある。
南米では、ペルーとボリビアのアンデス山脈に何キロも続く完全にまっすぐな道がある。
いわゆるナスカ・ラインだ。
これらのラインに沿って、寺院遺跡が点在している。
クスコから発するラインは、皇帝の儀式に用いられ、ラインに沿って聖地の遺跡が並んだ。
これらは、研究者が赤外線写真を撮るまで、直線であることがわからなかった。

年代的にも地理的にも大きく離れた数々の伝統社会に、なぜこれらふしぎな直線が築かれたのか、今日誰も本当のことがわからない。
これらはなんらかの魔力を持つラインで、「魂のライン」であると考えられる。
古代遺跡の位置で重要な特徴は、それがある種の地理的特徴、特に断層、地殻内の割れ目に近いことである。
たとえばアイスランドでは10世紀の国家の遺跡が、北米とユーラシアの構造プレートの間にできた断層の上に建てられている。
アメリカのオハイオ州では、2000年前のサーペントマウンドという400メートルに及ぶ説明のつかない土の建造物が建てられている。
これらの場所は、火山活動や流星の衝撃のために、断層の多い、非常に圧縮された地域なのだ。
存在そのものが、断層によってできている遺跡もある。
イギリスのバースでは、新石器時代初期からローマ・イギリス時代まで神聖であるとみなされていた温泉が、断層の上にある。
ギリシアにあるデルフォイの神託所は、断層から立ち昇る〝精神に影響を与える煙″に依存していた。
アリゾナ州のアナサジは、24時間周期で空気を吹き出したり、吸い込んだりする、断層に関係した空気穴の周囲にある。
昔の人々が地理を知っていたのは確かである。
彼らは石器時代には、石器にするためのフリントとその他の石を探して掘ることができたし、青銅器時代や鉄器時代には、鉱脈の位置を知ることができたのである。
しかし、なぜ断層をみつけて、その上や付近に聖地を建てるのか?
おそらく断層付近でおこる、特殊なエネルギー効果に関連している。
断層とは、地殻の中で巨大な力が働く場所なので、比較的上面近くに様々な鉱脈が多数混在していることが多い。
これが局地的な電磁異常や、地下水レベルの変化や、時には重力の変化を引き起こすのだ。
また断層は、地形の弱点もあらわす。
構造の圧力やひずみによって、起きやすいのである。
これが結果として、時折、地震となる。
段切面は収縮したり弛緩したりしている。
これによって、電磁場が移動する。
多量の岩が互いに衝突すると、時に圧電気を生む。
これはクオーツやクオーツを帯びた岩にかかる圧力によって生まれる電気である。
こうした構造の活動は、このような地域に湧き出る温泉に、放射性ラドンガスやその他の化学物質やガスを放出する時がある。
したがって断層ゾーンは特別なエネルギー地域なのである。

こうした地域は別のエネルギー現象、すなわち〝奇妙な光”を生じる傾向もある。
18世紀には、銅の鉱脈をみつける一つの手段として、採掘者が何百年にも亘って、地面から現れる〝光の玉”を利用していたと記録されたものもある。
ウェールズでは、今でも丘から時折現れる〝青い光”が鉱脈の存在を知らせるという言い伝えがある。
昨今では、これらを「UFO」と解釈する人々も多い。
しかし少数の研究者は、このようなエネルギー現象は、電磁気か未知のエネルギーの変わった形態であろうと考えている。
これら地球の光は、常に存在していたに違いなく、今日の一般的見方で「UFO」とされているように、過去の伝統社会でも、これらを自らの世界観に組み込んで、「霊魂」、「妖精」、「別世界への入り口」、「予言に用いる現象」などとみなしていた。
これらの〝光”に対する現代の我々の態度・・すなわち地球外のものはそもそも存在しないという態度・・は、我々の精神が地球や自然の、より精妙なプロセスから疎外されている証拠かもしれない。
この〝光”は、知覚をもった生きた惑星の性質を理解する上で重要な手がかりになるかもしれない。
地球の各圏は、非常に微妙なレベルでも相互に関連しており、地球は1個の脈動し、共鳴する有機体なのだ。
こうした見方をすると、我々は〝地球の上”ではなく、〝地球の中”に生きているのがわかる。
夜、星を見上げる時でも、地球の密度の薄い圏を通して見ているのである。
我々自身が、地球の「顔」の一部であり、つまり一つの現れなのである。
1854年、シアトル酋長はインディアンの伝統的知識をこう表現した。
・・・
我々は知っている。
地球が人間に属しているのではない。
人間が地球に属しているのだ。
我々は知っている。
あらゆるものが、家族をつなぐ血のように、つながっている。
あらゆるものが関連しているのだ。
・・・
地球との関連についての、このような伝統的な感じ方は、地球から消えていこうとしている。
しかし土壇場にきて、我々は過去の文化の中から、古代の知識を再び集めようとしている。
現代人の魂の内部で、回想のスピードは急激に早まっている。
皮肉なことに、地球から離れられるほどに技術の進歩が加速したおかげで、これまでにないスピードとスケールで互いにやりとりする手段が手に入ったのである。
これは情報テクノロジーと呼ばれるが、これ自体は手段にすぎない。
これをどう使うかが、肝心なのだ。
古代の知恵を完全に取り戻し、現代人に分かるように翻訳するには、物理的エコロジーも大切だが、それ以上のものを含めなければならない。
より深い面、精神や魂のレベルを除外してはならない。
これらも我らの遺産の一部、われわれの意識体験の一部だからだ。
(引用ここまで・写真(中)(下)は我が家のユリ)
*****
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「ナスカの地上絵(1)長さ50キロメートルの矢印を眺めたのは誰か?」(3)まであり
「ペルー・ナスカ 地上絵の直線は村落を結んでいる・・山形大・坂井教授が新説」
「4500年前の住人と岩絵・・河合隼雄のナバホへの旅(2)」(3)あり
「ホピの祭り・ヤヤ祭り(1)・・アニマルピープルと人間」
「ホピ族のペテログラフ(岩絵)・・吉田信啓氏「線刻文字の黙示録」(1)」(6)まであり
「地下世界とプラズマによる異次元・・飛鳥昭雄氏(3)」
「絶対的な善と悪、およびUFO・・グラハム・ハンコック・ダイジェスト(4)」(6)まであり
 「環境(ガイア)」カテゴリー全般
「環境(ガイア)」カテゴリー全般
















 写真(中)は「ボノボ」の群。からまった枝をみんなで外してあげている。
写真(中)は「ボノボ」の群。からまった枝をみんなで外してあげている。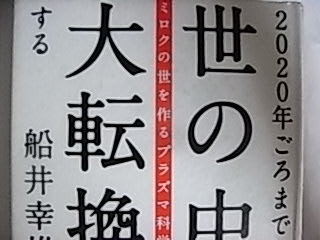
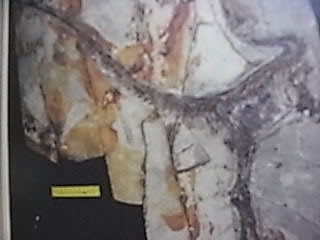
 wikipedia「パンゲア」より
wikipedia「パンゲア」より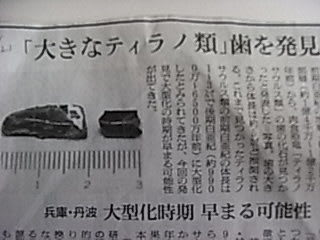





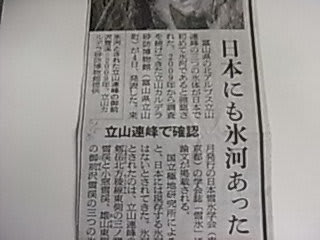





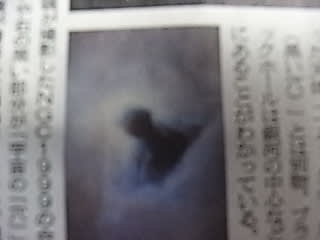




 「環境(ガイア)」カテゴリー全般
「環境(ガイア)」カテゴリー全般

 「スパコン駆使し結論」
「スパコン駆使し結論」


 wikipedia「植生」より
wikipedia「植生」より




