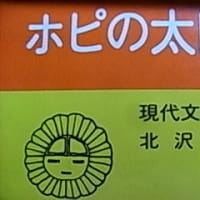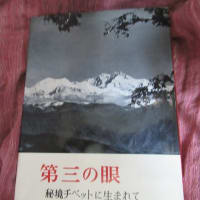朝日新聞「日曜版」・「日本人の起源」2011・05・01の記事です。
前にご紹介したマレーシアのニア洞窟探訪の記事の続きです。
・・・・・
「骨をよむ手がかりはDNA」
マレーシアから東京に戻った私は、国立科学博物館を訪ねた。
篠田謙一の研究室に向かう。
積み重ねられている大きなプラスチックのケースの中味は、江戸時代の人骨だという。
篠田のもとには、全国からさまざまな人骨が集まってくる。
沖縄・石垣島の白保竿根田原(しらほさおねたばる)の旧石器人。
富山市の小竹貝塚の縄文人。
東京・谷中の徳川家の墓地に埋葬されていた将軍の側室や子どもたち。
「私はよく“骨を読む”と言います。
骨からは、実にたくさんのことがわかる。
形態からは当時の人たちの姿形や生活習慣を、DNAからは彼らのルーツを読み取ることができますから」。
篠田はこのうち、古い人骨のDNAを調べる国内では数少ない研究者だ。
わずかでもDNAが残っていれば、それを手がかりに日本人の起源を探ることができる。
ここ20年ほどで急速に進んだ分野ゆえに、学会に大きな一石を投じることもある。
たとえば、縄文土器などの文化をもつ縄文人について、かつては「南方からやって来たほぼ均質な集団」というのが定説だった。
全国で出土した骨を元に、縄文人の顔つきを探ると、上下に短く幅が広いとか、彫りが深いといった共通の特徴があったからだ。
ところが、縄文人のDNAには別のストーリーが秘められていた。
2006年、篠田や山梨大教授らは北海道の縄文遺跡から出土した54体の骨のミトコンドリアDNAを分析。
その特徴をもとにグループ分けし、関東の縄文人のデータと比べてみた。
北海道の縄文人の6割を占める最大のグループは、関東では見られないものだった。
このグループはサハリンなど、現在の極東ロシアの先住民に目立つ。
2番目と3案目に多いグループも、カムチャッカ半島などの先住民に多い。
東北の縄文人も北海道と似たグループ構成だった。
対照的に関東の縄文人のミトコンドリアDNAを見ると、東南アジアの島々、中央アジア、朝鮮半島に住む現代人の特徴があった。
「北海道・東北と関東では違いが大きく、同じ縄文人とくくるのがためらわれるほどだ」と篠田は言う。
縄文人は「均質な集団」ではなく、日本列島の北と南でルーツが違っていた。
浮かびあがるのは、そんなストーリ―だ。
縄文時代、様々な人々がいろいろなルートで日本列島に入ってきたらしい。
アフリカから東南アジア、そして日本列島へ。
日本人の「祖先」のはるかな旅路の詳細は、骨の形や遺物を調べるだけではなかなか見えてこない。
いま、DNAを手がかりに、「祖先」の足跡が次第に明らかになりつつある。
篠田は言う。「私たちは、どこから来た何者なのか。それを知ることで、自分達がどこへ向かおうとしているかを確かめたい」
・・・・・
 {}「トヤマ・ジャストナウ・2014・02・05 小竹貝塚」
{}「トヤマ・ジャストナウ・2014・02・05 小竹貝塚」富山県文化振興財団 埋蔵文化財調査事務所は、日本海側最大級の貝塚である小竹貝塚(富山市呉羽町北・呉羽昭和町地内)の調査結果を発表した。
出土した人骨は91体。縄文時代前期の人骨が見つかった国内の遺跡の中では最多。
DNA鑑定で、南方系と北方系の異なる起源を持つ人たちが一緒に暮らしていたことがわかった。
多くの遺物によって、縄文人のルーツや生活ぶりを探る、大きな手がかりに!
小竹貝塚(おだけかいづか)は富山県のほぼ中央部、呉羽丘陵と射水平野との接点に位置する。
北陸新幹線建設に先立ち、平成21・22年度に発掘調査が行われ、大規模な貝塚とともに、埋葬人骨や竪穴住居などが出土している。
貝殻のカルシウム成分によって、土壌がアルカリ性を保ち、通常の遺跡では酸性土壌で腐ったり、溶けてなくなったりしてしまうような骨、木器などが残る。
古の人たちの暮らしぶりを伝えるタイムカプセルといってもいいようだ。
小竹貝塚は、約6,750~5,530年前の縄文時代前期の貝塚で、約1,220年間にわたって形成された。
遺跡範囲は東西約150m、南北約200m。
埋葬人骨(墓域)、貝層(廃棄域)、板敷遺構(生産・加工域)、竪穴住居(居住域)の区域分けがされていた。
貝層では、ヤマトシジミを主とする貝が最大で約2m堆積していた。
墓地として使用されていた貝塚で見つかった人骨は91体と、他に例を見ない数だ。
そのうち、男性は35体、女性は18体で、残りは性別不明だった。
死亡時の年齢をみると、10代後半から20代の若い男性、生まれたばかりの子どもが多く、厳しい生活環境だったことをうかがわせる。
身長を推定できる人骨は男性22体、女性7体あり、男性では165cm以上の、当時としては高身長の人もいれば、154cm前後の低身長の人もいた。
女性の平均身長は、縄文時代後・晩期の平均推定身長と同じ148cmだった。
国立科学博物館人類研究部が人骨の細胞の中にあるミトコンドリアDNA(遺伝子情報)を分析したところ、小竹縄文人はロシアのバイカル湖周辺や北海道縄文人に多い北方系と、東南アジアから中国南部に見られる南方系の2系統が混在することがわかった。
縄文時代中期以降の系統と遺伝的なつながりを確認することもできた。
一方、渡来系の弥生人や現代の日本人に多い型は見られなかった。
人骨のさらなる研究により、縄文人がどこから来たのか、ルーツ解明が期待される。
小竹貝塚からは、埋葬されたとみられるイヌが21体見つかり、縄文人の墓のそばに丁寧に葬られていた。
狩猟犬、愛玩犬として縄文人と一緒に生活し、丁寧に扱われていたことを示している。
現代のようにペットとしてイヌを可愛がっていたとは驚き。愛犬と仲良く暮らす縄文人の様子が目に浮かんできそうだ。
縄文土器・土製品は約13トン分が出土。
関東地方や近畿地方、東北地方で作られたとみられる土器があり、他地域との交流を物語っている。
石器は約10,000点出土しており、糸魚川周辺で採取されたとみられるヒスイを使った作りかけのペンダントが発見されている。
縄文時代前期のヒスイ製品としては国内で最古級だ。
骨角貝製品(こっかくかいせいひん)では、釣針、刺突具(しとつぐ)、針、装身具など約2,300点が出土。
装身具の中には、九州や伊豆諸島以南でしか採取できないオオツタノハという貝で作られた貝輪1点が見つかった。
太平洋沿岸の縄文遺跡では見つかっているが、日本海側では初めて。
ブレスレットとして、現代人が身に付けてもいいほど、素敵なデザインだ。
縄文時代にすでに釣針や針、ブレスレットやイヤリングが作られていたとは驚き。形も現代のものと大差ない。
タイの歯が象嵌(ぞうがん)された漆製品もあり、縄文人の工芸の技を垣間見ることができる。
当時の女性たちもお洒落をしていたと思うと、親近感も湧いてくる。
富山県文化振興財団 埋蔵文化財調査事務所では、
「小竹貝塚では、南方系と北方系にルーツを持つ人たちが一緒に暮らしていたことがDNA分析から明らかになった。日本海側の真ん中に位置するからだろうか。縄文人を語るうえで欠くことのできない重要な遺跡だ。
また、広範囲の地域との交流を物語る品々が出土した。日本海側の他の地域の遺物と比較し、小竹貝塚の特徴をより調べていきたい」
と話している。
 wikipedia「白保竿根田原洞穴遺跡」より
wikipedia「白保竿根田原洞穴遺跡」より白保竿根田原洞穴遺跡(しらほさおねたばるどうけついせき)は、沖縄県石垣市(八重山列島石垣島)にある旧石器時代から断続的に続く複合遺跡である。
新石垣空港建設前まで、同地はゴルフ場内にあたり盛土されていたため、地下にこのような洞穴があることは、把握されていなかった。
長大な洞穴の洞口が最初に見つかった、白保側(現在の遺跡の場所よりも北側)の小字名がそのまま遺跡名として利用されている現状がある。
白保竿根田原洞穴遺跡は2007年に新石垣空港予定地で見つかった遺跡で、NPO法人沖縄鍾乳洞協会によって、洞穴内から人間の頭、脚、腕などの骨9点が発見された。
このうち、状態のよい6点について同協会、沖縄県立埋蔵文化財センター、 琉球大学、東京大学等の専門家チームが放射性炭素年代測定を行ったところ、
そのうちの1点の20代-30代の男性の頭骨片(左頭頂骨)が約2万年前、他に2点も約1万8千年前及び約1万5千年前のものと確認された。
さらに国立科学博物館が、これらの人骨10点の母系の祖先を知る手掛かりとなるミトコンドリアDNA分析した結果、国内最古の人骨(約2万-1万年前)とされた4点のうち、2点はハプログループM7aと呼ばれる南方系由来のDNAタイプであることが明らかとなった。
これまで、直接測定による日本国内最古の人骨は、静岡県浜北区の根堅洞窟で発見された浜北人の約1万4千年前であった。
なお、人骨そのものではなく、周辺の炭化物などから測定した日本国内最古の人骨は沖縄県那覇市山下町第一洞穴で1968年に発見された山下町洞穴人の約3万2千年前のものである。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「アイヌ民族と沖縄民はDNAが近い「縄文系の血を残す」説は本当か?」
「42000年の旅路・・ボルネオ島のニア洞窟」
 「アイヌ」カテゴリー全般
「アイヌ」カテゴリー全般「ブログ内検索」で
北海道 15件
東北 15件
沖縄 15件
DNA 13件
縄文 15件
旧石器 12件
などあります。(重複しています)